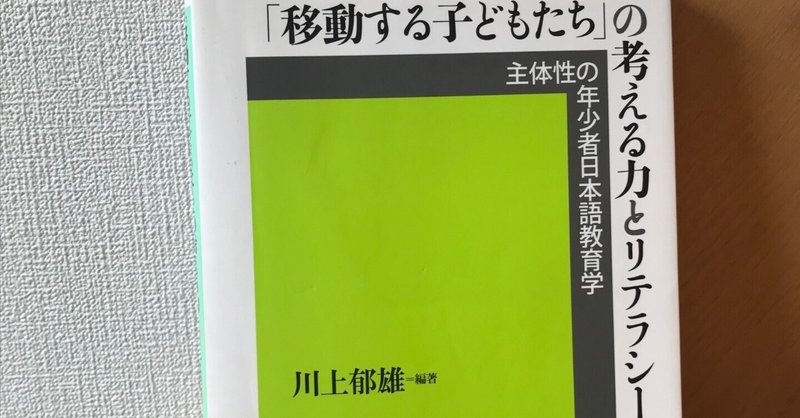
MY BOOK REVIEWS ③「移動する子どもたち」の考える力とリテラシー―主体性の年少者日本語教育学
このシリーズの3冊目にレビューする書籍は、『「移動する子どもたち」の考える力とリテラシー―主体性の年少者日本語教育学』(2009, 明石書店)。
この本は、2006年に刊行した『「移動する子どもたち」と日本語教育―日本語を母語としない子どもへのことばの教育を考える』(2006, 明石書店)に続く、「移動する子ども」シリーズの第2弾として編んだ本である。私が早稲田大学に着任してから7年後の刊行であった。
内容は、前著と同様に、私の論考のほかに、大学院日本語教育研究科の院生たちの論考をまとめたものである。本書の「はじめに」は「「移動する子どもたち」をめぐる風景」と題した。続いて、11本の論考を、以下の3部に分けて収録した。
「第1部 「移動する子どもたち」の主体性を育む実践とは何か」
「第2部 「移動する子どもたち」のリテラシーを育てる」
「第3部 「移動する子どもたち」の「ことばの力」を問う」
と続く。
第1部の「第1章 主体性の年少者日本語教育を考える」は私が書いたが、第2章から第11章までは、院生たち11人が実践研究を踏まえて書いた論考が並ぶ。
さて、この本のテーマは、「考える力」とリテラシー、そして主体性である。なぜか。その理由が、本書の「はじめに」で次のように述べられている。
「年少者日本語教育は、単に「日本語」を教えれば終わりという教育ではない。「読み書き能力」を超える「ことばの力」=リテラシーと、「ことばの力」を使っ
て考えること、そして子どもの主体を育成するという人間教育の一翼を担う教育
領域である。そのことを、子どもへの日本語支援を通じて探究した実践研究が本
書に収められている。」(「はじめに」、p. 4)
また、その問題意識として、
「国境を越えて移動する人口の流れは世界各地に新たな課題を生み出している。
それは新しく流入する人々だけにではなく、それらを受け入れる社会にもさまざ
まな課題を突きつけている。「移動する子どもたち」の課題とはまさにそのよう
な文脈にある社会的課題なのである。本書は、そのような社会的課題に対応すべ
く、子どもに寄り添う形で試みた年少者日本語教育の立場からの実践研究なので
ある。」(「はじめに」、p.6)
と書かれている。
第1章で私が議論したことは、子どもの「主体性」「ことばの力」「ことばの学 び」をどう捉えるかという論点であった。その議論の基本となるのが、子どもと向き合う「実践」であり、その実践で重要なのが、実践者が子どものことばの力の「動態性」「非均質性」「相互作用性」に留意することであると主張している。この主張は、今も変わらない。なぜなら、その主張は、年少者日本語教育の基本であると確信するからである。
では、なぜ、そう思うのか。早稲田大学で20年以上、年少者日本語教育の実践を多数検討してきた。この間、私が子どもを直接教えることはなかったものの、毎週、院生たちの実践報告をもとに、修士論文や博士論文の指導を行ったり、議論を重ねたりしたことから、この確信を得たからである。
本書の「あとがき」は「Children Crossing Borders (CCB)の未来へ向けて」と題した。その一節に次の文章がある。
「「移動する子どもたち」という研究テーマは、ひとりの子ども、あるいはひと
つの学校や地域で深く考えることも可能だが、同時に、私たち自身が複数の研
究視点を持ちつつ、移動しながら考えることも必要だろう。なぜなら、私たち
が考えようとしている子どもたち自身が、複数地点を行ったり来たりしながら成
長しており、その彼らの心象とことばの世界は私たちが経験できなかったものと
思うからである。」(「あとがき」、p.258)
このような実践研究の視点と発想が生まれるのは、このシリーズの①で述べた「ベトナム難民」家族の生活世界を探究した時の方法論があったからである。
「ベトナム難民」家族(特に、第一世代)は、日本で暮らしながらも、国内だけではなく、祖国や第3定住国の家族、親族、友人等とつながる生活世界に生きているということ、そしてその生活世界は日本や祖国、国際社会からの社会的要因の影響を受けること、さらに、その生活世界は固定的ではなく変化すること、つまり動態性があった。
したがって、目の前の人を、「国籍」や「出生地」「在留資格」などで「名付け」ても、その人自身の心の中や意味世界はそれらの「名付け」とは別の広がりがあるのだ。
これらの気づきは、「移動する子ども」学を構想する基盤となるものであったが、ただ、まだその時点ではその「学」の裾野の広がりは見通せていなかった。ただし、これらの子どもたちの「考える力」やリテラシー、「ことばの力」を考えれば考えるほど、当事者の子どもが持つ、目に見えない部分に強く関心を持つようになっていった。子どもが習得した漢字の数や、子どもが書いた作文の文法的な誤りを数えたりする研究とは一線を画した領域にこそ、これらの子どもを理解するヒントがあるのではないかと思うようになっていたからである。
「日本語指導が必要な子ども」ではなく、「移動する子ども」、そしてその英訳として、Children Crossing Borders:CCBを作り、海外の学会発表でも使用する戦略をとった。「サード・カルチャー・キッズ」(Third Culture Kids: TCK)を超える研究領域を示したかった。
その英訳の名称も含めて、さらに研究の視野を拡大しなければならないと思った。
私の在籍した研究科には、入試において「海外受験」という方法がある。その方法で海外にいる日本人や留学生が多数受験してくる。その結果、私の研究室にも、海外から入ってくる学生がいたが、その中に、日本国外で日本語を学ぶ子どもたちに出会い、実践研究をしたいという動機を持った学生が少なからずいた。そして、彼らと一緒に、日本国外で、つまり、海の向こうで日本語を学ぶ子どもたちについても研究することになった。
では、その研究成果はどうか。次は、そのことについて述べたいと思う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
