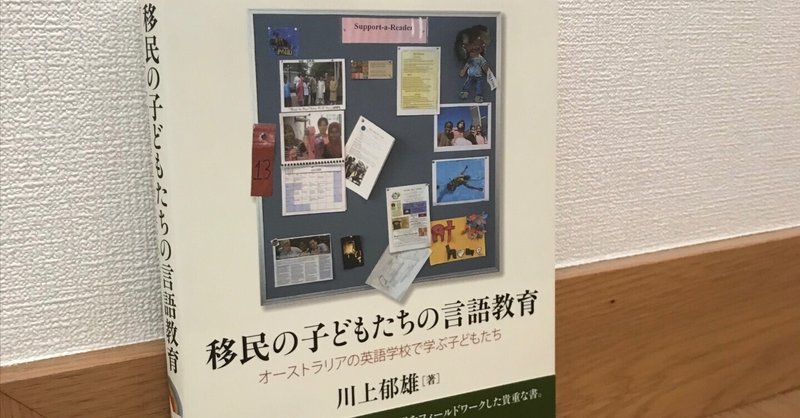
MY BOOK REVIEWS⑧移民の子どもたちの言語教育―オーストラリアの英語学校で学ぶ子どもたち
このシリーズの8冊目にレビューする書籍は、『移民の子どもたちの言語教育―オーストラリアの英語学校で学ぶ子どもたち』(2012, オセアニア出版社)。
この本は、オーストラリアの移民の子どもたちがどのように第二言語の英語を学んでいるかについて、連邦政府の言語政策、移民の子どもたちを受け入れている英語学校の現地調査を踏まえて、まとめたものである。オーストラリアの移民の子どもへの言語教育を政策文献調査と、現地の学校の教室まで入って調査をした研究は初めであった。
私は、大阪大学大学院博士課程に在籍中の1988年に、交換留学生として、豪州クィーンズランド(QLD)州ブリスベン市にあるクィーンズランド大学で1年間、オーストラリアの文化人類学、社会学を学んだ。同時に、多文化主義(Multi-culturalism)政策の学校現場を見てみたいと思っていたので、大学の休暇を利用して全国を旅し、いくつかの学校を訪問した。その時、州によって制度が異なることに気づき、いつか本格的な調査をしたいと思った。
その後、1990年から1992年まで、国際交流基金の派遣で、クィーンズランド州教育省に日本語教育アドバイザーとして勤務した。
今から振り返ると、1980年代後半から1990年代はじめに豪州に滞在したことは、豪州の多文化主義(マルチカルチュラリズム)や言語教育政策の転換期に遭遇した貴重な体験だった。J. Lo Biancoの『National Policy on Languages』が1987年に刊行された。1988年には、『オーストラリアの言語教育ガイドライン(Australian Language Levels Guidelines)』が刊行された。どちらも多文化主義の基づく施策であった。しかし、QLD州教育省に勤務していた1991年には、J.Dawkinsの『オーストラリアの言語リテラシー政策(Australia’s Language: The Australian Language and Literacy Policy)』が発表され、連邦政府は多文化主義より経済至上主義を優先する政策へ大きくシフトジェンジした。この政策が公表される前に、教育省ではこの政策のドラフトが回覧され、熟読するように上司に言われたことを覚えている。
2年間の教育省での勤務を終えて帰国し、宮城教育大学に勤務していた頃も、毎年のようにオーストラリアを訪ね、言語政策に関する資料集めや学校訪問を続けた。Penny McKayのESL bandscalesも入手し、2002年に早稲田大学へ移った後も、その調査研究を継続することになった。
本書は、そのような経緯で始まり、まとめられたものである。したがって、以下の3部で構成される。
第1部 移民の子どもたちの英語教育政策
(第1章)
第2部 移民の子どもたちが学ぶ英語学校の実践
(第2章、第3章、第4章)
第3部 移民の子どもたちとリテラシー教育
(第5章、第6章、終章)
日本における「オーストラリア研究」は、以前から、豪州の歴史、経済、社会、教育、文学、芸術など多様な領域において研究されてきた。どの領域においても移民や移民政策を含む「国づくりの内実」が強く影響していた。
ただ、移民の子どもたちがどのように第二言語の英語を学んでいるのか、またその第二言語の英語教育(ESL教育)の政策にはどのような考え方や思想があるのか等についてはほとんど知られていなかった。
そこで本書では、第1部では、移民の子どもたちへの英語教育の歴史と言語教育政策の思想を検討した。その上で、第2部では、ニューサウスウェールズ州(シドニー)、クィーンズランド州(ブリスベン)、ビクトリア州(メルボルン)の3つの「移民の子どもたちの英語学校」を調査した結果を述べた。3校で、合計3週間の学校調査であった。
さらに第3部では、移民の子どもの「ことばの教育」とは何かについて論じ、豪州から日本が学ぶべきことは何かを論じた。
第1部で気付くのは、多文化主義に基づき、移民の子どもに寄り添った政策や第二言語教育を重視するかと、新自由主義および経済至上主義に基づき、大多数の英語母語話者の英語教育を重視するかの「思想的な戦い」の歴史があることだ。
第2部では、移民の子どもたちに英語を教える優れた先生方や実践をたくさん見たこと、世界各地から背景の異なる多様な子どもたちや親が学校にくる現状を報告した。さらに、調査した英語学校で、日本からオーストラリアにやってきた生徒がいることも気づいた。日本人の生徒もいたが、インタビューすると、しっかりした日本語で答えてくれる、ロシア人の親を持つ生徒、また中国人の親を持つ生徒もいた。つまり、「移動する子ども」の現象はグローバルに見られるということだ。
その上で、第3部で、「移動する子ども」の「ことばの力」とは何か、21世紀に生きる子どものリテラシーとは何かについて考えた。
本書は、2010年度豪日交流基金「サー・ニール・カリー奨学金」の出版助成を受けた。
帯文には、ニューサウスウェールズ大学教授のトムソン・木下千尋先生から推薦のお言葉をいただいた。
「移民の子どもへの英語教育の教育現場をフィールドワークした貴重な書。
オーストラリアの移民の子どもへの言語教育は、
日本にいる外国人児童生徒への言語教育にも
大きな示唆を与えるでしょう。」
「移動する子ども」研究を、日本だけではなく、グローバルな視野で考えていかなければならないと、強く思った。そのために、研究主題に日本語教育の枠を超えて、どのようにアプローチするかを考えるようになった。それについては、次の本で述べたいと思う。
本書のカバーデザインは、今回も、桂川潤さんが素敵に作ってくださった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
