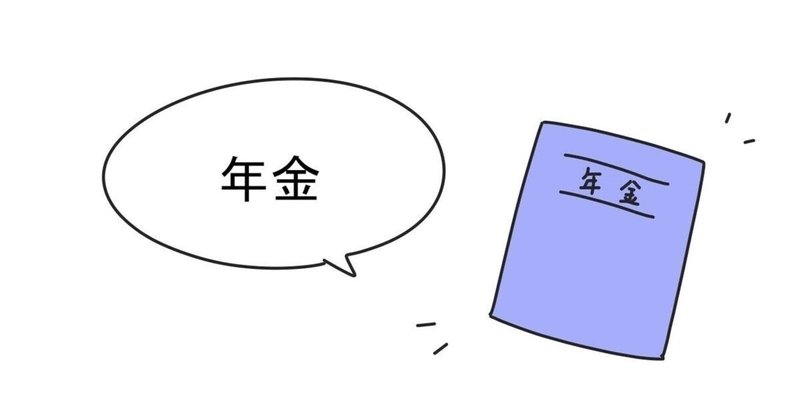
令和4年4月から年金のもらい方が変わります
令和2年に成立した「年金制度改正法」(正式名:年金制度の機能強化のための国民年金法の一部を改正する法律)によって2022年から年金制度が改正されます。
主な改正点は4点
① 被用者保険の適用拡大
② 在職中の年金受給の在り方の見直し
③ 受給開始時期の選択肢の拡大
④ 確定拠出年金の加入可能要件の見直し
①は、別の記事に掲載しています。今回は公的年金のもらい方にフォーカスして、②③について記事にします。④は別の機会に記事にします
https://note.com/iiisaf/n/nb9ed088af9d0
1 公的年金(老齢の年金)の種類
公的年金は、65歳を境にの種類が異なります。
65歳未満は、特別支給の老齢厚生年金
65歳以上は、老齢厚生年金と老齢基礎年金
65歳未満は、特例措置として年金をもらっているから「特別支給」という冠がついています。
65歳以上は、厚生年金法の本則に則った老齢厚生年金が支給され、別に国民年金(老齢基礎年金)も支給されます。
老齢厚生年金は、会社員や公務員などの被用者がもらう年金です。老齢基礎年金(国民年金)は、全国民がもらう年金です。自営業の方は老齢基礎年金のみの支給となります。
2 在職中の年金受給の在り方の見直し
① 在職定時改定の導入
65歳以降に老齢厚生年金をもらいながら、働いている人(厚生年金保険料を払っている人)について、年金受給額増につながる改善があります。
現行の「退職時改定」から「在職定時改定」に見直しされます。
退職時改定とは、老齢厚生年金をもらいながら、働いている(厚生年金保険料を払ている)場合、退職時又は70歳になった時に老齢厚生年金の受給額が増額改定されることです。
在職定時改定とは、毎年10月に老齢厚生年金受給額が増額改定されることです。

厚生労働省HP「年金制度改正法の概要」より引用
厚生労働省の資料によると、在職定時改定により標準報酬月額20万円で毎年13000円程度年金が増えるようです。
②「在職老齢年金制度」の改正
働きながら(⇒厚生年金保険料を払っている人)、受給している老齢厚生年金(特別支給含む)を在職老齢年金といいます。
在職老齢年金は、年金の支給停止の制度です。
65歳未満は、28万円を超えると支給停止
65歳以上は、47万円を超えると支給停止
28万円、47万円を超えても全額支給停止にはならず、計算式により段階的に支給停止額が増えていきます。

3 受給開始時期の選択肢の拡大
現在の年金受給開始年齢は、65歳です。これを繰り上げ・繰り下げ制度があります。
繰り上げは
・ 60歳まで繰り上げ可能
・ 老齢厚生年金と老齢基礎年金を同時に同年齢で繰り上げ
・ 繰り上げ1か月につき、年間受給額0.5%引き下げ
となります。
今回の見直しで、「繰り上げ1か月につき、年間受給額0.4%引き下げ」に改正されます。
繰り下げは、
・ 70歳まで繰り下げ可能
・ 老齢厚生年金と老齢基礎年金を同時に同年齢で繰り下げなくても良い
・ 繰り下げ1か月につき、年間受給額0.7%引き上げ
となります。
今回の見直しで、「75歳まで繰り下げ可能」に改正されます。
60歳まで5年間繰り上げした場合、年間年金額が30%減額だったところ、24%の減額となります。減額幅が少なくなるため、申請者の増加が予想されます。
70歳まで繰り下げした場合は、年間年金額が42%増額です。75歳まで繰り下げた場合は、84%の増額です。年金額が少ない人で、70歳を過ぎても働き続ける人には、有難い改正です。ただし、長生きをしないと、メリットを生かせないことが留意点です。

4 まとめ
今回の見直しは、「年金制度の面で働きやすい環境づくりの整備」が趣旨であるようです。
利用者は限定的との意見もありますが、今後の更なる改正も想定し、今回の改正も高齢者の労働者にとって大きな一歩であると信じています。
留意点は、年金制度は申請主義であることです。制度を理解して、働き方と年金受給の方法を自らが考えて、自分で年金受給の方法を申請しないといけません。これからも年金制度は見直しが続くと思いますが、改正内容を理解して、柔軟に対応しないと、人生100年時代を乗り切っていけないですね。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
