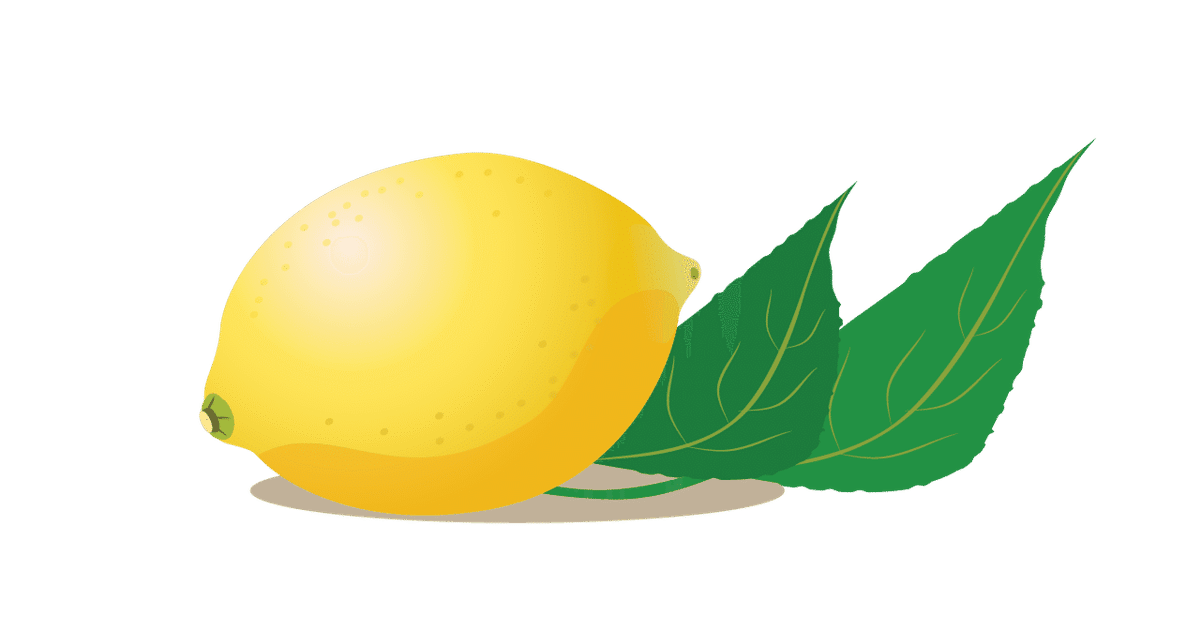
私の落選作品 その3(第30回 三田文學新人賞 応募作品)2
2.
手元に文庫本の『檸檬』がある。それをひもとくと、小説『檸檬』はわずか7ページあまりのとても短い作品で、以下のような書き出しではじまる。
えたいの知れない不吉な塊(かたまり)が私の心を始終圧(おさ)えつけていた。焦燥と云おうか、嫌悪と云おうか――酒を飲んだあとに宿酔(ふつかよい)があるように、酒を毎日飲んでいると宿酔に相当した時期がやって来る。それが来たのだ。これはちょっといけなかった。結果した肺尖(はいせん)カタルや神経衰弱がいけないのではない。また脊(せ)を焼くような借金などがいけないのではない。いけないのはその不吉な塊だ。以前私を喜ばせたどんな美しい音楽も、どんな美しい詩の一節も辛抱がならなくなった。蓄音器を聴かせて貰いにわざわざ出かけて行っても、最初の二三小節で不意に立ち上がってしまいたくなる。何かが私を居堪(いたたま)らずさせるのだ。それで始終私は街から街を浮浪し続けていた。
この冒頭の「えたいの知れない不吉な塊(かたまり)が私の心を始終圧(おさ)えつけていた。」という一文は、作品全体の基調を成すもので、音楽でいえば調性の決定的提示であり、そこに作者の宿命の主調低音を聴き取ることができる。「作者の宿命の主調低音」というのは、小林秀雄が『様々なる意匠』の中で用いたことばだが、ここで私はその文脈を離れて字義どおりに転用した。書き出しの一行で、短調の重々しい調性がピタリと定まり、続いて、いくつかのフレーズの繰り返しで物語が進行してゆく。「――と云おうか」「酒を飲んだ(で)」「宿酔」「いけない(のではない)」「不吉な塊」「どんな美しい」と、同じことばを二度三度と畳みかけてゆく。私はそこに旋回しながら進む音楽性を感じるのだ。
『檸檬』における「私」は梶井本人がベースになっているのだが、ここで「彼の心を始終おさえつけていたえたいの知れない不吉な塊の正体は何か」という問いに想到する。これについて梶井は否定形で例示しながら、本体とは相違するものを列挙していくが、肝心の「不吉な塊」そのものの内容については具体的に明示しておらず、読者の想像に委ねられている。おそらくその内実は二つの因子よりの混淆と察せられる。一つは当時の世相であり、もう一つはより個人的な家庭環境や自身の身体の問題だろう。
この小説が書かれた1920年代初めの大正時代は、第一次世界大戦による好景気がたちまち収束して戦後恐慌となり、各地で民衆の不満が小作争議や米騒動となって吹き荒れた時代である。よって暴力自体がより身近に切迫した環境にあっただろう。加えて梶井には家庭の問題もあった。自ら「商人の子」というように、高等教育を受けながら、友人たちのような裕福な家の出身ではなく、また放蕩癖の父親により異母弟妹との同居を余儀なくされていた。梶井は母親に対しては終生感謝と尊敬の念を抱き続けたが、父親の行状はいつも家庭における悩みの種だった。また、祖母からの感染で当時蔓延していた肺結核となり、すでに発症していた。そのような個人的また社会的状況にあって、自己の将来に思いを馳せた時、大志を抱くがゆえの重苦しさが、払いのけようにも払いのけることができない確たる物のように自分にのしかかり押さえつけているという実感があったのだろう。
先ほど小林秀雄の言葉を持ち出したが、ちなみに梶井は1901(明治34)年生まれ、小林は1902(明治35)年生まれであり、また梶井が東京帝国大学に入学したのは1924(大正13)年で、小林の入学は翌1925(大正14)年と、梶井は小林の一年先輩という関係である。
私はまず小説『檸檬』の冒頭部分の音楽性に言及したわけだが、梶井基次郎は後年大正教養主義と呼びならわされるようになった・個人の自由を認め・若者たちに生命の発露としての理想を抱くことが鼓吹された良き時代に、旧制第三高等学校で学生生活を送った恵まれた少数の若人の一人だった。彼は兄から借りた『漱石全集』を三高時代に読破していたし、1910(明治43)年創刊の『白樺』がもたらした清新な作品も含め、谷崎潤一郎など多くの文学作品に触れつつ友人たちと感想を語り合った。また京都で催される海外演奏家のコンサートや印象派をはじめとする美術展にも足繁く通った。そればかりでなく、一時期友人たちとの放蕩に加わることもした。音楽に関しては、中学時代の音楽の先生から西洋音楽の楽典を教わったことで楽譜に親しむようになり、1922(大正11)年にはベートーヴェンの第五・第六・第七交響曲やクロイツェル・ソナタの楽譜を購入し、オーケストレーションの研究もしている。またヴァイオリンのハイフェッツ、ピアノのゴドウスキーなどの来日公演を聴きに行ったり、ヴァイオリニストのエルマンの来日演奏会が京都市公会堂で開催された折には、終演後の帰りぎわに握手を求め、応じてくれた感激を友人に書き送ってもいる。さらに『檸檬』を書き上げた1924(大正13)年に開催されたベートーヴェン第九交響曲の日本初演には、二日続けて聴きに行っている。『檸檬』の構想段階でまず詩を作り、友人にそれを「アンダンテの第一頌歌」と伝えている手紙があることを前に記したが、この「アンダンテ」については、前掲の『檸檬』第一段落目の最後の一文「それで始終私は街から街を浮浪し続けていた」に示されている。物語の進行速度は街歩きということから、「アンダンテ」すなわち「歩くような速さで」との設定を企図したのだろう。
そう書き出された『檸檬』だが、第二段落目となる次の文は、「何故だかその頃私は見すぼらしくて美しいものに強くひきつけられたのを覚えている」と続く。ここで考えてみたいのは、「その頃」ということばである。『檸檬』には、この「その頃」ということばがこの後も複数回出てくるのだが、特筆すべきは、レモンを手にした際の感覚の快さを述べたあとで、ダッシュを引き「それがあの頃のことなんだから」と強調している箇所があるのだ。ここから、この小説を書いている梶井が、この物語当時の自分自身をかえりみた時に、客体化して眺められるほどの懸隔を自覚しているように察せられる。そこで読んでいる私としては、おそらく相当前の話なのだろうと推し量り、梶井の経歴から確認してみたところ、物語の体験は、梶井がこの小説を書き上げるほんの二・三年前の出来事だということが判明した。それを何かまったく別人にでも変身したかのように、懐旧の趣を籠めて書き記すとは、その間に彼の一身さらに人格に何があったのかという思念が湧出してきた。
ということで、「レモン体験」とも言えるこの物語のエピソードの実行は、史料によれば1922(大正11)年の春頃とされ、また小説『檸檬』の脱稿は1924(大正13)年10月であるので、その間に梶井がどう変わったのかを検証してみたい。
まず両時点の間に介在する断層であるが、1923(大正12)年9月1日に関東大震災が発生した。梶井は旧制三高の学生として京都で暮らしていたのだが、高校では二度落第し、友人たちは多く東京帝大に進んでいるため、自らも上京することを望んでいた。この年は最後の高校生活であったが、翌年無事に東京帝国大学に合格し、1924(大正13)年4月初旬に震災からの復興に動き出した東京に移り、東大生としての生活が始まった。その大学一年生の十月末までに書き上げたのが、現在の『檸檬』である。
梶井は1922(大正11)年にノートに書きつけた『秘やかな楽しみ』という文語詩からさらに発展させて、それまでの苦悶に満ちた半生をともかく葬り去りたい一心で、この「レモン体験」をもエピソードとして加えた散文を構想し、1923(大正12)年は中篇小説として創作を進めた。その草稿は梶井の没後『瀬山の話』として公開され、近年再発見されたものが実践女子大学の所蔵となり、小説『檸檬』の成立過程が詳しく研究されてきている。その研究では、これまで『瀬山の話』と称せられていた草稿には、『「檸檬」を含む草稿群』という呼称が付与されている。ここに至る途中の段階の草稿を携えて、梶井は晴れて東京帝国大学一年生としての生活を始めるべく、勇躍上京してきたのだ。
3.(続く)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
