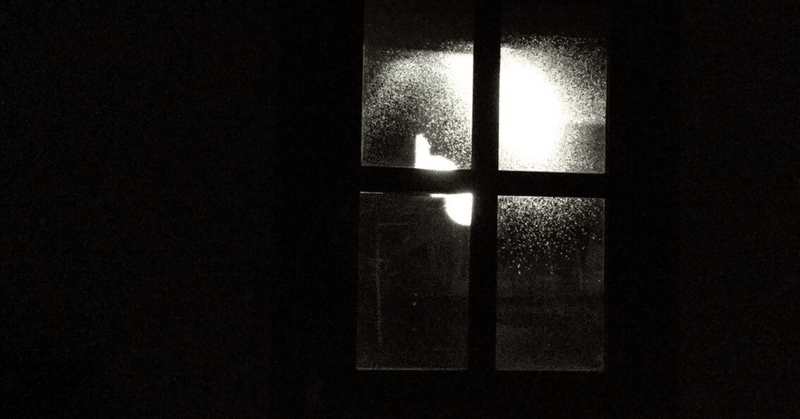
吉屋信子『屋根裏の二處女』読書会レポート試し読み(『ますく堂なまけもの叢書⑥平成の終わりに百合を読む 百合SFは吉屋信子の夢を見るか?』所収)
空前の百合ムーブメントの中で
吉屋信子を読む
ティーヌ
「読書サロン」主催のティーヌです。今回の吉屋信子『屋根裏の二處女』(国書刊行会)を課題本とした読書会は、「ますく堂なまけのもの叢書」さんで開催される「SFマガジン百合特集」読書会と合わせて「百合小説」をテーマとした同人誌として刊行される予定となっております。
益岡
「ますく堂なまけもの叢書」の発行人をしております、益岡です。
百合コンテンツのブームというのは、一部ではかなり爆発的に起こっているようなのですが、全体的にふわっとしているような気がして、個人的には実はあまりピンときていないんです。
だから今回、「SFマガジン」の百合特集号が話題になった直後も、あまり積極的にかかわりたいとは思っていなかった。
でも、ティーヌさんから、「おたくでやらないなら、うちでやるぞ」と挑発されまして(笑)僕にとっては得体のしれない「百合ブーム」を整理してみるのも必要なのかな、と思い始めました。
セクシュアルマイノリティの登場する小説を読む「読書サロン」は、一月に一年間で読む本を決めるのですが、毎年、なんとなく「古典枠」のような作品が選ばれるようになっていて、今年は吉屋信子である、と。吉屋信子を「百合小説」の古典というか、スタートと位置付けて読んでみて、そのうえで最新の百合ムーブメントを担おうとしている「SFマガジン」を読んでみたら、「百合」について何かわかるんじゃないか。そんなことを期待して、今回は二つの読書会を併録して一冊の本をつくってみたいと考えております。よろしくお願いいたします。
ティーヌ
それでは、この会は誰彼かまわずしゃべって、誰彼かまわず拾って……という会なので自由に発言してもらいたいと思うのですが……
ヘイデン
ではまず、根本的なところを聞いてみたいんですが、「百合」と「レズビアン文学」というか「レズビアン同士の恋愛もの」は別のものとして捉えたほうがいいんでしょうか?
柳ヶ瀬
同じものとして考えたほうがいいです!
一同 (笑)
益岡
力強い! 大丈夫? これ、宗教戦争に発展しない?(笑)
ヘイデン
私は、幼いころからBLばかり読んできて、レズビアンものには触れてこなかったのね。自分自身が女の子とも恋愛してるというのがあって「こんなことあるわけないじゃん」と思ってしまうから、百合には苦手意識がある。男同士の恋愛を描くBLは自分では絶対体験できないことだから、気持ちよく、完全なフィクションとして、ファンタジーとして摂取してきたんだけど、百合はそういう目では見られなくて、ずっと距離を感じている。だから、ぜひ詳しい方に、まず「百合とは何ぞや」ということを語ってほしい。
柳ヶ瀬
私はずっと百合小説を書いてきて同人活動も行っているんですが、私の認識では「百合文化」があって「レズビアン文化」があるとすると、この二つは確実に重なっていると思います。ただ、重ならない部分もある。ここまでは相容れるけれど、ここからは相容れないというような。だから、先ほど「同じもの」と言いましたが、「重なる部分もあるんだけど重ならない部分もある」というような捉え方がより正確かもしれません。
「百合」に持っているイメージというのは、主人公が女子高生で、なんかきらきらしてて……というような感じですか?
ヘイデン
そういうイメージもあるけれど、ファン層というか、受容の在り方として、「女性がBLを消費するように男性が百合を消費している」のかな、というようなイメージがあります。
銀河
その点でいえば、BLとの大きな違いは書き手に女性が多いということだと思います。百合の作者には当事者も多い。BLの作者にはゲイで男性で……という方はすごく少ない。
ヘイデン
確かに少ないですよね。
橋本
それは、吉屋信子の時代からずっと続く伝統だということ?
柳ヶ瀬
ずっとかどうかはわからないですけど、百合文化が台頭してきてから、百合オンリーの同人即売会に行くと、書き手の八割は女性ですね。
銀河
ただ、供給する側が女性であっても、受容する側がどうかというのは、また違う問題だと思います。男性による需要というか、消費はやはり多い。以前は半々くらいだったと思いますが、今は六割くらいが男性なのではないかと思います。昔は逆で、女性が六割以上だったようですけど。
ヘイデン
吉屋信子なんかは、女性の読者が中心だったわけですもんね。
トット
「SFマガジン」の百合特集号も、書き手は女性が多いんですか?
銀河
いや、それはちがうと思う。
益岡
そうですね。僕の印象ですけど、SF百合の担い手は今、圧倒的に男性だと思います。
銀河
これは、日本SFの風土的な問題だと思うんですけど……。
橋本
それは、日本における百合SFの受容者が男性に偏っているということ?
銀河
海外でも男性消費者はもちろんいると思うんですが、当事者が受容するメディアとして成立している部分があって、日本にはそれがほとんど見当たらない。早川書房が出している海外SFにはレズビアン作家の作品もいくつかあって、私はニコラ・グリフィスの『スロー・リバー』(ハヤカワ文庫SF)という小説が好きなんですが、女性どうしの恋愛の多彩なシチュエーションを煮詰めたような作品なんです。結構エロティックで。
橋本
私は非常勤講師としていくつかの大学で台湾文学の講義を持っているんですが、中国語圏でも日本の百合は大人気なんです。
柳ヶ瀬
そうなんですか! BLとどっちが浸透してます?
橋本
そこははっきり住み分けがされていて、どちらともいえないけれど、百合は圧倒的に女の子のファンが多い。全中国語圏の百合ファンが集まるフォーラムがあって、中国大陸はもちろん、マレーシアや台湾など、中国語ができるひとはみんな集まってくるんだけど、その参加者はほとんどみんな女性だと思います。男性は全然いない。
ヘイデン
BLも最近は腐男子もいますけど、圧倒的に腐女子に支えられている。当事者のファンもいると思いますし、セクシュアリティに関係なく読んでいる人は増えていると思いますけれど、まだ、読者が限定されているようにも思う。
その点、百合はもう少し幅広いようなイメージもあって、それゆえの区分けというか、「男の子向け百合」「女の子向け百合」というようなカテゴリーがあるような印象があります。
柳ヶ瀬
結構、掲載誌によってカラーが出るというのはありますよね。「百合姫」と「きらら」とか。
ヘイデン
そのあたりを厳密に分けるというか、捉える意味はあんまりないとは思うんですけど……でもなんか、面白いですよね。
銀河
私はこれは難しい問題だと思っています。この区分の可否というのは、「ビアン的な欲望」と「ヘテロ男性が女性に抱く欲望」というのが、どの程度区別可能なのかという問題に繋がってくると考えられる。これはかなり難しい問題をはらんでいると思う。
柳ヶ瀬
その二つを対立軸にできるのかという議論もある。オタク男性というか、百合好きのヘテロ男性の最近の傾向として、内面的な部分はジェンダーレスになってきているという印象を持っているので、対立軸として置くことが難しいというか、少なくとも「敵ではないかな」という(笑)
一同 (笑)
銀河
吉屋信子が現役作家として作品を発表していたときに、消費していた男性はあまりいなかったと思うんですよね。吉屋信子自身、女性ということで排撃されてきた面もある。少女小説出身であるということで受けた批判というか、評価もあったと思うんです。女性の書く、女性だけのためのものというか。それを踏まえると、「百合」には、明らかに「女性向け」とされてきた歴史があるとは思います。
ヘイデン
『屋根裏の二處女』は、少女小説?
銀河
これは、「少女小説」という枠組みは相当意識したものだとは思うけど……
柳ヶ瀬
竹田志保『吉屋信子研究』(翰林書房)によると、『屋根裏の二處女』は従来の少女小説とは一線を画した「オルタナティブな百合・同性愛小説」という位置づけになっています。吉屋信子自身もこの作品では少女小説からの脱却を意識していたと思うのですが……
ティーヌ
少女小説はもう少し、道徳というか、教育的配慮のあるものという印象もありますよね。
銀河
『花物語』なんかにはそういうところも顕著に出ている。でも、後半になるにしたがって変質していくんですね。女性の苦悩や痛みを描く部分も多くなるし、同性愛的な色合いも濃くなってくる。同時進行的に、吉屋信子は一般文芸への進出も志向していくことになって、『地の果まで』で一般文芸デビューする。以降は、人気作家・流行作家の道をたどっていくことになります。
柳ヶ瀬
『良人の貞操』とか『徳川の夫人たち』といった方向性ですね。
銀河
それをもって、少女小説からの系譜は途絶える。この、よくわからない謎の文体も途絶える(笑)
一同 (笑)
ティーヌ
こういう、お嬢様文体のようなスタイルが「吉屋信子的」なのかと思っていました。
柳ヶ瀬
いや、これはかなり異端ですよね。
橋本
この作品の異端さについては、嶽本野ばらの解説でも触れられてますね。
益岡
でも、こういう文体を「吉屋信子的」としてパロディするよね。僕は森奈津子さんが好きなので、森奈津子さんが、「吉屋信子的」にふるまうときって、こういう感じじゃない?
ティーヌ
「薔薇、白い薔薇……」みたいな(笑)
益岡
僕はむしろ、今回読んでみて「森先生、控えめにやられてらしたんだな」と思いました(笑)
吉屋信子文学を彩る
「肥大した自我」と「肉体的欲望」
橋本
さっき、そういう少女小説的な系譜は途絶えたというお話があったけれど、私の母は吉屋信子の大ファンだったのね。これを読んだとき、「母の秘密を覗いてしまった!」というような衝撃があったんだけれど(笑)
母は、ちょうど戦時中に女学校に通っていて、そのころの「Sの文化」を享受していたんだけれど、当時の女学校というのはエリート女性の園だったわけね。だから、母はずっとそのことを誇りにしていた。母は従妹とかなり濃密なS的関係を築いていたんだけれど、そういう関係にあったことを自慢している節もあった。
その頃に熱中していたのが吉屋信子の少女小説だったと聞いていて、それを踏まえると『屋根裏の二處女』は大正期の作品だから、吉屋信子の少女小説的な系譜というものは水脈としてずっと続いていたものなんじゃないかと思うのだけれど……
柳ヶ瀬
吉屋信子の文業としても、昭和期に一度、少女小説に戻るんですよね。『あの道この道』という作品が大ヒットする。
橋本
そうそう。その作品にはまってた話は聞いたことがある。
だから、作品の発表としては少なくなっても、女学校の中ではずっと読み継がれていたという現実はあったんだと思うんだよね。
柳ヶ瀬
私も『あの道この道』は読んだんですけど、大人の小説もやりながら、少女小説もやるというような流れになるきっかけというか、少女小説家としての復帰作というような位置づけですね。
銀河
吉屋信子には女性の恋人がいて、二人の往復書簡が残されているんですが、その中でも、パートナーから「大人の小説に行ったほうがいいんじゃないか」というようなアドバイスを受けている。吉屋信子の作家としての変遷には、割合、パートナーとの関係性というものが影響を与えている面もあるんですね。『屋根裏の二處女』を書いた時期というのも、当時のパートナーとの関係悪化と重なっていて、作品成立においては、そういう環境的な部分も影響を与えていたのではないかという分析もできると思います。
柳ヶ瀬
『屋根裏の二處女』には、直前の父の死が影響しているという見解もあります。
ティーヌ
私小説的な色合いが濃いということですかね。
柳ヶ瀬
私小説として読まれてきたという面は強いと思います。また、読書会が始まる前の雑談で作家が作品に織り込む「自我」についての言及があったと思うんですが……
酒井
それは私かな。吉屋信子の作品には、「肥大した自我」が感じられる、という……
柳ヶ瀬
私は、その「肥大した自我」の肯定を志向したのが『屋根裏の二處女』だったのではないかと思うんですよね。
橋本
「肥大した自我」という点でいうと、これは吉屋信子だけではない、同世代の女性作家にみられる傾向なのかな、と思うところがあって、私は博士論文で島田謹二という文学者を取り上げたんですが、彼があこがれていた関西の女性作家の作品に触れたことがあるんです。彼女の作品には吉屋信子作品にある「自我」の表出に似たものを感じる。特に、自分語りの過剰さというような面が共通していると思う。
関西には女性の書き手が育つ土壌があったように思うんだけれど、そういう書き手たちは、かなり高い教育を受けていて、その矜持もあった。そういうメンタリティが強く出ていると思うんだけど、そういう中で、女性たちがどう文学に接して、それを通して自己確立をどのように志向していったのか、それにとても興味がある。
柳ヶ瀬
こういう文体の異質さというか、インパクトというのは、国柄というか、土地柄も影響しているのかなと思うところがある。たとえばジェーン・オースティンの『高慢と偏見』なんか、吉屋信子のような、感傷的な文章を前面に押し出すような作風ではないですよね。この違いはどこから生まれるのだろう、やはり土地なのかな、と。
銀河
少女小説というのは、「令女界」のような専門誌があるわけですよね。そうした雑誌へ読者である女性たちが投稿するという、「雑誌投稿文化」から生まれてきている。吉屋信子的文体や自我の表出がみられる作品群というのに、一定の共通点があるのは、そういう事情もあるんじゃないでしょうか。雑誌の中では、「こういう風に書いたほうがいいですよ」といったような、レクチャーみたいなことも行われていました。女性がものを書く場、書いていい場、というものが限られていたという現実がある中で、そこで良しとされるフォーマットというものがかなりの権威を持っていたというのはあると思うんです。そこで育てられた文化というのがあると思う。
柳ヶ瀬
誰も刈ることのない芝が伸び伸びと育ったというか(笑)
銀河
投稿雑誌は女性同士の交流の場にもなっていたので、そこで女性の書き手たちのコミュニティができて、独自の作風が醸成されたということは言えると思う。その一方で、編集者が男性だったという事実もある。男性が求める女性作家像というか、少女作家像に沿うかたちで発展したというか、そういうバイアスもまた、あったのだろうと想像できます。
橋本
吉屋信子独自の文体というのはもちろん目に付くんだけど、『屋根裏の二處女』には海外文化の影響というものも大きいと思う。ドイツの詩が入ってきたり、ロマン・ロランへの言及があったり……当時の文学作品をよく読みこんでいるという印象を受ける。上田敏とか北原白秋、堀内大學の訳詩のインパクトも大きかった時代だと思うから、耽美的な文章への傾倒はそういうところからも来ているんじゃないでしょうか。
ティーヌ
少女小説の書き手になった女性たちは、きっと、ニーチェ全集とかドストエフスキイ全集とかが家にあるような人たちでしょうから、海外の影響というのは少なからずあるでしょうね。
橋本
この小説が発表されたのが一九一九年。歴史的にもいろいろなものが大きく動いた時期ですよね。
酒井
第一次大戦が終わって、大正デモクラシーが起こって……前年の一九一八年には米騒動があったり、学生運動団体である「新人会」が結成されたり……『屋根裏の二處女』が発表されたのは、そうした、市民運動というか、社会的なうねりのようなものが大きくなった時代にあたります。
橋本
時代が大きく変わったその時期の文学史にこの小説を置いてみると、この耽美的な雰囲気というのはとてもしっくりくる。
益岡
それは耽美な詩歌の影響ってこと? 日夏耿之介とか、そういうこと?
橋本
そうそう、まさにそう! ああいう耽美な作風をものすごく吸収していると思う。
銀河
散文詩的な印象というのはありますね。
柳ヶ瀬
少女小説の成立は、少女漫画に、文化の形成がすごく似ていると感じていて……男性が編集者として、検閲者として存在する中で、女性が書き手として活躍する、という……だから、少女漫画を読むように、少女たちは吉屋信子を消費していたように思います。
信子自身は、『花物語』には不完全燃焼感があったのではないかと思うんです。そうした部分が爆発したのが『屋根裏の二處女』なのかな、と。
橋本
このころの女学校の文化というのを知りたいよね。
柳ヶ瀬
知りたいですね。この小説でも、いくつか、文化的な背景がわかりづらいところがあって……私は最初の寮を退寮になった理由がわからなくて……
ティーヌ
あれはたぶん、成績不振だよね。それで何校も退学になっている。
橋本
そういう点でいえば、私はこの時代に女性の自分探しが主題になっているところがすごいと思う。充実している「個」ではなく、充実していない「個」、それも女性の「個」が大正時代に描かれているというのはすごいことだと思う。
ティーヌ
夏目漱石なんかが、日本文学が永遠に海外文学に勝てない理由として、「私たちはエス(自我)を書けない」ということを指摘して同時代文学を批判するんですけど、吉屋信子はこの作品で「自我」を書いているんですよね。
橋本
女性が内面を語る小説の系譜がいつから始まったのかというのは興味深いですよね。私小説の時代がやってきて男性たちが内面を語る小説は続々と現れてくるわけだけれど、女性にはあまり見られなかった。
でも、吉屋信子がここで自我を語っていたとすれば、女性が内面を語るという文化はいつから始まっていたのか……
ティーヌ
私がさっき「投稿文化」という指摘から連想したのは「和歌」なんですよね。「和歌」には、投稿の場というか、作品を投じて先生に添削してもらうというコミュニティが前提となって成立してきた歴史がある。その中には先生も女性で、女性だけで作歌するという環境もあるし、あったと思うんです。
橋本
先ほど少し触れた関西の女性文学者のコミュニティも和歌が基盤だったんです。でも、和歌というのは西洋的な「自我」を語る言葉を持たない文化だったと思う。それを吉屋信子は『屋根裏の二處女』で語っている。そんな作風をいざなったものは何だったのか。女性の書き手としては、先行者として岡本かの子がいるけれど……
柳ヶ瀬
岡本かの子とは仲が良かったみたいですね。
ティーヌ
和歌について補足すると、西洋的自我の表出というのとは違うかもしれないけれど、情感や物語性といったものを表現するという意味では、日本の文芸の中では詩に近い要素をもっている型式ではあるんですよね。だから、ある程度の影響というものはあったんじゃないかと思います。
橋本
プロレタリア文学の女性たちが出てくるのは、これよりだいぶ後だよね?
酒井
そうですね。個人的にはプロレタリア文学よりは、一九一一年創刊の「青鞜」の影響が大きいと思いますね。今ではフェミニズム誌のイメージが強いかもしれませんけど、もともとは女性の文芸誌といった位置づけで小説や詩の発表が中心だった。ものを書く女性たちのサロンのような役割を果たしていたはずですから、どこまでダイレクトに吉屋信子に影響を与えたかはわからないですけど、影響はあっただろうと思います。
銀河
「青鞜」の中で同性愛論争が巻き起こったこともありましたから、そういう点でも影響力は大きかったと思います。
S的な文化はもともと、日本の社会では許容されていたという実態がありました。これは家父長制に影響を及ぼさないものとして捉えられていたからです。結局、女は結婚して家に入る。Sは、あくまでそれまでの関係である、と。
でも、女性同性愛の果てに心中事件などが起こってきたりすると、これは社会の構造に影響を与える可能性が出てくるということですから、S的関係に対してもかなり厳しい目が向けられるようになる。
「青鞜」はそんな情勢の中、クラフト・エビングを紹介して女性同性愛を「変態性欲」として位置付ける。それには批判もあるわけですが、この作品はそんな渦中で書かれたということになります。
柳ヶ瀬
吉屋信子作品には「性的な欲望を持ってはいけない」というメッセージも垣間見られると思います。『屋根裏の二處女』の中にも「清い関係でいなければならない」という強い意志が感じられるシーンがある。
銀河
彼女の個人誌「黒薔薇」の中でも、「許される同性愛と許されない同性愛というものがある」というような発言があります。本人がそう信じていたのか、戦略的に書いていたのかはわからないけれど、当時の「青鞜」の議論を踏まえていたのではないかとは思っていて、「肉体的ではない、精神的な女性同士のつながり」ということを強調することで、女性同士の恋愛関係を弁護するような意図があったのではないかと個人的には解釈しています。
一方で『屋根裏の二處女』が完全にプラトニックな恋愛を描いているかといえば、全然、そうではない。肉体的な欲求も、直接的ではないけれど、描かれていると思う。
ティーヌ
私、主人公が寮で過ごす第一夜、蝋燭の火が燃え移って火事になりそうになるシーンは、「マスターベーションでもしてたのかな」と思って読んでた。
益岡 ……さすが、ちがいますね(笑)
※続きが気になる方は、文学フリマ東京等のイベントはもちろん、大阪阿倍野の「古書ますく堂」、神田神保町の「PASSAGE」などでも手に取って頂けます。
通販はこちら⇒https://ichizan1.booth.pm/items/1693873
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
