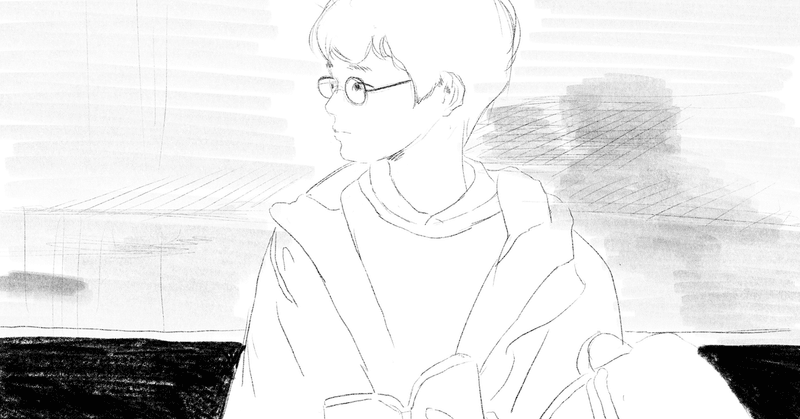
何度もセックスをして、わたしはやっと街で手を繋げた。
周りの目が気になるようになったわけではない。周りの目の存在に気づき始めていただけだった。
「これで、十分幸せです。」
全部、強がりでした。
むしろこの気持ちを早くすくい取ってほしかった。わたしがここにいるのだから、当然わたしはあなたにとって今一番近い存在なのだと確信していた。「誰にも譲らない」と思っていたわけではない。「せめてあと1分だけこうさせて」を、何万回と繰り返していただけ。
服を脱ぐ時も、体を洗う時も。
彼はすぐそばにいた、いてくれた。
わたしが好きそうな服を選んでくれた。
わたしが好きそうな本を選んでくれた。
わたしが好きそうな気持ちを選んでくれた。
積み上げていくのが恋だとしたら、わたしのこれは何になってしまうのだろう。進んでいくのが恋だとしたら、わたしのこれは何になってしまうのだろう。駅の反対側のホームに急行電車が来れば、それに表情を変えずに乗り換えるような女の子にはなりたくなかった。なんでもわかっているような顔が苦手だった。でも今も昔も、よく彼はわたしのことならなんでもわかっているような顔をする。わたしはひとつひとつの駅に止まらなければいけないような人間なのに、どうしてずっと隣にいてくれるのだろう。息継ぎのタイミングを合わせてくれた。どうにでも取れるように笑う、彼の全てが欲しかった。
彼のことなら何でも知っておきたいと思っていた。ただ、ずっとわかっていたくない。彼の積み上げている人生の中の小さな動きに合わせてわたしの心も動かしたかった。「そんなところもあるのね」と呟く。素直に咲く花にはなれないけれど、わたしなりの声で木漏れ日になりたい。
「もっと、やることがあるんじゃない。」
鏡の前で何度も練習を重ねてきた表情でわたしは言う。「一番になりたい」と思っていたわけではない。「もう、わたしにしちゃいなよ」と、少し思っていただけ。
◇
刺激を忘れさせてくれた。
彼と、わたしの生活。
わたしは、女の子ではなかった。優しく、毎日のように笑顔で過ごしている彼も、薄暗い部屋に入れば少しばかり悶えるような声を零す日々。
休日の昼下がり、わたしは本を読みながら彼に聞いた。
「最近、恋人には会っていますか?」
その時のわたしの気持ちは、少しの期待と悪戯だった。けれど彼は思ったよりも真面目そうな顔で言う。
「あまり、会っていないですね。忙しいみたいです、最近は。」
それを聞いて、わたしは下唇を噛んだ。
笑顔になってはいけない。
このままいけば、わたしの元へ来てくれるかもしれない、と。わたしの淡い心は、目を凝らせば少し黒くなっていた。
彼には女性の恋人がいて、最近は結婚をすることまで考えていたそう。ただ近頃どうも様子がおかしい。これほどまでに近くにいるのに、何も深く聞くことが出来ない自分に頭を抱えた。「自分が彼の支えになりたい」なんて、わたしにとっては綺麗事だったのだ。
「しをりさんは、最近どうですか?」
彼も、本を読みながらわたしに聞く。質問の意図はわからなかった。それでもせめて、素直に咲こうと思ったわたしは「あなたが好きなままですよ」とだけ呟いた。
彼のことを、わたしは愛していた。
一緒であれば、どうなってもいいと思っている。過去も現在も未来も、隣に居続けることを望んでいた。わたしはただの同性愛者であり、ただの人間だった。
それに応えるかのように、彼は最近わたしとセックスをしてくれるようになった。仕掛けたのはわたしの方ではあった。だとしても受け入れた彼のせいにしているわたしは、どうにも狡い。
そして「会いたい」と言えば、猫のような愛嬌でわたしの家に来てくれるようになった。その時お酒とアイスをいつも買ってくる彼は、もうわたしの好みだって知り尽くしている秀才だった。
◇
午後8時。彼とわたしは夜ごはんを食べるため、いつものように街へ出かける。
わたしの住んでいる街は静かだった。それでも少し足を伸ばせば街灯が鬱陶しく光る。居酒屋もそれなりに多いそこは、わたしたちが退屈になるようには出来ていなかった。
仕事終わりであろう人で賑わう近所のスーパーがいつもの光景になった。隣には彼がいる、愛する人がいるというこの日常を、どこか当たり前のように感じている自分が怖い。まるで同棲しているかのような笑顔で人参やじゃがいもを手に取る彼が神秘的だった。
その日家で作るのはカレーになった。
お互い料理は得意ではないが、見様見真似で作るごはんが幸福そのものだった。
「"いつか"もっとお洒落な料理にも挑戦してみたいですね。」
わたしの顔も見ずに彼は言った。"いつか"という言葉がわたしを今も惑わしている。それは"わたしと"叶えようとしてくれている言葉なのか、ずっとこれからも隣に居てくれるからこその"いつか"なのか。そんな気持ちもその場で表現出来ずにわたしはルーを手に取る。聞かなくとも知っている、ふたりが食べるのは決まって辛口だった。
わたしが思っているだけかもしれない。本当にわたしたちは恋人同士みたいだった。周りの人たちは、わたしたちに目もくれず、自分の買い物をそれぞれ済ましている。ただ"男ふたり"が、今からカレーを作ろうとでも言いたげな食材をカゴに入れている。こんなにもわかりやすく幸せをカゴに入れられる日が来るとは想像もしていなかった。
「他に、必要なものってないですかね。」
「まあ、なかったらその時はその時です。」
そんな会話を、もう自然と出来るようになった。思い出しただけで今のわたしは体が震える。全ての台詞が、頭の中で再生されていた。記憶力が乏しいはずのわたしも、彼とのことであれば何だって覚えていられた。
鬱陶しい光が終わる前。
わたしの家まではまだ距離があった。彼が何か言いたげな顔をしている。いつもであればなんでもわかっているかのような表情をする彼の様子がおかしかった。当たり前に慣れていたわたしは、そこで自分の胸の高鳴りにも気づく。その瞬間、彼は言った。
「ここからしをりさんの家まで、手を繋ぎませんか。」
◇
違う世界に飛ばされてしまった。
自分がこの地で生きていることを、うまく整理出来なかった。彼のことを、隅から隅まで想像した。言葉の本心だっていまだにわからない。デートをした日も、セックスをした帰り道も。彼はわたしと街で手を繋いでくれることはなかった。
周りにはそれなりに人がいて、各々の日常を送っている。夜道でも明るい、誰のことも逃さずに照らす街灯があるからこそ、"意味"があった。
誰も見ていない場所でなら、セックスが出来た。そのことを他に話す人なんていない。わたしが働いている職場でだって言うこともなければ、そんな話があるとも周りは思っていないだろう。
「彼女いないんですか?」と言う質問に「いないよ」とだけ答える詰まらない人間でいい。わたしは日々彼を想い、こうして手を繋いで隣を歩いている。
「あなたの恋人になれますか?」
本当は、そう聞いてしまいたかった。
でもそれは反則のようで。自分でもどこでどう線引きをしているか定かではない。ただその時は言うべきではないと思った。今、この瞬間。彼と街で手を繋げるかもしれない奇跡に、唾を飲み込んでいた。
今まで、いくら彼の手の甲にわたしの手の甲を当てようとも気づいてくれなかった。「手を繋ぎたい」と、たったその一言を仕舞っていた。
わたしにとって、誰も見ていない部屋でセックスをするよりも、街でふたり、周りの人がいる中で手を繋ぐことの方がよっぽどハードルが高くて、深く内臓の奥から押し上げられるような幸福だった。
◇
人は、恋をしている。
誰しもがその気持ちを眠らせている気がした。わたしもそのひとりであり、彼のそのひとり。
わたしの恋は、彼がいなくなったとしても終わることはないだろう。愛する人の吐息がかかる距離にいたい。
彼と手を繋いで歩いた、その時間はきっと1分もなかったかもしれない。ただ、わたしにとっては永遠に手に残る感触となった。服を脱ぐ時も、体を洗う時も。自分の体温を超える熱さがわたしの心を包んでいる。
手を繋げたその日、わたしは"やっぱり"泣いてしまって。家に着いた頃にはカレーを作ることを忘れていた。ずっと近くで感じていたくて、"やっぱり"わたしは部屋で彼に抱きついてしまった。
「泣いていいですよ。」
「もう、泣いています。」
彼はまたなんでもわかっているような表情に戻っていて。そんな彼が全て欲しくなったわたしは、彼とまた狂ったようにセックスをした。
そして朝になり、いつものように身支度を済ませる。
「いってきます。」
そうふたりで声を合わせて玄関を開けた。
まだ人の少ない午前4時。
わたしたちは手を繋いで駅へ向かった。
わたしは改札まで見送り、彼は始発に乗って帰っていった。
そして幸せな黒い線を目の下に拵えたまま。なんでもわかっているかのような顔をして職場へとわたしは向かったのである。
書き続ける勇気になっています。
