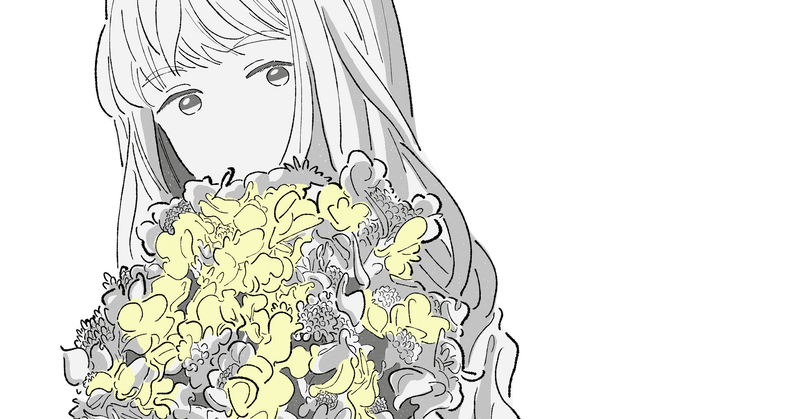
突然申し訳ないけれど、わたしは幸せものである
「僕の気持ちです」
そう言って彼はわたしにショートケーキの苺をくれる。ああ、たったこれだけでいい。
幼い頃、教室で日記を書いている女の子がいた。「日記なんて書いて、何になるのだろう」と、思いすらしなかった。「何か書いてるなあ」くらい、わたしの体は上の空だった。
窮屈な部屋に、ふたり。
わたしは恋人である彼と、同棲している。とても、小さな空間だ。27歳の男性と、そのふたつ歳下の、彼。
何も起きない、何も変わらない。ただ不思議と、ループしているような感覚はない。いつまでも保ちたい肌、いつまでも保とうとする体型、いつまでも保てる関係があって。
最近、彼はずっと家にいる。
フリーランスとして働いている彼は、このご時世で仕事が殆どなくなってしまったそうだ。だからといって、すぐに食べるものに困ったり、住む家がなくなってしまうわけではない。贅沢をあまりしないから、わたしたちには僅かだが、貯金がある。
けれどわたしたちは、贅沢をしている。幸せに生きる贅沢だ。目を凝らしても見えないもの、掴み取ることのできないもの。それこそ、とるにたらないものがあって。
本を読むのがわたしも彼も好きだった。
ただ別に、沢山の本を紹介したり、それについてためになるような文章は書けなかった。技術云々というより、自信がないのだ。自分の抱いた感情が間違っていると思ってしまう。
「しをりさん、今日も書くんですね」
彼が突然、そんな言葉を溢す。今更、何を言っているのか。わたしはあなたの隣でどれほどの時間、書いてきたと思っている。もうすぐここで毎日書く生活も400日になろうとしている。数えたことはないけれど、彼との恋の話が、大半だ。
気づかなかったのかもしれない。
彼は毎日、忙しかった。それはきっと、わたしも同じように。
仕事柄、わたしは毎朝4時に起きて職場に向かっている。かわって彼はと言うと、起きるのはいつも昼前くらい。出勤がわたしは早い分、夕方には帰ってこれる。そして彼はと言うと、帰りはいつも夜遅かった。
一緒に住んでいるのに、一緒に住んでいないみたいだなあ、と。そんなありきたりなことを思っていた。ただそれで、絶望することもなかった。朝起きたら隣に彼の寝顔がほころんでいる。夜、先に布団の中にいるわたしを少しだけ押して、もぞもぞと体温が入ってくる。小さな、大切な空間。目を開けることはないけれど、抱き寄せられる腕を夢の中で見た気がした。
「ただいま」
「おかえり」
きちんと、鼓膜が揺れた。目の前に人がいて、言葉を渡せば、言葉をまた渡してくれる。
「ああ、たったこれだけでいい」
そんな瞬間を積み重ねることができる、わたしは幸せものだった。
◇
彼が、わたしのパソコンを覗きこんでくる。
そんなことは今まであまりなかった。仕事から帰った後も、休日も、構わずわたしはこうしてエッセイを書いている。もちろん、彼も家にいる時、何も会話をしないわけではない。ただ彼に、気をつかわせてしまっていたのかもしれない。
「そんなことないです」
これは、彼が打ち込んだものだ。
わたしは彼に、ここでエッセイを毎日書いていることは伝えているし、このnoteのアカウントも伝えている。そもそもわたしが彼と知り合ったきっかけもSNSだった。『いちとせしをり』を誰よりも知っているのは、紛れもなく彼なのだろう。
「書きませんか?一緒に」
わたしは聞いた。彼が、愛おしいから。
ずっとわたしばかりが彼のことを書いていたから。彼のことをずっと見てきて、彼のことが好きで好きで堪らなくて何度も、泣いた。「ああ、たったこれだけでいい」に辿り着くために、わたしは死に物狂いで求めていた。
わたしは、本が好き。
その中でわたしは、新しい本をとにかく手に取り、読む人間ではない。一冊、気に入った本があればそれを、何十、何百回と読む。それこそ出てくる文章、言葉を宙で描けるくらいに。
わたしは特に、江國香織さんの書く文章が好きだ。
その中でずっと読んできた『とるにたらないものもの』という本がある。
この本には、とるにたらないけれど、欠かせないもの。気になるもの。愛おしいもの。忘れられないものが書かれている。
それは例えば、『輪ゴム』や『黄色』、『ケーキ』など、とるにたらないような、身近にある有形無形のものたちがあって。それを江國さんの目で、簡潔な言葉として綴られている。わたしの好きな、エッセイ集だ。
わたしがこれを何度も読んでいることを、彼も知っていた。「とるにたらないものものを、書こうよ」と言うと、それだけで彼は上機嫌に目を細めていた。
壮大な部屋で、ふたり。
まずわたしは、自分の好きなものを、書く。
『朝』
一生、忘れることができないであろう失恋は、朝だった。
「おはようございます」
声を細め、わたしは彼の耳を噛む。どうせ起きているのに、寝たふりが上手だった。
すれ違う。いつもそうだ。これだから朝はやめられない。プロポーズをするのであれば、朝と決めている。彼と過ごしているといつも思う、早く朝が来てほしい、と。
まだ彼とお付き合いをする前、わたしは夜中ひとり、"淋しい"と遊んでいた。「起きてますか?」と、彼のSNSの呟きを確認してから送る。すると彼は、すぐに電話をかけてきた。「どうしましたか?」と。
ああ、本当は電話するほどのことじゃないのに。彼がそんな手段を使うから、恥ずかしかった。「ちょっと、声が聴きたくて」と言えなくなってしまった。だってもうそこに、あなたがいるから。
そこから。深夜にもかかわらずラフな格好でふたり、ファミレスに行った。ずっと、その頃から好きだった。
他愛もない話をした。彼の話は別に面白いわけじゃない。こんなことを書いたら怒られてしまいそう。でもそれくらい、幸せだった。
あっという間に朝が来る。
食べられそうな光だった。
「また誘ってもいいですか?」を、零す。
彼とは友達になりたくなかった。その頃からわたしは、彼と手を繋ぐことを夢見ていた。今、わたしが「したい」と言えば、それだけで唇は重なる。それはいつも朝に、叶った。プロポーズをするのであれば朝と決めているのは、彼の寝起きの瞳が特別に、やさしいからだ。
◇
「ねえ、今度はあなたの番です」
わたしが言うと、彼は嬉々としている。
"もの"は、わたしが選んだ。
「『結婚』は、どうですか?」
真剣な表情をする。「それって、とるにたらないものなんですか?」と彼が言うから、頬が熱かった。
「いいんです」と、渡した。
彼は、受け取る。
.
.
『結婚』
僕が君とできないもの。
でも君は、僕と「結婚したい」と言って泣いていた。多分だけどそれを考えて生きるのが僕の結婚なのだと思う。
僕には恋人がいる。とても、女の子だと思う。彼女の似合う服は、僕が一番に見たい。彼女が笑う姿は、僕が一番に見たい。彼女は泣き虫だった。でも本当はその姿を見るのは僕だけで十分なのだろう。
君と朝。手を繋いで歩く道。
「ああ、たったこれだけでいい」と嘘偽りなく僕も思っていました。だからこれからもしてください。僕と君だからできることは結婚と、それ以外にもあふれている。
◇
突然申し訳ないけれど、わたしは幸せものである。
『性別』
それはわたしにとって、あってないようなもの。でもこれがないと、わたしの生きる意味は淡くなってしまう。
わたしは女の子になりたかった。今のわたしは鏡の前で項垂れる。苦しくて、あまり考えないようにしている。青い化粧室に、何度入っただろう。小学校の頃、掃除で"赤い方"に入った時の気持ちの正体に、20年経って気づいている。
愛していた。男性である彼のことを。ただもし、彼が女性だったとしてもわたしは彼のことを好きになっていたと思う。それは世間で言うところの、"真っ当な"関係として。
朝が来て、結婚があって。
どれも、大切だ。失いたくないものだ。
とるにたらないけれど、欠かせないものだ。
ワンピースを着て彼と手を繋いで歩いた日。時間は、夜だった。人工的な光が眩しい。星の説明ができないまま、わたしは彼と幸せになりたい。もっと、もっと。そうやって欲深くなるのが人間なのだろうか。
朝が残されている。でも朝も食べてしまったとしたら、わたしはそれ以上の味を感じられなくなってしまう。「もっと、自由に生きたいな」って。その言葉が淡くなるほど、わたしは彼の隣で色濃く咲く、雌しべになりたい。
◇
あなたが思ったことを、大切にしてほしい。
日常と生活があって。自由にそれを生きているのが自分だ。エッセイが、好きだ。もう、何度も言っている。わたしにとってこれが、思ったことを正解にできる瞬間。
今の世の中は、わたしが思っている以上に大変なことになっているのだろう。自分のすべきことなんて、大してわかっていない。自分の大切な人を守るため、誰かの大切な人を守るために、部屋の中で書いている。手を洗って、換気をして。また彼と、あの頃みたいに電話したいとたまに思う。SNSを見れば、必死に生きている人が沢山いた。
すーっと、深呼吸をした。
賢くない。でもわたしたちは今一度、とるにたらないものと生きていることを思い出してほしい。
よかったら、わたしと一緒にとるにたらないものを書きませんか。別に、発表しなくてもいい。宙に描くだけでもいい。大切なものほど身近にあるというのは、本当のことだろう。
わたしはこれからもずっと、幸せもの"もの"でいたい。そして、明日になったら恥ずかしくなるようなことを、一生書いていたいと、想う。
書き続ける勇気になっています。
