冒頭の30%と書き終えた後の調整が難しい
読書論の本をあいかわらずしこしこ書いている。全体の進捗からいえば25%書いたところか。思うのだけど、比較的長期のプロジェクトにおいて「25%進んだ」というのは本当にすごいことだ。僕が書いているような書評記事でいうと、一番難しいのは書き出し、冒頭の30%ぐらいが一番むずかしい。
3000文字の書評なら冒頭の30%は1000文字を書くまでがあたる。僕が最近書いた『忘却の効用』の書評記事でいえばだいたい下記の部分までだ。
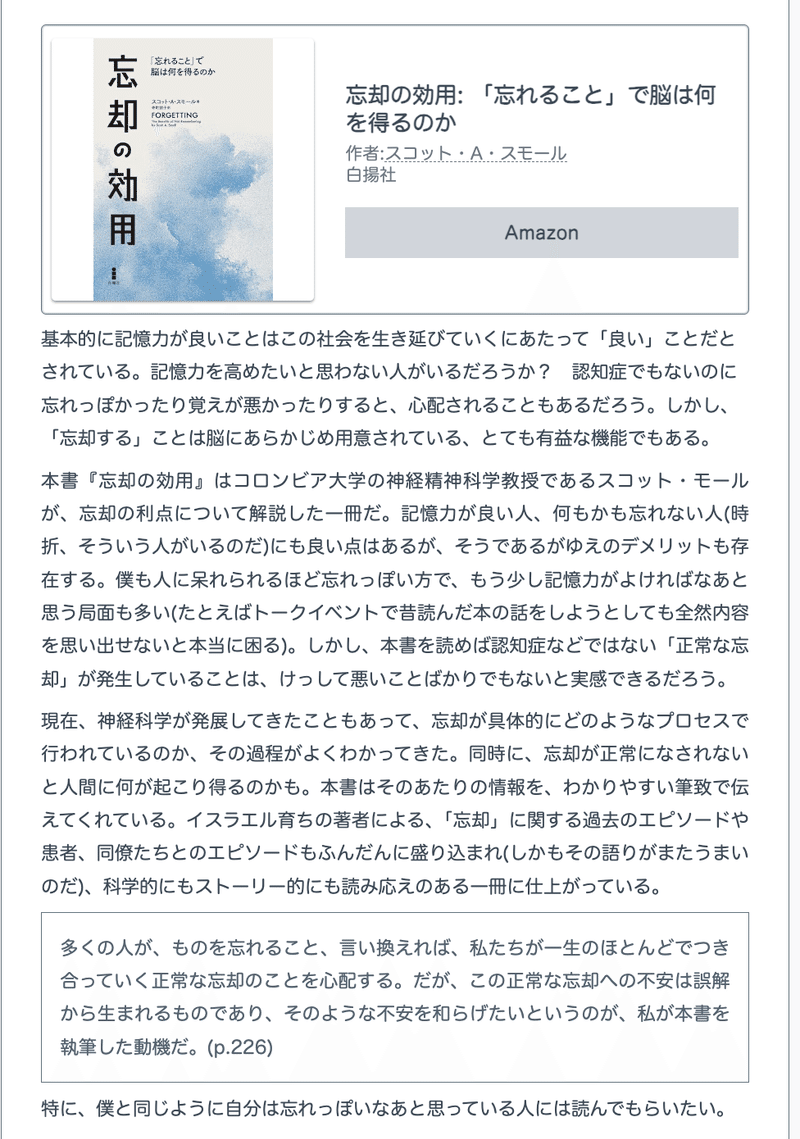
ここは記事の冒頭にあたるから読者の注意をひきつけないといけないし、そこで作った前提に興味をもち、本論に進んでもらわなければいけない。これは800文字の書評でも1600文字の書評でも同じだ。冒頭でしっかりとした前提を築き上げることができると、あとはその土台に事例を積み上げていく作業ともいえるから、そこからは比較的気楽に作業を進めることができる。
全体の30%も書けば書いている側にも全体を通してどのような論調、トーンの本になるかが想像できるようになるから、気分的にも相当ラクだ。逆にいうと全体の50%も書いたらそれがどのような本になるかはほとんど確定しているから、考えることは減り、自由度は失われていくといえる。
そういう意味でいうと『SF超入門』を書く工程はそれにはあてはまらず一冊一冊個別の文章を積み上げていく作業だったから、短距離走を50回以上繰り返すような苦しさがあった。書いても書いても後半に書く内容は何も確定しない。ただちゃんと読んで書いていくしかない。書く側としてはやることがシンプルでわかりやすい利点はあるが、体力的には著しく疲弊した。
プログラムでも同じだ──と書こうと思ったけれど、長期間開発に時間がかかるプログラムの場合の「25〜30%」進捗の線をどこに引くのかで変わってくるかな感がある。要件定義がしっかりしていて各APIの必要パラメータとレスポンスがきっかり決まって絶対にそれが変わらないのであれば、要件定義が終わった時点で作業はほぼ終わっているともいえる。
一方、ユーザーと調整しながら最終的な形を作り込んでいくWebサイトだったり、自社サービスで作りながらいろんなユーザーにテストしてもらって利便性を作り込んでいくタイプの構築なら、文章と同じように「実装しはじめて30%ぐらいさわれる形になる」までが一番むずかしいかもしれない。
とはいえ、それとは別に最終的に「細かく調整する」段階に二番目のむずかしさというか苦しいタイミングがくるのだが。冒頭の30%は「一度書き終わるまで」までで一番むずかしい瞬間で、「一度書き上げたあとにそれを全体として矛盾なく美しい形に磨き上げる」工程は書き終えた後の一番むずかしい、というか苦しい瞬間といえるのかもしれない。後者の苦しさは作業自体はいくらでも進められるが、終わりを自分で決めないといけないことからくる苦しさだけど。今回はここでじっくりと時間を使いたいな。
本の原稿。現在の進捗(文字数) 35393/140000 約25%
前回からの進捗⇛4%
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
