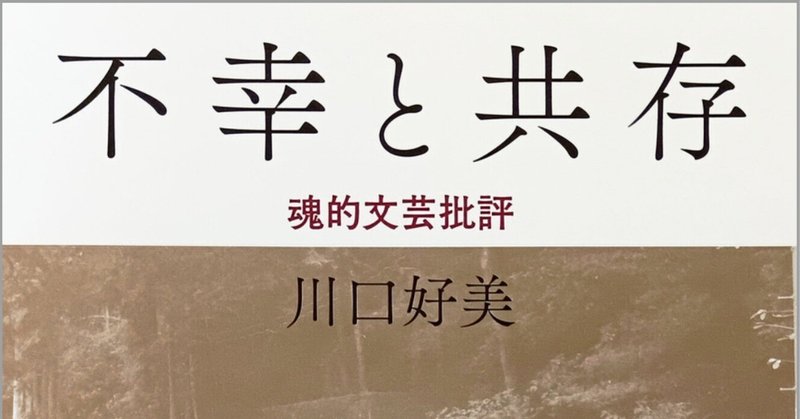
川口好美 第一批評集 『不幸と共存 魂的文芸批評』 後記
このたび(2023年12月)、川口好美著『不幸と共存 魂的文芸批評』を〈対抗言論叢書4〉として刊行することになりました。
この叢書は、「反ヘイト」のための言論・文芸雑誌として、すでに3号までを刊行ずみの『対抗言論』誌(2019年末〜)の関連叢書です。同誌の編集委員や、理念を共有する関係者のみなさんによる著作を収めるシリーズとしてスタートしました。
川口好美氏は、大学在学中に室井光広氏や山城むつみ氏に触発されて文芸批評を志し、2016年に登龍門である群像新人評論賞(第60回)を受賞した気鋭の書き手です。その記念すべき最初の評論集が本書、『不幸と共存』です。
群像新人評論賞受賞作であるシモーヌ・ヴェイユ論をはじめ、未発表の小林秀雄論、『対抗言論』誌に掲載された差別論や、この30年以上にわたってある種の文学的試みの極北としてあった室井光広氏へのオマージュ、そして掉尾を飾る最新の江藤淳論など、タマシイのこもった強力なテキスト群を収録。
通読すれば、なぜこの書が〈自己批評〉として書かれなければならなかったかがわかるはず。
文学が、たとえこの世の限りない不幸の確認であったとしても、真理の追求と、共存のための希望でもありうることを、本書は指し示しています。
《テクストの熟読を通じて〈私〉を問い、書くことの暴力のただなかで〈私〉を外部へ、他者へと開いていくこと——。小林秀雄、中野重治、秋山駿、江藤淳ら日本文芸批評の潜勢力を受け継ぎ、室井光広のてんでんこな魂とともに更新される文学的革命と連帯のミッション。シモーヌ・ヴェイユ論で群像新人評論賞を受賞した気鋭の批評家、待望の第一評論集!》
https://www.h-up.com/books/isbn978-4-588-46024-1.html
後 記
江藤淳についてのノートを長い “あとがき” を記すような心づもりで書いたので、ここでは簡単な事実確認のみにとどめたい。
本書には、商業誌デビューから現在までに書いた文章のほとんどが、おおよそ時系列で並べられている。一読してくれた方は〈こいつは7年という短くない期間、同じようなことばかり飽きもせず考えてきたのだな〉という感想をお持ちになるだろう。まったく同感で、自分自身呆れている。
もし評論集を出すことになったら、山城むつみの『文学のプログラム』や大澤信亮の『神的批評』のようなすっきりした構成の本にしようかな、とぼんやり思ってはいた。だがどうも本腰を入れて取り組む気になれなかった。本なんか出ても出なくても、これからも批評を書いていくことにかわりはないのだから……というのが正直なところだった。どの文章にもその都度必死に取り組んできたことはたしかだが、それらを単著としてまとめるために乗り越えなければならない物理的・心理的ハードルに立ち向かう野心がまったく湧かなかった。
気が変わったのは雑誌『対抗言論』の第3号に編集委員としてかかわってからである。ざっくり言うと、現在の自分の本領はいわゆる評論集のシンプルさではなく、むしろ雑誌的な雑多さにおいて——言い換えれば、超時間的な堂々とした面構えの本ではなく、不安定で流動的な時事的、時局的要素が混在するような本で、よりよく発揮されるのではないかと感じた。そういう本であれば作ってもいいとようやく思えたのである。この心変わりの象徴的な痕跡として、第三部「差別への問い(Ⅰ)」から「(Ⅱ)」への自己批判的な跳躍があったのだと、今になって思う。この本のさいごに江藤淳論が必要であるということもそのときはっきりしたのだった。
これを雑誌的と表現すべきかよくわからないのだが、本書は書き手のライフヒストリーとしても読むことができる。いわば、批評当事者(?)による記録文書【ドキュメント】である。第一部には北海道の上富良野町と斜里町で書いた論考とエッセイを収めている。第三部のテクストはすべて静岡県の川根本町で書いたものだ。いずれの土地も、自分の出生とは無縁の、偶然流れ着いた辺境的な場所である。そして両者のあいだ、第二部には、学生時代に文学を教えてくれた作家・室井光広氏の死が契機になって書かれた文章が置かれている。氏の死去と、北海道から静岡への引っ越しのタイミングが重なった。それは、批評家としての、人間としての、極私的な変化の時期でもあった。くどくどと言い募っても仕方ないが、一人の人間の死は、どんな死であれ、生き延びてしまった人間、生き延びようとする人間へのギフトになりうるのだ。
さてつぎはわかりやすく雑誌的だが、第三部には、商業文芸誌上に発表された他人のテクストを論じた時評と、そこから派生した書評と論争文を収録した。このような構成のアイデアが浮上したのは、雑誌作りに携り、目の前の出来事に批判的・論争的に介入することの難しさと必要さを痛感する過程においてだった。批判なんて、適当な言いっぱなし言われっぱなしでかまわない。どうせみんな一週間もすれば何事もなかったかのように忘れ、別の話題に飛び移ってしまうのだから。……こういう時間の流れを堰き止めるのはもはや不可能かもしれないが、しかし抗うべきだろう。すくなくとも批評にかかわる者は、自らの言葉を簡単には抹消出来ないものとして残すことで、言葉への責任を負いつづけるべきだ。そして当たり前だが論争は相手がいなければ成り立たない。時評に応答してくれた住本麻子氏にあらためて感謝する。また本書には収録しなかったが、今年は小峰ひずみ氏とのあいだでも論争があった。そちらもなんらかのかたちで残したいと考えている。真面目な議論は大事なので、これからも続けていく。
本書はまた日本文芸批評についての本でもある。意図していたわけではないが、事実としてそうなっている。文芸批評の系譜を、その魂的な問いの根底を、いささかでも感じ取ってもらえたら嬉しい。〈自分以外、同世代に文芸批評を書く奇特な人間はいないだろうし、たぶん今後も現われないだろう〉という予感に包まれながら日々生きている者として、この本を書いたことを素直に誇りに思う。だが、批判的な緊張関係を保ちながら文芸批評の蓄積を引き受け、それを最低の鞍部で越えようとするのではなく、その最高度のポテンシャルを身をもって窮め尽くし、生き切る、生かし切る——そのミッションにけして終わりはないだろう。
感謝すべき人は多いが、ここでは杉田俊介氏、室井陽子氏の名前のみ記し、特別な感謝を捧げたい。お二人の存在がなければこの本はなかった。
2023年11月
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
