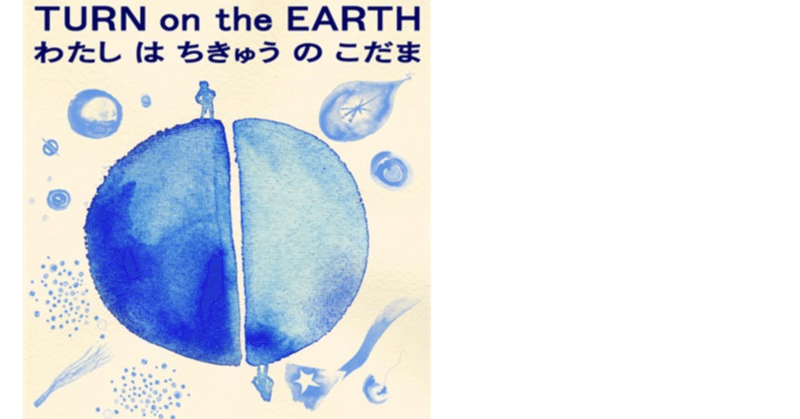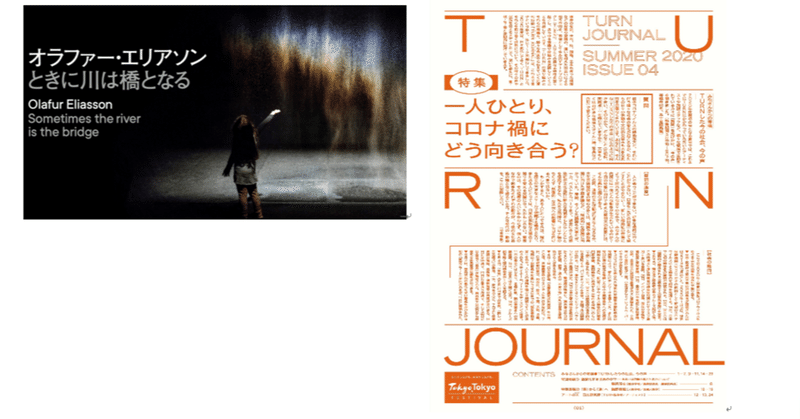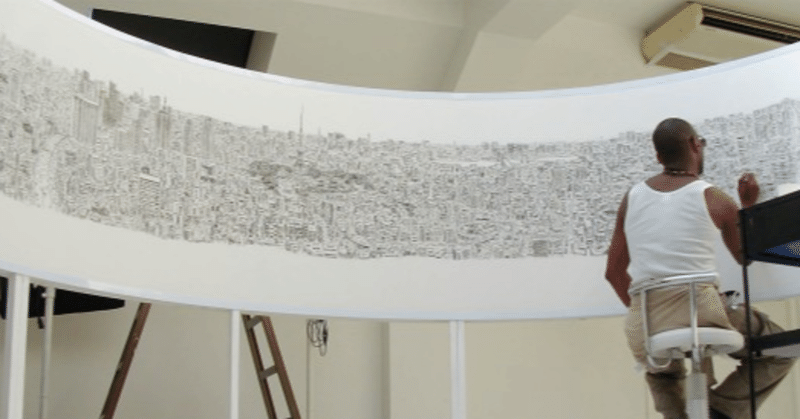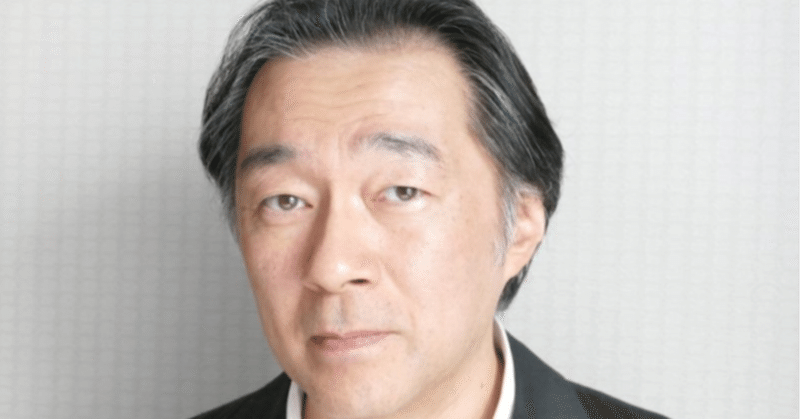2020年8月の記事一覧
『アートとは、違う感性、多様な感性のプラットフォームである』
オラファー・エリアソンのアートの定義が好きだ―『アートとは、違う感性、多様な感性のプラットフォームである。アートそのものには力がないが、プラットフォームでの「自分の声が尊重されている」という身体的な実感が「私の行動には意味がある」という思いにつながっていく。社会的なつながりが力となる。(NHK日曜美術館2020.8.16/ときに川は橋となる・東京都現代美術館~2020.9.27)』・・・そこから
もっとみる自閉症の人はなぜ電車が好きなのか(奥平俊六さんの著書より)
奥平俊六さんは、自閉症児の託児に数多く携わり、これまでに学童期までの自閉症児をのべ1000人以上みてきた日本絵画史の専門家である。そして二男をレイルマン・ダダとよび「電車好きの明るい自閉症児」と紹介している。奥平さんは、「自閉症の人は電車をみる前から、電車が好きなのである」という。それはなぜか。自閉症の特性と合わせて以下のように論じている。(「自閉症の人はなぜ電車が好きなのか」は、「芸術と福祉―
もっとみるコロナ禍で、ひきこもりの専門医斎藤環が探る「多様な感受性、認容性に配慮した繊細さ」
精神科医斎藤環が、ひきこもりの専門家ならではの視点で、コロナ禍で生まれた「オンライン」という距離、暴走する正義などを社会が新たに体験している今こそ「個人がもつ感受性、認容性は多様であり、それを・・・もっと繊細な配慮ができる社会に向けて回復していく手順」を探るチャンスだ、として以下のように述べている。(2020年8月1日毎日新聞)
【視点1 対面に潜む暴力。許容度には差がある】
オンラインでの