
向井秀徳、「らんど」を語る(6)
ZAZEN BOYSの12年ぶりとなるアルバム『らんど』がリリースされたのは、2024年1月のことだった。アルバムのリリースを前に、SPACE SHOWER TVでZAZEN BOYSの特集番組が放送されることになり、僕はインタビュアーをつとめることになった。それが今回の企画の始まりだった。
番組のインタビューは2時間に及んだ。ただし、2時間という時間は、すべてを聞ききるのはあまりにも短かった。『らんど』というアルバムに、向井秀徳は何を込めたのか。向井秀徳は今、何を感じているのか。それを言葉でつかまえておきたいと思って、全国各地でインタビューを収録することに決めたのだった。
10月某日。東京は渋谷区・笹塚にあるMATSURI STUIDOにて、最後のインタビュー収録をおこなった。武道館という大きな舞台を目前に控えた今、MATSURI STUIDOの地下室で向井秀徳は何を感じているのか、存分に語ってもらった。ここに書き綴るのは、そんな旅の記録であり、対話の記録である。(聞き手・構成 橋本倫史)
――向井さんがZAZEN BOYSを結成されたのは2003年ですけど、このMATSURI STUDIOも同じ年に借りたんですか?
向井 いや、ここを借りたのは2002年ですね。当時、私が住んでいたところで、夜中や朝方にギターを弾いたりしてたら、隣部屋から苦情が出ましてね。ある日、内容証明が送られてきたんです。「これ以上耐えられません」と。「これ以上騒がしくするなら訴えます」と。これはまずい、ここからエスケープしなきゃいけないということになったんですね。自部屋とは別に、自在に音が出せる場所がないかな、と。それで、当時ナンバーガールが普段からリハーサルしているスタジオが笹塚にあったわけよ。
――それも笹塚だったんですね。
向井 そう。この笹塚あたりでそういう場所ねえかなって不動産屋に問い合わせたら、「ちょうど今、電気工事の会社が事務所を閉めることになって、そこの地下室が空いてます」と。それがちょうど、ナンバーガールが解散するタイミングと重なったんですね。ここに住んでるわけじゃないんだけど、このMATSURI STUDIOという場所を確保できて、それからずっとここを拠点にやってますけども。
――じゃあ、最初の段階ではしっかりスタジオとして使っていく拠点を構えたというより、とにかく自由に音を鳴らせる場所を借りた、という感じだったんですね。
向井 そうやね。あの、聴力がね、他の人とちょっと違ってるのかもしれんね。
――聴力?
向井 普段スピーカーから音楽を聴くにしても、たぶん音がでかいんだ。ヘッドホンとかイヤホンとかじゃなくて、音を体感したいわけよ。また、体感できるようなオーディオ・システムを作ってるもんだから、一般の住宅では迷惑なんですね。自分としては、マイナス20dBぐらいで鳴らしてるつもりやけど、むちゃくちゃ響いてるわけですよ。こっちも低音が強烈に出る音楽を聴いているもんだから、隣の人は耐えきれなかったんでしょう。やっぱりそれは、自分で環境を整えなきゃいけないんだということで、ここを借りたわけです。このMATSURI STUDIOでも、そんな夜中には鳴らしたりはしてないんだけどね。このビルの上には、その工事会社の家族の人たちの住まいになってるから。でも、当初から理解を示してくださって、「音楽作業をしたいです」と言ったら、承諾をもらって借りることになったんですけど。それから22年になりますね。
「ふいに思いついたフレーズ、もしくはずっと頭ン中を彷徨っているフレーズの集合体」
――ZAZEN BOYSを結成されたばかりの頃だと、MVもここで撮影されてましたね。
向井 まさにそうです。「USODARAKE」とかね。
――あるいは、「感覚的にNG」という曲だと、地下室で過ごしている人の感覚が歌われてもいます。このMATSURI STUDIOという場所があることは、向井さんがどういう表現をするかってことにも大きく影響しているんでしょうか?
向井 もちろん、あるよね。歌詞を書く場所は一体どこなのか――それはもう、人それぞれ、多種多様だと思います。私の場合は、書こうと思って歌詞を書くときもあるんだけど、フレーズが浮かび上がって、それをノートに書き留めておくんですね。それを全部並べてみたら、自分の中でしっくりくる、と。そこで何を言っているのか、ひょっとしたら自分でもわかってないかもしれないけど、筋が通る気がするわけよ。
――ふいに浮かび上がったフレーズを、あとから並べてみたら、しっくりくる、と。
向井 思いつきの言葉にリアリティを求める、と言いましょうか。人によっては、歌詞を書くために旅に出る人もいると思うんですね。旅先で見た風景をスケッチするように、歌詞を書く。ナンバーガールのときだと、演奏のバックトラックは全部レコーディングが終わって、歌のメロディもある程度出来上がっているんだけど、そこにのっける歌詞だけできてないってこともあったんですね。これ、どうすっか、締め切りは明日やぞ、と。もう、レコーディングスタジオに泊まり込んで、そこにあったグランドピアノのカバーを布団にして寝たこともありましたけど。締め切りがあるという状況で、どうにかかっぽじって歌詞をひねり出した曲もありましたね。「鉄風、鋭くなって」っていうのは、そういう状況でできた曲です。ふいに思いついたフレーズ、もしくはずっと頭ン中を彷徨っているフレーズの集合体。それをずらっとまとめあげて一曲にすると、バラバラになっているようなことにはならずに、自分にとってはむしろ一本筋が通ったものができる気がしてるんですよ。そうやってまとめあげるときには、ある種の集中力が必要で、片手間ではもちろんできないし、旅先の缶詰旅館でもできない気がする。こういった場所があると、それに取り組めるような気がするから、ずっとここでやってるんですけどね。
「MATSURI STUDIOからやってきた我々がおこなう表現は、すべてがMATSURI SESSIONであると、私は言いたい」
――ここは曲が生まれる場所でもあり、セッションを重ねる場所でもあるわけですよね。ZAZEN BOYSを結成された頃から、今回の武道館公演に至るまで、ワンマンライブには一貫して「MATSURI SESSION」という名前をつけられています。この地下室で過ごす時間と、ここから地上に出てライブをおこなうことは、どういう位置関係にあるんでしょう?
向井 私がここにいること自体が、すべてにおいてセッションである、と。だから「MATSURI STUDIOからやってまいりました」と言うわけです。そこからやってきた我々がおこなう表現は、すべてがMATSURI SESSIONであると、私は言いたい。一言で言ってアジトですかね。基地であり、自分自身のいる場所ですね。ただ、常日頃からここで試行錯誤をして、ギターやシンセを弾いて、新たな自分の表現を求めて研究に研究を重ねている――イヤ、そういうことではないんですね。ほとんど何もやってないんです。Netflixで『極悪女王』を観て、感動して涙をぼろぼろ流すわけだ。一言で言って、ハートが揺れやすいタイプですからね。
――そうなんですか?
向井 だから、真正面から感動できるものに出会うと、非常に嬉しいわけですよ。まあ、MATSURISTUDIOというのは、自分ひとりの世界ですよ。そういう場所があってよかったと思います。「極悪女王」というのは、非常にフレッシュな話題ではあるんだけども、私が何に感動したかというと、人間の美しさがそこにある。人間がエモーションを吐き出す姿に感動したんです。個人個人の背景というのはそんなに詳しくわからないんだけど、俳優さんたちが肉体を駆使して表現する姿というのはこんなに美しいんだ、と。これ、すげえなと感動できたことが、私はすごく嬉しい。それをこのMATSURI STUDIOの地下室で、じとーっと、ずっとひとりで観続けるわけだ。その時間は私にとって非常に大切な時間ですね。東映ジャンクフィルムチャンネルをすべて観るのもそれと同じことなんですけど、『極悪女王』に関してはノスタルジーもあるね。

――当時、リアルタイムでプロレスをご覧になってたんですか?
向井 ちょうどその世代なんだよ。クラッシュギャルズと極悪軍団が社会をかき乱してた頃っていうのはね。プロレスがすごい人気で、新日本プロレスでタイガーマスクが、今だと「CGか」と言いたくなるような動きをして技を繰り出す。それがプロレスファンだけじゃなくて、世間を騒がすようなムーブメントを作っていたんですね。その時代に対するノスタルジーというものを、今回『極悪女王』を観ていて感じましたね。こどものとき、テレビでダンプが吠えている姿を見てたなあ、と。たこ焼きラーメンのCMにダンプはスッピンで出てたなあ、とかね。そんとき俺は、どういう感情で観てたんだろうなって、思い返したりしてね。小学校5、6年生だった頃の自分と邂逅しているような感じがして、やっぱりある種のセツナミーを感じるわけだ。私らの年齢だとそういう気持ちになる人がいっぱいいると思うけど、その時代をまったく知らない世代の人がみたら、「ほんとにこんな世界があったのか」と興味が湧くだろうね。まあ、あったんだけどね。そういう気持ちにさせてくれるっつうのは、すさまじいよね。まだ観てない?
――『極悪女王』を観ようと思ってNetflixを開いたら、ビンス・マクマホン・Jrというアメリカのプロモーターをテーマにした『Mr. マクマホン: 悪のオーナー』というシリーズが始まっていて、ちょっと、そっちを先に観よう、と。
向井 あなた、もしかして、プロレス大好き?
――高校生の頃は熱心に観てました。だから、『極悪女王』も楽しみにしてるんですけど。
向井 楽しみですよね。Netflixの配信ドラマシリーズって、ほんとにこの5年は盛り上がってるわけですけど、そういうものに対して、真正面から向き合える場所があるわけだ。受けてたとうじゃねえのって、毎回思ってますよ。もちろん、好みの問題としてピンとこないものもあるんやけど、MATSURI STUDIOというのはそういう場所ですね。
「夏が過ぎてひんやりしてきたっていう、まさに季節の移り変わりにあわせて日本武道館公演ができる 」
――いよいよ10月になって、武道館公演があと3週間後に迫っています。向井さんが武道館に立つというのは、まったくもって初めてのことですよね。今回、どういった経緯で武道館公演に至ったんですか?
向井 ライブ制作をずっと一緒にやってもらってる人がいるんですけど、その人から「この会場がとれました」とか、「この会場でやってみませんか」と連絡があるんですね。今回に関して言うと、「日本武道館の日程がとれるかもしれないけど、申し込んでみませんか?」というふうに、ライブ制作のプロフェッショナルとして提案があった。ライブというのは、そうやって始まることが多いんですね。たとえば日比谷野外音楽堂ではほんとにずっとライブをやってますけど、「何月何日にライブをやりたいんですけど」っつっても、できないわけよ。野音は週末しかライブができなくて、せっかくなら過ごしやすい季節にやりたいと思う人が多いから、抽選になるわけよ。その抽選に申し込んで、とれた場合にはライブをやりましょう、と。今回の日本武道館も同じような形で、現時点で空いてそうだから、エントリーしてみましょうという話になったんです。
――それがいつ頃のことだったんですか?
向井 もう、1年くらい前にはそういう話があったんだけど、それがちょうど『らんど』の大詰めの時期だったんですよね。「これ、予定通りリリースできんのか」って状況だったから、ライブツアーをどうするかとか、そういう組み立てはまだ曖昧な時期だったんだけど、でも、ぶち込んどくか、と。
――せっかく話があったんだから、と。
向井 12年ぶりのアルバム『らんど』を、2024年の初めのうちにリリースしたとして、その年の秋口ぐらいに日本武道館があれば、なんか楽しいじゃない、と。そういう具合のもんです。本来なら、もっとストーリーを作っていくものかもしれないんだけどね。アルバムならアルバムをリリースして、ツアーを組んで、その最終公演を日本武道館でおこなう――これだとわかりやすい物語としてヤマが作れると思うんですけども、そんな先のビジョンはまだ見えてなかったんですね。だから、何とも言えないところもあるんだけど、抽選にエントリーしてみるかってことが、今回の始まりです。結果的には、アルバムを無事リリースすることができて、日本各地でワンマンのツアーをおこなうことができて、夏が過ぎてひんやりしてきたっていう、まさに季節の移り変わりにあわせて日本武道館公演ができるというのは、ストーリーをつくることができたなと思っていますけど。
「自分たちのワンマンライブとして、自分たちのリアルな表現ができる頭打ちっていうのは、最初からありましたよ」
――向井さんが上京されたのが1998年で、ナンバーガールが「透明少女」でメジャーデビューされたのはその翌年の1999年でした。この1999年の活動を振り返ってみると、この年に最も多くライブをされているのは下北沢・ClUB Queで、ここは300人弱くらいのキャパですよね。ただ、この1999年にはライブをおこなう会場の規模がどんどん大きくなって、「透明少女」リリース直後に福岡で“凱旋公演”と言いますか、ライブをおこなう会場に選ばれたのはドラムロゴスでした。ここは1000人くらいのキャパだから、もともとナンバーガールが福岡で活動していた会場に比べると、一気に大きくなっている。その当時、20代半ばの向井さんの感覚として、会場の規模が大きくなっていくことに対して、どんな感覚を抱いていたんですか?
向井 自分たちのワンマンライブとして、自分たちのリアルな表現ができる頭打ちっていうのは、最初からありましたよ。商売としてはやっぱり、規模を大きくすることを目指すわけよ。どんどん大きくして、それこそスタジアムでライブをやって――そういう考え方は、私の中に最初からないんです。というのは、やっぱり、届かないんですね。声にしても、ギターにしても、マーシャルでむっちゃ大きい音を出しても、幕張メッセじゃ後ろには届かないですよ。マーシャルから出ている音をマイクで拾って、別のPAスピーカーで増強しているだけであって、リアルなマーシャル・サウンドの音圧はまったくもって届いてないんですよ。それが実現できるキャパシティというのは、やっぱり2000人くらいが限界だと思ってますけどね。それはもう、その当時からそう思ってました。もちろん、制作チーム、レコード会社の人たち、ライブ制作の人たちは「もっと裾野を広げていきましょうや」ということになるんだけど――それは商売だから、当たり前のことですよね。ただ、なんとなく私は、「ひとりでも多くの人に聴いて欲しい」とは、やっぱり思えないんですね。

――ただ、上京してメジャーデビューをされるときは、これから東京に乗り込んで行って自分の音楽で突き刺すんだという気合いでもって上京されたわけですよね?
向井 上京のときはもう、ひとりでも多くの東京の人間をぶち殺すぞっていう思いで出てきたはずなんだけど、ある線を越えると、すごく遠ざかっていくような気がずっとしてるんですね。あるラインを越えると、こちらに興味があるのかないのかよくわからない、そんなぼんやりとした人たちがその場にいるだけではないかって感じがするんです。手応えを感じることが出来なくなる。だから、ほんとはリキッドルームぐらいのサイズ感がやりやすいし、届いていると思えるし、コミュニケーションができているような気がするんですね。こんなことを話してたら、「売れないバンドマンがそんなことをほざきやがって、1万人入れてみてから言えや」って言われるかもしれんけどさ。1万人の人たちが興味を持ってくれるというのは、すごいことだと思います。すごいとわかっているからこそ、言ってるんだけどね。
「真剣にと言いましょうか、真摯にと言いましょうか、そういうふうに音楽に立ち向かう人たちと血を通わせたい」
――それで言うと、1999年には第1回RISING SUN ROCK FESTIVALが開催されて、ナンバーガールも出演されています。この年のRISING SUNはステージがひとつだけだったので、かなり大きなステージで、たくさんの観客の前で演奏する経験をされたわけですよね。
向井 フェスティバルの会場というのも、いろんな規模がありますけど、そういうイベントやフェスティバルというのは、ほんとに多種多様な趣味嗜好を持った人たちが集まるわけだ。自分が興味ないグループ、バンド、アーティストでも、こういう場所だから観てみようと思ってもらえる機会なわけですよね。すごく良い機会なんだよ。それこそ2万人ぐらいいたりするんだけども、全員が自分たちのことを知っているわけでもなければ、自分たちに興味があるわけでもない、そういう場所で演奏することがあるわけ。演奏させてもらうと言ったほうがいいわ。そういう機会があるというのは、ありがたいことなんです。
――ナンバーガールを再結成されたとき、「もういちどRISING SUN ROCK FESTIVALに出演する」ということを目的のひとつに挙げられてましたけど、それはやっぱり、あのステージで演奏するということが結構大きく焼きついているということなんだろうとも思うんです。ライブ映像としてステージからの眺めを観るだけでも、こんな規模で自分の表現を披露できたら興奮するだろうなというふうに思うんですけど、20代半ばの向井さんとしても、その大きな規模にまで自分の表現が届くようになにかを変えて挑んでいくということよりも、自分の表現は変えずにやっていくべきだという思いが明確にあったということですか?
向井 もう、すべて一言、自分にとって嘘くさくないかどうかってことに尽きるんですけども。ナンバーガールが始まったときは、そりゃ新鮮ですわ。受け止める側もね。「なんかメガネが出てきたぞ」って、そりゃ真剣に受け止められますよ。ただ、そのあとに新鮮で活きの良いのがいっぱい出てきて、ずっと移り変わるわけですよね。聴く人たちのほうも、どんどん移り変わっていって、そのときの世代に、時代のムードに合ったものが受け入れられて、盛り上がる。いちど盛り上がったものも、やがて盛り下がってしまう。その繰り返しなんですね。そういうのは、ちょっともう、いいんだと。かなり早い段階でそこに気づいてた部分はあると思うんだよ。ただ、我々を売ってくれたメジャーの人たちは、かなり理解が深くてですね、そういう考え方もわかってくれてたから、私どもにとっては幸せだったんだけども。自分にとって嘘くさくないことをしたいと、そういう思いでやっているわけです、ずっと。ただし、「わかる人だけわかればいいや」というところまでは突き放せないんですね。「ちょっとは俺の話も聞いてくれよ」と。「こっちもちょっと見てくれよ」と、そういう矛盾した、そして屈折した寂しがり根性は確実にありますんで、このせめぎ合いでやってきたんですけどね。「でも、そんなに近寄らないでください」と。そういうふうにやってくると、リキッドルームでライブをやるというのは、非常にリアリティがあるんですね。わかるかなあ。わかんねえだろうなあ。

――今年の夏にも、リキッドルームでZAZEN BOYSのワンマンがありましたけど、東京でワンマンとなると、ナンバーガールの頃も含めて、リキッドルームより大きい規模を選ばれることが多いと思うんですね。たとえば、渋谷のAXであるとか――。
向井 渋谷のAXとか言っても、今は誰もわからんぞ。
――昔の赤坂BLITZであるとか、ZEPP TOKYOであるとか、日比谷野音であるとか、豊洲PITだとか、なくなった新木場STUDIO COASTも、今年2月にライブがあったTOKYO DOME CITY HALLにしても、2000人から3000人キャパの会場が選ばれることが多いと思うんですね。向井さんの中ではリキッドルームの規模感が一番リアリティがあるとして、3000人ぐらいまでの規模であれば、どうにか届いている実感を持てる、という感じがあるんですか?
向井 そうね。なんかこう、血流が見える感じがするというかね。音楽を聴くっていうことに関して、ほんとにレジャーとして音楽を聴いている人もいると思うんですよね。そうじゃなくて、真剣にと言いましょうか、真摯にと言いましょうか、音楽に立ち向かう人っていうのがいるんですね。私自身がそういう人間のひとりだと思っているんですけど、そういう人たちと血を通わせることをしたいわけです。そうなると、「話題の彼をちょっとチェックしてみよう」っていうようなお気軽なものではなくなってくるんだな。「お気軽にどうぞ」って言えればいいんだけどね。「音楽を聴くのに、なんでどんな構える必要があるんだ」って言われたら、それはもう、その通りなんだけど。ただ、ライブにわざわざくるっていうのは、ある種の意気込みがあるはずだと思うんですよね。
「日本武道館だから、ひとつのスペシャル感が生まれる。これは一体何なのかと、私はずっと思ってるんですけどね」
――武道館公演のチケットは、早い段階でソールドアウトになりました。
向井 普段東京でライブをするときに、日比谷野音であれば3000人のお客さんが来てくださるわけだけど、今回はその3倍ぐらいになるわけよ。それも、そんな安い金額じゃないチケットを購入してきてくださるわけです。幾ばくかの興味を持ってくれたんだろうけど、そこにはきっと、いろんな人がいるんだと思うんですね。ZAZEN BOYSという名前は昔から知っているけど、聴いたことねえなって人もいるんでしょう、きっと。そういう人たちが、「日本武道館でやるなら、ちょっと観に行ってみよう」と思ってくれたのかもしれない。あるいは、「10年前はよく観に行ってたけど、ZAZEN BOYSってまだやってたんだ」って人もいるんでしょう。武道館でやるのかよ、じゃあ10年ぶりに行ってみよう、と。そういう人たちがいっぱいいてくれて、今回のライブが成り立つわけだね。ずーっと活動を続けてきてよかったなと思うことなんですよ、これは。チケットがソールドアウトになったというのは、その「日本武道館だから行ってみよう」ということがあったんだと思うんですね。
――観にきたことがないお客さんからしても、最近ご無沙汰だったお客さんにしても、「日本武道館でやるなら」と。
向井 日本武道館だから、ひとつのスペシャル感が生まれる。これは一体何なのかと、私はずっと思ってるんですけどね。日本武道館という響きが持つ――特にバンドにおける武道館公演が持つ特別意識っていうのは、一体何なんだろう?
――たしかに、観客の側からしても、特別感はありますよね。せっかくならそのライブに立ち会いたい、と。
向井 その特別感があるからこそ、観にきてくれる人がいっぱいいる、と。そして、この機会だから、初めて観にきてくれる人もいっぱいいるんでしょう。そうやって初めて観にくるお客さんがいるってところに対する気構えはあるんだけど、場所に対する気構えというのは、あんまりピンときてないんですよね。日本武道館という要素が持ち込む付加価値みたいなやつがあるってことは理解してるんだけど。こんなことやったら、もっと前からやっときゃよかった――そんな軽口を叩けるのは、ありがたいことに完売しているからです。最初はもう、どうなるかと思ってましたからね。チケットを発売して、初動で1500枚しか売れてなかったらどうするか、と。「そしたらもう、家族会議だ!」と、ワタシは思いましたね。メンバー、スタッフ、全員家族会議だ、と。「全員、家族を呼べい!」と。「いとことか呼べい!」と。そういうことになるんだろうなと思っておりましたらですね、ソールドアウトということになって、ほんとにありがたいことだと思ってますね。
「存分にディスイズ向井秀徳のわがままに付き合ってもらおうじゃねえかと思ってますね」
――ここまでお話を伺っているなかで、ある程度より規模が大きくなると届かない感じがする、というお話がありしたけど、日本武道館となると1万人近い規模になってくるわけですよね。武道館でやってみないかという話があったとき、実際にどうなるかはやってみないとわからないにしても、ちょっと面白いんじゃないかという感じが向井さんの中であったんですか?
向井 日本武道館の天井まで表現が届くかどうか。それはやってみないとわからん。ただ、俺には見えるから、「やりましょうや」と。1万人近い人たちの前で演奏するっていうのは、これまでないわけです。ZAZEN BOYSに関してはね。ナンバーガールの再解散ライブのときは9000人ぐらいのお客さんに来てもらったんだけど。ナンバーガールの再結成は、そこに関わってもらった人もいっぱいいたから、「最後ぐらい稼ぐか」ということだったんだけれども、何度も言っているように全然稼げなかった(笑)。規模が大きくなればなるほど、携わる人間も多くなってくるし、稼げないんです。それに、プロジェクトの規模が大きくなればなるほど、こっちがやりたいことのコントロールが難しくなってくるところも出てくるわけですね。どうすれば大きい規模のプロジェクトを成り立たせることができるかってことが先に行ってしまうと、こっちが届けたいと思ってる気持ちを発揮できるかというと、難しくなってくる部分もある。ただ、今回の日本武道館に関しては、これまでのZAZEN BOYSの活動のやりかたに則ってやっているもんでですね、たしかにキャパシティとしてはいつもより多いけども、やりかたはそんなに変わってないんです。日本武道館だから構えなきゃいけないということは、今の現状としてはないんですね。
――今回の武道館公演に関しては、グッズの事前先行販売もおこなわれました。
向井 そうね。グッズの制作も、いつも通りやるんだけど、数出しというのがあるんですね。何人のお客さんがきて、何人のお客さんが買ってくれるか、見込みを出すわけよ。それ、ずーっとやってまして、長年やってるもんだから、めちゃくちゃシャープかつシビアなんですよ。長年やってる人たちは皆そうだと思うけど、「こんだけ売れるだろう」という数がはっきり見えてくるんですね。もう、百発百中なんだけど、今回はまったく見えないんだ。
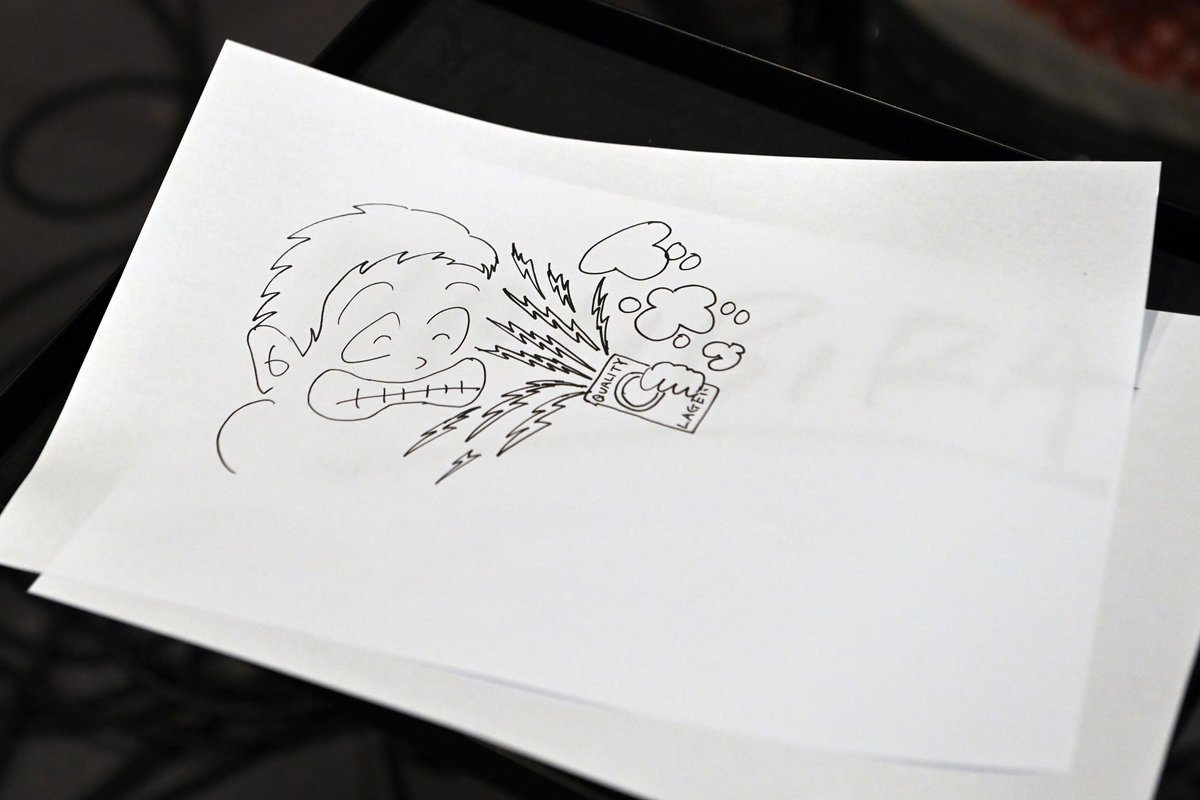
――今回の武道館公演に関しては。
向井 会場の規模がいつもの3倍なんだとして、グッズの数も3倍にすればいいのか――そういう話じゃないんですね。これをね、今現時点で、MATSURI STUDIOの地下室で思い悩んでいるところです。グッズのそろばん弾くより、練習せいやと言いたくなるんやけど――いや、それももちろん同時にやっとるんだけども――これが難しいんですね。はっきり申し上げれば、ライブが良かったら、お客さんはグッズを買ってくださるんですよ。これはもう、当たり前の話です。「ああ、よかったね」と、「この気持ちをどうにしかしたい」と。そしたら、なんか売ってる。Tシャツ、たぶん着ないと思うけど、ちょっと買って帰ろう――ライブのグッズを買いたいという気持ちは、それしかないんですね。
――この日の思い出として買って帰ろう、と。
向井 そうね。MATSURI STUDIOの地下室では、グッズの絵を描いたり、デザインをしたり、そういうことを目ん玉ひん剥いてやるわけだ。ただ、忘れちゃいけないのは、俺らはアパレルじゃねえんだ。もちろんテキ屋でもないし、漫画家でもないんです。なんで俺がこんなことやらんといかんとかいなと思うんだけども、そう思った次の瞬間、「貴様がやらんで誰がやるとや?」という声が聞こえてくる。「あんたのわがままでこんだけバンドをやって、こんだけ人にきてもらって、Tシャツを売るんだろう」と。だったら、自分にとって嘘くさくないものにしたいという気持ちがあるんですね。誰かに頼んで、「これだけお客さんがくるから、これだけ売れるものにするためには、こういうデザインにしなきゃいけないよ」っていうものをつくるんじゃなくて、存分にディスイズ向井秀徳のわがままに付き合ってもらおうじゃねえかと思ってますね。
「俺はモテたい。もしくは、私はちやほやされたい。自分が気分良くなりたいっていう、独善的な欲求。これね、タチ悪いことに、変わらないんですよ」
――ナンバーガールの頃に、向井さんはよく、「売れる売れない二の次で、恰好のよろしい歌ば作り、聴いてもらえりゃ万々歳。そんな私は傾奇者」という言葉を口上のように語ってましたけど、その言葉というのは、自分は上京してどんな態度で音楽をやっていくのかという決意表明のようなものだったと思うんですよね。それから20年以上経った今、その感覚というのは――何に向かって自分は音楽をやるのかという気持ちは、どんなふうなものとしてあるんでしょう?
向井 モテたいという感情は、全世界共通の、表現者の根本ですよ。これをやることで、俺はモテたい。もしくは、私はちやほやされたい。自分が気分良くなりたいっていう、独善的な欲求。これね、タチ悪いことに、変わらないんですよ。それとしか言いようがないんですよね。「私の欲求はおいといて、皆様に幸せを与えたい」とか、「ヨロコビを与えたい」とか――それ、順番が違うね。モテたいんですよね?と。これは根源的なことですよ。なぜバンドをやっているのか。モテたいからですよ。
――その「モテたい」というのは何を指すのか、人によってかなり幅があるような気もします。
向井 そうね。モテるということは、売れるってことなのか。あるいは、カネになるってことなのか。カネになれば、良い車が買える。良い車に乗れば、またモテる――そういう欲求は、ワタシの中にはまったくないですね。じゃあ、モテるって何なのか。いろんな人から「好きです!」と言われることが、モテるってことなのか?――いや、どうやら違う気がする。だって、「あんまり近寄らないでください」と言ってるわけだからね。モテるって何なのかってことは、追求していきたいね。
「そういうときにね、『10年後にまた会おう』とワタシは思うんです。『このcold beatを、10年後に聴きにこい』と」
――この1年、『らんど』のリリースがあったということで、メディアに出演される機会も多かったですよね。印象的だったのは、ランジャタイの国崎和也さんと対談された『META TAXI』と、日本テレビの『Apartment B』という番組で、このふたつはちょっと意外な感じがしたんです。たとえば、今年2月には松重豊さんのラジオにも出演されてましたけど、それはもうちょっと近い感じがするというか――。
向井 そうね。親和性が高いというかね。
――それに比べると、『META TAXI』や『Apartment B』は、共演される方たちもひとまわり、あるいはふたまわり下の世代の方たちでしたし、単に共演者がというだけでなくて、若い世代の番組だという感じがしたんです。
向井 国崎さんとのトークというお話をもらったとき、正直に言って、国崎さんのことをそんなに存じ上げなかったんですね。その番組を企画している人たちも、おそらくは若い人たちなんです。そういう人たちが、「こういう企画をやりたい」と言ってくれたんだけども、それは一体どういうことなのかもわからずにやるっていうことを、そのときの私は面白がったんですね。どういう企画なのか、よくわからなかったけど、安直な、軽薄な、芸能的な企画だというふうには思わなかったんですね。そうじゃなくて、面白そうだと思えたから、そこに乗っかっていったということです。テレビの企画も同じですよ。そこに出演されている方たちのことは存じ上げないけれども――もちろんMOROHAのアフロはずっと前から知っとるけども――こういう人たちがこういう考え方でやってるってことが伝わってきた。だから、世代というよりかは、本気かどうかってことですかね。で、そのときの私には、その企画は面白いと思えたわけです。それも結局、そのときの気分で変わったりするんだけれども。

――ZAZEN BOYSのライブでも、あるいは再結成されたときのナンバーガールのライブでも、結構若い世代のお客さんを見かける気がします。人によっては、「自分は昔から聴いてくれてるファンに向けて活動する」って場合もあるとは思うんですね。無理に若い世代に聴いてもらおうとは思わない、と。これまでのインタビューの中で、どんな言葉で表現するかということについて、「年齢を重ねたことで、変わってきた部分もある」というお話もありましたけど、50歳になられた今、若い世代に自分の音楽がどう届いていくかというところに関して、どんなことを感じてますか?
向井 ナンバーガールの再結成のきっかけとしては、若いバンドの人たちと対バンしたときに、「YouTubeで昔のライブ映像を観て、そこからナンバーガールにハマりました」と言われることがあったんですね。
――ナンバーガールが最初に解散したのは2002年ですから、今20代の人たちはきっと、まだ物心がつく前ですもんね。
向井 年を重ねて、ZAZEN BOYSや向井アコエレとして活動を続けていくうちに、そういう状況が増えていくわけよ。それは当然、嬉しいわけです。あるいは、「親から聴かされてハマりました」っていうパターンもある。そうだろうね、と。まだ生きとるわけやから、「だったら本物を見せたろかい」と思ったのも、再結成のきっかけのひとつだったんですね。ZAZEN BOYSに関しても、もう20年やっとるもんですから、そういうことはいっぱいあるわけだ。
――そういうことと言いますと?
向井 ZAZEN BOYSを始めたばかりの頃に、フェスに出演することがあったんだけど、最前列に若い女の子たちが並んでいたんです。「俺、こんな若い子に人気あるんだ?」と一瞬思ったけど、どうやらそうではない、と。演奏を始めても、皆俯いてるわけよ。誰もこっちを観てない。むしろ何かを耐えているような表情をしている。その若い女の子たちは、次のグループを待っていたんだな。そういうときにね、「取り去ることが出来ない記憶をオマエの脳内にきざみこんでやるから、10年後にまた会おう」とワタシは思うんです。「このcold beatを、10年後に聴きにこい」と。これをワタシは「10年殺しの呪い」と言っているんだけども、そのときの女の子たちが、実際に10年後に来てくれてる気がするんだな。それは嬉しいことですよ。
「人間というのは、結局のところ、乱れ散ってばらばらになるんでしょう。それが積み重なった場所に、また何かが生まれて、やがて乱れ散る」
――去年の12月から、1年近くにわたって、向井さんに『らんど』について語ってもらうインタビューを収録してきました。アルバムのタイトルは平仮名表記ですが、アルバムの12曲目に収録されている楽曲のタイトルも「乱土」です。これは一般には存在しない造語ですけど、「乱土」という言葉はどうやって浮かんできたんでしょう?
向井 これはね、たとえば「ニュージーランド」みたいに、アイランドとしての「ランド」なのかといったら、おそらくそうではないんです。じゃあ、乱れた土地なのか。「乱世」という言葉がありますね。乱世といったら、ほんとに大変なことが巻き起こっているわけですね。乱れていると。地上の上は、乱れきっていると。ワタシがここで「乱土」を選んだのはきっと、世界の状況を、時代の状況を表している言葉なんだと思います。我々は乱土の世界に生きているんだ、と。
――なるほど。向井さんの歌詞には時折ナマズが登場しますけど、この「乱土」にも「NAMAZU」が出てきます。この曲におけるナマズというモチーフは、地上が乱れきった世界であるのに対して、地下に潜んでいるイメージとして出てきたんですかね?
向井 地下に潜んでいるNAMAZU。「NAMAZU in muddy water」。泥水の中にいて、「地震がくるぞ!」と。「俺が予知するから待っとれ!」と。ただ、NAMAZUが地震を予知したときにはもう、地上は全滅している。そういう怖さ、終末感が感じられるね。いや、ワタシとしては、そんなことはまったく考えてないんですけどね。これもやっぱり、語感としての気持ちよさを求めたわけだ。ただ、今あなたが言った解釈を、わざわざしてみてもいいかもしれないね。地上はもう乱世である、と。乱れきっている。その一方で、NAMAZUはじっとりと地下の泥沼に潜んでいて、ずっとそのときを待っている。ただ、そのときがやってきたときにはもう、すべてが終わっている。そういう危機感みたいなものはありますね。
――その「乱土」のあと、アルバムの最後に収録されているのは「胸焼けうどんの作り方」です。
向井 「乱土」と「胸焼けうどんの作り方」、この2曲に関しては、つながってる曲ですね。今話したように、何かしらの危機感とか終末感がある。その先に、一体何があるのかと言ったら、「もう、ロックンロールでお祭りだ」と。祭囃子にのっかって、ロックンロールを鳴らすしかないんだ、と。そういう結論じゃないですかね。この、作り方について説明している部分に関しては、ワタシ自身でもよくわかりませんけども。
――この、レシピ的な部分ですね。
向井 ええ、ええ。それはワタシ自身もよくわかりませんけど、最終的には、とにかくもう、皆で集まって、乱れ散って、ばらばらになろうぜ、と。どうだっていいや、と。諦めちゃいけないんだけども、時にはやけくそになろうや、と。この曲が最後にきてるってことは、そういった意味合いがあるんじゃないですかね。

――今の言葉、すごく印象的でした。「皆で集まって」という枕詞が置かれたら、普通は「ひとつになろうぜ」という言葉が続くと思うんです。でも、そこに「乱れ散ってばらばらになろうぜ」という言葉がくるのが、向井さんの言葉だな、と。
向井 ひとつになれるなら、とっくの昔にひとつになっとるわ。人間というのは、結局のところ、乱れ散ってばらばらになるんでしょう。それが積み重なった場所に、また何かが生まれて、やがて乱れ散るんでしょう。そういう場所に――乱土としか言いようがない場所に、我々は住んでいるんだということですね。
〈了〉
2024.10.3 東京で収録
ZAZEN BOYS 日本武道館公演決定!!
武道館ではメンバーの誰もがコードを全く憶えていない名曲などを含め豊富なセットリストを組み、二部構成をもってして3時間超の公演を行う。(向井秀徳)

ZAZEN BOYS MATSURI SESSION
2024年10月27日(日)日本武道館
出演 ZAZEN BOYS
開場16:00 開演17:00
(問)ホットスタッフ・プロモーション 050-5211-6077<平日12:00〜18:00>
いいなと思ったら応援しよう!

