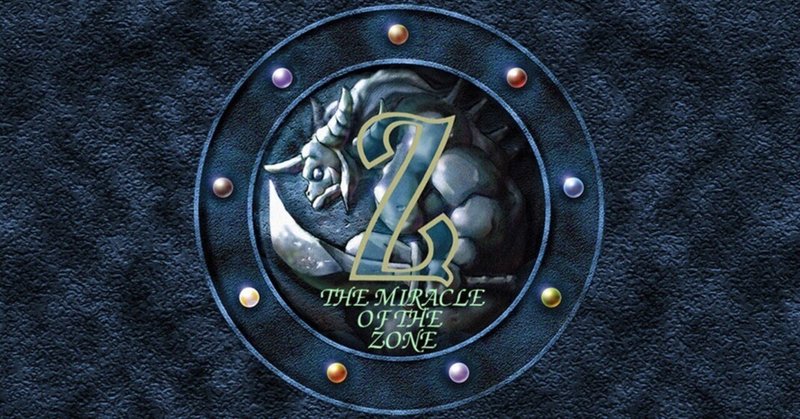
2024年に『ザ・ミラクル オブ ザ・ゾーン』をやることになりそうなのでルールをおさらいしてみた。
古えのTCGも好き好き大好き。
はれのちしとどです。よろしくお願いします。
今回はタイトルにもあります通り、2024年の今、1997年発売のTCGである『ザ・ミラクル オブ ザ・ゾーン(略称:MOZ)』をプレイすることになりそうなので、完全に忘却しているであろうゲームルールをおさらいします。
ちなみに普段は『マジック:ザ・ギャザリング』で遊んでます。
◆はじめに
なぜ、この時代に『MOZ』が話に挙がっているのか。
そんなこと私が知りたい。
知りたければ調べればよい。知識は力である。
というワケで、触れればすぐにわかる情報でしたが、「プレミアムバンダイ」で2022年の中頃から復刻版の予約販売が始まっていたらしいのです。へー。
で、それの第2弾の予約が今年の頭に終了し、今の時期に購入者の手元に届き始めている・・・、というのが事のあらましの様子。
で、その購入者のお一方が私の身近におり、私が古えのカードゲーマーであったことから、なぜか自宅に初版のスターターデッキが眠っていて、「じゃあ、対戦だ」という話。

とは言え、20年以上前のTCGなので、改めてルールを確認しておくに越したことはありません。「スターターと拡張ブースターのカードパワー差で勝負になるのか」などの不安はありますが、まずは学びます。
※『グリフワール編』の公式ルールに記載されている内容を参照していますので、それ以降のルールとは異なる場合があります。
◆カードの種類
どんなカードゲームを遊ぶにも、まずはカードの種類と働きを覚えることが重要です。『MOZ』のカードはおおまかに分けると3種類。
『召喚師カード』『召喚獣カード』『補助カード』
『召喚師』は、プレイヤーに代わって戦場で『召喚獣』を操り、このゲームの勝負を行う軸となる存在。
各『召喚師』ごとに、『名前』『性別』『年齢』『レベル』『召喚属性』『抜き手(行動速度)』『特殊能力』が設定されており、対戦相手の『召喚師』や自身の『召喚獣』と作用しあって、ゲームに起伏をもたらす。
『召喚獣』を出せる『天(上)』『左』『右』の面には『召喚属性』が記述されており、何も記述のない『下』の面には『補助』を出すことになる。
『召喚獣』は、『召喚師』により異次元「ゾーン」より呼び出され、一時的に力を貸してくれる存在。おおむね、クリーチャー。
各『召喚獣』ごとに、『名前』『属性』『サブ属性』『パワー』『特殊能力』が設定されており、『召喚師』同様にゲームに作用しあう。
『補助』には、更に5種類の区分があり、それぞれの役割を果たす。
1.ヘルプカード
『召喚師』の『下』の面に出せる唯一のカード。
『召喚師』や『召喚獣』をパワーアップさせる。
2.スペシャルカード
ゲーム進行の大詰めで使うカード。
逆転要素を含むカードが多い。
3.ヘルプ&スペシャルカード
上記のどちらとしても使えるカード。
4.リバースカード
対戦中に『ホール(墓場)』に置かれた『召喚獣』を復活させるカード。
5.属性チェンジカード
『召喚師』の『召喚属性』を変更するカード。
◆基本的なゲーム進行
次はゲームの進行についてまとめます。
基本は2人対戦。1人1つのデッキを用意する。
デッキの内容は、『召喚師』5枚+『召喚獣』&『補助』を合わせて50枚の2つの束で55枚。50枚の方は『ゾーン』と呼ぶ。
自分の『召喚師』5枚の使う順番を決め、裏返しで伏せておく。
互いに『ゾーン』をよくシャッフルし、自分の『ゾーン』の上からカードを7枚を引いて最初の手札とする。
ゲーム開始。
互いに1人目の『召喚師』を戦場の中央に置いて公開する。
『召喚師』同士の相性による作用を処理した後、『抜き手(行動速度)』の数値を確認して、数字が大きい方が先手になる。同値の場合はジャンケン。
先手プレイヤーから行動を開始する。
ターン中の流れは以下の通り。
1.ゾーンの上からカードを1枚引く。
2.天・左・右・下のいずれかの面にカードを1枚出す。
3.条件に合致するカードがない場合はカードを裏向きで1枚出す。
4.出たカードの効果による処理を行う。
5.召喚師と召喚獣の作用を確認し、パワーの合計値を計算。
以下、後手のプレイヤーも同様の流れを、お互いの『召喚師』の4面がすべて埋まるまで交互に繰り返す。
お互いが『召喚師』の4面すべてにカードを出し終え、『パワー』の合計値を計算した後、プレイヤーは『スペシャル』を使用するかを決定する。使用するプレイヤーがカードを出した後、『スペシャル』の効果処理を行い、改めて『パワー』の合計値を計算する。
基本的には、『パワー』の合計値が高い『召喚師』が勝利し、それの持ち主であるプレイヤーが『勝利ポイント』を獲得する。
『勝利ポイント』とは、『召喚師』の勝利時に戦場に残っている『召喚師』以外のカードの合計枚数である。
例外として、『MOZ』のルールに定められている『コンボ』を成立させたプレイヤーは、その『召喚師』が『パワー』の合計値に関わらず勝利する。双方が『コンボ』を成立させた場合については別記。
『コンボ』によって勝利した場合、『コンボ』ごとに定められている『倍率』によって『勝利ポイント』が増加する。
1人目の『召喚師』同士の戦いが終わった後、ポイントになったカードをすべて『ホール(墓場)』に置き、対戦を終えた『召喚師』を別途分かりやすい状態で置く。その後、互いに2人目の『召喚師』を戦場の中央に置き、1人目のときと同様にゲームを進行する。手札は1人目から継続した状態で使用する。
これを3人目以降も繰り返し、いずれかのプレイヤーが『勝利ポイント』を50ポイント獲得した場合、そのプレイヤーがゲームの勝者となる。
◆補足ルール
ルールに記載されている補足となる部分をまとめます。
1.『補助』について
『リバース』や『属性チェンジ』の『補助』カードは、『召喚師』の対応する面に、『リバース』であれば『ホール』から、『属性チェンジ』であれば手札から、『召喚獣』と同時に置いて使用し、勝敗の決定時には『勝利ポイント』に加算される。
2.カードの引き忘れについて
ターンの最初に引くべきカードを引き忘れた場合、カードを場に出した後にはその分のカードを引くことはできない。
3.「ゲームをおりる」について
お互いのプレイヤーは対戦中に1度だけ、進行中の『召喚師』によるゲームを終了させ、その時点で対戦相手の『召喚師』の勝利とすることができる。『勝利ポイント』も、その時点で戦場にあるカードの枚数となる。
ただし、「ゲームをおりる」宣言は、どちらかのプレイヤーが今の『召喚師』での4枚目のカードを引く前にしか行えず、自身がすでに『ゾーン』からターン開始時のカードを引いていた場合は、場にカードを1枚出してからしか宣言できない。
4.『スペシャル』について
お互いのプレイヤーが同一の『スペシャル』を使用していた場合、双方の効果がなくなる。
5.引き分けについて
『パワー』の合計値が同じであったり、『スペシャル』の効果によるものなどで引き分けが発生した場合、そのゲームで戦場に出ていた『召喚師』以外のカードは『ホール(墓地)』に置かず、別途『保留』した状態にする。
『保留』されたカードは、次の『召喚師』のゲームで勝利したプレイヤーが『勝利ポイント』に加算して獲得する。
6.『召喚師』が1巡した場合
5人目の『召喚師』による勝敗が決まった後にいずれのプレイヤーもまだ50ポイントを獲得していない場合、再度5人の『召喚師』を好きな順番で並び替えて裏向きに伏せ、ゲームを続行する。
7.『ゾーン』がなくなった場合
『ゾーン(山札)』がなくなった場合は、その時点では何も起こらないが、次の自分のターンを迎えて『ゾーン』からカードを引けなかった時点でゲームに敗北する。
しかし、『ゾーン』が残り1枚であることを確認できたときに、次のターンの敗北を回避するために「わざとカードを引き忘れる」ことは有効である。※公式のルールブックに記述がある。
閑話。
上記のテクニックは、「ルールの手引き」に裏技みたいな雰囲気で書いてはありますが、「ルールの抜け穴」的な部分をあえて「こういうこともできる」とゲームの戦術に組み込んでしまうのは面白いなと思いました。
自分の視点から見えないカードが存在しているゲームではなく、デッキの内容をしっかり把握するプレイヤーであれば最後の1枚を覚えておくことも可能でしょうし、「1ターンに1つずつ盤面を埋めていく」という、明確なゲームの終わりが示されているルールだからこそ生まれた奥深さなんだろうなと思います。
以上、基本的な進行に関わる箇所についての補足をまとめました。
その他に、カード単位での細かいルーリングの不明点が発生したら公式の「ルールの手引き」を参照するのが良いと思われます。
◆コンボについて
勝利条件を覆す『コンボ』についてまとめます。
『グリフワール編』の時点では11個のコンボが存在しており、それぞれに『強さ』と『倍率』が設定されています。基本的にはより『倍率』が高い方が勝利しますが、同じ『倍率』の『コンボ』を成立させ場合は、より『強さ』が上位の方が勝利します。
なお、双方が同じ『コンボ』を成立させた場合は、『パワー』の合計値が高い方が勝利します。
コンボが成立するのは、すべての面のカードが表向きである必要があるため、戦場のカードを裏向きにする『ガード(0化)』によって妨害が可能。
強い順にまとめると以下のとおり。
1.貝竜コンボ
召喚獣がすべて貝属性の竜である x6
2.マイナスハリケーンコンボ
召喚獣のパワーがすべて「-100」である x6
3.100ドラゴンコンボ
召喚獣がすべてパワー100の竜である x5
4.フラッシュハリケーンコンボ
召喚獣の属性とパワーがすべて同じである x5
5.ドラゴンコンボ(マッスルコンボと同値)
召喚獣がすべて竜である x4
5.マッスルコンボ(ドラゴンコンボと同値)
召喚獣がすべて男である x4
6.貝獣コンボ
召喚獣がすべて貝属性である x4
7.セクシーコンボ
召喚獣がすべて女である x4
8.ハリケーンコンボ
召喚獣のパワーがすべて同じである x4
9.アニマルコンボ
召喚獣がすべて、獣・魚・鳥・虫のいずれかの同じもので揃っている x3
10.フラッシュコンボ
召喚獣がすべて同じ属性である x2
◆デッキ構築について
デッキの構築にはいくつかの条件や制限があります。
1.デッキの枚数について
デッキの枚数は、必ず『召喚師』5枚+『召喚獣』&『補助』を合わせて50枚の合計55枚でなければならない。
また、デッキ内に同名カードは1枚ずつしか入れることができない。
(所謂、シングルトン構築でなければならない。)
2.『召喚師』について
『召喚師』には、おおよそ強さに応じてレベルが設定してあり、デッキに選択できる『召喚師』の枚数には条件や制限がある。
レベル1~2を1人以上、レベル3~4を1人以上、レベル5・6・7以上は各1人以下にしなければならない。
例として、レベル2が2人+レベル3が3人のような低レベル帯でまとめることは適正だが、レベル5が3人+レベル6が2人のような高レベル帯だけの構築は認められない。
3.その他の構築制限
・『召喚獣』について、パワーが100の竜は5枚までしかデッキに入れられない。また、同パワーの召喚獣は12枚までしかデッキに入れられない。
・「天災」であるカード、「悪魔の所業(無効)」であるカード、「天の奇跡」であるカード、「送還(墓場送り)」であるカードは、それぞれ1枚までしかデッキに入れられない。
・『スペシャル』カードである、《チェンジ(同族交換)》《チェンジ(属性無視交換)》はそれぞれ1枚までしかデッキに入れられない。
・「神の障壁」であるカードと「ブロックマン」であるカードは、合計3枚までしかデッキに入れられない。
・「SP封じ」であるカードは、合計2枚までしかデッキに入れられない。
◆おしまい
私の個人的な覚書きであるところが主ですので、『MOZ』のルールをまとめたものとしては不完全であることが予想されますが、1990年代末期のノリで書かれたルールブックを改めて読み返し、自分の手で書き留めることでルールへの理解が深まったように思います。
カードを眺めていると、割と「当時だから許されてたんだろうな」みたいな描写もあって時代の流れを感じますね。
これで実際に遊ぶことになっても問題ないでしょう。
多分。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
