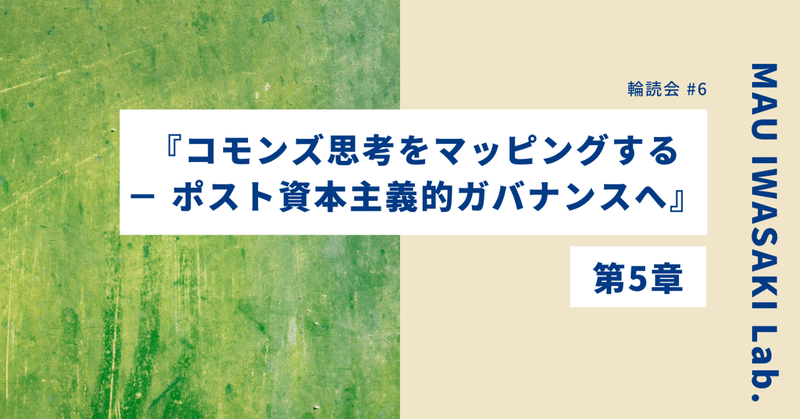
コモンズ思考をマッピングする 第5章
研究室で輪読を行なっている『コモンズ思考をマッピングする ——ポスト資本主義的ガバナンスへ』の第5章「都市コモンズの囲い込みとカウンターヘゲモニー」について、全体のサマリ、ゼミでの議論内容、読んだ感想をまとめていきたいと思います。(文責 中川)
サマリー
第5章は、J・ジェイコブスとE・オストロムの対比から始まります。
二人の女性は多くの共通点を持つと同時に、対照的なところもあると筆者は述べます。
ジェイコブスは、下町に集積する小規模企業と住民の暮らしの多様性が都市の創造性の源泉であるとし、そうした洞察に基づく街づくりの理論を提案しました。
オストロムは条件次第でコモンズによって、持続的な天然資源の管理が可能であることを明らかにしました。
二人の仕事は様々な可能性を抑圧してきた支配的な理論に風穴を開け、その結果、理論的、実践的にあらたな潮流を解き放つ効果を持ったことに共通点があります。
二人のはっきりとした違いは、オストロムが大学における分野横断的な研究の進展に関心があったことに対して、ジェイコブスは大学における新たな研究分野として定着させることに関心がなかったことです。
ジェイコブスとオストロムの仕事を重ね合わせると、「都市のコモンズ」というテーマが見えてきます。
ジェイコブスの都市論にコモンズを加味して再構成するには「安全性」をコモンズ=共有財としてみなすことが有意義だと筆者は考えます。
ジェイコブスは、大都市の最も基本的な構成要素である「通り(Street)」に多様な人々がやってきて賑わうのは「安全性」が確保されているからとしました。
通りの安全性という視点からの活動を重ねることで、近隣コミュニティは、都市の自治(Self-Governance)を支える基盤であるとしました。
さらに筆者はジェイコブスとオストロムの共通点をはっきりさせるために、二人とハイ・モダニズムとの対立を考えます。
ハイ・モダニズムは少数のエリートのみが社会改革を構想できるという考え方をもちますが、オストロムが明らかにしたのは、庶民が高い自治能力を持つということでした。
ジェイコブスは、ル・コルビジェの最も先鋭な批判者として位置づけられます。
コルビジェの考え方は、オートメーション化された集権的システムを社会全体に広げることで理想的な社会を作ることができるというものであり、都市の計画についても、それぞれの都市の歴史をすべて破棄して、ゼロから作り直すべきとしました。
対して、都市の暮らしの観察者から出発したジェイコブスは、コルビジェが夾雑物として都市から取り除こうとしたものの中にこそ、都市の生命の源泉があるとしました。大都市における小規模企業の多様性、住む人々の多様性、そして、多様な技能や経験を持つ人どうしが出会う、さまざまな場があるという点に、都市の創造性の源泉があると考えたのです。
次に筆者はP2Pアーバニズムとファーベラの地力改装について述べます。
ニコス・サロリンガスはジェイコブスやアレグザンダーのハイ・モダニスト批判を踏まえて、活き活きとした街を再生する方法論の理論化を探り、「P2Pアーバニズム」を提案しました。
P2Pアーバニズムは街を修復し、つくっていく、住民たちのボトムアップ的で小さなスケールの積み重ねを、専門家たちが支援する仕組みを作ることに重点をおきます。
この場合のコモンズ、共有資源は、建築と街づくりについての知識、技術ということになり、アレグザンダーの「パタン・ランゲージ」はこうした考え方の優れた先行例と見なすことができると筆者は指摘します。
「パタン・ランゲージ」は人々がなかば無意識のうちに共有してきた街づくりの知識コモンズを意識化する試みだったと見ることができ、P2Pアーバニズムは「パタン・ランゲージ」をコモンズの視点から語り直す活動という面を持つと述べます。
サリンガスのP2Pアーバニズムの取り組みは、ファベーラの住民の自力支援を一つの柱としつつ、アレグザンダーの生成的な方法によって、住民自らの手で街づくりを進める方法をもう一つの柱にしようとしています。
さらに筆者は、コミュニティ・ランド・トラスト(CLT)に注目します。
CLTの基本的な考え方は、居住コストのうち、土地コストを低い水準で安定させるために、非営利団体のCLTを設立し、そこにある程度の資金を投入し、土地を購入、その土地は永久に売買せずにCLTが保有し続け、土地市場から除外してしまい、そこに住宅を建てると言うもので、住宅コストの上昇を抑えることができます。ファベーラの環境改善を進めた結果、低所得者層は他の地域に移転してしまい、住民が中高所得層に入れ替わってしまうという展開を避けるためであり、米国やプエルト・リコでも実際に運用が行われている例を指摘しています。
ゼミでの議論
日本における都市の近代化について
ジェイコブスがあげる通りと、日本においてモールと呼ばれるような商業施設に言及がありました。両者の違いは職住混在であること、オーナシップがあることが大きいのではないかという指摘がありました。
また、通りを介したコミュニティという部分で、本年のGood Design大賞にチロル堂という駄菓子屋とその仕組みが選出されたことに話が及びました。
経済合理性ではない価値をいかに作るのか?ということがこれからの社会のテーマになって来るのではないかという議論になりました。
コルビジェとその後継者たち
当ゼミでは度々話題になりますが、コルビジェの都市計画から議論が始まりました。
コルビジェとその著作から、その思想を受け継いだ坂倉準三、さらに弟子ではあるが違う方向性へと進んだ吉阪隆正に話が及びました。
本文でも触れられる、小さな成功そして、小さなデザインや小さなスケールの実験に触れつつ、ハイモダニズム的なグランドデザインの限界について議論されました。
感想
第2章でのハイモダニズムに対する議論を引き継ぎ、この章でもオストロムやコルビジェの話題が登場しました。
ハイモダニズム批判の文脈から市場経済の価値が劣化しつつあるのではないか?経済を追求した結果極端に不幸せになる状況をどうすればいいのか?という部分に話が及びました。さらに共助を軸として、経済的でないのに育てれば育てるほど、経済になっていくような仕組みを考えていくのではないかという議論になったのが印象的でした。
そういった意味で今回あがったチロル堂や、おてらおやつクラブのような取り組みがヒントになるのではないかと感じました。
市場経済は人類を発展させてきましたが、負の側面も明らかになりつつあります。今回出てきた事例は、「共助の仕組み作り」とそれが生み出す「価値の可視化」という面で共通点があるように感じます。今後もオルタナティブな取り組みに注目しながら新たな価値について考えていきたいと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
