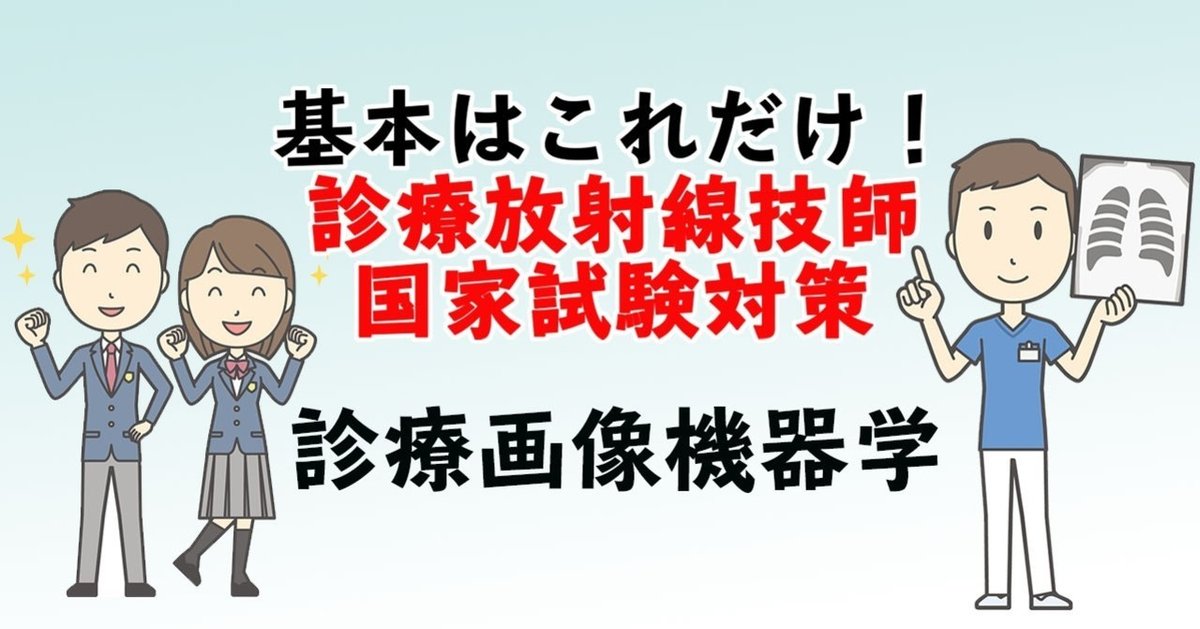
【診療画像機器学】②MR・超音波・眼底編
X線装置編、いかがでしたでしょうか?
今回はX線を使用しないMRや超音波、眼底について書いていきたいと思います。
画像、画像の中の記号や単位の説明、また太字は覚えてくださいね!
まずはMRIから!
☆MRI編
どうやって画像を作るのか?等の基礎知識はどの教科書にも載っていますのでそのあたりで調べてみてください!画像付きの方がわかりやすいかと。
MRI装置の構造
各コイルは、内側(人が入るところ)から外側に向かって
RFコイル→傾斜磁場コイル→シムコイル→静磁場コイル
という風に並んでいます。
静磁場コイルは冷却が必要なため、液体ヘリウムで満たしたクライオスタットという真空断熱容器の中にあります。
シムコイルは静磁場の均一性を向上させる操作を行うためのコイルで、この操作をシミングと呼びます。
シミングには
パッシブ(受動)シミング→装置の磁石のまわりに金属片や金属板をはりつける
アクティブ(能動)シミング→電磁石を使って均一性を調整する
2つの方法があります。
装置の分類
MR装置には静磁場の発生のしかたによる分類があり、
・超電導方式(高磁場、液体ヘリウムでの冷却が必要)
・常電導方式(低磁場、維持費が高額)
・永久磁石方式(低磁場、大きい、重い)
があります。
超電導装置の液体ヘリウムは何らかの原因で漏れ出してしまった場合急激に気化し、体積が何百倍にも大きくなり、爆発を引き起こし、酸素濃度も低下します。
これをクエンチといい、ごくまれに確認されており、煙などが見られた場合、速やかにガラスを割る、ハンカチ等で鼻や口を覆うなどの対策をとる必要があります。これも時々安全管理学として出題されることがあります!
ここから先は
3,510字
/
8画像
¥ 500
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
