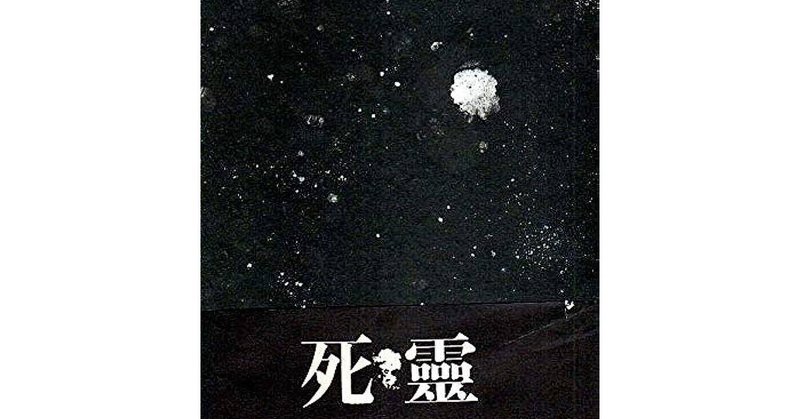
哲学を文学にすると
まともに哲学書を読み通したことがないのに、哲学をなぜ自分のそばに置いているかといえば、学生時代ぼくの周りで、といっても左翼小児病にかかった小さなサークルではということだが、ぼくだけが埴谷雄高を理解していると思われたからだ。みんな一様に難しいというのに、ぼくには何か既視感のような感触が確かにあった。「死霊」の最初のページからどこかに馴染みの雰囲気があった。中学校の理科の実験室の暗がりのような場所とか、街外れの古い病院の木製の手すりのある回り階段とか、鬱蒼とした森に続く小道で斃れた医学生と彼を労わるように寄り添う少女というカップルの面影とかがそこにあった。
「死霊」を再読して1章をとにかく読み終え、先日第2章に入って三輪与志の性格描写の部分を読んで、それは三輪与志の恋人の母が彼をどんな人物か確かめようとする場面での地の文で、彼の有名な自同律の不快を解説するエピソードが語られている部分なのだった。その数ページがさっぱり分からなかった。ええっ、何と言うことか。全く何を言っているのか理解不能に陥ってしまって、もう眠くなるモードに入って抵抗できなくなったのだった。
今日、そのページから読み始めてみると今度は普通に読めた。こんなことがあるのだろうか。それは三輪与志の哲学の出発点を描いていた。ぼくにはサルトルの「嘔吐」との同質性が感じられた。(モノとしての)存在が自身を持て余して現象を待ちわびている瞬間の、不気味な出会いが似ていた。
「このひっそりと恐ろしいばかりに静まり返った、身動きもせぬ世界、毛筋ほども身動きすれば自身の形が崩れてしまう世界は、<ある>と言う忌まわしい繋辞を抱きしめて、歯を噛みしめたまま、身動きもせず跨っている、あっは!存在と不快と同意語であるこの世界は、忌まわしい繋辞の一つの端と他の端に足をかけて、悲痛な呻きを呻き続けているのだ。誰がこの呻きを破って、見事な、美しい、力強い発言をなし得るのだろう。」
、、、よかった。ぼくは自分のほとんど唯一のアドバンテージが失われたかと思った。これでまた読み続けられると安堵したのだった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
