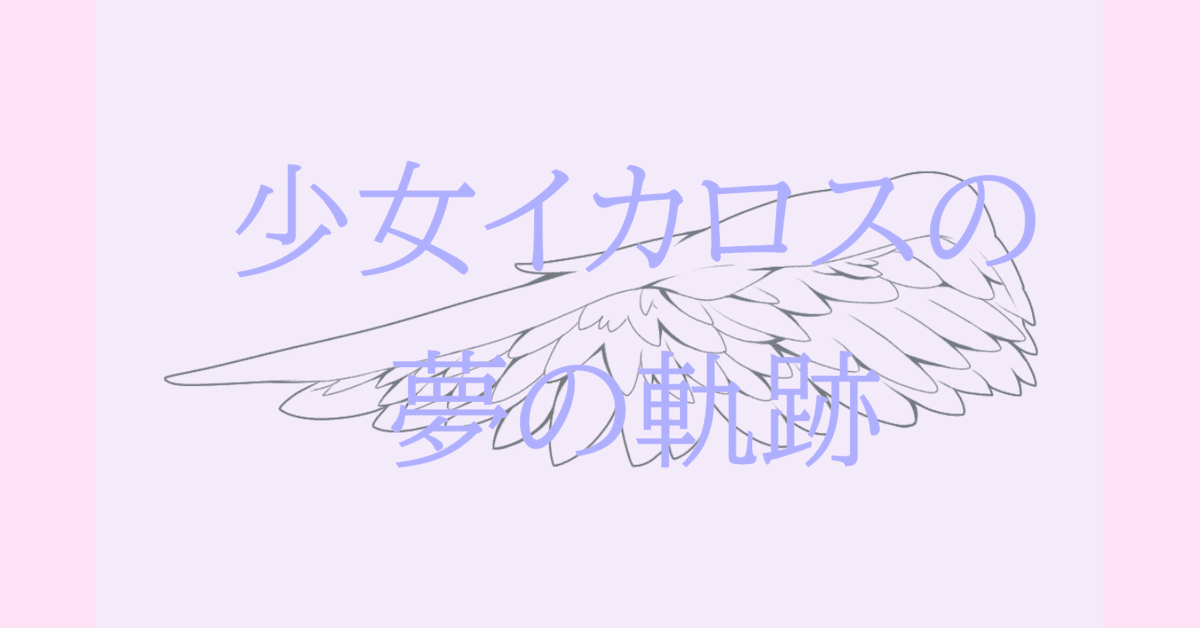
少女イカロスの夢の軌跡
教室の隅、微かな煌めき。
けれど、当時の私には充分すぎる程に美しい光だった。
小学校の頃に感じたあの光が、今私の隣に居る。それだけの事実が、私を満たす。心の中にとぷとぷと注ぎ込まれる幸福が、私の何もかもを満たしていた。
視界も、思考も、聴覚でさえ。私の全ては彼のもの。
他人から疎ましそうな目線を送られることも少なくはなかったが、それが気にならない程には彼以外が見えていなかった。
「おはよう」「また明日」「おやすみ」
そう彼の唇が動く度、私は耳から侵されていく感覚に酔う。彼の言葉が、音が、私を満たす。
けれども、昔感じた光よりも随分と……鈍く、重たくなっているようにも感じられた。それに対して、少しの物足りなさすら感じて。
あの時感じた強い光は、今や闇に飲まれているようで、私には一つだって魅力的には見えなかった。
彼の隣はいつだって私。それなのに、彼がそうなってしまった理由なんて、私には知る由もなく彼との関係がついえてしまった。
それから幾年か過ぎた頃、私はまたあの時の感覚を思い出した。……いや、それ以上の感覚を得たのかもしれない。
彼よりも、強く明るい光を見たのだ。
初めは少しの好奇心だった。Twitterのタイムラインで見た、一見暗い濁った海のようにも見える場所。仲の良い友人に誘われて、フラフラとその辺りを歩いていた。その時に、視界の端にその光が写り込んだ。
夜の街。ネオンが輝く街並み。
ギラギラとしているこの街の中、1人際立ってきらきらと煌めきを放っている。
「こんばんは。こんなところでどうしたの?」
心臓の鼓動が、ばくばくと鳴り止まない。
頭の中でその音が響く。目の前が白く埋まる。脳がぐつぐつと沸騰して、気分が昂っていく。
強い、強い光。それに触れたい……そう強く、強く思う。
「こん、ばんは」
やっとのことで開いた口からは、自分が思うよりも高い声が漏れだした。
そんなことよりも、もっと私にとって重要なこと。すぐ近くに見える、強く明るい光に触れてしまいたい。その光を、もっと浴びたい。もっともっと近くで浴びていたい。
その後は誘われるようにして彼の働くお店に入った。
そこがどんなお店で、とか、今どのくらいお金を持ってて、とか。そんなことすら考える余裕すら残ってない。
彼が、傍にいる……それだけで、充分に幸せになれた。
勧められるがまま、何杯かお酒も飲んだ。そのまま呑まれて、ふわふわと浮ついた気持ちでいた。
それでも、彼から目を離すことが出来なくて。
視界が真っ白になっても、彼の姿だけははっきりわかった。彼の光で目の前は白く塗り潰されているというのに、その中心にいる彼だけが、何故かしっかりと見えていた。
その後も何度か彼のお店に通い、少ないお金を沢山たくさん使って、彼の光を浴び続けた。
彼のお気に入りになれているかは分からなかったけれど、他の女の子達の視線を感じるに、恐らく金額と彼の感情は釣り合っていなかったのだろう。
でもそれも、どうでも良い。だって、私が浴びたいのは「光」なんだ。「彼が良い」んじゃない。「彼の持つ光が良い」んだ。
彼だけじゃない。色んな人からそれを浴びていたい。もっと沢山、もっと長く、もっと、もっともっと……
そう考える度に、どんどんと私は孤独に飲まれていく感覚がしたのだ。
ホストクラブに来て気付いたのは、私の求める「光の強さ」は「どれ程の人を魅了しているか」にある程度比例するようだ、ということ。
ここのホストクラブの所謂「No.1」の称号を持つ人は、そもそも姿がぼんやりとしてしっかりとは認識できなかった。
けれど、アイドルやモデルといった人達には強い光を感じない。寧ろ、影って見える人まで居た。
不思議な感覚を抱えながら、私はまた彼に会いに行く。強い光と代償に、普段より大きい額のお金を支払う。
今日も、あのほわほわとした強い幸福を感じる。
そう、思っていた。
お店に入ると、顔馴染みのボーイさんから「お待ちしておりました」なんて声を掛けられる。
なにか約束でもしたっけ?覚えてない、知らない。
困惑、不安。一抹の負の感情。
何も返せずにいると、ボーイさんから住所を伝えられて、そこに行けと言われたのでタクシーを捕まえてそこへ向かった。
伝えられた住所はマンションの一室。呼び鈴を鳴らして、先程の旨を伝える。
扉が開いて、中から出てきた人物の姿は、想像していたものよりも若干のズレが生じていた。
ぼさぼさの髪の毛、よれた服。それでもまだ、私の目には光が写る。
私を見た瞬間に、彼から倒れ込むように抱き着かれた。
「え、と……どう、どうしたんですか……?」
強い困惑、混乱。私には耐え難い現実が頭の中を殴って回る。
怖い。こんなことは、必要じゃない。
隣に居たかった。触れ合うのは、望んだことじゃない。
「……はは、ごめんね?」
お酒を嗜んでいたのか、彼からはアルコールの匂いがした。
そうか、これはお酒のせいだ。元々こういうことを望んでいる訳では無い。
私を呼んだのだって、手頃な奴だったから……そう思うことにした。そのまま私の脳に蓋をした。
彼の話を聞くに、他の子とは違う雰囲気を持つ私に安心を感じたのだそうで。
確かに、他の人よりベタベタしなかった。けれど、それは触れ合いたくないという気持ちからだった。
だからこそ、こうやって好意を向けられていることに嫌悪感すら感じている。今すぐに突き飛ばして逃げたいくらいだった。
それなのに、それなのに。
私は未だ光を求め続けていた。
もはや依存だ。ここまで来ると、禁断症状も出てきそうになる。
それほどに、私は光に魅せられてしまった。
だから、この時彼の言葉を聞き入れてしまったんだと思う。……そう、思いたい。
「俺さ、ホスト辞める。だからさ、隣に居て欲しい。……付き合って欲しいんだ。」
隣に居る。私にとって、その言葉は魅力的過ぎた。
もちろん直ぐにはい喜んで、とは行かなかった。けれど、あの光を独り占め出来る……そう思っただけで、脳がどろどろと溶けてしまう感覚に襲われた。
なのでその時は、付き合うことは保留にして、隣に居ることだけを承諾した。
「まだ私が、貴方のことを好きじゃない」
なんて言葉を置いて帰る。その言葉は、私の感情を置き去りにしそうだった。
少しずつ、彼の隣に居る時間を増やすと、どうも光に魅せられてしまうようで。
「お前のことしか見ていないから」
なんて、甘言を少しばかり垂らされただけで、ころりと落ちてしまうくらいには彼への独占欲が沸いた。
彼の持つ光は、誰より強くて美しいのだ。
そんなものだから、彼はホストを辞めることになり、私は彼の彼女となることになってしまった。
……少し、不安な事があった。
「本当に愛されているかどうか」といった典型的な不安では無い。寧ろ、それは十分だ。
何度かデートにも赴き、恋人として愛し合うことだってした。……その度その度、身体が光に焼かれていく感覚がするのだ。
不安の対象はそっちだ。ふわふわと空を飛んでいる私が、焼け落ちてしまう感覚に陥る。
それが、どうしたって不安だ。じわりじわりと肌が火傷して、傷が残る。いつの日か自分で背負った羽は、光の熱で溶ける。
そして、私の全てが焼け落ちてしまったその時。
……私は、どうなってしまうのだろうか、と。どうなろうと、私はそれに抗う事が出来るのだろうか、と。
その一抹の不安を抱えながら彼と過ごす日々は、陰っていくように感じられた。
それからまたいくらか月が過ぎて、寒さに凍えるようになった頃。
何の気なしに、フラフラとまた夜の街を徘徊していた。
何度も足繁く通ったおかげか、キャッチからの逃れ方も覚えていた。寧ろ、寄せ付けないようにしている。
最近の彼はどこか忙しそうだった。夜が深くなるまで帰ってこず、朝もいない時だってあった。
少しの寂しさと、困惑。
それは、私の不安を増幅させるのには十分な材料だった。
今日もまた、彼は帰らないようだったので、寂しさを埋めるために、夜の街へふわり降り立った。
人気ホストを辞めさせた姫、としてそこそこ有名になってしまったらしい。周囲の視線が体全体に刺さる。
それが私の火傷跡に刺さると、その辺がひりひりと痛み出す。
え、────
声が、喉から零れ落ちた。視界が暗く染る。その中、“それ”だけが浮いて残る。先程まで感じていた痛みが消える。
私より大人っぽい女性の腰に手を回す彼、……いいや、それ。
一瞬で全てを理解出来た。そして呆然とする。
そうしている間にも、それと女性は唇を合わせ、笑い合う。
なんで、どうして、そんな女と。
つかつかと詰め寄り、それの腕を掴んだ。
女性はこてんと首を傾げ、それは酷く驚いた顔をした。
「どう、したの?こんなところで……偶然だね?」
目が泳ぐ。どうして?どうして、そんな行動。そんなにこの女に信頼が置けるの?その仮面が剥がれるほど?
ああもしかして、辞めたのも、こいつが、あぁ。
「ねぇ、その女と今すぐ別れて。もう二度と浮気しないって誓って。」
───そしていつしか、私と永遠を誓え。
また、ぼんやりと夜の街を歩く。視線が痛い。けれど、もうどうでもいい。
結局、“あれ”とは私が別れることになった。
あの時、私は怒りに身を任せ、周りを気にすることなく叫んだ。
そのまま殴ろうと腕を上げたが、いとも容易く止められてしまった。
平常心を取り戻したそれに宥められて、「二度と会うな」と残して帰路に着いた。
付き合っていたあの頃は、あれだけ光に魅せられ、不安になっていたのに。
無いとまた「欲しい欲しい」と求め始めるのだから困る。依存とは恐ろしい、そう身に染みて感じる。
だから、また光を浴びることの出来る場所へ足を向ける。
その時、鈍く重たい空気感が肌を撫ぜた。強い既視感。それに飲み込まれてしまいそうな感覚に陥る。
「久しぶり、翼ちゃん。」
その声を、私はよくよく知っていた。
小学校の頃感じた煌めき。いつしか闇の中に飲まれた輝き。
「……真守、くん」
名前を呼ばれ、呼び返す。強く感じる、知らない感覚、幸福。
どくどくと心臓が脈打つ。呼吸が浅くなる。息が、息の仕方が、分からない。
不意に抱き寄せられて、包み込まれる。その感覚はまるで深海だ。強い水圧に肺が潰され、呼吸が少しづつ出来なくなっていく。
私は、知らないのだ。海水から酸素を取り出す方法を。知らない。けれど、どこか安心出来る。それに戸惑いを感じた。
「ねぇ、空の旅は楽しかった?」
……空。そうだ、私は今まで確かに空を飛んでいた。
羽が崩れたのは何時だったのだろうか。私と羽、羽と羽同士を繋ぎ合わせていた蝋が溶け、無くなったのはいつだったのか。
そんなもの分かるわけが無い。落ちている間ですら、私は飛んでいると錯覚していたのだろうから。
「……分からない。」
だからこそ、私はそう答える。楽しかった?もう分からない。それに、その意味も。どうして、私が空を飛んでいたと知っているの?
「そう……それなら、今度は」
────海の中へ、おいで。
その瞬間、私の肺に残された空気がごぽりと音を立てて出てくる。代わりに水が肺に流れ込む。彼の音が、闇が、空気が。
彼以外が暗く染る。彼だけが浮いて残る。
深海も、悪くは……無い、のかな。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
