イノベーションとは何かがよくわかる「ビジネスモデル全史」
先日、私より随分年下で、IT生え抜きのデキる上司に言った。「戦略とか、フレームワークとかが分からなさすぎるんです。」その時にオススメされた本の1冊。様々な、その時代に革新的だったビジネスモデルがずらっと紹介されている。古くはメディチ家や日本では越後屋から、現代ではFacebookやアリババまで。
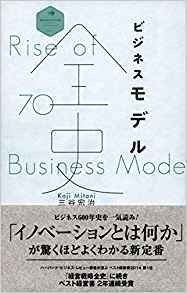
この著者は、ビジネスモデル革新時期を3期に分けている。
1期(1990年ごろまで)
この頃までに、基本的なビジネスモデルはほとんど出来ている。いかに作るか、いかに売るか。というモデルが多い。(ジレットの)替え刃モデル、プラットフォームモデル、小売業態の色々、大量生産モデル、リーン生産モデルなど。
2期(1990~2001)
ネット系ビジネスモデルが加わる。ネットの普及により、これまでトレードオフだったリーチとリッチネスが両立可能に。誰に、どんな価値を提供し、どうやって対価を得て、どうオペレーションするのか、の各レベルで自由度が増したため、ビジネスの形態の幅が広がった。オープンイノベーション、クラウド、ロングテールなど。
3期(2002〜)
ここではあまり新しいビジネスモデルは生まれてこず、かわりにグローバルレベルで市場の上位集中度が高まっている。巨大プレイヤーと、小さい外部企業が結びつきやすくなっている。ビジネスモデルはイノベーションの素になるという説も。appleが世界同一基準となるiphoneを世に送り出したことによって多くのサービスが生まれ、appleがその収益の一部を得続けるなど。この時期生まれたものには、フリーミアム、オープンイノベーションなど。
また、ビジネスモデルを大まかに4つに分けてあり、それがとてもわかりやすかった。
儲け方:替え刃、ポータル(広告)、検索語(グーグル)、有料会員...
作り方:クラウドソーシング、水平分業、リーン生産...
売り方:ダイレクト・ワンストップ、オムニチャンネル...
決済・資金調達:マイクロペイメント(ペイパル)、モバイル端末決済、クラウドファンディング...
この4柱に分けると、自分の仕事のどの部分にイノベーションの余地があるのか考えやすい!そして、今残っているビジネスモデルたちがなんと美しく、必然感があることか。それぞれのビジネスモデル誕生のエピソードを読むと相当に苦労があったのがわかるのだけど、どれも今では誰でも考えられるレベルに自然に存在していて、感動する。今、自分が考えようとすると「全ては産みつくされていて、もはや何の余地もない」みたいな絶望的な気分になったりするけれど、きっと全然そんなことないのね、という気持ちになった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
