言語学の方へ、言語学から出発して
花粉の季節ですね。ふと、人間に対する自然の逆襲、というイメージがわきました(苦笑)。
年度末なんで、バタバタしている部分もあるんですが、自分の時間は多少できるので少し読書の時間も取り戻せました。今は、言語学関連の本を読み進めています。
一応、仕事で英語を教え、休日に詩学を探求、みたいなライフスタイルが確立されつつあるんですが、いずれにせよ、「ことば」に関わる営みなんですね。そう考えると、やはり、言語学という科学は無視できない。とはいえ、言語学というのは比較的新しい学問でもあって、元々は哲学が担っていた問いの一部を継承しているような面もあるので、わたし自身もゼロからスタートというよりは、哲学を勉強していた頃に抱えていた問いを、言語学の枠組みや用語で整理し直している、という感覚なんですよね。哲学から言語学というのは、習得論の用語を借りれば、「転移」がしやすい学問かと思います。
それで、一般教養の『言語学』なんか読み直していたんですが、それこそ、フランス現代思想を勉強していた頃にそれとなく読んだソシュールなんかから始まり、ロマン主義のゲーテに由来する「形態学」があり、わたし自身、脱構築の核にあるとみる「語源学」があり、あるいは「統語論」は大学受験の『英文解釈教室』みたいだし、詩の音楽性を追求するならば、やはり、「音声学・音韻論」を勉強した方がいいじゃないかとか、色々連想がつながりはします。

正直、大学にいた頃は言語学をやろうとは思いませんでしたけどね…。まあ、でも、年齢もあるかなという気もしますね。ある意味、文学や思想を通して「実存的に」問うていた問題系を、もう少し距離をもって、ひとと共有できる仕方で整理し直したいということかもしれません。
★
それでですね、特に、「認知言語学」なんですね。わたし自身の出自はフランス系なので、もちろん、全然知らなかったんですけど、チョムスキーのいわゆる「生成文法」に対する批判意識から生まれた英語圏の言語学の一流派で、広く認知科学(心理学や脳科学も含む)とも関係がある言語学なんですね。で、わたし自身が最初にこれに興味を持ったのは、やはり、ウィトゲンシュタインの野矢茂樹先生経由なんです。

この新書、有名なものですが、ウィトゲンシュタインや日常言語学派の哲学に通じた野矢先生が、認知言語学の専門家・西村義樹さんと対話するというものなんですね。で、確かに、読むと後期ウィトゲンシュタインの問題系を発展するような仕方で議論が深められているような部分もある。わたしなどが偉そうに言うことでは全くないんですが、明らかに、『哲学探求』のウィトゲンシュタインは言語の「使用法」みたいな問題にこだわっていて、認知言語学の「用法基盤モデル」(Usage-Based Model)というのは、これの継承者みたいにも見えてくるわけです。
で、これは最新の研究ですが(笑)、わたし自身がいま追っているフィリップ・ベックさんの詩法が「ボワローに抗して」という文言を掲げていて、これもやはり、頭の中にある「意図」というよりは頭の「外」にでた言語、いわば「用法」の次元での言語の展開を重視するものなんですね。もちろん、ウィトゲンシュタインや言語学者が(どちらかと言えば)「日常言語」を相手にするのに対し、ベックさんは「詩語」を探求しているわけですけど。でも、ベックさんにおいてもウィトゲンシュタイン(やスタンリー・カヴェル)が重要とわたし自身は見ていて、どこか通底する部分がある気もしているんです。
という意味ではですね、認知言語学陣営のジョージ・レイコフが『詩と認知』と訳されている本で、「日常言語」の比喩と「詩語」の比喩の連続性を指摘するのは、わたしは存外面白いと思うんですが…。ここは少し意見が分かれそうな気もします。(例えば、野沢啓さんの『言語隠喩論』はレイコフに対しかなり批判的のようでした。)
認知言語学というのも、内部で色々タイプが分かれるみたいなんですよね。上記の、『言語学の教室』も、元々はフランス系の酒井智宏さんが企画されたシンポジウムが出発点になっているみたいで、酒井さんが研究されていたジル・フォコニエというフランスの言語学者は、アメリカに渡り、認知言語学者と近いところで「メンタル・スペース理論」なんていうのを提唱していたりもしたそうです(https://www.jstage.jst.go.jp/article/gengo/144/0/144_55/_article/-char/ja/)。個人的には、フォコニエは目下の関心ではないんですが、これを訳されているのは(わたし自身も多少関わりがあった)駒場のフランス語部会の坂原茂先生ですからね…。狭い世界だな、という気もします。(大堀壽夫先生や坪井栄治郎先生は一般教養で英語とか習ってた気がするんですけどね…。まあ、そういう「名前」を記憶から掘り起こして、いま、文献を追っているわけです。)
現代文なんかでも出てきそうな「記号論」の池上嘉彦さんも、学問的には「認知言語学」に分類されるみたいです。素人目に見ても、どちらかと言うとその先駆け的な位置にいらっしゃったのかなとも思いますが、分野の古典的な教科書とされるウンゲラー/シュミットの『認知言語学入門』など、訳されています。
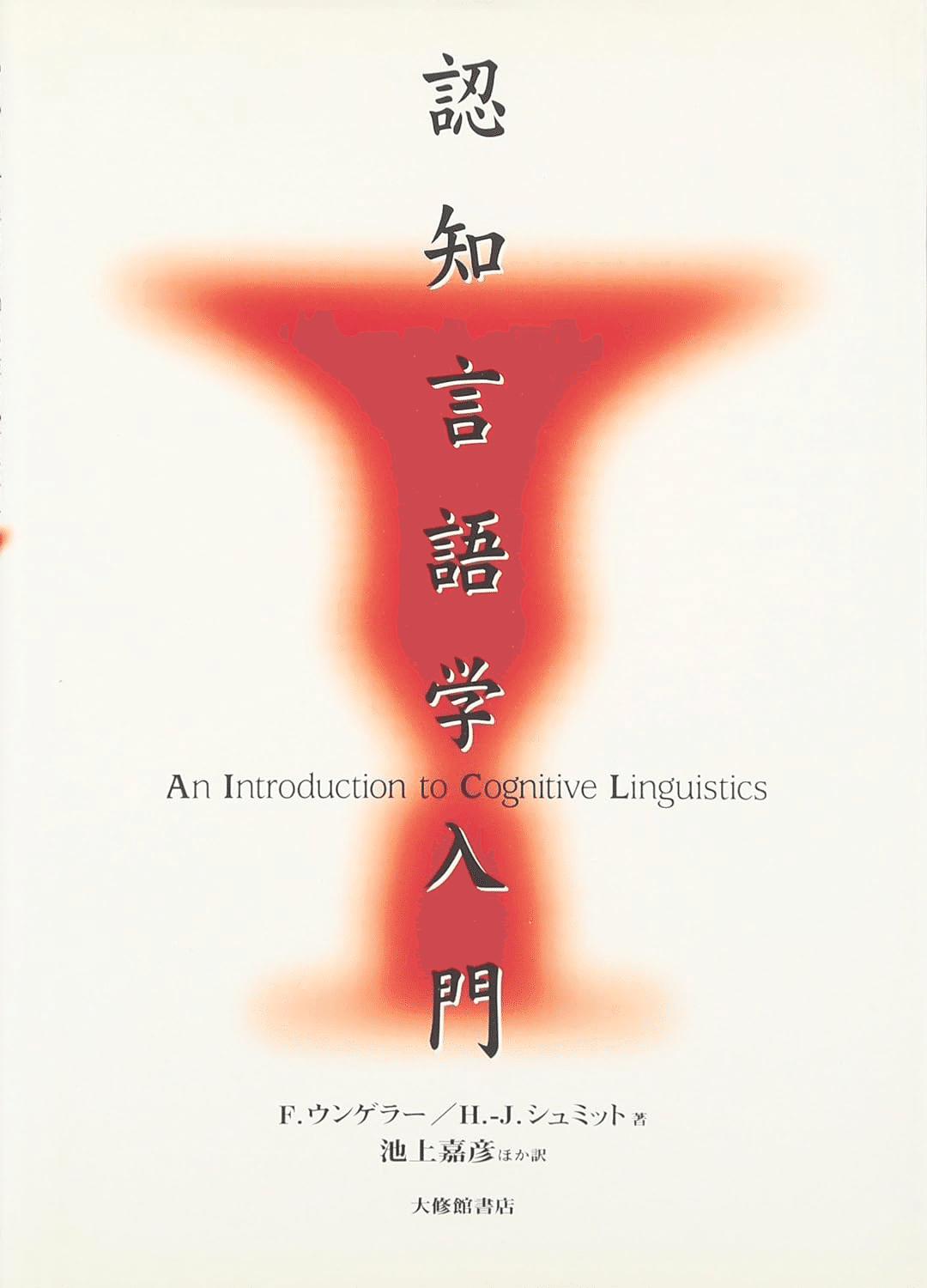
たとえば、氏による訳者解説にこんな文言があるんですね。
「表現の形式が違えば、たとえ同じ状況を言語化しているとしても、把握の仕方が違い、したがって意味も異なるというのが認知言語学の基本的な姿勢である。(考えてみれば、そのような認識は文学でははるか前から当然のことであったわけである。〔中略〕」
この辺りの文言を見ても、池上氏は少し文学論や文化論に寄せる仕方で認知言語学にアプローチしていたのかな、と(素人目には)見えるのですが、個人的には、まさに、このあたりに関心があるわけです。言語そのものにある文学性、みたいな問題ですね。
で、また全然違うと言えば全然違う文脈なんですが、佐々木中さんが『夜戦と永遠』で論じたピエール・ルジャンドルのテクスト論なんかとも遠く響き合う気がするんですよね。あそこでは、文学を超えて、テクストは「ダンス」になるんですが!
☆
まあ、しかし、きちんとした学者の書き物を読んでいると、「結局自分は何の専門家にもなれなかったな」としみじみ感じてはしまいますね。でも、社会に出るとよくわかるんですが、「適性」みたいなものは如何ともしがたく、誰にでもあるのかなと思います。わたしは「専門」はないんですけどね、貫通する「転移」の身体感覚で、何とか乗り切っていければ、と…(苦笑)。
Have a nice pollen day!
栗脇
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
