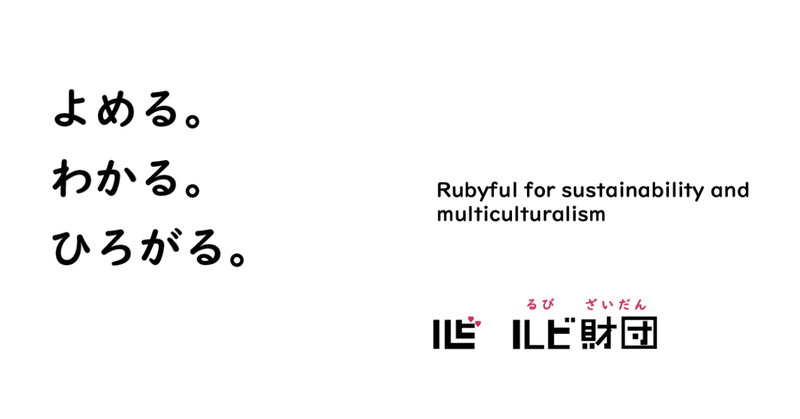
ルビと自由:言葉の力で自分らしく生きる
先日設立されたルビ財団に、理事として参加することになりました。ルビを活用することが、私が大切にしている「自分らしく生きる」ということにつながると考えてますので、そのテーマで書きたいと思います。
ルビ財団のウェブサイトはこちら
音読と自信
思い出してみてください。学生時代、先生に指名されて教科書を音読した経験はありますか?その経験が辛かったと感じる人も多いのではないでしょうか。
落語家の柳家花緑さんは文字を認識するのが難しい識字障害で、今はそれを受け入れて大活躍をされています。
この記事に子どもの頃された経験が書かれています。それによると、学校で音読に苦労し、クラスメイトに笑われていました。
https://fujinkoron.jp/articles/-/960?page=2
同じような経験を持つ一般の方も少なくありません。
東洋経済オンラインに掲載された『学校で「なぜ本を読むのか」のサポートが必要、子どもが本嫌いになる3大理由』によると、子どもが本を読まない上位3つの理由のうち、第3位が「音読で恥をかいたから」だと述べられています。https://toyokeizai.net/articles/-/662641
さらに私が以前、西任暁子さんのサポートをしていた際、数百人がオンラインで参加した話し方教室で新美南吉の『てぶくろを買いに』の音読を実施しました。この経験から、音読による失敗体験を抱え、人前で話すこと自体が嫌になったという受講生もいたことを知りました。
たまたま知らない漢字があって読めなかった
ということが、笑いの対象になる、本を読むこと、話すことへの自信を失う原因となることがある。
もしルビが振られてたら、それは起きなかったのではないでしょうか。
算数が苦手で馬鹿にされた場合、「算数なんていらないし」と自己弁護が可能かもしれません。しかし、日常的に使う言葉について馬鹿にされると、心へのダメージ、他の学習への影響は大きいと言えないでしょうか。
ルビは子どもっぽい?
子どもが読解力を身につけると、ひらがなが多かったり、ルビがついている本を「子どもっぽいから嫌だ」と感じることがあります。
この意見の裏には、「ルビなしの本を読めるのが良い、読めないのはダメ」という価値観が潜んでいる可能性があります。これは、「何かをできる人が素晴らしい、できない人はダメ」という価値観につながります。
これが、先程の音読のときの笑いに繋がります。
もし大人の本でもルビが一般的に振られていたら、本を読む際の「ルビありの本は子どもレベル」といった先入観が減り、単に「この本が楽しそうだから読む」という理由だけで本を選べるようになる可能性がある。
何かをできないことで人を笑うのではなく、
それぞれが自分のやりたいことをする、自分らしく生きることができる。
もちろん、親を始めとした大人が人と比べることをやめられない限り、子どもが人と比べて馬鹿にするのはきっと止められないでしょう。そこが完全になくなるのはまだ時間がかかるかもしれない。
でもきっと、日常的に使う言語で笑われるということが少なからず減る。本を読むこと、話すことが嫌という人を少しでも減らせる。
ルビ財団の活動がそのような世界をつくることに貢献できればと思い、活動しています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
