
三宮から明石へ、その2
敦盛塚を過ぎ、蕎麦を食べて、久足は垂水で一泊します。
現在の敦盛塚から垂水までは、線路脇に大型トラックがビュンビュン通る海沿いの幹線道路があり、歩道は確保されているものの、歩いていると気が休まりません。途中、海釣り公園を経て、垂水に着きました。
かくて堺川といふ砂川をわたれば則、播磨の国にて明石の浦なり。さて塩や村といふをすぎて須磨より二里というに垂水といふ村にいたりて、この村の阿波やなにがしといふものゝ家にやどる。
久足は、須磨で月を見たかったようですが、須磨には人を宿すところがなく、あっても海から遠いとかねて聞いていたので、垂水に宿ることにしたようです。
さてこたびこのあたりにものしたるは、もとより月見むとてのしわざなるを、ほどよくもこよひは名だゝる十三夜にて、空にちりばかりの雲もなきはいとうれし。須磨の里には人やどす家もなく、はたうみべにとほければ、この村にやどりたる也。この所は海にいとちかく、宿りのうらはやがて海なれば、月見むためにいとたよりよし。夕げなどたうべ、ゆあみなどするほどに、はや日もくれかゝりたれば、宿りのそともよりうみべにいでて月を見んとす。
夕食を食べ、湯浴みをしたのち、いよいよ念願の月見です。
日もくれはてゝ名にしおふ長月の光ちりばかりもくもりなく、金波とかやいひて波にたゞよひうつるさま、いはんかたなく、淡路島はたゞむかひのかたに見えたれど、いさゝか月にさはらず、又東のかたに和泉・摂津の国の山々もあれど、そはいととほく、よるのめにはわかぬばかりなれば、月のいでたるかたには何のさはりもなし。まことに昔より「須磨・明石の月」といみじくいへるもうべなるかな。うみ風いとしづかにして、汀の波もいさぎよく、うみの面なだらかにしてものすごからず。かけてもことの葉にはのべがたきけしきなり。かばかりめでたき月のけしきを、これまで見たることなく、よしのゝ花にもおとらずなん。されば歌よまんにも口ごもりて、いとくるしけれど、又よみいでぬもはえなきこゝちのせらるれば、からうじてひねりいでたる。
契ありてこよひこそ見れいく秋かこゝろにすみしうらの月影
感動のほどが伝わりますね。ここで久足は湧き出るまま十三首の短歌を詠みます。
さて、こちらは夜ではなく昼ですが、久足の感動を追体験したく海を眺めたものの、休業中(?)のアウトレットモールが淡路島を遮り、まあ、そんなもんか、という眺めです。
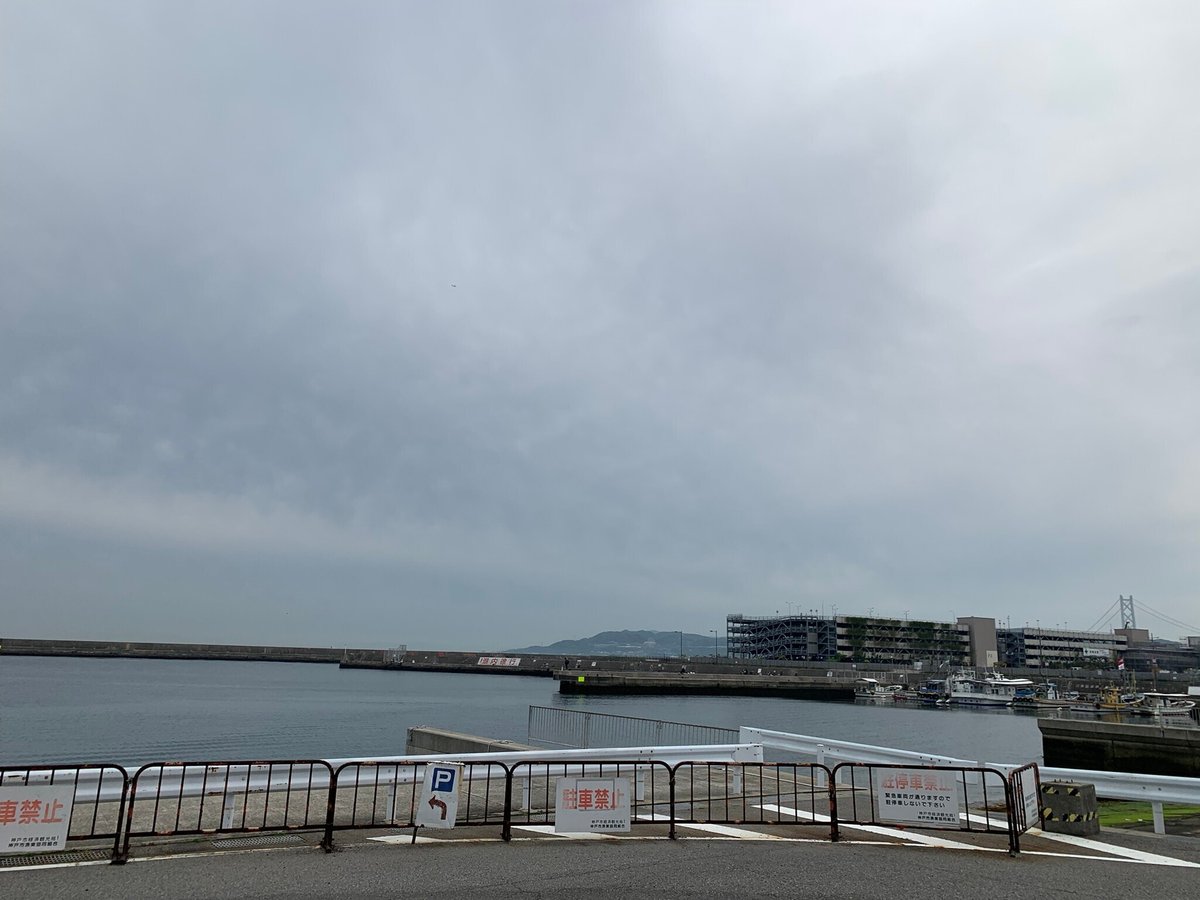
一方の久足は、筵(むしろ)を敷かせて夜が更けるまで月を眺めつづけます。
むしろなどしかせてたゞひとりしづかにながめ居たるも、いとおもしろくたとへむかたなし。やうやうよもふけゆくにつけては、浦風すゞろに身にしみてさむければ、かくばかりをしとおもふよを、などうちすえながら、しぶしぶ宿にかへりてよるのものひきかづきたるも、いといとなごりたゞならぬこよひのさまにて、わすれがたしや。まことにこのとしごろおもひかけたる、すま・あかしの月をゝりよくも十三夜にちりばかり心にかゝる雲もなき光をみたること、としごろのほいかなひてうれしともうれしくおぼゆるを、かたはらいたくおもはん人もありぬべくや。
「しぶしぶ宿にかへりて」に、後ろ髪引かれる思いがよくあらわれてますね。
たまたま見たのではなく、歌枕という歴史的な時間、それを見たいと思い続けた久足の個人的な時間、そして九月十三夜にちょうどたどりつくように旅をした時間、と幾層もの思いと時間が重なり、この感慨にいたったわけです。
そうなんですよね。久足を追って旅をしているとよくわかりますが、目の前の風景を、古人も見ていた(ぼくの場合は、久足が見た)、と幻視することで、感慨は何倍にもなります。時間を越えた共感が、感動を呼ぶともいえますね。
さて、久足はここで一泊ですが、こちらはまだまだ歩きます。といっても久足はこの日、三宮発ではありませんから、久足より歩いているわけではありません。
翌十四日、まず海神社に詣でます。
十四日。朝とく宿りをいでゝ、このさとなる日向大明神といふにまうづ。大社也。この御社の御ことを海(ワタツミ)大明神とも申といへば、『式』に見えたる〔明石郡〕海神社なるべし。又このさとに遊女塚といふ大きなる塚有て、ふるきよの墓と見ゆれど、ゆゑよしをしる人なし。


場所は移動しているようですが、遊女塚(宝篋印塔)もちゃんと残っておりました。
つづけて向かった先は、千壺陵こと五色塚古墳です。これは圧巻でした。




又千壺陵といふもこのさとより半町ばかり入たる所にあり。この千壺の陵といふは五色塚ともいひて小だかき岡なれど、もとよりの岡にはあらでまたくつくりたる山也。めぐりに堀の跡も有て、千壺の名もしるく、あかき壺をおほくうづめたり。
さて五色塚といふゆゑよしは、里人のつたへに、「仲哀天皇と神功皇后の御あそびに、この壺に五色の花をさしたまひて、このめぐりなる堀の水をひとつのつぼにいれ給へば、おのづから千のつぼにもその水のみちたるによりてかくいふ也」といへど、いと俗にうきたることなり。よりて考に、こは『書紀』に押熊王襲坂王の仲哀天皇の陵を明石につくりたまへるよし見えたる、その陵なるべし。
さてこの千壺といふは壺のごとく見えたれど、そのまはりの見えたるのみなれば、おそらくは底なくして陵にをさめる埴輪ならんか、又は壺なるか。しるべのをのこは「ふかさ三尺ばかりのつぼなり」といへり。もとより壺はあかき色のつぼにて、まづふもとより五、六間上のかたに一つらにうづみめぐらし、又五、六間も間をおきてその上もおなじやうにうづみめぐらしたり。おほかた上のかたまでには四、五段もある也ければ、千つぼとはいへど、こはたゞ数のおほきをいへるにて、千の数にはまさるべし。かゝるふるき世の陶器を見ること、よにめづらしき見ものなり。
又この岡はなべて石おほく、これももとよりの石にはあらで、わざときづきたるさまと見ゆ。里人のいふには、「この石はこの国にはなき石にて、淡路島には今のよにもこの石のごとき石あれば、この石は則あわぢしまよりとりてきづきたるものならん」といへり。こはふるきよのつたへはしらで、今のよのさまにあはせていへるなるべけれど、『書紀』に淡路島より石をはこぶよし見えたれば、よくかなへり。かばかりあきらかなる陵なるを、なにゆゑ五色塚といひて、かゝるつたなき伝はいへるならん。この陵の上にちひさき石の神祠あり。これを里人は「仲哀天皇さま」といへり。さもあるべし。
さて、かくのぼりて見奉りたるは、いとかしこけれど、この陵には御なきがらをさめ奉らざるかりの陵なれば、くるしからぬことならんとおもひゆるしてなむ。
現在は、学術調査に則りつつ復元された姿となっており、壺もレプリカですが、久足はそれ以前、江戸時代の五色塚古墳の様子を詳細に書き記しており、じつに貴重で興味深い記述です。
なんでも、久足が聞き書きしている「この石はこの国にはなき石にて、淡路島には今のよにもこの石のごとき石あれば、この石は則あわぢしまよりとりてきづきたるものならん」という村人の言い伝えも、調査の結果、事実だと認定されているそうです。
さて、すぐに舞子の浜です。
もとの道にいでゝ八町ばかり海辺をゆけば、舞子の浜といへる名だかきところにいたる。この浜の松は枝さしひきて横におひひろがりて木立よにめづらし。又所のさまもおもしろし。この浜の茶屋によりて見わたする淡路島は十八町むかひなれば、その島の家居、山田などもいとかすかに見えつゝ、かゝる島をかくまぢかく見たるさまもめづらし。その外にとほく南より東かけて紀伊・和泉・河内の山々たちづゞき、紀伊国の友が島といふは辰巳の間にものよりはなれてちひさく見ゆ。小豆島は申酉の間に見えたり。その外にも島々とほく見えたり。この小豆島は「いやふたならび」とよみ給へる大御歌のごとく、ふたつならびたてり。明石の家居は西にながくさしいでゝ、いとながめおほくけしきよし。かくよの常ならぬ所なるを、舞子の浜てふさとびたる名をしも、いかなるをこ人がつけたりけむと心づきなし。言の葉にかけむもいかゞなる名にはあれど、わがごときさとびたる口つきには、かつは幸なるべくや。
白妙の袖うちふるかとばかりに舞子の浜に波ぞより来る
昔たがまひこの浜のなごりよりかざしの花と波のよすらむ
しかしいまは、松云々というより、明石海峡大橋に圧倒されて、他は目に入らない感じですね。

間近で見ると、自然もすごいけれど、現代の土木技術もすごいな、と感嘆せざるを得ません。

なんというコンクリートの塊でしょうか。久足が見たらなんというかなぁ。

さすがにこちらはヘトヘトになってきましたが、大蔵海岸を経て、ようやく明石到着です!
久足は、いくつかの神社に立ち寄りつつ、人丸社に向かいます。
この舞子が浜をすぐれば松のさまもよのつねにて、その色もかはりたり。やゝゆきて山田村といふをすぎ、ちひさき川ふたつをわたりて大蔵谷といふにいたる。こゝはやがて明石の入口なり。右のかたに八幡の御社おはします。その御社より三町ばかりゆけば稲爪大明神といふ額をかけたる御社おはしますにまうづ。いと大社なり。こは『式』に〔明石郡〕「伊和都比売神社」とあるをかくよこなまりたるにはあらじか。
この御社のまへより街道にいでずして北のかたにゆけば、休天神御社といふおはします。こは菅公の筑紫にくだり給ふ時いこひ給へるふるき跡にまつりたる御社なりとぞ。


この稲爪神社のあたり、旧街道の風情が残っていて気持ちいい道です。

この御社より壱町ばかり東のかたいさゝかこだかき岡のうへに人丸御社おはしますにまうでんとす。この道に護石大明神といふ御社おはします。壱町ばかり坂をのぼれば門あり。その門の前はうちはれてけしきよく、下には明石の家居立つゞき海べもいとちかく、淡路島はたゞむかひに見えたり。
かくて人麿大人の御社の御前ちかくをがみ奉るもいとたふとくかたじけなし。この御社をこの所にまつりたるは、「ほのぼのとあかしのうら」といふ御歌のあるよりのことなるべし。この御歌のことをひろく古ごと学ぶともがらは何とかやあげつらふもありときけど、さのみいはんはこちたきわざなれば、わがこゝろには、
なる柿のもとのこゝろはいはでたゞことの葉まもる神とあふがむ
いかにせむぬさとりあへぬ旅に又たむけとすべき言の葉もなし
御社の御前にはこのあたりしる明石の殿のたてられたるいしぶみあり。
人丸神社は、明石市立天文科学館のうえにあり、久足のいうように眺望のいいところです。



さて、この御社にまうづる道に俳諧師芭蕉といふをぢのたてたる碑ありしは、いとうるさくぞ見えし。このばせをといふ人の碑、所々によくあるものにて、中には所の名だてになれるもすくなからぬがおほき中にも、ことにこの御社などにむげにいやしき言の葉をはゞかりもなくたてたつこそおほけなけれ。されど、これはをぢのしわざといふにもあらねば、なまじひに好事、後人のしわざのあしきにやあらん。
又船の形したる梅のあるも、「ほのぼの」との御歌よりおもひよれるにや、いと俗に心づきなし。
又盲杖桜とて盲人の歌をよみてめのあきらかになりたるによりて、その杖をこの御社のみまへにたてたるに、花さきいでたる也といへるもうけがたく、はたその歌といふをもきゝたれど、さばかりのしらべともおもはれず。
又この御社を火防と今は申て敷島の道ならぬ火のまがをまもり給ふといへり。こはかぐつちの神にもおはしまさぬをいかゞ、と思ひて人にとへば、「人丸と申御名を、火とまる、とおしまげたるよりのしひごとなり」とぞ。
やっぱり久足、いろいろ文句つけてますね。
芭蕉自身が悪いわけじゃないと断りつつ、後世の好事家がつくった芭蕉句碑を「いとうるさくぞ見えし」といってますが、それもちゃんと残ってます。

「うけがたく」という盲杖桜もあります。

久足も「人丸と申御名を、火とまる、とおしまげたるよりのしひごとなり」と聞き書きしてますが、いまも「人丸」=「ひとまる」=「火止まる」ということで、火除けをうたっているようです。
さて『式』に見えたる〔明石郡〕赤羽神社と申もこのあたりときゝしかば、たづねとふに、「十町あまりゆきて又十町かへる所なり」といへば、この明石より船にのらんに時うつりてたよりあしければ、えまうでず。
この御社の北のかたなる御門より坂をくだりて明石の町にいる。町の中に忠度塚とて忠度卿の墓あり。杉の大木二もとありて塚じるしなり。前にはいしのいがき有。又なにをゑりたりとも今はわかりがたき石碑と、又この所しるあかしの何某の歌をゑりてたてられたると、ふたつあり。
まことにこの忠度卿の言の葉はよにすぐれ給へるがうへ、しかもその道に心ざしふかくて、都おちの時、俊成卿の御館に一たびひきかへされたること、又「花はこよひのあるじならまし」てふ歌を箙に結つけられたる事など、いと優にやさしき御心なりや。そのことゞもをおもひつゞけて、ねもごろにをがみ奉るつひでに、
末つひに木の下陰を宿としてのこるしるしの石もはかなし
かくてこのあたりしる明石何がしの城のほとりをとほりて船場といふにいづ。こゝはやがてうみべなり。こゝにて茶屋に入てものなどくひつゝ大坂にとくゆく船にのる。時は午の刻ばかりになん。
久足は明石から舟に乗って大坂もどる予定ですので、ちょっと距離のある赤羽神社は気になりつつ、パスしたようです。よってこちらもパス(さすがにつかれているので、助かった)。
忠度塚も健在で、折しも藤がきれいでした。「前にはいしのいがき有。又なにをゑりたりとも今はわかりがたき石碑と、又この所しるあかしの何某の歌をゑりてたてられたると、ふたつあり」という記述とも齟齬しないかな。


久足は明石城内は通っておりませんが、いまは公園になってますので、こちらは城中を通ります。いい感じに手入れされていなくて、かえって風情がありました。





さあ、久足は舟に乗って大坂に向かいます。船路は悠々たるものですね。
この船は五百石ばかりもものつみのする船なれば外にのりたる人もおほく、いとにぎはへり。けふは天気いとよくをそろしきばかりの波風のなきはさるかたなれど、いと風ぬるくしかも追風ならねば、舟のゆくことおそきはわづらはし。もとよりこの船は沖のかたにとほくこぎいづることなく、街道より二、三十丁計沖のかたをかよふなれば、かりそめにもあやふからず。はた陸のかたの詠(ママ)もいとおほし。きのふけふかよひたる道ながらも、海の中より見るさまはまたことなるけしきにて、おもしろき船路なり。この船路よりはるかにむしまどといふ島見えたり。この島を「日本最初、をのごろ島なり」と船人のいへるはいかゞあらむ。
かくて和田岬につきたるほど日もやうやうくれそめて、月の光のあかく見えそめたるはいとはなやかにて、ちりばかりも雲もあらず、所のさまも、すま・あかしのけしきにおとらず見ゆ。
ぬけいでしけしきとぞ見るこまつるぎわだのみさきの秋の夜の月
さて、このあたりは遠矢の浜といひて、『太平記』に見えたるかの本間孫四郎がみさごの鳥をいおとして足利のしこ臣らがめをおどろかしゝ古跡なり。こよひ舟にのりたるは、月見むためにはあらで大坂にはやくかへるべきたよりなりしを、こよひもかくおもしろき海辺の月を見ること幸也。されば船のゆくことおそくして日のくれそめたるも今さらうれしくて、やゝこぎゆくほどの月のけしきたとしへなくおもしろく、月のためにわざと船うけたらんやうにおぼゆ。
舟うけてこよひさやかに見むものとおもひやかけし波の月かげ
かくて御田村の沖をゆくほどより風はさゝかにふきいでゝ、舟はやく西宮の沖にいたるほど、けさよりのつかれにや、ふとまどろみたるほど、船人のあはたゞしくゆすりおこすに、何ごとにかとめをさませば、はやくも大坂の安知川新堀といふに舟はてたる也。時は子のこくばかりなり。
これより町つゞきなれど、道筋いとまぎらしきを、からくして道頓堀にいたる。かくて藤や何がしの家に又もやどりぬ。
ほとんど月見の遊覧船のようで、気持ちよさそうですね。
さあさあ、こちらも三宮にもどりましょう。明石から電車に乗って約15分で着きました。
15分!
半日というか、日中ずっと歩きとおした行程が、電車だとたった15分!
普段、当たり前すぎてなんとも思っていませんが、電車って、文明ってすごいなぁ、と小学生のように感動するのでした。
しかしこうなってくると、いまの時代、歩く方がずっと贅沢だよな、と思ったりもします。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
