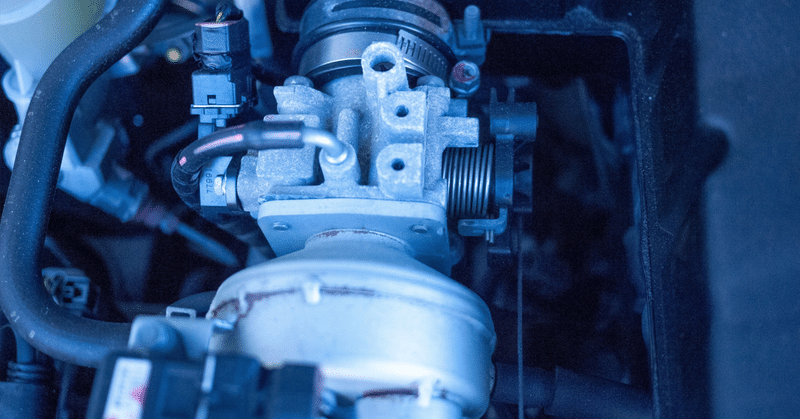
「名言との対話」12月30日。横光利一「私はただ近づいてくる機械の鋭い先尖がじりじり私を狙っているの感じるだけだ」
横光 利一(よこみつ りいち、1898年〈明治31年〉3月17日 - 1947年〈昭和22年〉12月30日)は、日本の小説家・俳人・評論家である。
大分県宇佐市出身の父は「鉄道の神様」呂呼ばれた技術者で転勤が多かった。利一は中学4年のとき、国語教師に文才を認められた。それが契機で小説家を志望するようになった。
早稲田大学予科に入学。1920年に菊池寛に紹介され、生涯にわたって師事する。大学は中退し、小説を書く。1923年に刊行した『日輪』『蠅』は構成のうまさと文章表現の新鮮さで衝撃を与えた。1924年、川端康成らと一緒に『文芸時代』を創刊し、新感覚派運動を先導した。『上海』はその集大成である。
新心理主義に転じて1930年に『機械』を刊行。1934年の『紋章』は行動主義の作品。1935年には『純粋小説論』で私小説に反対し、『家族会議』を書く。そしてヨーロッパ文化との対決をめざした『旅愁』に着手するが、この長編は完成しなかった。
こういった経歴を眺めると、常に新しい問題意識を持ちながら考え、実験し、執筆し、行動した作家であることがよくわかる。時代をリードするタイプの影響力のある作家だった。
よく知られている代表作『機械』を読んだ。天真爛漫な工場主とその妻、そして3人の工員の心理描写を描く筆致はさすがだと感心した。この本は風呂でkindleで読んだ。「ハイライト」という機能があり、他の多くの読者が線を引いたとことがわかるという仕掛けになっている。不思議なことに、私が線を引くところと同じところが多かった。
「いかなる小さなことにも機械のような法則が係数となって実体を計っていることに気付き出した私の唯心的な目醒めのの第一歩となって来た。」「私たちの間には一切が明瞭に分かっているかのごとき見えざる機械が絶えず私たちを計ったままにまた私たちを推し進めてくれているのである。」「その間に一つの欠陥がこれも確実な機械のように働いていたのである。」「私はただ近づいてくる機械の鋭い先尖がじりじり私を狙っているの感じるだけだ。」
つまり、「機械」という奇妙なタイトルをつけた意味を探そうとしている読み方が共通していたというわけだ。この小説は、それぞれの登場人物の性格や心理描写のうまさはあるが、そのドラマも大きな意味では、それぞれが部品や歯車の様に構成されており、まるで一つの機械のようにできているのという世界観を感じた。それで「機械」という変わったタイトルをつけたのだろう。
横光利一の作品は他には読んではいないのだが、「新心理主義」という視点でこれほどの作品を仕上げる力量をもっているとしたら、新感覚、新心理主義、行動主義、純粋小説論、反ヨーロッパという見地から、次々に人目そばだてる作品を書くことができたのだろうと納得する。
太宰治の弟子の小野正文が太宰の自宅に訪ねたとき「作家にとって大切なのは勉強すること、つまり本を読むことだ」「横光利一が行詰っているのは不勉強のためだ」と言われたというエピソードを読んだことがあるのを思いだした。それが本当なら、最後の長編小説『旅愁』が完成しなかったのはそのためかも知れない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
