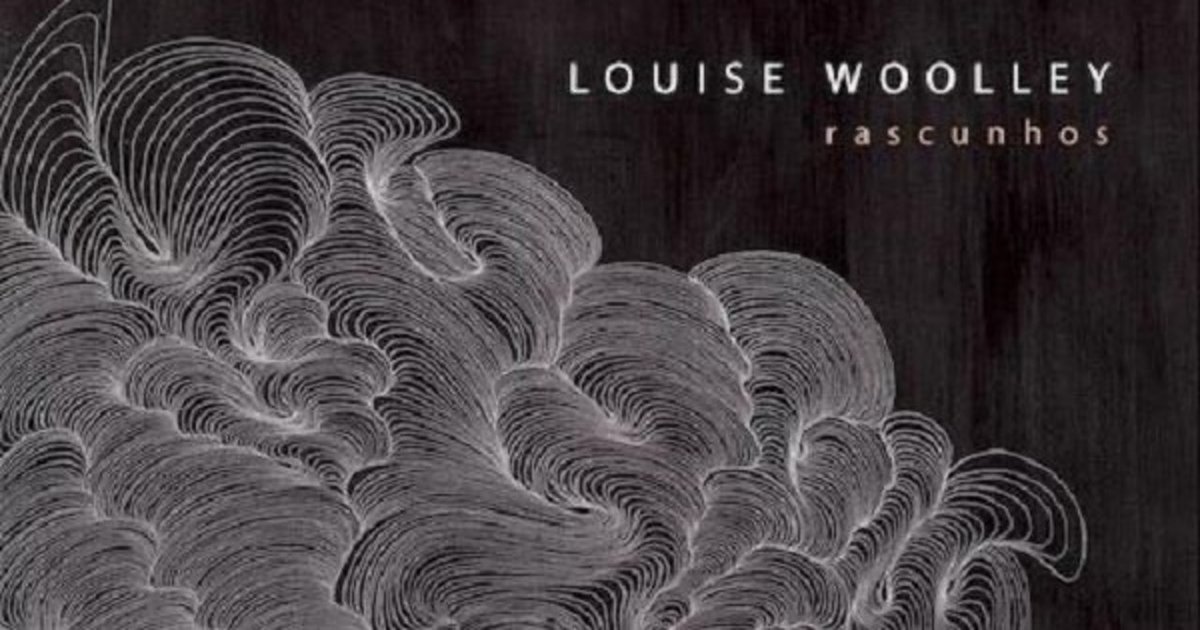
作曲と即興のはざまに 〜 ルイス・ヴーレイ
(4 min read)
ところで関係ないことですが、「〜〜嬢」「〜〜女史」「女流〜〜」「才媛」「紅一点」などといった表現って、女性はしませんよね。する男性の心理のなかには女性差別意識があると思います。関係ありやなしや、この手の表現にむかしからなんとなく感覚的に違和感があったぼくは、使ったことがないんですね。
ルイス・ヴーレイ(Louise Woolley)。ブラジルのジャズ・ピアニストですが、その最新作『Rascunhos』(2020)では、収録曲にほぼタイトルが付いていません。ラスト8曲目だけ「Primeiro Dan」と題されていますが、それ以外は「Rascunho」に番号が振ってあるだけなんですね。なんだか愛想ないなあ。おかげで曲題で指し示せませんが、ちょっと番号で管理するクラシック音楽みたいですね。
基本ジャズだけど MPB(特にミナス派)にも交差しているこのアルバムの特色は、どこまでが作曲されたラインでどこからが即興なのか区別がつきにくいというところにあるかもしれません。曲はすべてルイスの自作のようですが、用意されたコンポジションとくりひろげられるインプロヴィゼイションの境目がわかりにくい、というかこれ、ほぼ区別がなしと言ってもいいくらいじゃないですか。
作曲も即興も全体が渾然一体となっていて、しかもそれを聴いていると心地いいです。ルイスのピアノ演奏や、作曲もそうかな、かつてのビル・エヴァンズを思わせるタッチを感じます。リリカルにメロディをつむぐときのピアノ演奏に特にそれがあるように思うんですが、ビル・エヴァンズの影響はいまでも全世界のジャズ・ピアノ界におよんでいますし、ブラジルのジャズでも多いということで、むべなるかなと。しかしエヴァンズふうに弾いているのが作曲されたラインなのか即興ラインなのかはよくわかりません。
あ、いや、でもコンポジションは主にヴォーカル(ハミングだけ、ルイスではない)と管楽器二本で表現されていることが多いかもしれませんので、ピアノ演奏のほうはアド・リブなのかもしれないですね。ホーンやスキャットによるメロディ・ラインは、オーソドックスなジャズのようにテーマ提示みたいなことだけで使われているのではなく、曲中でどんどん出ます(特にスキャット)が、それもたぶんコンポジションです。
ってことは、ピアノや管楽器がアド・リブ・ソロをくりひろげている最中にもスキャット・ヴォーカルでコンポーズド・ラインがどんどん歌われているということで、やはり作曲と即興が複雑に交差し入り混じり、一体となって作品が進んでいっているんだなとわかります。2010年代以後の新世代ジャズの特色のひとつとしてアンサンブルとソロの渾然一体化、不可分化があるとぼくは感じていますが、このルイスのアルバムでも同様のことが言えるんでしょう。
リヴィア・ネストロフスキのスキャットの次に印象に強く残るのは、ダニエル・ジ・パウラのドラミングですね。どの曲でも強く激しく刻んでいて、しかも一筋縄ではいかない複雑でモダンなビートを表現しています。パッショネイトでもあるし、いいなあ、このドラマー。ルデーリでも叩いているひとですよね。シンバルの使いかたが個人的にはお気に入り。スネア・ワークもいいです。特に5曲目「Rascunho No. 9」では本当にみごとです。
アルバムではその5曲目で強く激しく盛り上がり、ここがクライマックスに違いないと思うんですけど、続く6曲目「Rascunho No. 7」はさわやかボサ・ノーヴァ調。MPB ふうで、これもなかなかいいトラックですね。ダニエルのリム・ショットを中心とするドラミングも調子よく、サックス・ソロ、フリューゲル・ホーン・ソロともにいいフィーリングですね。軽みがいいと思うんですよ。快適です。
(written 2020.2.19)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
