
DX支援を振り返る〜組織支援を通して見えた難しさと可能性
こんにちは!
株式会社Mutureの中村ひろやと申します。
Mutureは2022年4月27日に設立しました。先月を終え、Mutureも1歳を無事迎えることができました。1年と少しの期間しか経っていませんが、この機会に、これまで挑戦してきたMutureの目指す「DX支援」について振り返ってみたいと思います。
Mutureの目指すDXとは?
私たちMutureが目指す夢は「相利共生の未来を実現する」です。その夢を実現するために、一人ひとりの「個」の意思やWillを尊重し、ビジネスを行う上で直面する様々なトレードオフを超えていく取組みを生み出していきます。
例えば、個人と集団、意思と事業、短期と中長期など、システム最適化の中で見過ごされがち不均衡が存在していると考えています。そこで、私たちが組織に入り込むことで、それを乗り越えた相利共生な状態を作っていくことを目指しています。

では「DX支援」として何に取り組んでいるのか。こちらは端的に言うと「プロダクトに向き合うチーム作りを通じて、プロダクトの成功を目指す」というものになります。チーム作りという組織支援に重きが置かれていることが大きな特徴です。
チーム作りは、一筋縄ではいきません。例えば、チームを構成する一人ひとりの「個」が自分の役割を再認識し出来ることを増やしたり、「チーム」としてプロダクトマネジメントやスクラムの考え方を学び実践したり、「組織」として決裁構造や決裁の認識を見直したりと、個からチーム、そして組織構造と、向き合う範囲は広大です。もちろん、人に向き合う以上は感情などの合理性だけでは説明のできない複雑性に目を向ける必要もあります。

私は「PM」としてプロジェクトに参加をしていますが、世間一般のPMよりもチーム作りに重きが置かれたロールを担っています。実際に取り組んできた内容を一部ご紹介してみたいと思います。
組織支援として行ってきたこと
実際にクライアントと何を行なってきたかを振り返ります。まずは中心となるチーム作りですが、ここではプロダクト改善のスクラムを回していける状態を目指しました。

そのために、初めにプロダクト改善に必要となるもののリストとして「デザイン検討バックログ」、開発の進行管理のために「開発バックログ」の2種類のバックログを導入しました。次に、デザイナーやエンジニアに改善の内容を伝えるためのバックログチケットの記載ルールを明確化し、チケットの受け渡し方法を整理したりと、まずスクラムを回していくための土台づくりに取り組んできました。
そして、バックログを通してプロダクト改善に取り組めるように、定点観測する実績数値を整理したり、その数値からどのように課題仮説を立てるか?どのようソリューション仮説を立てるか?というプロセスをチームとして経験を積むようにしてきました。
さらに、前提となるプロダクトに対してどのように向き合うか?どのような構造で捉えるか?を学ぶために、プロダクトマネジメントについての輪読会を開催しました。『プロダクトマネジメントのすべて』、『プロダクトレッドオーガニゼーション』の2冊を事業責任者とPdMと読み進めることで、一緒にプロダクトづくりを進める上での前提を揃えていきました。
プロダクトマネジメントのすべて 事業戦略・IT開発・UXデザイン・マーケティングからチーム・組織運営まで
プロダクト・レッド・オーガニゼーション 顧客と組織と成長をつなぐプロダクト主導型の構築
しかし、バックログが導入されただけでは、スクラムは回っていきません。優先順位を決める・デザインを決める・実装範囲を決めると「意思決定」が段階ごとに必要です。そうなると、「組織」としての意思決定構造や、事業とプロダクトの関係性に目を向ける必要が出てきます。
特に意思決定構造については、チームとしてもチャレンジが必要です。具体的には、「自分よりも職位の高い人が意思決定をして決まったことを実現する」のではなく、「誰も正解はわからないので、なるべく早く実験をして学習をする」という意識に変わっていく必要があります。それは、誰かが意思決定をしてくれるというセーフゾーンを抜け出し、自ら意思決定をしていくという勇気と覚悟が問われる挑戦だと考えています。
そこで、プロダクトチームのリーダーとしてのPdMが意思決定を行なうためにも、事業責任者との共通言語づくりが大事です。ビジョン実現のために今季目指す姿や、優先順位の可視化、プロダクトとしてのKPI作りなど事業とプロダクトの繋ぎ込みの設計が求められます。

チームに取り組んだ。組織にも取り組んだ。では、これでスクラムを回していけるか?というと、最後は「個」に向き合うことも重要です。一人ひとりが持つ創造性と主体性を発揮していくことがプロダクトの成功に向けて重要だと考えています。そのために、毎週チームメンバーと1on1を行い、タスクの棚卸しに加え、振り返りを行なったり、悩みや困難に対しては一緒に考えるようにしています。
また、自分たちが何ができるようになるのか?その目指す姿を例示し、一つずつ経験値を積むことがチームとしての練度を高めると考え、スキルマップを作成して優先度を決めながらUIのデザインや、UXリサーチ、UXデザインのプロセスに当事者として巻き込むことを意識しています。

組織・ヒトに向き合う難しさとやりがい
個人、チーム、組織と、抽象と具体を行き来しながら組織変革に携わっていますが、上記のやり方も試行錯誤しながら一つひとつ企画し、アクションをしたことにより生まれた途中成果物になります。
そのような組織変革に取り組むことで直面した難しさのなかで代表的なものは2点あります。

一つは、プロダクトの成長を組織変革のスピードがトレードオフということです。事業成長だけを優先するならば、Mutureがプロダクトを主導したほうが改善のスピードは早い。そう言えるかもしれません。
しかし、私たちが実現したい関係性は、仮にMutureがいなくとも、オーナーシップを発揮してプロダクトの成長をリードできるチームです。そこで経験を積んだメンバーが他事業に移り、その経験を発揮することで、結果的にクライアントの企業変革につながっていくことを目指しています。チームが変わっていくことを簡単に諦めずに組織変革に取り組み続ける必要性があります。
もう一つは、組織間の関係性の歪みです。こちらも当たり前のことですが、我々が接するクライアントの部署は会社を構成する数多くの部署の一つです。プロダクトに関連する様々な部署とのコミュニケーションやプロダクトに関する要望は常に発生しています。目の前の組織だけ向き合っていると、組織間の力学やミッションの違いにより、プロダクトをつくるチームがプロダクトに集中できない状況に陥っていく事態を見逃す可能性があります。組織間のコミュニケーションや、そもそも組織が持つミッションに対しても向き合う必要性もあります。
組織に向き合った結果と2年目の挑戦
人に、チームに、組織に、向き合い続けることの難しさを実感しながら、それでも自分たちの目指す夢に向けて、チームとクライアントがワンチームとして協力しながら歩み続けてきた1年でした。これまでの会社の常識と異なるプロセスやアプローチに前向きに挑戦してくれるクライアントメンバーだからこそ、少しずつその実感を得られ始めています。
例えば、週間でのプロダクトの実績のレポートとプロダクトチームでの定例MTGの定着、優先順位を決めたものの確実な実行とその進行のマネジメントといったプロダクトへの向き合い方を実践し始めています。またマネジメントレイヤーもプロダクトマネジメントについて学び、一緒に1年を過ごしたことで、「仮に失敗するかもしれないが、やってみないとわからない」と学習を前提とした意思決定をすることに抵抗がなくなったとおっしゃってくれました。チームメンバーも、新しくPdMとしてのキャリアに踏み出してくれたり、ノーコードでの実装を積極的に取り組んでくれたりと、1年間で本当に多くの変化を実感しています。
「啐啄同時」という言葉がありますが、一方的な変化を起こすのではなく、本質的な変化を一緒に起こそうとしてきたからこそ実現できたのだと思います。
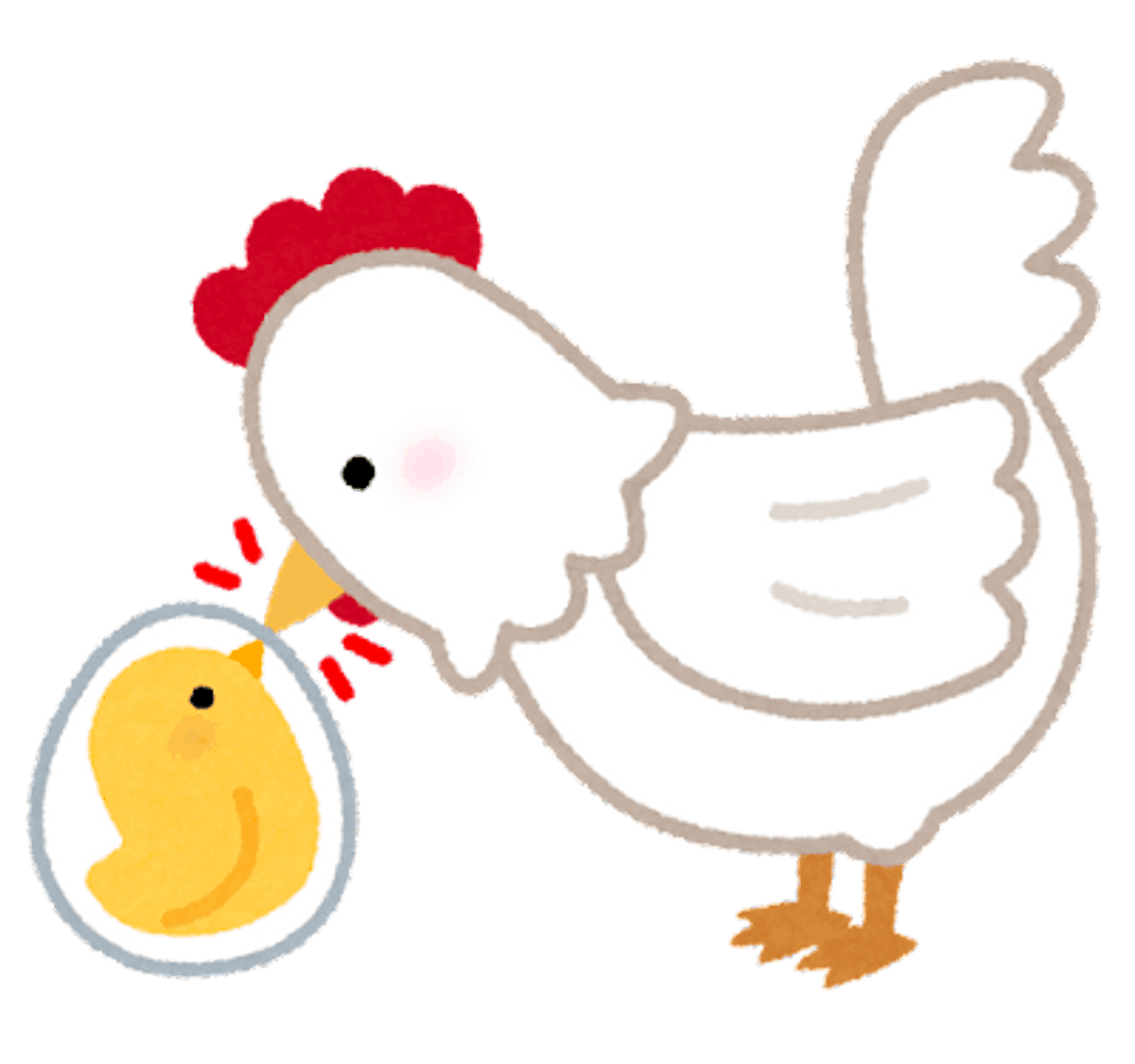
そしてこれから2年目です。クライアントと一緒にスクラムを回しながら、プロダクトが目指すビジョンに向けて前進していきます。Mutureの2年目のNSMは「相利共生のもとMutureが起こしてきた変化をアウトプットと成果に変え世の中に届けよう」。勇気を持って、前例のない環境に身を投じてくれたクライアントのメンバーと一緒に、プロダクトの成長を実現したいと考えています。

最後に
いかがだったでしょうか。DX支援を行っていく会社としてはヒトのことばかり触れてしまい、ギャップがあったかもしれません。しかし、ここまでヒトに向き合うことができることもMutureの大きな特徴になります。
まだまだ道半ばです。試行錯誤の途中です。もし、プロダクトの成功に向けて組織成長を実現する必要を感じられた経験をお持ちの方でしたり、デザインの力でプロダクトと組織の両方にアプローチしたい方がいらっしゃれば、ぜひ一緒にこの難題に取り組んでみませんか?
Mutureでは、絶賛採用募集中です!以下のページが応募ページになりますので、ご覧いただけたら嬉しいです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
