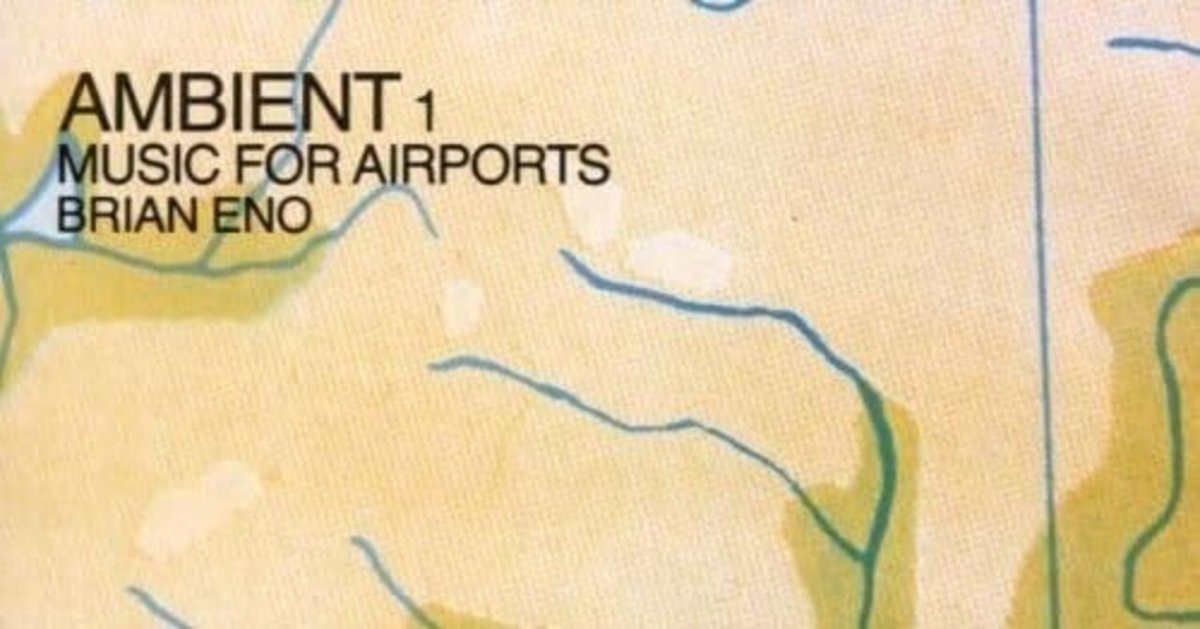
Brian Eno / Ambient 1: Music for Airports
30年以上前になるが、当時「環境音楽」というものがあることを知った。モノの本によると、その環境に適した音楽とか、そんな紹介がされていたようが記憶がある。その時はなんかつまんなそうだなと思ってスルーを決め込んでいた。
それとほぼ同時に「アンビエント」というカタカナ言葉も聞くようになり、これも何かでヒーリング的な意味合いで使われていたものだから、ウィンダム・ヒルみたいなものかと思ってそこもスルーしていた。
どちらも20代前半の頃の話だ。

ブライアン・イーノが1979年に発表した『Ambient 1: Music for Airports』は、彼が提唱した環境音楽のアルバムで最初にアンビエントという言葉が使われたのがこれだった。それ以前にも彼は「雰囲気としての音楽の利用」について考え、少しずつ形にしていってはいたが、この作品で最初の完成形ができたのではないかと思う。
アルバムのタイトルの通り、空港で流れることを想定して制作されたアルバムで、空港という環境やその場の雰囲気を邪魔しないということを目的とした音楽といえばいいのだろうか。
イーノは、本作を制作するにあたり、次のようなことを言っている。
中断可能な音楽であること(空港ではアナウンスとかが随時入るので)
人々の会話の周波数とは違っていて、会話パターンとは異なる速度であること
空港の生み出すノイズと共存しないこと
そんな前提をもって本作を聴く。曲数は4曲でタイトルらしいタイトルは無く、以下のような表記となっている。
1/1
2/1
1/2
2/2
それぞれ「1面の1曲目」「1面の2曲目」「2面の1曲目」「2面の2曲目」とでも言っておこうか。これらも聴き手に変な先入観を持たせまいとしているかのようだ。
「1/1」は約17分もある曲だが、イーノが言うように途中で聴くのを中断しても中途半端感はないし、会話をしていても曲に引っ張られることはない。ピアノとシンセサイザーがゆったりと、ただ流れていくだけ。そして確かに空港という場所で発生するノイズ(アナウンスであったり、人々の移動する音や話声など)とは共存しない。これは「2/1」以降の曲にも当てはまる。
ルー・リードの『Metal Machine Music』のところで俺は「聴き手とのコミュニケーションなんてものは一切発生しない」と書いたけど、実はこのアルバムにおいても同じものを感じている。ただしこちらは環境に溶け込んでいるという点で、言い方を変えるなら「気にならない」ということだろうか。俺自身がそういう聴き方をしているからそう思うのかもしれない。
恐らく20代でこれを聴いていたらまったくもって理解不能であっただろう。40代になって初めて聴き、50を過ぎてからようやく分かってきた。でもこれを制作したイーノは当時30代前半なんだから凄いよな。イーノのアンビエントシリーズの中では本作が最も「環境音楽」という言い方に相応しいと思っている。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
