
読んだはしからすぐ忘れるから!31冊目「岩石はどうしてできたか」32冊目「中二階」33冊目「漫画映画と共に」
最近のお気に入りの岩波科学ライブラリーから「岩石はどうしてできたか」読了。

岩石の源は水かマグマか、この論争から出発した地味な学問は、プロ・アマチュアを問わず大勢の研究者に育てられ、やがて地球史や生物進化の謎の解明にも大きな役割を果たした。そしょていまや月の探査にも活躍する。岩石の魅力にとりつかれた世界中の研究者を肖像画つきで紹介してたどる岩石学の歴史。
岩石はどうしてできたか、水成論から火成論の論争から岩石学の歴史を描く。タイトルに惹かれて読み始めたものの、何しろ岩石(地質)に関する知識がほとんどないので、頻出する(そしてほとんど詳しい解説のない)専門用語たちにクラクラして、かろうじて字面を追うので精一杯でした。基礎的な本(図鑑とか)から勉強せねば。
内容とはあまり関係ないのですけれど、面白かったのは著者みずから描いた研究者たちの肖像画(あとがきでちゃんと「これこれこういう時の写真を元に描いた」と丁寧に説明)と、新聞歌壇に投稿しているらしい著者の短歌が帯とはじめと終わりに載っていること。別に結社に入っているわけではないのかな。ちょっと気になる。
参考文献
「デ・レ・メタリカ」アグリコラ(岩崎美術社)
「鉱物論」アルベルトゥス・マグヌス(朝倉書店)
「死線を越えて」賀川豊彦(改造社)
「月の科学」久城育夫ほか(岩波書店)
「火山及び火山岩」久野久(岩波全書)
「地質学の歴史」ゴオー(みすず書房)
「四国はどのようにしてできたか」鈴木堯士(南の風社)
「裂ける大地」諏訪兼位(講談社選書メチエ)
「アフリカ大陸から地球がわかる」同上(岩波ジュニア新書)
「地球科学の開拓者たち」同上(岩波全書)
「花崗岩が語る地球の進化」高橋正樹(岩波書店)
「火成岩成因論」坪井誠太郎(岩波講座)
「日本地史学の課題」松本達郎(平凡社)
「変成岩と変成帯」「科学革命とは何か」都城秋穂(岩波書店)
「岩石学Ⅲ」都城秋穂ほか(共立全書)
「ジオコスモスの変容」山田俊弘(勁草書房)
続いてニコルソン・ベイカー「中二階」。
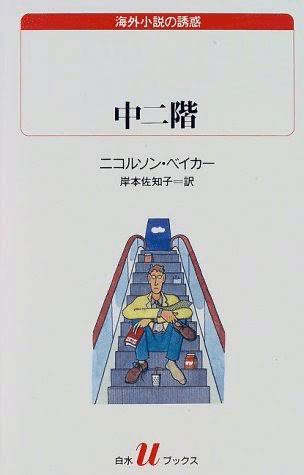
200ページもない小説ですが、なかなか時間がかかりました。膨大な脚注が間にはさまっていて、読み進める感覚(リズム)がなかなか摑めなかったというか、乗れなかったのです。
中二階のオフィスに戻る途中のサラリーマンがめぐらす超ミクロ考察ーー靴紐はなぜ左右同時期に切れるのか、牛乳容器が瓶からカートンに変わったときの感激、ミシン目の発明者への熱狂的賛辞等々。これまで誰も書かなかったとても愉快ですごーく細かい注付き小説。
とにかくやたら出て来る具体名(商品名)のかげで、語り手の「私」に関する具体的な情報はほとんどない(名前すら!)ということを訳者(岸本佐知子)あとがきで気がついた。この、本編を凌駕せんばかりに注が挿入される手は一回きりだけれど、この著者の他の小説もまた別の仕掛けがしてあるようで、続けて読みたくなってきたのでありました。
日本のアニメーション黎明期(最初期)に活躍した山本早苗の自伝「漫画映画と共に」は、晩年に書き溜めていたものを娘さんがまとめた自伝。小さい頃から絵がうまく、しかし画家を志しながら父親に反対され、それでも何度か家を出て働くもののうまく行かず、誘われて携わったアニメーションの世界でたくさんの名作アニメーションを制作した山本早苗(善次郎)の生涯。アニメーション制作を始めるころよりも、画家になるという目標に向けて足掻いている若き戸田善次郎青年の悪戦苦闘ぶりがとても面白いです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
