敗北を抱きしめて
1945年8月15日の玉音放送で昭和天皇は、「堪え難きを堪え、忍び難きを忍び」という有名な一節を残しました。恥ずかしいことですが、戦後生まれの私はこれを「戦争で辛かったろう、よく堪え忍んでくれた」という意味だと、長い間誤解していました。玉音放送の全文をよく聴けば、そうではなく「無条件降伏の後に来る、異民族による侵略によっていかに日本国民が辛い目にあうか、自分はよく知っている、堪えてくれ」というメッセージだったということがよくわかります。当時の多くの国民の目線からは、それが当たり前の感覚だったのでしょう。しかし実際には、戦後日本は奇跡的な復興を果たし、私たちは平和で豊かな生活を享受するようになりました。
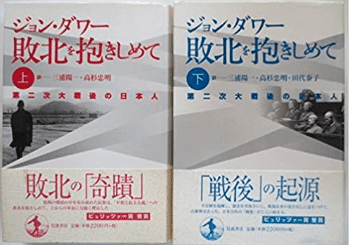
ジョン・ダワーは米国の歴史学者であり、日本の近代史の専門家です。彼が2000年に著した「敗北を抱きしめて」(原題:”Embracing Defeat”)[1]は、歴史上初めて異民族の支配を受けた日本人が、いかにたくましくその変化を「抱きしめた(”embrace”した)」かを、多くの歴史資料に基づいて克明に描きあげた作品です。私は初め、英語の原文で読み始めたのですが、表現の難解さについていけず、訳書に切り替えて最後まで読みました。日本語版には、原著にはない多くの図版が加えてあり、日本語に問題ない方は訳書で読むことをお勧めします。
レジリエントな人々
当時の日本人は敗戦をどのように受け止めたのでしょうか。最初は虚脱だったのだ、とジョン・ダワーは言います。それまでの「命に代えても国を守らねばならない」という悲壮な決意が、いきなり無意味になってしまったのですから、虚脱感を覚えるのはわかるような気がします。

占領軍が来てみると、天皇や多くの国民が心配したような、異民族の支配下における「耐え難い、忍び難い」服従を強いられることはありませんでした。むしろ、戦前・戦中の厳しい規律から市民を開放した「開放者」として迎えられた、とも言えるでしょう。本書の上巻64ページには、漫画家の加藤悦郎が書いた「天降る贈物」という風刺絵があり、人々が空から降ってくる「民主主義」という贈物を嬉々として受け取っているようすが描かれています。
私の父方の祖父は府立第六高等女学校(今の都立三田高校)の初代校長でしたが、戦前としては先進的な女子教育を行った人です。いわば、当時の典型的なインテリの1人といってよいと思いますが、彼が戦後に書いた半生記の中で、終戦の後の心情を以下のように述べています。
「その時善良な国民は、夢から覚めた如く、空虚な感情で、やがてよくも騙されていたものだと感じた。明治の始めから70余年、時代に深く騙されていたのである」(「我が言行」私家版、1958)。
「よくも騙されていたものだ。」これが虚脱感から抜け出した多くの人々の感想だったのではないでしょうか。
その後、庶民はタガが外れたように「カストリ文化」(酒粕から作られた粗悪な酒に象徴されるサブカルチャー)などデカダンな生活に溺れます。しかしそれは同時に、日本に極めて大きな活力が溢れていた時代であり、それが戦後日本の繁栄に大きく貢献したことは確かでしょう(もちろん、戦後直後の食糧難、多くの傷痍軍人や戦争孤児、戦後何年もかかった外地からの引揚げ、さらにはシベリア抑留など多くの困難があったことは確かで、この本にはそのような状況も細かく描かれています…)。
私は2011年の東日本大震災のあと「レジリエンスとは何か」を科学的に明らかにするための学際的研究を行ったことがあります。そこで見つけたことの1つは「レジリエンスとは単に元に戻る(“bounce back”)、ということではない。むしろ、大きな災厄をきっかけとして新しい自身に脱皮していく(“bounce forward”)ことだ」ということでした。戦前・戦中の価値観を捨てて新しい社会を「抱きしめた」戦後日本人は、極めてレジリエントであったと言えるのではないでしょうか。ジョン・ダワーも本書の巻頭言で、このように言っています。
“日本は、世界に数ある敗北のうちでも最も苦しい敗北を経験したが、それは同時に、自己変革のまたとないチャンスに恵まれたということでもあった。(中略)アメリカ人が奏でる間奏曲を好機と捉えた多くの日本人が、自分自身の変革の筋立てをみずから前進させたからである。多くの理由から、日本人は、「敗北を抱きしめ」たのだ。(中略)そして敗北は、より抑圧の少ない、より戦争の重圧から自由な環境で再出発するための、本当の可能性をもたらしてくれたからである。”
占領政策のダブル・スタンダード
しかし、かといって著者は占領政策を大成功と手放しで賛美しているわけではありません。本書の下巻では、様々な矛盾を多角的に検証しています。そもそも、GHQ(連合国最高司令官総司令部)は占領政策において中央集権的な権力を持っていて、あらゆることはGHQの承認がなければできなかったと言います。これは民主主義とは相容れない、大きな矛盾です。せっかく平和憲法を作ったのに、朝鮮戦争勃発後は日本を共産主義に対する砦とすべく警察予備隊(後の自衛隊)を発足させたり、吉田茂・岸信介・児玉誉士夫・笹川良一など戦争遂行に力のあった保守有力者を重用したりしました。また、極東裁判は米国が中心で、日本占領下で苦しんだ東アジアの国々の意見が十分に聴かれなかったのも、ある意味ダブル・スタンダードであったと言わねばならないでしょう(最近思うのですが、欧米の人はある時には高邁な理念を述べますが、別の時には臆面もなく自分の都合を押し付けることが多くないでしょうか。その点、日本人はより実直であるように思うのは、私の気のせいでしょうか)。
米国はイラクやアフガニスタンで、日本で成功したのと同様な民主化を行おうとしましたが、いずれもあまりうまく行っていないようです。それは占領政策の違いなのでしょうか。それとも、占領された側の国民気質の問題なのでしょうか。もし、災厄を”embrace”できる柔軟な心が私たちの強みであるのであれば、今後起きてくる人工知能技術の発展による大きな脅威も、日本人はうまく乗り切れるかもしれません。そんなことを思う今日このごろです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
