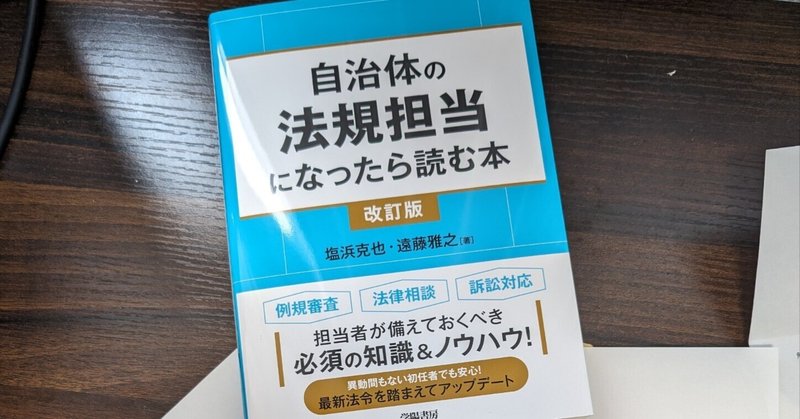
『自治体の法規担当になったら読む本 改訂版』(学陽書房/2024年)勝手に書評
「自治体の○○担当になったら読む本」の嚆矢である本書は、平成26年に初版が刊行され、今回、平成28年の行政不服審査法の改正などの新規項目を追加して、令和6年4月に改訂版が刊行された。
本書は、自治体において主に例規の審査や法律相談、訴訟対応などを受け持つ部署(総務課・法務課・文書課・行政課などさまざまな呼称がある)の担当になった職員向けに書かれたものであり、まずはこれ1冊さえ読んでおけば、法規担当の業務のほぼ全てを網羅的に理解・体感できるものとなっている。
なお、改訂版と初版との違いは、下記の記事を参照されたい。
『自治体の法規担当になったら読む本 改訂版』(学陽書房/2024年)改訂版と初版との違い|tomo (note.com)
本書は、大きく8の章に分かれており、2章から5章までが例規審査、6章が議会対応、7章が法規担当の日常の業務、8章が法律相談や訴訟対応についてである。ボリュームを見ても分かるように、法規担当の仕事は、とにかく例規審査が中心であることが端的に表れている。
法規担当の仕事は、役所の中でも特殊な位置付けにある。予算をとって事業をして、ということもないし、窓口に出て申請を受け付けてということもない。とかくデスクワークと相談対応が中心であって地味で目立たない。そのため、役所にいても何をやっているのかよく分からない部署になっている。
本書は、この「何をやっているか分からない」法規担当の一連の仕事をほとんど全て網羅しているところに特徴がある。例規審査一つとってみても、新旧対照表や例規のローカルルール、過誤について詳細に触れているのは本書だけである(第5章)。
また、例規審査に必要なそもそもの例規の見方(第2章)や、議案の提出のタイミング(第3章)、例規審査のポイント(第4章)についてもコンパクトにまとまっており、法規担当になったばかりの方に必要最低限の知識が身につくようになっている。
法規担当は、分厚い『法制執務詳解』(石毛正純著)や『ワークブック法制執務』などを読んで例規審査をしていくのであるが、そもそも例規審査とは何か、どこを見ていくのかというのが身につくのが本書である。
議会対応では、「先議」「追加提案」「再議」「専決処分」といった議案を提出する方法についても余すところなく触れられている。議案の修正、訂正、撤回など、できるだけ関わりたくはないが、知っておきたいルールにも丁寧に取り上げられている(第6章)。
法規担当は、法令改正やその影響による例規改正について、常にアンテナを張っておかなければならない。アンテナの張り方が第7章に載っている。官報を読む、制度の趣旨をつかむ、検索のコツを知ることは重要であり、法規担当の基本である。
例規審査と法律相談は両輪である。これはどちらも重要というよりは、どちらも同じ比重(割合や時間といってもよい)が必要であるという意味である。頼りにされる相談者になるためには、解決策も多く持っておくとよい。法律だけで解決できるものではない。
近隣住民からの騒音苦情に対して、騒音の受忍限度や賠償額などを検討するのではなく、「地域の理解を求める」というのも大事な視点である(231ページ)。
弁護士相談や訴訟対応というのは、揉めた事案の行きつく先ではあるものの、解決の糸口でもある。第8章の法律相談・訴訟対応についても一読しておくとよい。
私は、法規担当になる前の部署では、公営住宅の管理業務をしていた。入居の申し込みの受付から抽選の準備、説明会の開催、毎日の家賃の処理、滞納整理、苦情対応、住宅への訪問・指導、予算決算などとともに、少し法律を知っていたので裁判や差押え、強制執行による追い出しなどもやっていた。しかし、これらは法令を見ながらやっていたのではなく、マニュアルや口伝によって動いていた。忙しくて勉強する間はなかった。
本書の最初にあるように、法規担当という仕事は、「これほど勉強になる仕事もない」のである。仕事をしているだけで、法令の勉強ができるのは法規担当だけである。法治国家・行政国家である日本において、法令を知らず行政を実施することはできない。法令の知識はどの部署においても活用できるので、是非ラッキーだと思って法規担当を愉しんでもらいたい。本書を一読することで、その愉しさの一端を見ることができるのではないかと思う
本書の構成は、次のとおりである。
【目次】
第1章 法規担当の仕事へようこそ
1-1 法規担当の仕事って?
1-2 法規担当の一日
1-3 法規担当の一年
1-4 法規担当が備えたい3つの知識
1-5 法規担当に欠かせない3つの力
第2章 例規審査の基本
2-1 例規集の見方
2-2 例規の種類
2-3 条例と規則の使い分け
2-4 条文の構造
2-5 例規の構造
2-6 委員会等の例規
2-7 要綱とは何か
2-8 公示・告示・公告の違い
2-9 通達と行政実例
2-10 例規の公布
第3章 例規策定の手続
3-1 例規の制定改廃の流れ
3-2 例規の審査
3-3 法令との整合性
3-4 条例案と予算案
3-5 例規改正のタイミング
3-6 検察協議と自治体
第4章 規定別・例規審査のポイント
4-1 題名
4-2 前文
4-3 目的規定・趣旨規定
4-4 定義規定・略称規定
4-5 権利制限規定・義務規定
4-6 許可規定
4-7 給付規定
4-8 使用料規定
4-9 手数料規定
4-10 附属機関規定
4-11 委任規定
4-12 「公の施設」条例
4-13 指定管理者制度
4-14 罰則規定
4-15 附則
第5章 立法技術のポイント
5-1 用字・用語
5-2 改め文とは
5-3 条項の改正
5-4 条項の追加・削除
5-5 改め文に迷ったときは
5-6 改正方法の選択
5-7 条文のわかりやすさ
5-8 例規のローカルルール
5-9 「新旧対照表」方式の例規改正
5-10 例規の過誤
第6章 議会対応のポイント
6-1 議会対応の勘どころ
6-2 議決と法規担当
6-3 議案と議会
6-4 専決処分の取扱い
6-5 議案の修正
6-6 議案の訂正・撤回
6-7 議員提案の条例
6-8 住民提案の条例(直接請求)
第7章 法規担当の仕事術
7-1 法律を理解するコツ
7-2 条項ずれは恥ずかしい
7-3 官報の読み方・使い方
7-4 法令の情報を収集しよう
7-5 制度の趣旨をつかむコツ
7-6 お手本(ベンチマーク)
7-7 検索のコツ
7-8 「規定すべき内容」の固め方
7-9 法務の効果的な執行
7-10 必要なのはワープロ術?
第8章 法律相談・訴訟対応
8-1 法律相談の勘どころ
8-2 頼りにされる相談者になるには
8-3 相談しやすい法規担当になるには
8-4 弁護士相談の勘どころ
8-5 訴訟対応の勘どころ
8-6 訴訟の種類と裁判の流れ
8-7 訴訟を意識した日常業務を
8-8 適正な行政手続
8-9 行政不服審査制度
8-10 情報公開制度の対応
https://ssl.shiseido-shoten.co.jp/products/detail/67141
以下、好き勝手に書評チックなことをしてみることとする。
第1章 法規担当の仕事へようこそ
第1章は、法規担当の仕事とはどういうものかという導入部分である。法規担当の1日・1年はあくまで参考程度に読んでおくとよい。人それぞれ、背景事情や知識量が異なる(法学部卒かそうでないか、法律を勉強したことがあるか、役所経験はどうかなど)ので、法規担当に備えたい知識や欠かせない力のうち、どの点が自身に足りていないかを少し意識しておくとよいと思う。
なお、本書が指摘している以下の点は、法規担当としてとても重要だと思う。
・法制執務の参考書は、事案ごとに内容を確認して、実務に触れながら知識を習得していくのが効果的。あらかじめ通読する必要はない。
・法規担当の仕事は、慣れや経験が大切。
・法律の運用に当たっては、「暗記」よりも「解釈」が重要。
1-1 法規担当の仕事って?
法規担当の仕事として、①例規審査、②法律相談、③訴訟対応の3点が挙げられている。私としては、③はそれほど重要ではなく、①と②がメインであり、両輪であると考えている。
1-2 法規担当の一日
官報やニュースのチェックは日課にしておくとよい。官報は、最初のうちは眺めるだけでよいが、いずれ、自身の担当部署の例規に関わるのではないかピンとくるようになる。
自治体の規模などにもよるが、議会がないときは、当方は定時で帰れることも多い。私自身、係員には、やっても20時まで、水曜はノー残業と呼び掛けており、皆実践してくれている。もちろん、3月定例会のシーズンは、こうはいかない。
1-3 法規担当の一年
法令の改正が多いからか、いつも3月定例会は条例案や規則改正が多く、大変忙しい時期になる。当方でも1月~3月は休めないときもある。土日も休めない。
1-4 法規担当が備えたい3つの知識
行政法的な知識や民法の知識については、あるに越したことはないが、なくても何とかなる。また、外部の研修でも学ぶ機会があるので、地方自治法とともに研修で学んでしまえばよい。余力があれば本を読む。
1-5 法規担当に欠かせない3つの力
法的思考力であるが、気を付けなければならないのは、弁護士的に、原告・被告の主張を考えるというような発想ではなく、まずは両者の意見を聴いて、仲介するような能力が求められる。答えは法令にはなく、事前の根回しや交渉で決着がつくことも多い。
第2章 例規審査の基本
2-1 例規集の見方
第2章は、法令や例規というのはどういうものかという基本の部分である。「2-1 例規集の見方」の部分は、意外と他の書籍で見かけない記述である。絵入りで分かりやすい。例規集上の例規の体裁について、改正をするとどのように溶け込む(改正部分を重ね合わせる)のか一目で分かるようになっている。
2-2 例規の種類
法令の体系のピラミッドの図は、覚えてしまうとよい。また、法令(法律・政令・府省令)と、例規(条例・規則)の順番や、それぞれの概要も一緒に押さえておくとよい。告示・訓令・要綱というのは、自治体ではよく見るものであるから、原則として、法規ではないということを意識して覚えておく。
「法令」というと、通常は、“法”律と法律に基づく命“令”(政令・府省令)のことを指す。ただし、条例や規則なども含めて法令ということもある。
命令は、「改善命令」「中止命令」といった具体的な処分を表す命令とは異なり、国の行政機関が制定する法形式の総称である。
また、条例と規則を併せて「例規」という。慣“例”による“規”範の略である(塩浜克也他著『公務員の仕事の授業』(学陽書房・2019年)130ページ・131ページ参照)。
例えば、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第18条第3項第1号には、「法令(条例を含む。以下この章において同じ。)に基づく場合」とあり、この法律(のこの章)においては、法令に条例を含むことを明記している。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条第1項は、「普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第二条第二項の事務に関し、条例を制定することができる。」と規定しており、この「法令」には、(当たり前だが)条例は含まれない。
法律に基づく命令とは、「政令(内閣が制定する命令)、内閣官房令(内閣総理大臣が内閣官房の主任大臣として発する命令)、内閣府令(内閣総理大臣が内閣府の長として発する命令)・省令(各省大臣が発する命令)、会計検査院規則等をいう。」とされている(コンシェルジュデスク 行政実務キーワードバンクオリジナル)。
個人情報の保護に関する法律第61条第1項は、
「行政機関等は、個人情報を保有するに当たっては、法令(条例を含む。第六十六条第二項第三号及び第四号、第六十九条第二項第二号及び第三号並びに第四節において同じ。)の定める所掌事務又は業務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用目的をできる限り特定しなければならない。」と規定している。
同法第69条第2項第2号は
「行政機関等が法令の定める所掌事務又は業務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することについて相当の理由があるとき。」
と規定しており、この「法令」には、条例を含む。これに対して同条第3項は「前項の規定は、保有個人情報の利用又は提供を制限する他の法令の規定の適用を妨げるものではない。」と規定しているが、この「法令」には条例は含まれない。
特に最初のうちは、権利を制限したり義務を課すのは法律、政令、府省令、条例、規則によると考えておけばよい。なお、政令は内閣法第11条で、内閣府令は内閣府設置法第7条第4項で、省令は国家行政組織法第12条第3項で、それぞれ法律の委任を受ければ権利を制限したり義務を課すことができることになっている。
なお、権利を制限したり、義務を課したりするというのは、土地収用や課税といった権利の制限・剝奪、是正命令や改善命令といった一定の作為の義務付け、営業停止命令などの一定の行為の禁止、強制執行や即時強制などの人の身体・財産に対する実力の行使などがこれに当たる。
これに対して、各種の社会保障給付や補助金の交付、行政主体による道路や水道などの公共施設の提供といった給付的行政作用(私人に対して金銭やサービスなどの便益を提供する行政作用)や、土地所有者との合意に基づき売買契約により任意に土地の所有権を取得したり、違法建築物について、是正を求める行政指導をするなどの任意的行政作用(行政処分・権力的事実行為によらない行政作用)については、権利の制限や義務の賦課に当たらない。そのため、これらの事項を法律や条例で定める必要はない(興津征雄著『行政法Ⅰ行政法総論』(新世社・2023年)6ページ、112ページ~114ページ参照)。
法規(Rechtssatz レヒツザッツ)というのは、国民の権利を制限したり国民に対して義務を課すことのできる規範である。日本においては、法規は法律という法形式によってのみ体現することができる(法律の法規創造力)。(板垣勝彦著『公務員をめざす人に贈る行政法教科書第2版』(法律文化社・2023年)5ページ参照)
要綱は規程形式の内規の呼称であり、要綱という法形式があるわけではないという指摘がある。条例は「令和○年○○市条例第○号」、規則は「令和○年○○市規則第○号」、訓令は「令和○年○○市訓令第○号」、告示は「令和○年○○市告示第○号」となるが、要綱は「令和○年○○市要綱第○号」とはならない。要綱は、法形式でないので、要綱(という名称の規程)の制定を一般的に知らせるのであれば告示形式をとることになるし、単に「決裁」「制定」「実施」などとしているところもある(森幸二著『自治体法務の基礎と実践~法に明るい職員をめざして~』(ぎょうせい・2017年)56ページも参照するとよい)。
2-3 条例と規則の使い分け
条例で定めるべきか、規則でよいか、それとも告示か要綱でよいかは、本書にあるように戸惑うことがある。ただ、戸惑う事態が発生すること自体(そのように迷うこと自体)があまりないので、困ったときに読み返せばよい。他都市で事例のない新規制定の際に困るだけである。
2-4 条文の構造
条・項・号・ただし書という条文の構造が端的に書かれており、まずはここに書かれていることを覚えてしまおう。少しだけ補足すれば、枝番が付された条(第○条の2)というのは、第○条とは別の条であり、枝番号が付いていない条の“子分”ではない。また、号にも枝番号は付くが、項には付かない。(白石忠志著『法律文章読本』(弘文堂・2024年)8ページ~11ページ)。
項は、段落である。「また」、「さらに」、「加えて」などの接続詞を用いない代わりに、項で段落分けすると覚えておけばよい。また、本書にあるように、「なお」の代わりに「ただし」「この場合において」「前項の規定にかかわらず」が用いられる(38ページ参照)。
第2項以下がない場合は第○条第1項とはいわないので(39ページの図を参照)、第2項以下がなくて号がある場合は、第○条第○号となる。
2-5 例規の構造
例規の構造が、原則として①題名、②目次、③前文、④本則、⑤附則、⑥別表、⑦様式という順番に作られていることは覚えておく。なお、目次や前文に出会う機会はあまりない。
政令は「○○法施行令」、省令は「○○法施行規則」の名称が付されることは、単純な話であるが実務上は重要である。また、訓令には「○○規程」の名称が付される。「○○訓令」とすると語呂が悪いからだと聞いたことがあるが本当だろうか。まさか規程形式(条文の形式)だからではあるまい。
附則が書ければ一人前といわれるが、本則にしても附則にしても、他の例規や他都市の例規、法令などの文言を前例踏襲して作るのであるから、附則を創作するようなことは(ほとんど)ない。
別表は法令の末尾、附則の次に置かれるが、条文の中に置くのを「表」という。要綱などにおいては、別表を多用する癖があるが、表で十分なケースも多い。末尾をいちいち見る手間を考えれば、まずは表でどうか、と考えるべきである。
2-6 委員会等の例規
少し長めの蛇足をしたい。法規担当をやっていると、教育委員会規則、教育委員会訓令、消防本部訓令、会計管理者訓令、企業管理規程など、さまざまな法形式に接する機会がある。議会規則・会議規則は地方自治法第120条に、傍聴規則は地方自治法第130条第3項に、公平委員会規則は地方公務員法第8条第5項に、教育委員会規則に地方教育行政の組織及び運営に関する法律第15条・第16条にそれぞれ規則を制定できる根拠がある。
議会の規則の制定権は、会議規則と傍聴規則のみ地方自治法に規定されており、その他の規則の制定はできないものとされている(『自治体法務研究2021夏』73ページ)。そのため、例えば、議員の政治倫理条例の施行規則は、本来であれば、長が定めることになるが、議会には訓令の制定権があるとされているので、施行規程として訓令で定めることが通例である。
地方公営企業法第10条で、「管理者は、法令又は当該地方公共団体の条例若しくは規則又はその機関の定める規則に違反しない限りにおいて、業務に関し管理規程(以下「企業管理規程」という。)を制定することができる。」とされており、水道局や市営の病院など、地方公営企業法を適用して管理者を置いている場合は、「規程」を制定することができる。
分からないのは、消防と会計管理者である。本書46ページにも、「会計管理者等の例規の制定権」として、会計部局に対する内規(訓令等)を定めることができるとされている。訓令は上級機関から下級機関への指示命令である(30ページ)。執行機関である長とその補助機関である職員(副知事や副市長以下)が、このような関係にあるのは明らかであるが、消防長や会計管理者が同じ補助機関である職員に対して訓令を発することができるのかよく分からない。
指揮監督権があることを理由として訓令の制定ができるとするのであれば、消防本部においては、消防長が「消防本部の事務を統括し、消防職員を指揮監督する」(消防組織法第12条第2項)と定められており、消防本部における訓令を定めることができる根拠はここにあるといえる。
会計管理者については、地方自治法第170条第1項において「法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、会計管理者は、当該普通地方公共団体の会計事務をつかさどる。」とされており、会計事務について、会計課内の内規(訓令)を定めることができるといえる。果たして正しい解釈であろうか。
2-7 要綱とは何か
要綱について、昭和40年代の開発ラッシュで~という記述はよく見るものである。いわゆる行政指導的な要綱や条例の代わりに作ったような違法要綱のイメージがあるが、では、私たちに身近な要綱はこういうものなのか(伊藤和之著『基礎から分かる!自治体の例規審査』(学陽書房・2023年)52ページも参照のこと)。
いや、実際は行政指導の要綱よりは、補助金交付要綱、懇談会等の設置要綱、申請等を処理する手続を定めた要綱、契約書の約款のひな形を定めた要綱、例規の解釈を定めた要綱などが一般的かと思う。
要綱に類似する「要領」「指針」について、厳密な取扱区分がなく、告示や例規審査を避ける意図でこれらの名称を使うのは望ましいことではないとされている。そのとおりである。もっとも、厳密な取扱区分を定めている自治体は少数ではないだろうか。国の名称に合わせて、「指針」や「ガイドライン」とするところもあるし、当方では要綱のさらに細かい規定は「要領」でという慣例があったりする。
2-8 公示・告示・公告の違い
公示・告示・公告の違いについて、本書の著者である塩浜克也氏のブログでは、同じく鳥取市公文規程を引いて「実務において「法令中に『公告』と規定されている場合であっても、それが法的効果を伴う場合には『告示』により公示する。」という対応もしっかりしてますね。」と述べられている。
https://kei-zu.hatenablog.com/entry/20050916/p2
2-9 通達と行政実例
御承知のとおり、「通達」は「技術的助言」と名前を変えて、世に出回っている。技術的助言を無視するような運用は通常はしないのであるから、通達行政は存続しているのである。本書にも、引き続き参考になるとされている(56ページ)。本書にある第一法規株式会社提供の「現行法規(通知通達検索)」は検索が容易であり、とてもよい。
行政実例は、『地方自治関係実例判例集』で調べる。なお、株式会社ぎょうせい提供の「GovGuide」に収録されており、調べるのであればこちらが便利である。地方財務実務提要なども収録されており有用である。契約することをお勧めする。
審査基準や処分基準は、行政処分をする際に参考とする基準のことである。審査基準や処分基準を規定するのは、条例でも規則でも要綱でもなんでもよい。決裁でも伺い定めでも構わない。例えば、公の施設の禁止行為として、「物品販売、募金その他これらに類する行為をすること。」が規定されており、「その他これらに類する行為をすること」が何なのかを細かく(要綱とかで)規定したその要綱とかが審査基準である。
法規担当は、多くの相談を受けるが、行政実例が答えをくれることも多々ある。裁判で違法とされた事例(57ページ)もあるが、ほとんどは適法に生きているのであるから、活用することをお勧めする。
第3章 例規策定の手続
長くなってしまったが、第3章に入りたい。ここでは、原課から提出された条例案や規則などをどのような手続をとって議会にあげていくか、改正などをするかが書かれている。
とにかく68ページ~69ページのチェックリスト(例)がよくできている。これを見て審査をしながら、その自治体独自のローカルルールを追加していくのがよい。これをもとに例規審査のマニュアルを作ってもよいだろう。初めて審査をするときは、手元にチェックリストをおいて、一つ一つ項目を見ていくだけで勉強になる。
3-1 例規の制定改廃の流れ
例規審査の工程は、各自治体さまざまであるから、各自治体のスケジュールを確認したほうがよい。本書のスケジュールはあくまで一例である。
「審査に入る前に」(64ページ)という部分は重要である。①政策を決定する手続、②法的な手続、③パブリックコメントがあげられている。これと77ページ・78ページの「3-6 検察協議と自治体」の部分で書かれている④検察協議が、審査前に押さえておくポイントである。当方ではこのほか、⑤議会の委員会も関係する。この委員会は、議会が閉会しているときに開かれる勉強会的な委員会のことである。62ページにあるように、⑥庁内の審査会も関係するだろう。
長から議会へ報告することが必要なものとして、地方自治法に規定するもの以外で留意したいものとしては、次のものがある。
・いじめ重大事態の報告(いじめ対策基本法第30条第3項)
・災害時における市町村等の事務の委託の報告(災害対策基本法施行令第28条第4項)
・市町村障害者計画の策定の報告(障害者基本法第11条第8項)
・新型インフルエンザ等対策の実施に関する計画の作成の報告(新型インフルエンザ等対策特別措置法第8条第6項)
・国民保護計画の作成の報告(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第35条第6項)
なお、当局側ではないが、地方自治法第243条の2の7は、普通地方公共団体の長等の損害賠償責任の一部免責条例について、「普通地方公共団体の議会は、前項の条例の制定又は改廃に関する議決をしようとするときは、あらかじめ監査委員の意見を聴かなければならない。」と定めており、監査委員の意見を聴くことを義務付けている。
条項ズレのような規定の整備の場合も例外はない。規定の整備の条例改正を180条の専決処分事項としている自治体もあるが、その場合、意見聴取の規定の潜脱ではないかと思われる。違法である。意見聴取をせずに条例案を議決した場合は、法令違反として再議の対象となる(地方自治法第176条第4項)。
パブリックコメントを法規担当課が所管していることも多いだろう。規則等の制定改廃にもパブリックコメントを要する自治体もあるので注意が必要である。条例の制定改廃や行政計画の制定等に限る自治体も多い。
条例は行政立法ではないので(塩野宏著『行政法Ⅰ第6版』(有斐閣・2021年)104ページ参照。川端倖司著『条例の法的性質と地方自治の保障』(弘文堂・2024年)113ページも参照のこと。)、法律同様にパブリックコメントの対象にするのはいかがかという意見もあろう。また、法規命令を対象にするのであれば、政令・内閣府令・省令・外局規則・独立機関の規則と同様に、地方公共団体の法規命令としての規則を対象とするのも納得できる。
行政手続法は、法規命令以外にも、審査基準・処分基準・行政指導指針といった行政規則も対象としており、自治体でも同様の規定をしているところもある(宇賀克也著『行政法概説Ⅰ第7版』(有斐閣・2020年)316ページ参照)。
行政手続法に初めて触れたときには、国のパブリックコメントと自治体のパブリックコメントを混同することもあるので、注意しておきたい。
3-2 例規の審査
「形式の審査」として、「利用許可」とせず「利用の許可」のようにしますという部分は、ぜひ覚えておいていただきたい。原課の案では複合の語が多数出てくる。複合の語は、十分に定着しているものを除いて、全て定義して使わなければならないので面倒である。慣用的な表現には注意が必要である。
67ページで、e-Gov法令検索が更新が早いとされているが、第一法規株式会社提供の現行法規(履歴検索)、ぎょうせい株式会社提供の法令Webのほうが見やすく、それほどタイムラグはないので、契約していればこちらのほうがお勧めである。
「点検」の部分で、「者」は「シャ」、「改める」は「カイめる」と読むことが推奨されている。「者」は「物」「もの」があるので有用と思われるが、他はどうだろうか。「超える」も「チョウえる」とすると、「越える」と間違いないのでよいかもしれない。意味のあるものだけ音訓を変えればよいと思う。国のように、全部変えて読む必要はない。
3-3 法令との整合性
上乗せや横出しなど、法令との整合性を気にするような例規の制定の機会はそれほどない。3年で異動するといわれる自治体においては、法規担当としての3年間で1度出会うかどうかぐらいのペースではなかろうか。
3-4 条例案と予算案
「3-4 条例案と予算案」は、見落としがちな部分である(72ページ・73ページ)。「予算との整合」にある具体例を意識して、予算を忘れないようにしたい。
3-5 例規改正のタイミング
国の役人がアレなのが大きな要因ではあるが、地方議会の定例会のタイミングを無視した法令の改廃がよくある。定例会など、6・9・12・2・3の前後どこかの月が通例なのだから、よく考えてほしいものである。
少し込み入った話になるが、法令の改正に伴って生じる条例の改正であれば、「この条例は、○○法の一部を改正する法律(令和○年法律第○号)の施行の日から施行する。」とすれば解決できるのではないかとも考えられる。実際に多くの自治体で用いられる手法であり、実例も多い(全国例規集では1万件以上ヒットする。)のだが、疑義がある。
当該一部改正法の施行日が、地方議会の議決日より前の場合はどうだろうか。意図せず遡及する取扱いになってしまわないだろうか。条項ズレぐらいならそれでも構わないかもしれないが、実質的な内容を伴った規定の場合はそうはいかない。
「この条例は、○○法の一部を改正する法律(令和○年法律第○号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。」という規定も多くある。私としてはこちらが正しいように思うがどうだろうか。
なお、石毛正純著『法制執務詳解新版Ⅲ』(ぎょうせい・2020年)188ページ以下によれば、上位法と下位法の関係にある場合で、上位法がその施行期日を公布の日から一定期間経過した日とする場合や上位法がその施行期日を下位法に委任する場合には、「法律の施行の日から施行する」という書き方をするとされている。条例の公布の方が先であることが前提なのだろうか。
対処方法としては、①臨時会、②専決処分、③追加提案、④先議が挙げられている。どれも実務上よく使う用語であるし、実際に行われるので覚えておくとよい。
自治体によっては、臨時会を開かない慣行があるところや、専決処分を許さない慣行があるところもある(実際に聞いたことがある)ので、注意が必要である。
第4章 規定別・例規審査のポイント
例規のそれぞれの条文に規定される内容ごとに審査のポイントが述べられている。例規は、厳格な前例踏襲であり、既存の表現をそのまま使わなければならない(鎌田薫他著『立法学講義<補遺>』(商事法務・2011年)332ページ参照)。そのため、条文は、その規定される内容によって、書き方が同じであり、審査のポイントも同じになるのである。
4-1 題名
新規制定の場合の題名に厳格なルールはないのだが、通常は、法令や他都市の例規を参考に題名を決める。
昭和22年頃までは法律でも題名が付けられないことがあり、「決闘罪ニ関スル件」(明治22年法律第34号)、「立木ニ関スル件」(明治42年法律第22号)などは、便宜的に公布文の中の語句をもってその法律の同一性を表示する名称としている。
○決闘罪ニ関スル件〔明治二十二年十二月三十日法律第三十四号〕
〔総理・司法大臣副署〕
朕決闘罪ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
〔決闘挑応罪〕
第一条 決闘ヲ挑ミタル者又ハ其挑ニ応シタル者ハ六月以上二年以下ノ重禁錮〔有期懲役〕ニ処シ十円以上百円以下ノ罰金ヲ附加ス
法律に基づいて自治体が規則を定める場合、例えば、建築基準法について定める場合、建築基準法施行規則が省令として既に存在するので、○○市建築基準法施行細則というように、規則だけれど「細則」という題名にすることもある。
改正の場合は、2以上の例規であれば「及び」でつなぎ、3以上であれば「等」とする。あまり出てはこないが、整備や整理を冠することもある。今般の刑法の改正に伴う拘禁刑については、整理条例を制定することになろうか。
4-2 前文
理念条例という意味のない(政治的には意味のある)条例を制定せざるを得ないことがある。そのような場合は、前文を設けることが多い。
理念条例である自治基本条例について、条例で定めることの意義を逢坂誠二・元ニセコ町長が「フロンティア180」(2001年春季号)において、「時代が変わったり、また町長が替わったりして、まちづくりの手法が変わったとしても、まちづくりに係る制度や仕組みを町民の権利として安定して保障することである」と述べているとされている(自治体法務検定委員会編『自治体法務検定公式テキスト政策法務編』(平成29年度検定対応)220ページ参照。)。理念条例のメリットとして、長が替わっても生き続けるという意味があるということだろう。
本書に掲げられているもの以外に、議会基本条例、環境基本条例、手話条例、家庭教育支援条例などで設けられている例を見る。
なお、法制執務の本であれば、この前文の前に「目次」の説明がくることが多い。条文が款・章・節等に区分されている場合は、目次が付いている。また、昭和22年以降の法令では、目次の後に関係条文(第○条-第△条)が付いている。
目次は、比較的量の多い法令に付ける。目次は、大部の法令について、条文の理解と検索の便を図るために付けられるものである。どの程度分量が多ければ目次をつけるかについての基準は特にない。条文が多くて分かりにくいと感じるのであれば付ければよい。
比較的条数の少ない条例に対して、市民の検索の便のために付けたいと相談を受けたことがあるが、1条のみの条文にも章が必要になるなどうるさいので諦めてもらったことがある。
4-3 目的規定・趣旨規定
ざっくりと委任条例なら趣旨規定、それ以外は目的規定だと考えてよい。なお、補助金の交付要綱では、目的規定を設けて、そこに必ず公益上の必要を書かなければならない(稲葉博隆著『自治体リーガルチェック法務の心得21か条』(第一法規・2018年)89ページ参照)。
4-4 定義規定・略称規定
「第○条において同じ」「以下この条において同じ」といった対象条項の限定については、定義された用語が用いられる条項が少ない場合やその法令で用いる用語について、特定の条項に限ってその意味を縮小したり、又は拡張したりして用いる場合に用いられる。明確な基準はないが、法令の場合は、条項・章節等が3つ以下あるいは連続するときに用いられているらしい(石毛正純著『法制執務詳解新版Ⅲ』(ぎょうせい・2020年)88ページ・89ページ)。
よくやってしまう間違いとして、「同」がある。略称を用いた場合は、「同日」や「同法」などとしてはならない(伊藤和之著『基礎から分かる!自治体の例規審査』(学陽書房・2023年)87ページ参照)。
例えば、
(1) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で次のいずれかに該当するもの
ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の一時保護、配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の女性自立支援施設における保護又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第23条第1項の母子生活支援施設における保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
という条項がある場合、アの配偶者暴力防止等法を「同法」とすることはできない。
古い法令・例規で「本条」「本項」と表現されているものは、現在では、「この条」「この項」と表現されるのが一般的とされている(白石忠志著『法律文章読本』(弘文堂・2024年)25ページにも同様の記述があるので参照のこと。)。
4-5 権利制限規定・義務規定
特定の行為を行うに際して、行政庁への届出を義務付けるものがあるとされている。行政庁とは、自治体を1つの法人として捉えたとき、ものを考えてそれを外部に表示する頭に相当する器官(機関)である(板垣勝彦著『ようこそ地方自治法[改訂版]』(第一法規・2018年)145ページ参照)。
この義務規定の義務付けの実効性を担保するためには、併せて罰則が定められることがあるとの記述がある。届出については、届出がされない場合、それを強制するようなことができないので(なお、行政上の義務履行確保としての民事執行手続の利用について、宝塚市パチンコ条例判決(最判平成14年7月9日民集56巻6号1134ページ)参照)、罰則をもって実行性を担保する必要がある。
4-6 許可規定
許可制をとるか、届出制をとるかは難しいところである。本書では、公共の福祉の要請、個人の自由への配慮が挙げられているが、一律に判断することはできない。その判断においては、およそ政治的な面もあるので注意が必要である。
4-7 給付規定
給付自体は、条例で定めなければならないものではない。多くは規則や要綱で定められているとされている。
変な話ではあるが、例えば、補助金の交付を条例で規定すると、それは負担付き贈与契約ではなく、行政処分と解されることがある。そうすると、申請拒否には教示文が必要になるし、審査請求ができることになる。訴訟では処分の取消訴訟(行政事件訴訟法第3条第2項)と申請型義務付け訴訟(同条第6項第2号)を提起することになるし、住民訴訟は2号訴訟となる(地方自治法第242条の2第1項)。なお、契約であれば、訴訟は、補助金の交付を受けることの地位の確認訴訟(行政事件訴訟法第4条)で、住民訴訟は4号訴訟となる(稲葉博隆著『自治体リーガルチェック法務の心得21か条』(第一法規・2018年)95ページ・96ページ参照)。
4-8 使用料規定
使用料については、本書にある公の施設の利用、行政財産の目的外使用のほかに、地方公営企業の給付についての料金(地方公営企業法第21条)、地方公共団体が管理する国の営造物の使用についての使用料(地方財政法第23条)などがある(松村享著『基礎から学ぶ入門地方自治法』(ぎょうせい・2018年)248ページ参照)。
本書にあるように、使用料は条例で定めなければならないので、全てを規則に委任することはできない。使用料の額は、他の公の施設、近隣他都市の状況などを見て政策的に判断することになる。
自治体の財産には、①不動産である公有財産、②動産である物品、③債権、④基金の4種類がある。現金(市の歳入歳出に属する歳計現金のこと)は、②の物品には含まれない。現金は、指定金融機関への預金など、管理等の方法が別に定められているからである。
少し敷衍すると、公有財産は、公用(庁舎のように市町村で利用する)又は公共用(住民の利用に供する=公の施設)に供することにした「行政財産」とそれ以外の空地などの「普通財産」に分けられる。
普通財産は、山奥の空地などのことで、できるだけ民間に売り払って民間で使ってもらうようなものである。地方自治法上の規制はそれほどないので、基本的には自由に売ったり貸したりできる。
それに対して、行政財産は様々な規制がある。庁舎のような公用財産は、市町村が(=私たちが)使うので住民は独占して使用できない。ただし、スペースに余裕がある場合(例えば、役所に自動販売機を置く場合)などは、行政財産の使用許可(俗に目的外使用許可という。)によって使用を許可することができる。
芸術文化施設、スポーツ施設、市民館などは、公共用財産=公の施設として、基本的には住民が自由に使用できるが、使用には市町村の許可が必要である。
なお、公の施設は、民間企業にその管理を委ねることができる。これを「指定管理者制度」という。委託と違って、指定管理者は、市町村に代わって使用を許可することができる(市に代わって行政処分ができる。指定管理者制度のように自治体でない民間の者が行政処分ができる例としては、他に「指定確認検査機関」の行う建築確認がある。)。
4-9 手数料規定
手数料の対象事務とその金額は、市町村の判断で定めることができるが、本書にもあるように、全国的に統一して定めることが特に必要と認められる事務については、法令で定める金額を標準として定めなければならない。
手数料に関する規定は、手数料を徴収する事務、金額、徴収方法、手数料の減免、過料等について規定される。
4-10 附属機関規定
長の諮問機関であるにもかかわらず、条例ではなく要綱等で設置されている例が多々ある。附属機関と私的諮問機関の洗い出しを実施していない自治体は、早急に対処しないと、裁判で負ける可能性があるので注意が必要である。
本書にもあるように、附属機関であるならば、構成員は非常勤の特別職となり、報酬を払うことになる。私的諮問機関であれば、構成員は民間人であって、報償費を払うことになる。附則機関であるのに、報償費を払うのはおかしいとして住民訴訟が提起されて負けるのである(負けるといっても、長に過失なしとされて、実際の支払が求められることはない。)。
附属機関なのかそうでない私的諮問機関なのかの違いは、条例で設置しているかどうかではない。条例で設置しなければならない附属機関であるのに、違法に私的諮問機関として要綱で設置していることが問題なのである。
附属機関かどうかの判断基準として統一のものはない。裁判例も統一的基準を持っているわけではない。当方では、次のような基準で判断をしている。参考にされたい。
①合議体である(2人以上で構成されている)。
②外部委員(他都市、都道府県、国などの職員を含む)が1人以上いる。
③議題をとりまとめ、結論を出す(方向性を示す、答申する、調査する)
以上全てに当てはまれば、附属機関である。
なお、
④報酬がある。
という点も考慮に入れてよい。附属機関の委員は、非常勤特別職であり、報酬の支払いが義務であり、事前に報酬を辞退できない(112ページ)。そのため、無報酬の構成員がいれば、附属機関でないといえるかもしれない。
仮に私的諮問機関を設置する場合は、要綱等の作成について、次の事項に注意すべきである。
①私的諮問機関は意思決定を行わない。そのため、定員や議決の方法について定めてはならない。
②「設置する」といった恒常的な組織であると誤解を招く表現は使ってはならない。③私的諮問機関の名称には、「審議会」「協議会」「審査会」「調査会」「委員会」の名称は用いない。
④「答申」や「意見書」といった会議体としての結論を出してはならない。
⑤委員の選任をするのに「委嘱」という用語は用いない。
なお、さきに引用した『基礎から分かる!自治体の例規審査』の著者である伊藤和之氏のブログ「自治立法立案の技法私論~自治体法制執務雑感Ver.2」の記事
附属機関(5)
https://hoti-ak.hatenablog.com/entry/2019/05/17/214925
が詳しいので、こちらも参照されたい。
このブログは、自治体法規担当にとってとても有用である。
塩浜克也氏のブログ
「自治体法務の備忘録」
https://kei-zu.hatenablog.com/
とともに、過去の分も含めてぜひとも通読してもらいたい。
4-11 委任規定
法律案は「両議院で可決したとき法律となる」とされており(日本国憲法第59条第1項)、条例案は普通地方公共団体の議会の議決事項となっている(地方自治法第96条第1項第1号)。
国の常会(通常国会)は、毎年1回1月中に召集され、会期は、150日間と定められている。延長は1回まで可能である。また、だいたい夏~秋頃に臨時会(臨時国会)が開かれることが多い。地方議会は、3月、6月、9月、12月の4回定例会が開かれることが多い。
このように、国会、市議会は、それぞれ開催時期が限られており、法律や条例を制定・改正・廃止するのは大変である。そのため、国や市は、もっと機動的な(簡単に作ったり改正したりできる)政令、府省令、規則に詳細な事項を委任している。
ただし、政令・府省令は、原則として国のパブリックコメントに付すことが必要なので、長の規則よりは、制定改廃に時間がかかる。
条文の最後に付すような包括的な委任条項は、条例においては原則として不要である。法律では委任する命令の形式を明記する意味があるが、条例の実施に関する事項については、特に委任がなくても定めることができるし、執行機関がどこかは明らかであるからである(伊藤和之著『基礎から分かる!自治体の例規審査』(学陽書房・2023年)130ページ参照)。
基本的には、特定の事項を委任するために個別の条文に「規則で定める」といった規定を入れる。なお、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法のように、法律の条文に個別の委任規定がなくても、委任先?が勝手に個別事項を定めているケースもある(「自治実務セミナー」2024年2月号35ページ北村喜宣執筆部分参照)。
当該事例は、次のようなものである。
○再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法
(再生可能エネルギー発電事業計画の認定)
第九条 自らが維持し、及び運用する再生可能エネルギー発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気を市場取引等により供給し、又は特定契約により電気事業者に対し供給する事業(以下「再生可能エネルギー発電事業」という。)を行おうとする者は、再生可能エネルギー発電設備ごとに、経済産業省令で定めるところにより、再生可能エネルギー発電事業の実施に関する計画(以下「再生可能エネルギー発電事業計画」という。)を作成し、経済産業大臣の認定を申請することができる。
(中略)
4 経済産業大臣は、第一項の規定による申請があった場合において、その申請に係る再生可能エネルギー発電事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一 再生可能エネルギー発電事業の内容が、電気についてエネルギー源としての再生可能エネルギー電気の利用の促進に資するものとして経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
二 再生可能エネルギー発電事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
(以下略)
○再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則
第五条の二 法第九条第四項第二号に規定する再生可能エネルギー発電事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれる基準は、次に掲げるものとする。
一 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を電気事業者が維持し、及び運用する電線路に電気的に接続することについて電気事業者の同意を得ていること。
二 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を設置する場所について所有権その他の使用の権原を有するか、又はこれを確実に取得することができると認められること。
(以下略)
本来は、法第9条第4項第1号と同様に、「再生可能エネルギー発電事業が円滑かつ確実に実施されるものであって、経済産業省令で定める基準に適合するものであること。」などにすべきであった。法律であっても、このように粗雑な規定もあり、それは法制局の立法技術が稚拙であることに由来しているのである。
4-12 「公の施設」条例
122ページ「公の施設」ではない公共物について、公の施設と単なる行政財産との区別は微妙である。「鶏が先か、卵が先か」の話ではないが、住民全員が自由に使える施設を作ると、自動的に公の施設になるのか。条例でそれを設置しなければ単なる行政財産なのか、附属機関のように、違法な公の施設なのか。
4-13 指定管理者制度
公の施設条例を作る(公の施設を作る)ときには、直営であるか、指定管理者であるかをまず確定する。それにより、条例制定の時期も利用料金(使用料)の額も違ってくるのである。
4-14 罰則規定
刑罰を設けると、検察協議が必要となるため、過料で済ましておくというケースもある。罰金でも過料でも問題となるのが額である。他の例規や他都市の事例を参考とすることが多いと思うが、最高額であるべきとの主張がされることもあり悩ましい。正解はないので、他都市が過料3万円のところ、じぶんたちが5万円というのも特に問題はない。
4-15 附則
施行期日と経過措置は、結構悩む部分である。初めて法規担当となったときには、施行日を4月1日とか、原課が指定した切りのいい数字を入れたくなるが、公布の日でよいのではないかと一度立ち止まって検討する必要がある。
施行日が中途半端な日付であったり、年度の途中である場合で、それが法令等の施行日とかでないときは、その日付が何なのかよく検討しなければならない。
規則の様式を改正するときなどは、旧様式を使えるようにしないと困ったりする。経過措置は、色々なケースを検討して、原課の実務を知って作る必要があるので注意すべきである。
第5章 立法技術のポイント
5-1 用字・用語
初めに最低限覚えておくべき用字・用語が抜き出されている。すなわち、句読点、及び・並びに、又は・若しくは、その他・その他の、から・まで・しなければならない・するものとする、することができる・することができない、である。
法制執務上覚えておくべき用字・用語は多々あるが、注力するポイントを絞ってもらっているのでありがたい。仮に追加するとすれば、直ちに・速やかに・遅滞なく、係る・関する・ついて、者・物・もの、時・とき・場合ぐらいであろうか(伊藤和之著『基礎から分かる!自治体の例規審査』(学陽書房・2023年)の該当部分を参照するとよい)。
主語の後には、読点を打つとされているが、主語に限らず、主題の「は」の後には読点を打つ。並列する名詞が2個のときは、読点を用いないで「及び」「又は」等の接続詞で結ぶ。並列する語が2語であっても、動詞、形容詞又は副詞を並列している場合は、読点を打つ。
「直ちに」と「速やかに」と「遅滞なく」は、いずれも時間的近接性を表す表現である。「直ちに」は、時間的即時性が最も強いもので、一切の遅滞を許さないときに用いる。「遅滞なく」は、時間的即時性が最も弱いもので、合理的な理由があれば遅滞は許される。「速やかに」は、直ちにと遅滞なくの中間である。
「直ちに」と「遅滞なく」に反して遅滞した場合は、不当又は違法と判断される場合がある。これに対して、「速やかに」は、訓示的な意味で使われる場合が多いといわれており、その遅滞は直ちに違法にはならない。
そのため、行政庁側に対して急いで行うような規定を設けるときは、速やかにが用いられることが多い。補助金交付要綱などが最たる例である。
なお、時間的即時性が直ちに→速やかに→遅滞なくと解されることについて判断した裁判例として、大阪高裁昭和37年12月10日判決がある。
「係る」と「関する」は、いずれも、ある言葉とある言葉をつないで用いられる用語である。「その」という意味や、「〇〇の」「〇〇が行う」「〇〇に属する」「〇〇の対象になっている」「〇〇に関係する」など様々な意味で用いられる。
「係る」は、ある語句とある語句を「直接的に」強く結びつけることを意識して用いられる。「関する」は、係ると同様に「〇〇に関係する」「〇〇についての」という意味で用いられる。ただし、「関する」は何らかの関係性がある場合に用いられ、「係る」より広く、より緩やかな意味合いで用いられる。
「者」は法律上の人格者である自然人(生きている生身の人間)と法人を指す場合に用いる。「物」は人格者以外の有体物を指す場合に用いる。「もの」は者や物に当たらない抽象的なものを指す場合や、法人格なき社団・財団だけを指す場合、関係代名詞に当たる用法で用いる場合などがある。
「物」は一般に行為の客体である民法第85条の有体物、物件、物質を指す場合に用いる。「もの」は、自然人や法人のほかに、人格のない社団・財団を含んでいる場合やそれだけを指す場合に用いる。また、「愛知県外に居住する”者”で、やむを得ない事情があると教育委員会が認める”もの”」というように関係代名詞的な用法で使われる場合がある。
「時」は時点や時刻を強調する場合に用いる。「とき」は仮定的条件を表す場合に使われる。「場合」も「とき」と同じように仮定的条件を表す場合に使う。「場合」と「とき」はどちらを使うかの明確な基準はなく、慣用や文脈の語感により決める。
「時」は、例えば「当該職に就いていた”時”に在職していた執行機関の組織等」というように用いる。同じ条文で大きな仮定と小さな仮定を使うときは、大きな条件に「場合」を、小さな条件には「とき」を使う。例えば「…職員が職務に復帰した”場合”において、他の職員との均衡上必要があると認められる”とき”は」というように用いる。
5-2 改め文とは
まずは改め文の種類を押さえる。これを知らないと官報も読めない。改正すると改めるで迷わないように。
5-3 条項の改正
1つの条文の中に対象となる文言が複数ある場合は、最初のころ見落としがちであるので、注意すべきである。
5-4 条項の追加・削除
改め文でなるほどという部分はここではないだろうか。条項を途中で加えるときは、既存の条項を先に動かして、そこに番号を空けて追加することになる。
少し特殊な例外を紹介したい。
直近の例で、児童福祉法等の一部を改正する法律(令和4年法律第66号)では、児童福祉法第6条の2の2第5項を第4項に繰り上げているが、改め文では、「同条第三項を削る」としか出てこない。
通常、項を廃止する場合は、廃止した項の部分のスペースを埋めるため、後ろの項の繰り上げを行う必要があるので、第4項を削り、第5項を第4項とし・・・という改め文が必要になる。
しかし、児童福祉法は、実は項番号がない。項番号は、昭和23年頃から付けられるようになったもので、それ以前の法令には項番号は付けられていない。そのため、項番号をずらす必要はなく、このような場合は、自動的に繰り上がることとなっている。
第二条 児童福祉法の一部を次のように改正する。
目次中「第二十一条の十七」を「第二十一条の十八」に改める。
第六条の二の二第一項中「 、医療型児童発達支援」を削り、同条第二項中「の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練」を「及び知識技能の習得並びに集団生活への適応のための支援」に、「供与する」を「供与し、又はこれに併せて児童発達支援センターにおいて治療(上肢、下肢又は体幹の機能の障害(以下「肢体不自由」という。)のある児童に対して行われるものに限る。第二十一条の五の二第一号及び第二十一条の五の二十九第一項において同じ。)を行う」に改め、同条第四項中「除く。)」の下に「又は専修学校等(同法第百二十四条に規定する専修学校及び同法第百三十四条第一項に規定する各種学校をいう。以下この項において同じ。)」を、「障害児」の下に「(専修学校等に就学している障害児にあつては、その福祉の増進を図るため、授業の終了後又は休業日における支援の必要があると市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が認める者に限る。)」を加え、「訓練」を「支援」に改め、同条第五項中「 、医療型児童発達支援」を削り、「の指導、」を「及び」に、「付与、」を「習得並びに」に、「訓練」を「支援」に改め、同条第八項中「指定障害児通所支援事業者等」を「指定障害児通所支援事業者」に改め、同条第三項を削る。
5-5 改め文に迷ったときは
本書にあるように、探すなら衆議院のウェブサイトもよいが、官報情報検索サービスを契約しているようであれば、そちらもよいし、各自治体の例規集で原議検索してみるのもよい。なお、府省令には注意されたし。
5-6 改正方法の選択
一部改正と全部改正、全部改正と廃止制定については、実務上迷う機会というのはそれほどない。全部改正自体があまりないからである。
例えば、当方で経験した例としては、次のようなものがある。
景観法の改正及び景観計画の新規策定があり、もともとあった景観条例の内容が大幅に変更されることとなった。廃止制定でもよかったが、そもそもの景観条例も景観法に基づいていたことから、連続性を考慮して、全部改正とした。
ある公の施設について、全面改修を行うとともに、直営から指定管理者とすることとした。部屋も運営方法も全部変わるので、全部改正で考えていたが、事業に関する規定や使用の許可など、ほとんど全ての条文をいじるものの、それぞれの条文はそれほど大部の変更にはならないことが分かったので、一部改正とした。
5-7 条文のわかりやすさ
書籍では絶対に書けないが、「文の構成をあえて複雑にする」ということがある。どうしても議会を通したい条例があるが、条文の中身まで深く聞かれたくない、条文で規定することがなかなかに困難であるというような規定を設ける場合が挙げられる。括弧を多用するなどがこれに当たる。実際、法律でもあえて複雑にしているのではないかと思われるものもあり、議員を煙に巻く手法なのであろう。
「具体的な事例」にあるように、号建てにしていくと大変分かりやすいのであるが、肝心の号がとても長くなってしまうこともある。また、これぐらいであれば、号建てにせずに本文に書けばよかったのに、と思う例も散見される。いずれにしろやりすぎは禁物である。
5-8 例規のローカルルール
この記述がある書籍は他にないのではないか。なかなかローカルルールまでカバーしようとは考えない。変態である。
理由のないローカルルールは減少させていくことが望ましいという指摘はもっともである。厳格な前例踏襲が必要な法制執務ではあるが、意味のないローカルルールに捉われる必要はない。
ただし、逆に言えば、ゼネラルルールに疑問があれば、自治体内で統一したローカルルールによって、これを書き換えることもあってよいと思う。実例はそれほどないと思うが、当方でも実はある。特に経過措置において顕著である。省令にもそのような傾向があるのは気のせいだろうか。
5-9 「新旧対照表方式」の例規改正
今後、新規に法規担当になった方がベテランになる頃には、多くの自治体や政令などでは新旧対照表方式になっているのではないか。
特に、改め文方式であるにもかかわらず、参考資料として新旧対照表も付けているような自治体は、早急に新旧対照表方式に移行すべきである。
当方は、15年ほど前から新旧対照表方式であるが、デメリットとしては、読み合わせの分量が増える=時間がかかること、税条例など分量が大部になることがあること、附則等は改め文方式なので、改め文の知識も必要になることなどが挙げられる。
メリットとしては、やはり分かりやすい。見た目ですぐに誤りを見つけることができる。溶け込んだ後のイメージもしやすいし、溶け込まないようなケースがほとんどない。
また、新旧対照表方式はローカルルールの最たるものなので(実際は、壮大な表の改正という改め文方式である。)、自分自身でルールを作ることができる。例えば、当方では、改め文のときほど下線を引かない(単語を特定しない)し、条の一番先頭に加えたり削ったりも容易である。同じ単語が2個あっても、そこにそのまま線を引くだけでよい、などがある。分かりにくければ、分かりやすいようにルールを作ればよいのである。
5-10 例規の過誤
著者も自負するように、他の書籍ではほとんど見かけない記述であり、本書で最も注目すべき部分でもある。「6-6 議案の訂正・撤回」とともに熟読してほしい。
簡潔にいえば、過誤は遡って修正できない。国のように官報正誤で直すのは国会を軽視したインチキ手法である。当然に、自治体の公報で同じようなことをしてはならない。議会軽視につながる。
それぐらい、法規担当は意識を張って例規審査をしなければならない。過誤というのは本当に一大事なのである。なお、条項ずれに関しては、「変更解釈」によって、放置することも可能であるとされている点に注意が必要である(169ページ)。
この「変更解釈」というのは、そういうものが慣例でずっと受け継がれているというだけであって、何か公に認められているものではないが、国も地方もこれで大丈夫であるという共通認識である。経緯や結果が分かり切っているのだから紛れがないということだろうか。
少し検索してみれば、例えば、
「法令の制定又は改廃に伴い必要とされる都市計画の条項ずれに係る形式的な修正について(技術的助言)」という事務連絡(平成31年3月28日付け国土交通省都市局都市計画課長補佐)において、
「都市計画において引用されている法令の条項は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定(同法第21条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)による告示があった日において有効であったものとして解釈されることから、条項ずれに係る都市計画の修正を直ちに行わないという理由のみをもって、都市計画そのものの効力に影響を及ぼすものではない。」
とされている。条項ずれを修正しないからといって、その効力には影響はないというのである。
本書には、平成23年法律第35号(地方自治法の一部を改正する法律)について記載されているが、直近の例として、会社法の例がある。
会社法第202条第1項第1号は、
(株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合)
第二百二条 株式会社は、第百九十九条第一項の募集において、株主に株式の割当てを受ける権利を与えることができる。この場合においては、募集事項のほか、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 株主に対し、次条第二項の申込みをすることにより当該株式会社の募集株式(種類株式発行会社にあっては、当該株主の有する種類の株式と同一の種類のもの)の割当てを受ける権利を与える旨
と規定されており、「次条第二項の申込みをすることにより」となっている。
会社法第202条の2第2項は、次のような条文である。
(取締役の報酬等に係る募集事項の決定の特則)
第二百二条の二 (略)
2 前項各号に掲げる事項を定めた場合における第百九十九条第二項の規定の適用については、同項中「前項各号」とあるのは、「前項各号(第二号及び第四号を除く。)及び第二百二条の二第一項各号」とする。この場合においては、第二百条及び前条の規定は、適用しない。
そして、第203条第2項は、次のような条文である。
(募集株式の申込み)
第二百三条 (略)
2 第百九十九条第一項の募集に応じて募集株式の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を株式会社に交付しなければならない。
一 申込みをする者の氏名又は名称及び住所
二 引き受けようとする募集株式の数
3 前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、株式会社の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付した
第203条第3項にもあるように、「申込み」について書かれているのは、この第203条第2項であり、第202条第1項第1号の「次条第二項」は、第202条の2第2項のことではなく、第203条第2項のことであり、過誤が起きている。
こういった事例について、この「次条第二項」を、(法制執務のルールを無視して)、変更解釈を行い、第203条第2項だと読むのである。
仮に、第202条の2第2項に「申込み」とあったらどうだろうか。その場合は、お得意の「官報正誤」によったのであろう。国も大概である。
実際に過誤を発生させないためにどうするかであるが、本書にもあるように、まずはクロスチェックが重要である。クロスチェックをする前提として、5年・10年といった法規のベテラン職員を配置しておくことが求められる。素人がいくらクロスチェックをしても意味がない。
当方では、全ての条文や内容の1文字1文字(これは条例に限らず、一般議案(単行議決や単行案ともいう)も承認も諮問も報告もそれこそ全てである。)を係内で読み合わせる。
当方には、弁護士職員2名(管理職員と係長級)、私(係長級)と、主任1名、担当3名がおり、議案は弁護士職員を含めて全てに配布する。
主任と担当が案を作り、それを配布し、全員でチェックする。その後、私を含めた主任、担当の計5名で密室に1日籠り、まずは、議案についての疑問点、修正点、問題点などを洗い出す。後日、修正した議案を再度配布し、5名で1日かけて読み合わせを行う(3月定例会などは2日間かかる。)。1文字1文字全て読む。
読み合わせ後、原課に点検に出す。点検後、修正をした後に、議案の体裁を整えて、再度配布し、5名で2度目の読み合わせを行う。1度目と読む人を変えるなどの工夫をしている。さらに、2回目の読み合わせ後に原課に点検に出し、これを最終版とする。
なお、議案の概要をまとめた資料を、事前に作成し、議会などに配布している。議案の概要(要点)は、この時点で修正がないように、係内と原課でチェックをしている。
議案のチェックには、過去の議案を参考にするのが最も効果的であり、当方では、DocuWorksを使って、全ての議案の検索ができるようにしている。一般議案も報告も検索できる。なお、秋からはD1-Lawgueを契約予定であり、これに変わることが期待されている(Lawgueについて気になる方は個別に聞いてもらいたい。)。
また、株式会社ぎょうせいの政策法務支援システム、GovGuide(電子書棚)、それから、第一法規株式会社のコンシェルジュデスク、全国例規検索、類似例規検索なども活用している。
例規審査には、審査を容易にするツールが多くあるので、できるだけ契約しておきたい。なくては困るが、ありすぎて困ることはない。当方は、たぶん日本一さまざまな法規のコンテンツを契約していると思われる。次年度はぎょうせい株式会社の答弁リンクを導入予定である。
第6章 議会対応のポイント
6-1 議会対応の勘どころ
本書にもあるように、議会側(議会事務局側)は、当局側(執行機関側)と直接やりとりをするようなことはない。例えば、議会として、直接に各部局に通知を出したり、質問をしたりはしない。窓口となる当局側の部署が必ずある。それが法規担当部署である。
招集は、長の権限である。議会関係の時の流れは会計年度ではなく暦年(1/1~12/31)なので、3月定例会といえば第1回定例会のことである。予算自体が4月1日から使えないと困るので、時期をずらしている。
条例案や一般議案とは別に、長からの報告として書かれている前年度からの継続費、継続費の清算などは、条文とともに確認したい(176ページ)。
一般質問の答弁の準備で、法的な助言を求められるケースはそれほどない。純粋に法的なものであればよいのだが、多くは政治的な面が絡む。できるだけ、法規の担当者で答えるのではなく、管理職員に対応してもらうべきであろう。
6-2 議決と法規担当
議会の議決が必要な事件については、ざっくりと覚えておくとよい。例えば、条例の改正に議決は必要であるが、規則の改正に議決は必要ない。議決が必要とする条文がないからである。
議決事件は、地方自治法第96条第1項に15個羅列されているが、「その他法律又はこれに基づく政令(これらに基づく条例を含む。)により議会の権限に属する事項」という第15号の規定があるので、第96条に規定されている事項が議決事件の全てだと思ってもらってよい。
条例案の議決、議長からの送付後には、公布の準備を進める。といっても、即日公布の自治体も多くあり、「公布の準備を進める」というのはフィクションだったりもする。どのようにしているかは、各自治体のルールによる。
6-3 議案と議会
6-4 専決処分の取扱い
両者は、合わせて読むとよい。まず、議決事件の処理方法には、3種類がある。
①議会の議決
②179条による専決処分
③180条による専決処分
である。
なお、「議決事件」とは何かであるが、議会が会議において処理すべき事項が「案件」であり、案件の提出を受けて、議会は具体的な活動を行うことができる。この案件を地方自治法上は、「事件」と呼んでいる(同法第96条、第99条、第101条第2項・第3項、第102条第3項~第6項、第109条第6項・第8項、第112条第1項、第117条、第119条)。案件の種類としては、議決事件(議案、動議、請願、陳情等)、選挙、質問、報告等がある。
さて、①は、通常どおり議会の議決を経るものである。
②の179条専決は、3月末の市税条例の改正や、緊急の補正予算などに用いられる。急を要するとき(議会を開いている時間がないとき)に長が専決処分(市長決裁)で条例改正や補正予算を決めてしまうのである。なお、次の議会での「承認」が必要となる。
③の180条専決は、あらかじめ議会側がこれは長が専決処分をしてよいと定めたものについて、専決処分するものである。自治体によって何を専決処分できるかは差があるが、一定額以下の変更契約、一定額以下の損害賠償の額の決定や和解、訴訟物の価額が一定以下の訴えの提起などについては、専決処分事項とされていることが多い。中には、条例の規定の整備を専決処分事項にしている自治体もある。羨ましい。
180条専決を行った場合は、次の議会で「報告」が必要となる。一定額というのは、185ページにあるように、自治体によってバラバラではあるが、例えば、損害賠償や訴えの提起であれば、中核市レベルで100万円、指定都市レベルで500万円が相場のようにみえる。何度もいうが、他都市の事例をそのまま使うのが法制執務であるから。
注意しなければならないのは、いずれの専決処分も、(次の)議会で承認or報告を行わなければならないというところである。特に、臨時会を挟んだ場合や、議会の開会中に専決処分するときなどは忘れがちである。開会中に専決処分をしたら、追加提案として(追加提案と同時に)報告するなど、忘れないようにしたい。
いつ議案を議会が審査するかによって、先議と追加提案に分かれる。通常の議案審査は、本会議から委員会に付託され、委員会で審査されて、本会議最終日で議決される。議決後に長が文句をいうのが「再議」であるが、再議をするような自治体は稀なので、とりあえず無視してよい。
6-5 議案の修正
議案の修正案が出される場合も、再議と同様に、長と議会がもめているとか、何かイレギュラーな関係にあることが多く、あまり気にしなくてよい。修正案が出されるようなときは、議会側(議会事務局)や議員から何らかのアクションが事前にあることがほとんどであり、そのときにこの186ページに戻ってくればよい。
6-6 議案の訂正・撤回
できれば一生見たくない部分である。長が議会で謝罪する、正誤表を作る、訂正のシールを作るなど、自治体によってさまざまだが、いずれにしろ大変なことである。
議案のチェックを十二分にして、訂正は起こらないようにしたい。当方では、だいたい5年に1回のペースぐらいで発生しているが、ここ7~8年はうまくやれている。うまくやれているというのは、深い意味があるが、深堀してほしくはない。
6-7 議員提案の条例
二元代表制の原理からすれば、議員提案条例に(執行部側の)法規担当が関わることはない。そのため、この項目について、(表向きは)重視すべきものではない。
しかし、現実には、議員には条例の作成能力がないことが多く(たとえ弁護士などの法曹有資格者であっても、法令・例規の立案ができるものはいない。)、他都市の条例をそのまま使っていておかしくなっているものや、そもそも条例の体をなしていないものなどが多い。
そのため、特に与党系の、可決が見込まれるような条例案については、法規担当も何らかの形で関与していかないと大変なことになる。193ページにあるように法規担当が見るという自治体も多いだろう。
経験がある方は分かると思うが、なかなか執行部側の条例案とは勝手が違う。何度も直したりとか、議員に意図を聞いたりなどが難しかったり、議会事務局を通さないといけないといった縛りがある。間違いを指摘しても、直してくれなかったりもする。どこまでいっても、議員提案の責任を当該議員にあるので、致命的なミスではない限りは容認することになろう。当方もそうしている。
6-8 住民提案の条例(直接請求)
この項目は、実際にそのような話があってから見ればよい。直接請求がされるような自治体はほとんどない。当方はここ数年で2回もあったが。
第7章 法規担当の仕事術
7-1 法律を理解するコツ
いきなり知らない法律を読むことはほとんどないので、何らかのきっかけで読むことになる。国のポンチ絵(198頁)は、パワーポイントで1頁にまとめたいけど、例外にも全部触れたいという意図が見え見えで、文字ばかりで大変に分かりにくいものもある。省庁のホームページなど、国民向けの解説の方が分かりやすかったりする。
また、例規に影響がある最新の法令改正の情報などは、第一法規株式会社提供の例規整備NAVIの例規整備チェックシートや、株式会社ぎょうせい提供の法令改廃情報の法令トピックスに載るので、こちらのほうが分かりやすい。
7-2 条項ずれは恥ずかしい
恥ずかしいが、変更解釈があるし、致命的ではない。ただ恥ずかしいだけである。
第一法規株式会社提供の法令FOCUSや株式会社ぎょうせい提供の法令改廃情報の法令改正に例規への影響が載るので、官報とともに、これをチェックしておけばよい。
7-3 官報の読み方・使い方
当方では、紙の官報を見ながら、法令改廃情報や法令FOCUSをチェックしていくこととしている。官報そのものを見て、例規への影響などが分かるようになるのはしばらく先なので、法令改廃情報などが更新されたら、官報とともに見る癖をつけておけばよい。
毎日、官報を見る先輩もいるだろう。そのような先輩は情報も早く、いち早く原課に知らせるなどしている。尊敬すべき点ではあるが、少し気持ち悪い。
7-4 法令の情報を収集しよう
7-3で取り上げたように、官報そのものを見て条項ずれなどを発見するのは、さすがに新任法規担当には難しいので、法令改廃情報や法令FOCUSを使ってほしい。
パブリックコメントも毎日チェックしている先輩に遭遇することもあるだろう。官報同様に気持ちわ(以下略
ここに書かれている官報、パブコメについては、毎日の習慣にすると、例規改正に備えることができて有用であるが、雑務も多い新任法規担当には無理だと思われるので、数年経過したら習慣化してみるとよい。
閣議案件、総務省、人事院勧告については、それほど見ることはないが、衆議院のサイトは見ることも多い。国会に提出された法案の審議状況を見ることができるため、例えば3月末の地方税法の一部改正などは、ここを逐一チェックしながら動向を探ることになる。法案の審査は、一定の流れがあるので、同様の法案をいくつか探して、「経過」をたどると、今どのぐらいの段階なのか目安を付けることができる。
7-5 制度の趣旨をつかむコツ
特に法令であれば、国のポンチ絵や通知などを見る。命令であればパブリックコメントにも資料が付いているのでそこを見るとよい。各部局宛てに所管省庁から通知が来ていることが多いので、それらをもらうようにするとよい。各部局の中には、催促しないと通知を回してくれないところもあるので注意が必要である。
7-6 お手本(ベンチマーク)
国の法令のベンチマークについて書かれているが、当方では、まずは自分のところの条例を参照するようにしている。先人をどれぐらい信用するかによって変わるとは思うが。
条例(例)や参考例といったものと書きぶりなどを変えている自治体もあるが、まずは条例(例)どおりでよい。言い回しを変えるレベルならいいが、条項を追加したり、削ったりなどすると、後々、条例(例)となぜ違うのか、どうしてこうしたのかといったことが分からなくなり大変である。きれいだろうが汚かろうが、要は間違いなく読めればいいので、愚直に準則に従っておくのも一つの手である。
7-7 検索のコツ
どのような相談を受ける場合でも、私や私の課に属する弁護士職員は、まずは、インターネットで検索をしている。グーグルがよい。
キーワード検索をすると、各省庁の見解、大学教授や弁護士の見解、例規関係の会社(株式会社ぎょうせい・第一法規株式会社など)の見解、他都市の事例などが見つかることも多い。ただし、個人の運営しているブログやSNSなど、信用できるサイトか否かをしっかりチェックすること。
基本的には、インターネットで調べることにより、ほとんどの問題は解決する。インターネットを是非活用してほしい。若い方は、インターネットに慣れ親しんでいると思うので調べることに対して抵抗はないかと思う。半日ぐらいかけてがんがん調べてほしい。
私のような古い世代は、まだインターネットの黎明期で、メディアリテラシーなどが叫ばれていたときを生きていたので、インターネットに懐疑的な場合も多い。しかし、今やインターネットでは国や県の見解、大学教授の見解など、確かな情報がたくさん落ちているので、恐れずに活用してほしい。
7-8 「規定すべき内容」の固め方
規定すべき内容については、自身の自治体の他の例規の規定ぶりを参考にしたり、他都市の事例を参考にして決めていく。
特に法令に基づかない独自条例(自主条例)である場合には困難が伴う。庁内会議などでしっかりと内容を詰めておいてもらわないと、なかなか規定が決まらないことも多い。
7-9 法務の効果的な執行
「政策法務担当」の例が出ているが、果たして政策法務担当は思った通り機能しているのだろうか。当該課の例規がミスったときは、この政策法務担当が責任をとることになるのか。
各自治体で違いがあるだろうが、例えば当方では、文書主任者、広報主任者、内部統制責任者、公益通報担当者、多文化共生主任者、市民協働主任者、男女共同参画担当者、防災担当者などなど、さまざまな役割が管理職等に与えられているが、果たしてそれらの役割を十分に果たせているのか疑問である。
7-10 必要なのはワープロ術
例規の体裁をWordで整えている自治体も多いのではないだろうか。当方もそうである。Wordは、表やインデントなどレイアウトで苦労することも多々あり、悩みの種である。インターネットで検索して、解決法を探ることも多い。
後閲機能が好きな方も多いが、コメントが全部表示されなかったり、修正が多すぎると、どこをどうやり取りしたのか分からなくなるなど、難点もある。お金があれば、D1-LAWGUEを契約することをお勧めする。
LAWGUEは比較的最近始まったサービスである。第一法規株式会社がFRAIM株式会社と提携しているサービスになる。例規に限らず、契約書や通知文などの作成支援ツールで、自治体がそれぞれの契約書や通知文などのサンプルや過去の事例をあらかじめ登録しておくことで、契約書等を作成するときに、本来入れるべき条文が入っていないなどの指摘をしてくれる。また、条文の入れ替えなどもでき、文書作成が容易になるとともに、ミスをなくすことができる。初期導入費用が高いことが難点であるが、法規担当部署のみならず、契約部署でも活躍できるので、かなりお勧めである。
第8章 法律相談・訴訟対応
8-1 法律相談の勘どころ
新任法規担当は、相談について即答してはいけない。分かるものであっても落とし穴が潜んでいるのが法務の怖いところであるので、一旦先輩に尋ねることを忘れてはならない。法規担当の意見が課の意見、部の意見、市の意見と広まっていく怖さは想像以上であるので、用心されたい。
「行政が解決すべき課題を認識しているのは、その業務を担当している原課の職員」という指摘はまさにそのとおりであり、原課にしっかりと考えてもらってから相談を受けるようにしたい。
相談を受けたら、まずは、7-7にあるように、インターネットで検索をして調べる。これだけでかなり糸口がつかめる。
第一法規株式会社の提供するコンシェルジュデスクは、地方自治法の解説などが収録されている。キーワード検索ができるので、こちらもかなり活用できる。
第一法規株式会社は例規関連の会社であり、業界シェア第2位である。約4割の自治体が採用している。業界シェア第1位は株式会社ぎょうせいで、約6割の自治体が採用しており、例規関連のシステムはこの2社が独占している。過去には、新日本法規やクレステックなども聞くことがあったが、今はほとんど聞かない。当方では、メインの例規構築・検索は株式会社ぎょうせいであるが、それ以外の第一法規株式会社のオプションシステムをほとんど全て契約している。
調べることができる内容は、①地方自治法、②地方公務員法、③行政手続法、④行政不服審査法、⑤行政事件訴訟法、⑥情報公開、⑦個人情報保護、⑧債権管理、⑨契約事務、⑩財務事務など多岐にわたる。ただし、それぞれ契約が必要である。それほど高くないので、全て契約したい。
次に、第一法規のWEB法制相談がある。過去に各自治体から第一法規株式会社に寄せられた相談への回答が多数収録されている。疑問の解決になる事例も多々あるので、是非参考にしてもらいたい。
なお、WEB法制相談は、有料で、法制執務に関する相談について、月5件まで第一法規株式会社の専門の職員(県のOBや役所OBが多いらしい)から回答をもらえる。非弁ではないかという批判もあるらしいが、大丈夫なのであろう。
プレミアム法制相談というサービスもあり、メールにて第一法規株式会社契約の弁護士等に相談ができるもので、こちらは地方自治法や民法など、どのような相談にも対応してもらえるものになっている。自治体内弁護士や顧問弁護士とともに、セカンドオピニオンとして利用できる。
類似の事例など、裁判になった事例があれば、判例を検索すると答えが見つかることがある。令和元年時点の少し古いデータになるが、株式会社ぎょうせいが提携しているTKCの判例検索は、判例全文と要旨を合わせて296,582件が収録さている。
第一法規株式会社のD1-Law.com判例体系は、判例総件数が297,752件、要旨総件数が389,902件、本文総件数が289,934件の収録件数となっている。
総数ではそれほど変わらないが、収録されている判例が異なっているので、両社を契約することで、たいていの判例は探すことができる。
別途契約が必要となるが、TKCの判例検索は、多数の文献とのリンクや検索、参照が可能となっており、例えば、最高裁判所調査官解説、判例地方自治、判例タイムズなど、判例の内容を詳しく知りたい場合に役に立つ。なお、ほとんどがLGWANに対応しているが、一部有斐閣などの文献は現状ではインターネットのみの対応となっている。
D1-Law.com判例体系は、主要判例が判例タイムズの解説情報とリンクしているが、文献としてはそれぐらいである。最近では、最高裁判所調査官解説等も別料金で見れるようになっているようだ。
解説情報が少ない代わりに、D1-Law.com判例体系は、現行法規とリンクしており、法令に直接アクセスできるほか、別途契約のQuickReaderにより目次と見出しを強調表示して、簡単に要旨が分かるような機能が加えられている。
次に、第一法規株式会社には、国からの通知・通達の主なものを検索・閲覧できる現行法規[通知通達]がある。国から業務の指針や法令の解釈などが示されている場合があり、こちらも活用するとよい。
次に、株式会社ぎょうせいの電子書棚がある。電子書棚は、加除式書籍を契約している場合に受けられるオプションで、電子上で加除式図書を閲覧・印刷等ができる。また、令和5年度から「Gov-Guide」というサービスが追加され、電子書棚をデータ化して横断検索・閲覧等ができるようになっており、コンシェルジュデスクと対になるサービスである。
地方財務実務提要など、法規担当であれば誰もが見る書籍が完全電子化され、さまざまな加除式図書を横断的に検索し、ダウンロードやコピーなどができ大変便利である。用途によってコンシェルジュデスクと使い分けていくとよい。
以上のような検索ツールを使って、相談の答えを探していくことになる。
なお、ついでに例規検索等についても補足しておく。
まず、例規集データベースの構築等であるが、議決された条例や規則などをデータベースに搭載する業務について、第一法規株式会社の場合は、令和元年まではデータをメールで送信し、更新を依頼していた。ぎょうせい株式会社の場合は、システム上に登録すれば、自動的に出稿できる形になっている。更新の期間については、両社にそれほど違いはない。
紙台本については、第一法規株式会社は加除を行ってくれる。ぎょうせい株式会社の場合は、新しく全ページが送られてくるので、それを丸ごとこちらで差替える形となっている。ぎょうせい株式会社の場合、綴り方やサイズなども指定できる。
次に、例規の検索についてである。例規集については、一言でいえばぎょうせい株式会社はシンプルである。検索に関するオプション等も最低限が備えられている印象で、原課職員には触りやすいと思う。第一法規株式会社はさまざまな機能が附属しており、一見するとごちゃごちゃとした見た目であるが、法規担当者からすると、痒い所に手が届くような作りになっている。
ぎょうせい株式会社の場合、条文にリンクする法令が、当該条例等の施行日時点の法令に固定されており、その法令の未施行の改正等を見たい場合は、「法令Web」という別の入口から入る必要がある。
第一法規株式会社の場合は、D1-Lawの現行法規にリンクするので、そのまま未施行部分も表示させることができる。施行日時点の法令にリンクさせるほうが原課職員が間違いにくいという点ではぎょうせい株式会社のシステムもよいが、やはり法規担当としては第一法規株式会社のように法令の改正前後の情報をダイレクトに見ることができるほうが使い勝手がよいように思う。
第一法規株式会社は、条文ごとの沿革を比較したり、引用している法令等に簡単にリンクすることができる。全国例規集ともリンクしているので、全国の似たような例規との比較も容易である。
ぎょうせい株式会社の場合は、引用情報からたどっていく必要があり、一手間多くかかる。また、全国の例規と比較するためには、政策法務支援システムに入りなおす必要がある。
次に、例規の編集機能である。当方は、平成23年から新旧対照表方式で条例、規則等を改正しているので、改め文の生成については分からないが、新旧対照表方式を作成する場合は次のようになる。なお、当方では、議案を提出する場合は、まず原課に例規システムを使って新旧対照表を作ってもらう。また、本番の議案についても必ず例規システムから出力したものを使っている。少し珍しいらしい。
ぎょうせい株式会社の一番の利点は、出力する新旧対照表のレイアウトを(限界はあるが)自由にこちら側で編集できる点である。本文のみならず、ヘッダ、フッダ、表など細かく指定できる。なお、条文を出力する際の設定についても同じように細かく設定することができる。
ぎょうせい株式会社は、条文ごとに入力窓が出るので、そこで編集をする。第一法規株式会社に比べると編集に一手間かかる。また、編集後の点検は、例規の構造等を除いて、基本的には編集した条文のみの審査になるので、全体の審査をする場合は、溶け込み後の条文を更に点検する形になる。なお、ぎょうせい株式会社は、こちらで点検項目や点検用語を追加することができ、自治体独自のルール等を点検するように設定することも可能である。
第一法規株式会社は、ワードを編集するようなイメージで、直接入力によって条文を編集していくことができる。直截的な作業が可能である。また、ぎょうせい株式会社と異なり、全体の点検を行うため、編集していない条文もチェックしてくれる。ただし、表など分量が多いものは点検に要する時間が多大になるのが難点である。
法令検索については、前述したように、ぎょうせい株式会社は法令検索の入口が、条例の時点とリンクしている「法令/検索」と、時点を変えられる「法令Web」の2種類に分かれている。例規の場合と同じように、シンプルな作りとなっていて、原課職員にとっては見やすい。しかし、引用している法令の情報などは、関連情報のタブから当該条項を選んで、と法規担当からすると一手間かかる仕様になっている。
第一法規株式会社は、法令のみならず、判例検索や通知通達検索、コンシェルジュデスクなどともリンクされており、条文だけではなく、その条文の解釈や当該条文が争いになった事例などを横断的に調べることができ、法規担当としてはとても助かる。ただし、当然のことながら判例や通知通達、コンシェルジュデスクなどは別途契約していないとリンクされない。法令だけを契約しているだけでは不十分となってしまい。
なお、令和元年時点の情報で、株式会社ぎょうせいの法令の登載件数は35,549件、新旧対照表が60,000件以上搭載されており、現行日本法規から作成されている。D社は、収録件数36,236件、告示データ22,519件、制定時からの履歴約22,700件、様式50,000件以上で、告示などのデータが多数ある。
全国の例規の検索についてであるが、一昔前は、全国の例規を検索したい、比較したいと考えた場合は「eLen」を使っていた自治体が多いかと思う。現在は、第一法規株式会社もぎょうせい株式会社も同様のサービスをLGWAN上で提供しており、こちらを使っている自治体も多いのではないだろうか。本市でも、例規の制定・改正の際だけでなく、広く活用している。
第一法規株式会社の全国例規集はシンプルな作りで操作性もよく、直感的に操作できるので原課職員にも好評である。その代わり、基本的には条文の印刷しかできず、過去の条文の参照も限られたものしかできない。また、例規同士の比較については、類似例規検索・比較の契約が必要となる。
ぎょうせい株式会社には政策法務支援システムという例規の比較システムがある。第一法規株式会社に比べると動作速度が遅く、ログインが必要など手間がかかるが、収録されている過去の例規も多く、多くの例規の比較も容易である。
次に、第一法規株式会社の例規整備NAVIには、自治体法務担当者向けの雑誌として、「自治実務セミナー」のほかに「政策法務Facilitator」や、過去の雑誌等を閲覧することができる。また、多くの自治体で利用されていると思われる例規整備チェックシートは、更新頻度も早く、いち早く例規の改正情報が手に入るため大変重宝している。例規の改正例も示してくれるため、原課職員も利用している。おおもとの例規の契約を第一法規株式会社としていれば、法令FOCUSにより、法令の改正があった場合の例規への影響を知ることができる。
ぎょうせい株式会社については、第一法規株式会社の法令FOCUS同様に、法令等の改正があった場合の例規への影響を知らせてくれるサービスとして、法令改廃情報検索がある。
見やすさは法令FOCUSのほうが上であるが、ぎょうせい株式会社の場合は、事前に登録しておけば、指定した例規に影響があった場合、当該例規の所管課に直接メールでお知らせをしてくれるサービスがあり便利である。
また、ぎょうせい株式会社には法制執務相談室というサービスがある。新たに相談できるものではなく、過去の相談事例の蓄積がされている。相談したい場合は、株式会社ぎょうせいの担当者に直接相談する形になる。
8-2 頼りにされる相談者になるには
230ページにあるように、まずは「事実関係」の確認が重要である。当方は、相談の際は必ず相談シートと資料を事前に提出してもらってから行っているが、実際に会って話を聞くと、相談シートに出てきていない事実が出てくることが多々ある。
相談者が重要視していなかった、伝えるまでもないと思っていたというならまだ分かるが、不利になりそうなので言えなかったというケースもある。そのような場合は、みんなが不幸になるのでやめてほしいのだが、なかなか、なくならない。
最初のうちは、とにかく時系列にそって内容をまとめ、こちらの主張、相手方の主張、争点となっている事項を整理し、そのあとで法令や判例や文献をみていくようにする。とにかく事実をたくさん聞いて、あとで調べるようにするとよい。
この辺りは、最近連載が始まった、愛知県春日井市職員で弁護士の吉永公平著「自治体職員と事実認定の身近さ(自治体職員に身近な「事実認定」入門)」(判例地方自治509号166~169ページ)が参考になるので、ぜひ読んでもらいたい。
8-3 相談しやすい法規担当になるには
第一法規株式会社やぎょうせい株式会社からくる法令改廃についての情報は、積極的に、即時に担当部署へメール等で伝えるとよい。担当部署には所管省庁から通知等はいっていることも多いが、意識してもらうためにも、気にせず送ればよい。また、当方では、合わせて庁内の電子掲示板にも必ず法令改廃の情報をあげて、周知を図っている。
233ページの庁内法律相談のフローは秀逸なので、フローがない自治体は、パクることをお勧めする。
8-4 弁護士相談の勘どころ
通訳になるという視点は重要である。弁護士相談には、その時点で持っている、ありとあらゆる証拠を持って行って相談する。また、事前に事実をしっかりと整理しておく。
気を付けなければならないのは、弁護士も全ての法律を知っているわけではないということと、行政法や地方自治法についての知識はほとんどないことである。
行政法に至っては、旧司法試験では試験科目ですらなかったし、新司法試験(現在では司法試験)でも取り上げられる主要なものは行政救済法のうちの行政訴訟の部分だけであり、知識が偏っている。
そのため、民事的な解決については十分示してくれるのだが、地方自治法や議会関係、予算など、色々とフォローしないといけない事案も出てくるので、その辺りは注意しなければならない。
顧問弁護士であれば、通常、当該自治体と長年の契約によって知識も十分であったりするが、若い方だと怪しい。
8-6 訴訟の種類と裁判の流れ
訴訟自体が少ない自治体も多いので、いざ訴訟となったときに読めばよい。訴訟については、ロースクール卒の方や弁護士職員、顧問弁護士に一任するようなイメージで構わない。餅は餅屋である。
8-7 訴訟を意識した日常業務を
訴訟というのは病理であるので、日常業務をしていて出会うことはまずない。もっとも、予防法務の観点から、日々の業務について、訴訟を意識して臨むことも大切である。
職員個人に対する提訴について、訴訟の危険性が高い部署であれば、管理職員は公務員賠償責任保険に加入しておくとよい。また、自治体に対して訴訟告知をし、事実上顧問弁護士に助けてもらうという手もある。
住民から不服があると言われた場合、庁内に住民相談等があると思うが、それ以外に、法的には次のような手段がある。
1つ目は、不許可とか手当の減額などの「行政処分」についてする「審査請求」。2つ目は、「訴訟」である。
「審査請求」は、住民から申請があったけど不許可にするときや、命令など不利益な処分をしたときに、住民が市町村や都道府県に不服を申し立てて、それを自治体が審査する制度である。行政不服審査法という法律に基づいた制度である。基本的には処分を行った課(処分庁担当課)や、審査庁担当課が審査請求を受け付けて処理する。
審査請求とは少し違うが、行政手続法上「行政指導の中止等の求め」「処分等の求め」というものもある。これは、「各課で行っている行政指導をやめてください」とか、「〇〇会社が違法な行為をやっているので処分してください」といった求めをすることである。
「訴訟」には、先ほどの不許可処分を取り消してほしいと訴えるような「行政訴訟」とか、例えば公園などの遊具の管理が不十分で事故が起こったときや市民病院で医療事故があったときなどに提起される「国家賠償訴訟」、自治体のお金の管理が不適切であったときに住民から提起される「住民訴訟」などがある。それぞれ、行政事件訴訟法、国家賠償法、地方自治法に基づいた制度である。
自治体が適正な行為をしていても、それに不満があれば自由に訴えることができる。変な話であるが、何でもかんでも「訴えること」自体は自由である。実際に、例えば、「〇〇課長の態度が気に入らないから訴えてやる!」「私のゴミ捨て場が遠いから訴えてやる!」などでも訴訟はできるし、極端に言えば「私が大好きなアイドルが選挙で1位にならなかったから訴えてやる」というのも可能である(これは本当に窓口で言われたことがある。)。
国民には憲法に基づいて裁判をする権利があるので(憲法第32条)、「訴えてやる」といわれたら、それは権利であるのでしょうがない。ただ、訴えてもそれが「認められない」だけである。
気を付けてもらいたいのは、審査請求や訴訟を「自治体に止められた」などと言いがかりをつけられないようにしてほしい。審査請求も訴訟も基本的に自由なので、こちらで止めることができない。「負けるから止めなさい」といった助言はしないようにして、「裁判をしても認められない可能性もありますが訴えるのは自由ですよ」ぐらいにするとよい。
8-8 適正な行政手続
各部署から寄せられる相談が、行政処分に関するものであるときは、注意が必要である。争いになっているポイント以前に、行政手続法・行政手続条例を遵守していないケースも多く、手続違法で負けてしまう場合もある。
例えば、生活保護費の返還請求をして争いになっているとする。争点は、「収入があるのに申告をしていなかったこと」だったとしても、返還請求の際の命令書に理由の付記がなければ、それだけで負けてしまう。また、返還請求について審査基準や処分基準を作っておらず、漠然とした金額で返還を請求していれば、それも違法である。
行政手続法違反は、相談があって初めて発覚することが多い。8-7と同様に、予防法務の観点からは、庁内の研修などを通じて、周知徹底を図るとよい。リーガルドックという手もあるだろうが、私はやや懐疑的であるので割愛する。
不利益処分なのに弁明の機会を付与しなかった場合はどうか。不利益処分をする場合には、聴聞又は弁明の機会の付与が必要である。もっとも、中には例外により付与が必要ない場合もあるので注意されたい。
聴聞等が必要であるのに、これを行わなかった場合、処分は取り消されることになる。これは、当該処分の内容が違法でなかったとしても、手続上の違法だけで取り消されることになるので注意が必要である。
処分の理由が不十分だと言われた場合はどうか。、処分をする際は理由の付記が必要である。理由が適切に付記さていない場合は、聴聞等の場合と同様に、手続上の違法だけで取り消される。
弁明の機会を付与しなかったり、処分の理由が不十分である場合は、職権により処分を取消し、新たに手続を行った上で、再度処分をすることになる。
8-9 行政不服審査制度
訴訟と同様に、行政不服がほとんどない自治体も多いので、審査請求があったときに読むとよい。少しだけ補足すると、以下のようになる。
住民が救済を求める方法としては、
①損失補償の請求
②国家賠償法に基づく損害賠償請求
③民法上の不法行為に基づく損害賠償請求
④行政事件訴訟法に基づく取消訴訟
⑤行政不服審査法に基づく不服申立て
などがある。また、この他に各種救済制度として、
⑥苦情処理制度
ⅰ)請願制度(憲法16条、請願法)
ⅱ)行政相談委員制度(行政相談委員法)
ⅲ)行政苦情推進会議(総務省設置法)
⑦オンブズマン制度
も、救済制度として挙げられることがある。行政不服審査制度は、このような各種の救済制度の一つである。
ざっくりと、役所の行った処分(税の賦課、督促、許可の取消し、申請の拒否など)に不服がある場合は審査請求をすることができる。審査請求は、処分の通知が届いてから3か月以内にすることができる。
不服を申し立てたいといわれたらどうするかであるが、まずは、それは不服を申し立てることができる「処分」なのかを考えるとよい。
不服申し立ての対象となるのは、「行政庁の処分」であり(法1条2項)、いわゆる処分性のある行為が対象となる。
処分性がある行為とは、行政庁が法律により認められた優越的地位に基づいて、一方的に住民の法律上の地位に具体的変動を及ぼす行政庁の行為である。
具体的には、判例があれば判例に従う。処分性の範囲の概念の拡大が認められた例として、
①2項道路の一括指定
②労災就学援護費の支給決定
③食品衛生法に反する旨の通知
④病院開設中止の勧告
⑤土地区画整理事業の事業計画決定
⑥保育園の廃止を規定した条例
などがある。従来は処分性が認められないと考えられていたものでも、解釈が変更されたりしているので、疑義がある場合は判例や他都市の事例を調べるとよい。
判例等がない場合は、処分性の概念の3要素を考慮する。すなわち、
ⅰ 行政主体の意思を決定し、自己の名で外部へ表示する権限を有する行政機関の行為で、
ⅱ 対等な立場にない、優位な立場を有し、一方的に相手方に指示、命令等を下し、
ⅲ 当該行政庁の行為の根拠となる法律、条例等の法律効果として発生している行為
となる。
行政不服審査法は、自治体が行う全ての処分が対象である。処分というのは、行政庁が法律により認められた優越的な地位に基づいて、一方的に住民の法律上の地位に具体的変動を生じさせる行政庁の行為のことで、例えば、許可、不許可、認可、許可の取消し、免許の取消し、改善命令、停止命令、是正命令、過料、督促などが処分に当たる。
当該処分について、長や知事などの指揮・監督が認められていれば、長や知事などに審査請求することになる。例えば、保健所長が行う処分、福祉事務所長が行う処分は、通常は長に審査請求することになる。
審査請求は最上級行政庁に対してするとされている。
上級行政庁とは、
「上級行政機関とは、下級行政機関に対し、指揮・監督権をもつ行政機関である。他方、行政庁とは、行政体の意思または判断を決定し、国民または住民に対して、これを表示する権限をもつ行政機関である。したがって上級行政庁とは、当該事務に関し、処分行政庁である下級行政機関を指揮・監督する権限を有し、かつ対外的処分権限が帰属する上級行政機関である」(コンメンタール行政法Ⅰ行政手続法・行政不服審査法(第2版)日本評論社p361)
とされている。
行政不服審査法上の審査請求ではない制度としては、次のようなものがある。
制度が異なるものとして、
ア 固定資産課税台帳に登録された価格に関する「審査の申出」(地方税法第432条)
イ 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙の効力に関する「異議の申出」及び「審査の申立て」(公職選挙法第202条第1項、第2項)
ウ 農用地利用計画案に対する「異議の申出」、「審査の申立て」(農業振興地域の整備に関する法律第11条第3項、第5項)
エ 地方公務員法第8条第7項及び第51条の規定に基づいて定める人事委員会規則又は公平委員会規則(「不利益処分についての不服申立てに関する規則」)で規定する「再審の請求」
オ 非常勤の地方公務員等に係る保障の実施についての「審査の申立て」(地方公務員災害補償法第70条第1項)
カ 住民監査請求(地方自治法242条)
相手方が自治体ではないものとして、
ア 地方独立行政法人(市立大学等)…独立した法人格を有する行政主体
イ 地方公務員災害補償基金…地方共同法人
ウ 特許出願に対する拒絶査定等工業所有権に係るもの(特許法、実用新案法、意匠法及び商標法)…国への不服申立て
私人間の紛争の裁断として、
ア 公害紛争処理法第42条の19に基づく公害等調整委員会の責任裁定
イ 土地収用法第47条等に基づく裁決
その他、
ア 監査請求(地方自治法第75条)
がある。
なお、審査請求書の受付を拒むことはできないので、補正すべき点があるような場合は、受付けて補正をし、補正されない場合は当該審査請求を却下するという流れになる。
248ページに2つの教示があるが、教示は適切かという視点は重要である。
教示は、処分を口頭でする場合以外に義務付けられる。教示すべき事項は、不服申し立てができる旨、不服申立てすべき行政庁、不服申し立てできる期間である。教示は書面で行わなければならない。処分の相手方以外の利害関係人には教示をする必要はないが、求められたら教示をする必要がある。
なお、不動産登記法156条や供託法1条の5のように、個別法の中には、処分庁等を経由した審査請求を義務付けているものもあるので注意が必要である。
申請を全部認容する処分や相手方にいかなる不利益も与えない処分でない限りは、処分の際に教示が必要となる。ただし、申請を全部認容する処分であっても教示が必要となる場合がありますので注意してほしい。
例えば、生活保護の開始決定は、改正生活保護法65条に「保護の決定…についての審査請求」との規定があり、開始決定についても審査請求ができる規定となっている。
また、国税に関しては国税庁のホームページに以下のような例示がある。
(教示を必要としない処分)
57-2 国税に関する法律に基づく処分のうち、たとえば次に掲げるような不利益を与えるものでない処分については、審査法第57条第1項の教示を必要としないことに留意する。
(1) 納付すべき税額を減少させる更正または賦課決定で更正の請求をまたずに職権で行なう処分
(2) 青色申告の承認の申請に対してこれを承認する処分
(3) 相続税の延納申請に対してこれを申請どおり許可する処分
(4) 酒類の製造免許申請に対してこれを申請どおり免許する処分
(5) 差押えを解除する処分
制限的な内容を有する附款を附されたもの(一定の条件を付与して許可する場合など)には教示が必要である。
例えば、行政財産の目的外使用許可において、「①公用又は公共用に供するために必要を生じたとき等は許可を取り消すことができる、②取消しの結果、損失が生じても補償しないこと、③第三者に使用させないこと」といった条件を付して許可をする場合が多いと思われるが、その場合でも教示は必要である(昭和39年10月27日自治行第125号通知)とされている。
審査請求書に必ず記載しなければならない事項としては、
①審査請求人の氏名・住所
②審査請求人が市から受けた処分の内容
③処分を知った日
④審査請求で求める結論(○○の取消しを求めるなど)とその理由
⑤教示の有無
⑥審査請求の年月日
がある。
1962年に制定された行政不服審査法は、2014年に全部改正されている。改正前の古い教示文を使用してしまった場合については、解釈によるが、教示がなくても審査請求期間の進行は妨げられず、また、処分が無効になることもない。
なお、教示については、正当な審査請求期間までは効果が認められるとされているので、処分から3か月を経過するまでは、正しい教示文を再度送付するのがよい。この場合、処分をやり直す必要はなく、教示文だけを修正すればよい。
昭和37年10月29日行管理第99号行政管理庁行政管理局長から大蔵省大臣官房文書課長あて回答によれば、「教示は、その性質上原則として処分の際に行うべきものと解されるが…処分の際に教示を行うことを失念したために、処分を行った後に別途教示を行う場合においても、教示の効果は異なることはないと解する」とされている。
教示文を付け忘れてしまった場合であるが、法に規定があるのは、審査請求ができる処分について「教示をしなかった」パターンのみである(法83条)。教示をしなかった又は一部教示を欠いた場合は、不服申立書を処分を受けた者が提出することにより、救済されるという仕組みをとっている。
したがって、教示をするのを忘れたとしても直ちに違法となるわけではない。ただし、審査請求がなされた場合、適切ではないと評価される可能性はある。
なお、旧法の関係になるが、『行政不服審査実務提要』(ぎょうせい)には、教示制度の運用について、昭和37年8月27日の参議院内閣委員会において、教示制度は一応の訓示規定であり、教示をしなかったことに対する法律上の制裁はないが、服務上は問題があるとされている。
関連して、教示を懈怠した場合でも、以下のような通達や裁判例等がある。
・処分でないものは、たとえ教示があったからといって審査請求することはできない。
・教示を行わなかったとしても、それによって処分が無効になることはない。
・教示が欠けていても、審査請求期間の正当事由にはできない。
・教示がなくても、審査請求期間の進行は妨げられない。
実務家や学者の間では、教示文を付け忘れた場合、審査請求に係る正当な理由があるものとして、いつまででも審査請求ができてしまうという見解もあるので注意されたい。
○行政不服審査法 (審査請求期間)
第十八条 処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して三月(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して一月)を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
2 処分についての審査請求は、処分(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定)があった日の翌日から起算して一年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
3 次条に規定する審査請求書を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便で提出した場合における前二項に規定する期間(以下「審査請求期間」という。)の計算については、送付に要した日数は、算入しない。
処分ではないのに教示文をつけてしまった場合はどうか。この場合、教示があったとしても、処分ではないものについては、不服申し立てができることにはならないとされている(社会保険審査会平成6年2月28日裁決)。
○行政不服審査法 第82条 (不服申立てをすべき行政庁等の教示) 一部抜粋
行政庁は、審査請求若しくは再調査の請求又は他の法令に基づく不服申立て…をすることができる処分をする場合には、処分の相手方に対し、当該処分につき①不服申立てをすることができる旨並びに②不服申立てをすべき行政庁及び③不服申立てをすることができる期間を書面で教示しなければならない。
○行政事件訴訟法 第46条 (取消訴訟等の提起に関する事項の教示) 一部抜粋
1 行政庁は、取消訴訟を提起することができる処分又は裁決をする場合には、当該処分又は裁決の相手方に対し、次に掲げる事項を書面で教示しなければならない。
一 当該処分又は裁決に係る取消訴訟の①被告とすべき者
二 当該処分又は裁決に係る取消訴訟の②出訴期間
三 法律に当該処分についての③審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがあるときは、その旨
2 行政庁は、法律に処分についての④審査請求に対する裁決に対してのみ取消訴訟を提起することができる旨の定めがある場合において、当該処分をするときは、当該処分の相手方に対し、法律にその定めがある旨を書面で教示しなければならない。 ⇒審査請求前置の場合
処分をした部署ではなく別の部署に審査請求書を提出したいと言われた場合はどうか。当方でも、不服申し立ての相談で、このような主張を審査請求人がしてきたことがある。改正法においては、原則として審査請求書は「審査庁」に提出することになっているので、処分をした部署ではなく、審査庁を担当する部署が受領することになる(法19条参照)。もっとも、処分庁(処分をした課)を経由して審査請求することも認められているので(法21条)、処分をした部署が受付けて、審査庁担当課に送付することもできる。
審査請求人が外国人で印鑑を持っていないと言われた場合もあった。審査請求書については、押印を廃止しているので、押印は不要である。なお、正副2通提出するなどの決まりがありますのでよくチェックしておかなければならない。
補足であるが、各種申請書や届出書等で、まだ署名・捺印が残っているようなものについては、外国人の場合は署名で足りるので注意されたい。
○外国人ノ署名捺印及無資力証明ニ関スル法律
〔署名〕
第一条 法令ノ規定ニ依リ署名、捺印スヘキ場合ニ於テハ外国人ハ署名スルヲ以テ足ル
②捺印ノミヲ為スヘキ場合ニ於テハ外国人ハ署名ヲ以テ捺印ニ代フルコトヲ得
審査請求に不備があった場合、その場で直させて良いか聞かれることもあるが、不備があればその場で直させるなど、補正を命じない方法が適当である。その後の手続を迅速に進めるためにも、チェックすべきである。
審査請求をしたのに督促が未だに届くと苦情を言われたこともある。審査請求をしても、手続の続行は妨げられない。執行停止を申し立てない限り、督促等をすることは可能である。また、申請書の提出等を妨げるものでもない。
裁決までどのくらいかかるのか聞かれた場合はどうか。参考書等によれば、裁決までの標準的な期間は6か月とされているが、多くの自治体では少し多く時間がかかっているのではないか。
なお、裁決までの期間の定めがある法令もあるので注意してほしい。
(例)
○生活保護法(昭和25年法律第144号)
・審査請求に対する裁決が50日以内だったが、70日又は50日に伸長
○宗教法人法(昭和26年法律第126号)
・裁決について4月以内の規定を保持
下水道法(昭和33年法律第79号)は、異議申立てに対する決定が30日以内だったが、当該規定は削除された。
8-10 情報公開制度の対応
全ての部署に関係するのが情報公開と個人情報保護制度である。情報公開については、原則として全部公開であること、基本的には行政が取得した又は作った文書は全て情報公開の対象になることをまずは覚えておく。
自治体職員が作成した文書や取得した文書などは、住民等から見せてほしいといわれたときは全て見せなければならないし、必要があればコピーを渡さなければならない(有料が多い)。
このような制度を情報公開制度といい、情報公開に関しては、各自治体で「情報公開の手引」のような審査基準をもっている。
良くテレビとかで真っ黒に塗られた文書が公開されたといったニュースを見ることがあるが、あれは例外で、普通は全部公開する。黒塗り(非公開)にはしない。
対象となる文書の中に、個人情報や、まだ住民には公開できない検討中の情報とか、企業の業務上のノウハウといったものが入っている場合だけ、例外的に黒く塗って公開することになる。
情報公開と似た制度で、個人情報保護制度がある。個人情報保護制度は、住民等の個人情報を適切に取扱い、管理し、必要があればその利用を停止したり、修正したりする制度であるが、主に使われているのが自己情報の開示制度である。
自分の入院した時のカルテの情報や、自分が申請したり苦情を申し立てた記録など、自分についての情報を情報公開のように開示することを求めるものである。
情報公開は、「誰に対しても同じように」開示しなければならないので、例えば自分の情報であっても、それは個人情報なので黒塗りで出ていく。しかし、個人情報保護制度上の自己情報の開示を使えば、その人にだけオープンになって出ていく。
相手が、情報公開を求めているのか、自分の情報の公開を求めているのか良く聞いた上で、請求を受け付ける必要がある。請求書が違ってくるし、必要書類も変わってくる。
なお、最近よくあるのが、弁護士が代理人として個人情報の開示請求をしてくることがある。この場合、その弁護士本人の本人確認書類(住民票等)も必要になるので注意されたい。お前たちの法解釈が間違っているとか、ひまわりサーチで検索しろと言ってきた特権階級気取りの弁護士もいたが、個人情報保護委員会に問合せて、弁護士も(当たり前だが)例外なく本人確認書類を出してもらうことにした。弁護士だろうが何だろうが、ただの任意代理人である。
★おわりに
以上、長々と好き勝手に書いてきたが、新任法規担当には一番お勧めできる本である。できればこの記事も一緒に読んでもらえると嬉しいが、読んで意味があるかどうかは分からない。結構、色々書いて楽しかったので、随時追記していきたいと思う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
