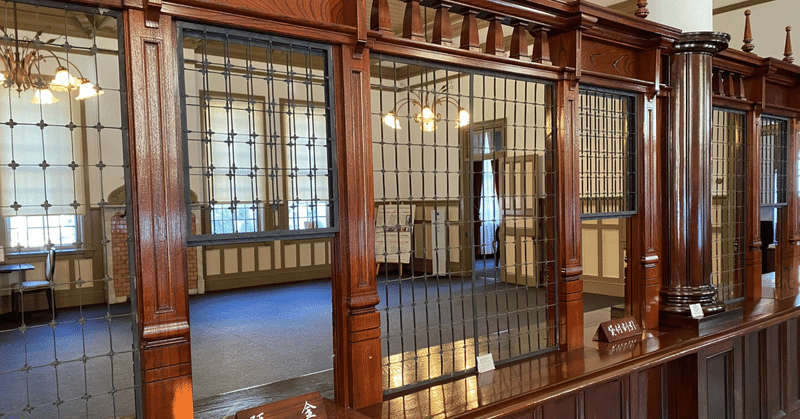
【納得】申請書・報告書にキラキラな表現を使うべき理由
佐藤ひろおです。早稲田の大学院生(三国志の研究)と、週4勤務の正社員(メーカー系の経理職)を兼ねています。
ちょっと漠然としちゃいますが、申請書・報告書は、現状のマイナスな側面を踏まえ、改善を訴えるものです。
国や地方自治体のみならず、会社などの勤め先なども同じです。うまく表現できないので、さっそく具体例をおみせします。
・申請書:ごみが散らかっているので、掃除をすべきだ(掃除をするための人員が欲しい、指示を出してほしい、予算を出してほしい)
・報告書:みんながミスを放置しているので、私がミスの修正に取り組んだ。同じミスが繰り返し起きないように、仕組みを考えました
ごみの散乱は困りますし、ミスの放置もいただけません。しかし、「ごみが散乱し清潔じゃない」「ミスが放置され、他部署やお客様に迷惑を掛けている」が事実であろうと、申請書や報告書にその通り書くべきではない。
ぼくは、ダメな現状を言語化すれば、だれかを批判することになり、関係者に恥をかかせて恨まれる。だから書くべきではない、と思っていました。でも、それだけじゃないことに、今日気づきました。←遅い
申請書や報告書は、別の組織・担当者に回付されることがあります。すると、ごみとかミスといった具体的な内容を顧みられることなく、自分も属する集団のすべてが全否定されるリスクがあります。
たとえば自分がA地区に属せば、A地区の内部では「ごみが散乱してきたない。掃除しよう」と表現できますが、他の地区からみれば「そもそもA地区すべてがダメだ」と受け取られます。過度に一般化された評価が瞬時に定まるので、A地区は人員も予算も得られません。「もうA地区に関わるな。打つ手無しだ、あそこは」と決めつけられます。
たとえば自分がA部署に属し、自部書がミスを連発している。「ミスを是正しよう」は内輪の論理です。組織全体から見れば、「そもそもA部署のすべてがダメだ、切り捨てろ」と言われます。
ありのまま書けば、A地区の古老、A部署の中間管理職のメンツがつぶれて波風が立つ。しかしそれよりも、地域や組織全体のなかで、自分にまつわる地区・関係者のすべてが切り捨てられるリスクのほうが遥かに恐ろしい。
「待ってください!ちっとも実態を見てないですよね。いちど説明の機会を設けさせてください」と反論する機会も与えられない。
この世界は、書類のみで生殺与奪が決せられることが多い。
……というわけで、たとえ自分の属する地区にごみが散らかり、廃墟のように雑然としたり、自分の属する部署がミスを連発して機能停止していても、申請書・報告書には、
「A地区は、より清潔にする余地がある」
「A部署は、業務の精度をいっそう高めることができる」
みたいな、キラキラ言葉で表現しなければいけない。
ただの言い換えだ。ものすごく空虚な気持ちになります。でもぼくは、まさに今日、このキラキラ言葉の必要性に納得ができたんです。
キラキラ言葉に納得できた理由
ぼくは会社員として、この真理に到達できませんでした。
会社では、ごみやミスを放置するような周囲へのいらだちを、制御しきれなかったのだと思います。自分がなしとげた改善の幅に、目を奪われたのだと思います。「無意味・無気力が蔓延する環境のなかで、ぼくだって本当はやりたくもないのに、ごみ・ミスが減るように、周囲の反対を押し切って改善したのだから、その改善の幅を見てくださいよ。正当に評価してもらえないと、成仏できませんぜ」っていう気持ちが大きかった。
でも今日、会社の業務から離れ、
早稲田大学が提供している「自分の研究分野に予算を引っ張ってくる」講座を受けたときに、目からウロコが落ちました。
研究予算を得られるかは、申請書類1通で決まることが多い。地域や会社よりも、よりシビアな書類文化(文書行政)の世界です。
すべての研究は、現状(先行研究)の不十分さを批判するところから始まります。これは実際にそうです。
しかし研究予算の申請書に、「わが分野の先行研究は、まだ解明していないことが多い」と書けば、「そもそも分野全体に、もうやりようがないんじゃないの?もう辞めとけば?」と決めつけられる。
「〇〇への研究が十分になされていない」と書けば、「もうそのまま研究しなくていいので、寝ててどうぞ」と思われてしまう。「〇〇の視角が足りない」と書けば、「わざわざ視座を設定して見るほどの価値もないんだろ」と思われてしまう。
先行研究が不十分だと思うならば(不十分と思うがゆえに、自分が研究を始められるわけだが)、その実情をいったん飲み込み、それを研究する理由と、研究する意義(のみ)を書くべし。先人の視角が不十分だと思うならば、その視角を設定する必要性と効果(だけ)を書くべし。
上の比喩なら、現状が不快(ごみが散らかり、ミスが多い)だから、改善する申請書・報告書を書き始めようと思うわけだが、いったん山積みのごみ・ミスのことを忘れて(口をつぐんで)、清潔のすばらしさ、正確さの意義のみを歌い上げればよい。
「ごみが落ちていないA地区が実現したら、小鳥がさえずり、子供たちが集まって憩いと交流が生まれ……」と。「A部署のミスがなくなれば、これだけの利益と全体への貢献があり……」と。
ひたすらポジティブな側面だけを書く。申請書類=賛歌です。いちばん綺麗な言葉で、正しい音程と発音で、自部署・自地域・自分野の将来性を歌い上げたひとが、予算・人員などを獲得する。
以上、小手先のテクニックのような気がするし、逆に人間社会を生き抜く渡世の神髄のような気もしますが、申請書・報告書をキラキラ言葉で埋めるべき理由について、ものすごく納得できた!!という記事でした。
自分が好きなこと、意味があること(研究)についてならば、真剣に取り組めるので、お説教がすんなり耳に入ってくるのかも知れません。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
