
「国選弁護報酬について本気出して考えてみた - 刑裁サイ太のゴ3ネタブログ」という深澤諭史弁護士のXリポストの記録


国選弁護報酬について本気出して考えてみた - 刑裁サイ太のゴ3ネタブログ https://t.co/mBlFd23q3p
— サイ太 (@uwaaaa) November 21, 2023
ピーチクパーチク言ってた人たちが弁護士登録を抹消してクソリプおじさんになったり,Twitterが炎上して引退している間に,私は5年前には真面目な提言もしました。

サイ太先生が炎上覚悟でまたブログ書いてくれるはず! https://t.co/t4yVDV6KP8
— 浜木綿弁右衛門 (@leplusallez) February 25, 2018
総論
国選弁護報酬はどのように定められるべきでしょうか。
単純な発想として,「労力と得られた成果に応じた報酬」とすべきであることは当然でしょう(民事などでは目的物の価額によって報酬が決められますが,これが労力と必ずしも比例しないようにも思われるところですが・・・。)。
そうすると,基本的には汗を流した方が報酬が高く,得られた成果が大きければ報酬が高くなる制度が望ましいことになります。
他方で,現在の国選弁護報酬の基準は,「機械的に算定できる」ことに重きを置き,「労力と得られた成果に応じた報酬」という要素はほんのスパイス程度に考えられているに思われます。これは,法テラスの意向はもちろんのこと,真の敵である財務省からの圧力によるものではないかと推察されるところです(国選ブログ事件の際も,「敵は財務省」という話が出ていましたね。)。
この基準については,弁護活動の質を法テラス,ひいては法務省が評価することが妥当かどうかという議論からも正当化されうるものです。
しかしながら,「機械的に算定できる」ことに囚われるがあまり,他の要素が蔑ろにされているのが現状です。
国選弁護報酬について本気出して考えてみた - 刑裁サイ太のゴ3ネタブログ https://keisaisaita.hatenablog.jp/entry/2018/02/26/185256






























提言-「被疑者・被告人の権利を守る方向にインセンティブを働かせる」
現在,多くの弁護士が国選弁護を担当しており(日弁連の資料によれば,約7割の弁護士が国選弁護人契約をしています。),その多くの弁護士との間で国選弁護契約を締結している法テラスとしては,その多くの弁護士を適切に誘導していくことが,システムを構築する側の当然の責務だと思います。
憲法37条に規定されている弁護人選任権を保障する制度に,「機械的に算定できる」ことを重視するような程度の覚悟で首を突っ込むべきではありません。憲法に明文で保障されていてもこの程度の扱いなのかという意味では,憲法改正で教育無償化を謳う美辞麗句の欺瞞を如実に表しているかも知れません。
国選弁護を担当する弁護士は多く,かつては詐欺を働く愚か者がいました。それ自体,弁護士の側も反省すべき点はあるかも知れません。そこで,そのような愚か者を排除し,心ある弁護士が国選弁護を経済的な心配をすることなく受任させる方向に導くことが望まれます。
これらの問題を解消するため,私は「被疑者・被告人の権利を守る方向にインセンティブを働かせる」という方向性を提案します。国選弁護人を導くという意味では,このような方向に努力をさせることは弁護人の責務にかないますし,なにより,このような権利が実現されるのであれば,国民からの理解は得られやすいでしょう(圧倒的な政治力を背景に「必要な負担は国民に求めざるを得ない。」などと放言できる某団体とは違うのです。)。
国選弁護報酬について本気出して考えてみた - 刑裁サイ太のゴ3ネタブログ https://keisaisaita.hatenablog.jp/entry/2018/02/26/185256
同じ報酬ならいつやっても同じです。被疑者段階は最大でも20日ですが,被告人段階なら1回結審の事案でも期日まで1ヶ月以上あります。のんびりやる方が楽に決まっています。
しかも,被疑者段階で示談を成立させてしまえば,起訴猶予処分になる可能性が高まり,被告人国選事件になれば得られていたであろう報酬を失います。
このように,現状の規定では,①示談報酬が起訴前後で同じなので,時間的余裕のある起訴後にやる方が楽であること,②示談をしないことによって被告人国選の報酬をみすみす失うことから,起訴前の示談に対するディスインセンティブが2重に働いていることになります。
これを解決するのは簡単で,起訴前の示談報酬を上げればいいだけのことです。上記のディスインセンティブが両方とも解決します。「国民の視点」的に言っても,早期に示談を成立させる方向にインセンティブが働くことになりますから,理解も得られると思います。
国選弁護報酬について本気出して考えてみた - 刑裁サイ太のゴ3ネタブログ https://keisaisaita.hatenablog.jp/entry/2018/02/26/185256
判決で認定落ちになるということは,裁判においても認定落ちが争点となり,検察官との間で争われることになります。当然,結果が出ずに訴因どおりの罪が認定されてしまう可能性もあるでしょう。他方で,訴因変更を事前にさせてさえいれば,争点とはならなくなり,被告人の地位は安定します。
以上からすれば,このような訴因変更の場合にも特別報酬を出してしかるべきです。その算定に当たっても,起訴状と,訴因変更申立書や判決とを見比べれば容易に判定できるでしょうから,機械的な算定にも馴染むものです。
国選弁護報酬について本気出して考えてみた - 刑裁サイ太のゴ3ネタブログ https://keisaisaita.hatenablog.jp/entry/2018/02/26/185256
・起訴日と同一日の接見は報酬の対象とするべき
現在の規定では,起訴後の接見では接見報酬は出ません。しかし,起訴されたかどうかの連絡はないのが普通です。そのため,知らずに接見に行き,起訴されていたというケースもよくあります。この場合,少し前であれば各地方事務所で報酬を算定していたことから,空気を読んでくれることも多かったと聞いています。しかしながら,本部で集中的に算定するようになり,機械的に取り扱われるようになったため,接見報酬が出ないようになったと聞いています。
しかし,被告人の立場から考えるとどうでしょうか。起訴されたとすれば,その後の手続がどう進んでいくのか心配になります。また,保釈も可能になりますからそのことの説明を聞きたがっているかも知れません。そのような中,接見報酬が出ないのでは,接見に行くのを怠る方向にインセンティブが働いてしまっています。
もちろん,起訴後にも接見報酬を付けるべきではありますが,少なくとも,起訴日と同一日の接見は起訴の前後を問わずに報酬の加算対象とすべきであると考えます。
国選弁護報酬について本気出して考えてみた - 刑裁サイ太のゴ3ネタブログ https://keisaisaita.hatenablog.jp/entry/2018/02/26/185256
・被疑者の飼っているペットの餌やりにも報酬の手当をすべき
我が国では,ペットを飼養することは社会の様々な階層に普及しており,当然,被疑者もペットを飼っていたりします。身内がいればいいものの,独り身のさみしさを紛らわせるためにペットを飼っていたりすると,ペットの生命にも危険が及びます。
そこで,国選弁護人がその世話をするために駆り出されるわけですが,これに対する報酬の手当は現状ありません。職務基本規程上,別途の費用を取るわけにもいかず,ペットの世話を頼まれた若手弁護士が悩むポイントでもあります。
人里を犯す熊を射殺すると熊を殺すなとかいう投書が寄せられる世の中ですから,こういう費用を支出しても国民の理解は得られるんじゃないですかね。
賢明な読者には伝わっていて欲しいですが,この項はサイ太流のジョークです。ただ,ここに記載した問題意識は真面目です。リアルで「国選弁護人の職務の範囲ではありませんので諦めてください」と伝えて信頼関係を保持できるスキルが欲しいです。
国選弁護報酬について本気出して考えてみた - 刑裁サイ太のゴ3ネタブログ https://keisaisaita.hatenablog.jp/entry/2018/02/26/185256
懸念
ただ,このような方向性を取ることには,懸念がひとつあります。それは,「被疑者・被告人の権利を守って現状の報酬,少しでもサボると現状よりも減額になる」という報酬基準を策定してくる可能性です。
たとえば,これまでの財務省のやり方からすると,「被疑者段階で示談すれば現状どおり,被告人段階で示談してもそれは時間的な余裕もあって楽勝ということだから現状よりも減額します^^」「起訴後に接見を一定回数以上行っていないと報酬を減額します^^」などと言い出しかねません。
法テラス・財務省との折衝を担当する日弁連関係者には,弁護士のため,ひいては被疑者被告人のために,全力で戦ってきて欲しいと思います。
go3neta 5年前
国選弁護報酬について本気出して考えてみた - 刑裁サイ太のゴ3ネタブログ https://keisaisaita.hatenablog.jp/entry/2018/02/26/185256










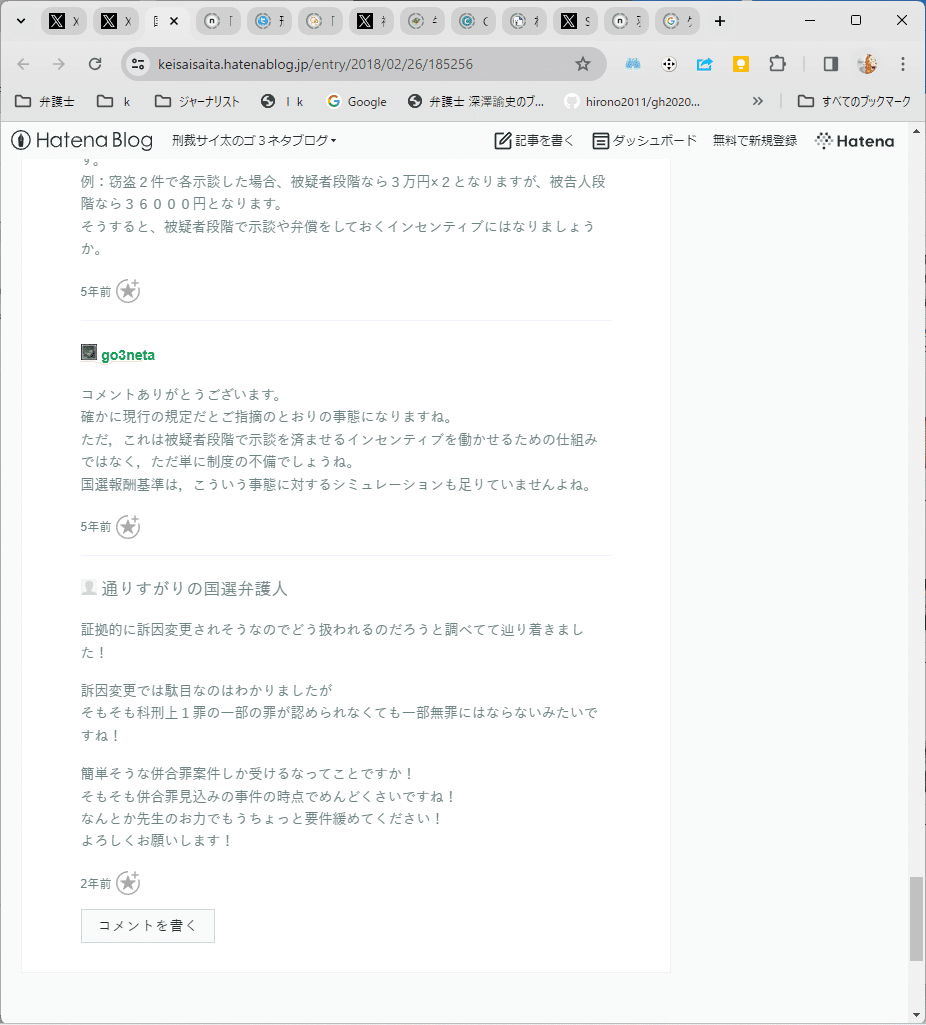
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
