【読書】「無理」の構造 この世の理不尽さを可視化する
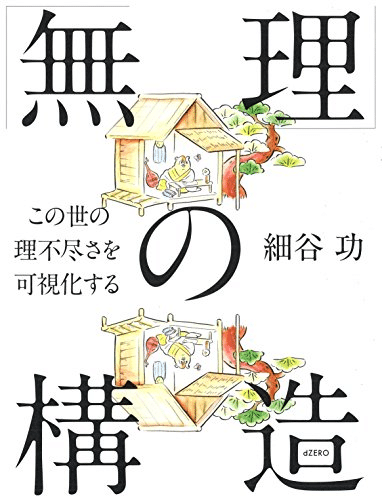
なぜ、お互いに分かり合えないのか?
見えている人と、見えていない人は、どちらも思う。
この理不尽さを説明してくれる本であり、ほぼ各章ごとに気づきがあった。
人間心理の非対称性を、頭の隅につねに置いておくと、色々な現象がすんなりと腑に落ちる。
会社や組織、また仕事において、この構造が当てはまるケースが多く、中小企業と大企業、スタートアップと成熟企業、のように違う性質の組織では構成する人の思考も異なるので、どうしても見えているものが違ってくる。
私自身、10年くらい、いくつかの会社の社員として働いていたが、その間に見えていたルールや考え方は、独立して個人事業主になってからは、180度違う向きから見るように変わったものが多くある。
すべてを自分で企画し判断する個人事業主では、自分で考えて情報収集して決断するのは当たり前だけれど、社員だった頃には微塵もそんなこと想像していなかった。会社で決まっているルールを調べて、その通りに業務や諸手続きをこなすのが当たり前と思っていた。どちらが良いではなくて、組織の成り立ちが全く違うのだから、この違いは今後も存在するものだろう。
そして、今回読んで、もっとも共感したのが17章「公平さという幻想」。
世の中は基本的に不公平であると言う前提を置けば、ほとんどの理不尽さが解消する。
人生は不公平にできているからこそ、与えられた公平ではない環境の下で努力することに意味がある。努力の成否は他人と比べて結果が良かったかどうかではなく、比較対象は、努力しなかった自分。
外からの評価ばかり求めて努力しても、報われないと感じる時が必ずやってくる。比べるべきは、過去の自分だと何度も繰り返し、自分に言っている。
能動的に努力を続けていくためには、その対象に対して楽しさや爽快感や何らかの魅力を感じていたい。そういう、楽しそう!とか、愛着を感じる瞬間を見過ごさず、大事に捉えて続けていこう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
