
正調粕取焼酎 資料 2
1.粕取焼酎 出土品総覧
2002.09.30 公開開始/ 2004.04.18 goida氏にコレクション寄贈
2005.11.19 up date
■注:「○○蔵」は所蔵者を指す。
【吟】は吟蔵粕もろみ取り焼酎。他は籾殻+普通酒粕使用の正調粕取焼酎、または普通酒粕もろみ取り。










2.兵に告ぐ
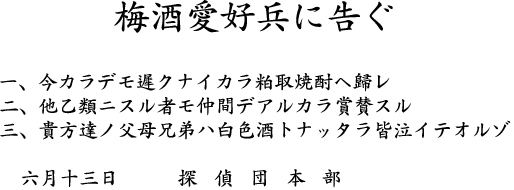
3.粕取、未だ死なず! 『ヤマフル』続報!
(2003.07.26 構成 by 猛牛)
今年、試験的に蒸留を再開、6月に「横浜焼酎委員会」が主催した大イベント『本格焼酎大選集』でも関東の焼酎ファンに好評を博した、正調粕取焼酎『ヤマフル』。佐賀県唐津市は鳴滝酒造株式会社さんの作品だが、その『ヤマフル』について、同社の古舘正典専務から続報を頂戴したので、ここでご紹介しよう。
ある第三者機関において、試験的とはいえ再蒸留為った『ヤマフル』が大きな支持を得たというのである。
この連絡を拝見したとき、わては本当にうれしかったですばい! 「古舘さんが取り組まれた地道な努力が報われましたね」と、わては心底思った。これをまたひとつの契機にしていただき、ぜひとも正式な『ヤマフル』復活の日が訪れたら・・・と願っておりまする。
「正調粕取、未だ死なず!」、なのだっ!
猛牛さん
ご無沙汰致しております(私はしょっちゅうHPを覗かせて頂いていますので、実感ではそうでもないのですが)。
先月の横浜では大変お世話になりました。ものすごく刺激ある、また楽しい体験をさせて頂きました。ありがとうございました。
さて、実は今回、嬉しいご報告をと思いメール致しております。 猛牛さんは、つい数年前まで、専門的な技量をお持ちの第三者機関の担当者が各蔵元を回り、新酒のできの評価や貯蔵・出荷のアドバイスを行う恒例行事があった事をご存知かと思います。
ここ数年はその形態が変わり、各蔵が新酒を機関へと持参して、担当者室で様々な批評を頂くようになりましたが、昨日弊社の者がそれに行って参りました(残念ながら私は所用により行けませんでしたが・・・)。
その報告が、つい今しがたあったのですが、その者が言うには、本年蒸留しました「ヤマフル」が極めて高い評価を頂いたとの事なのです!!(申し訳ありません。嬉しくて、興奮して書いております)。特にきめの細かい香りと、何と言っても独特の甘みを高く評価され、このまま何もせず、今すぐにでも市販できるという言葉まで頂きました(私は、もう少し寝かしたいと思っていますが)。
本来なら清酒が主役のこの行事ですが、時間のほとんどが「ヤマフル原酒」に費やされてしまった程だったそうです。
試験的に醸造を行った正調粕取、私自身品質にはある程度の手ごたえを感じてはいましたが、専門的技量をお持ちの第三者の高評価には、正直ほっとしたと同時に、心底喜びを感じております。
試行錯誤を繰り返しながら、手探りで、でも手を抜かずやってきた事が、報われたような気がしております。
これからの貯蔵や製品化に関するアドバイスも沢山頂きましたので、これからも手を掛け、最良の状態で市場に出せるよう努めたいと思っております。
興奮して、なんか支離滅々な文章にて申し訳ございません。とりあえずご報告まで。皆様に今お伝えしたいのは、「心からの感謝」です。ありがとうございました!!
鳴滝酒造株式会社 古舘 正典
4.『辛蒸』に関する塚田定清先生からのご回答
(2002年9月、私の『辛蒸』についての質問メールに対する、田苑酒造株式会社・相談役 塚田定清先生から頂戴したご回答。
辛蒸についてお答えいたします。相談役の塚田定清と申します。
1)鹿児島のお酒について歴史的な背景を先ず述べさせていただきます。
ご承知の通り、温暖の地、鹿児島では美味い酒が造れませんでした。仕方なく、酒もろみを蒸留して焼酎にしました。戦前まで米焼酎を造るところ、芋焼酎のみのところ、又両方造るところがあり、米焼酎は芋焼酎の2倍の価格で売られておりました。
戦中からの経済統制で米が自由に利用できなくなり、戦後、すべての焼酎屋が芋焼酎を造らざるを得なかったのです。
現在鹿児島ではお酒と言えば焼酎、焼酎と言えば芋焼酎ですが戦前は米焼酎も30%位飲まれていたのです。又清酒も(地酒=現在は雑酒ですが熊本の赤酒も同じ)造られており、この酒を美味しくする、又酒が腐らないように柱焼酎として辛蒸を添加していました。
米焼酎はこの清酒もろみ(仕込水がやや多いのですが清酒造りと全く同じ方法でもろみを造りました)を蒸留したものです。焼酎は蒸留酒ではありますが基本となるのは醸造酒造り(清酒)にあり、このことは現在も全く同じで、良いもろみ(発酵=醸造酒)を造る技術を焼酎メーカーは(最後に蒸留の工程がありますが)競っていると言っても過言ではありません。
ところで、焼酎造り500年の中で明治の終わり頃から、もろみを安全に造る技術や方法が科学的に解明されはじめました。その中で捨てられたものもかなりあります。
辛蒸も醸造アルコールに代用されて、無くなった一つの例です。この捨てられた技術・焼酎を現在の技術で再現したら、全く新しい発見があるのです。
たまたま辛蒸については弊社の前身である焼酎蔵から古文書が発見されたことで再現することができ、平成5年、日経新聞の文化欄に取り上げられたことで話題になりました。
再現してみるとこんな美味しいものだったのかとの思いです。今は芋焼酎王国ですが捨て去られた鹿児島の米焼酎を復活させる一歩にしたいと思っています。
2)3)について
清酒粕を利用する焼酎は粕取り焼酎として全国的に造られていました。しかしご案内のような造り方なので個性的な焼酎でした。
これに対して鹿児島で造る清酒粕利用の焼酎は(辛蒸)もろみ取りだったのです。焼酎を造る(蒸留する技術=蒸留釜を持っていた)技術を持っていたから、清酒粕をもろみにしたのです。
蒸篭では籾殻を利用しなければなりませんので強烈な焼酎になります。辛蒸は古文書の仕込方法を再現すると同時に解明された現在の技術も取り入れましたので皆様に評価されたものと思っています。
4)確かに現在の清酒の状況から、入手が困難になっております。香露さんや美少年さんに無理なお願いをしています。しかし協力いただけると思っています。
5)約15KLです。
6) 特別な関係はありませんが、お願いしている卸屋さんが積極的に販売下さっています。
尚、ご不明な点はお電話下さればお答えいたします。ありがとうございました。
(了)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
