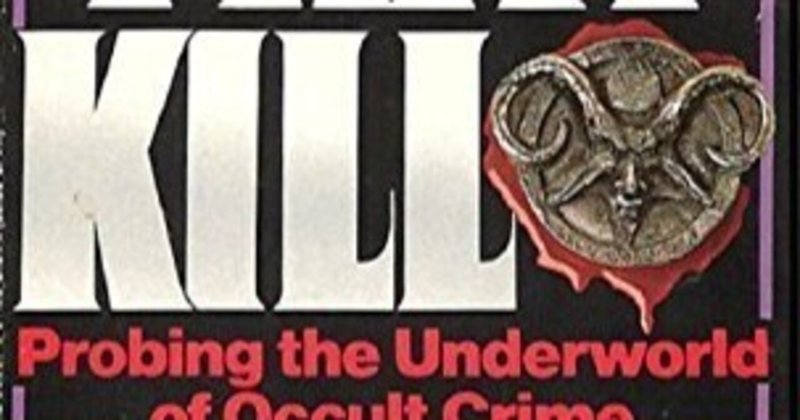
5/25(土) あなたの聴かない世界特別編に向けてのメモ②米英サタニック・パニック
カルト宗教組織による犯罪の目撃者や捜査にあたった人物らの証言を下敷きに書かれたラリー・カハナー『Cults That Kill』(1988)や、モーリー・テリー『The Ultimate Evil』(1989)は、全米にカルトの恐ろしさを植え付けた。その結果、反動的にメディア上で異教の拒絶≒キリスト教が補強されていく。それはアントン・ラヴェイが記したように、アイデンティティの担保としての悪魔が必要であるかといわんばかりであった。この社会現象は今日サタニック・パニックとして包括されており、サムの息子事件(犯行自体は70年代後半であり、そのバックにカルト組織がいるという事実が重要だった)が話題になった80年代後半から90年代初頭は、もっとも苛烈な反応が生まれた時期とされている。
悪魔を想起させるイメージはたとえ子供向けアニメであろうと排斥の対象であった。たとえば『スマーフ』のキャラクターが六芒星を描くシーンには批判が寄せられた。また、当時再興したニューエイジ運動の一要素たる東洋思想も同様で、ヨガ教室さえも攻撃された。実際に起きた弊害はNetflixドキュメンタリー『サムの息子たち: 狂気、その先の闇へ』に詳しい。
なお、「政界やメディアは児童の性的な人身売買を行う悪魔崇拝者に支配されていて、ドナルド・トランプは彼らと戦っている」というQアノンの主張が記憶に新しいように、サタニック・パニックは今日でも続けられている。
80年代後半に爆発した米サタニック・パニックだが、その種火は早くからまかれていた。1980年にカナダで出版された『Michelle Remembers』は、ある精神科患者が主治医に診療の一環として悪魔崇拝の儀式に参加させられたという報告が基になっている。ベストセラーとなった本書は、世間に悪魔崇拝及びその組織への恐怖を拡散した。この小説内で「儀式」が行なわれたのは50年代半ばかから後半とされている。Church of Satan設立とほぼ同時期であったため、この本の影響でラヴェイやCoSへの風当たりは必然的に強くなった。
映画『エクソシスト』(1973)などが示すように、フィクションに対するこの種の反応は珍しくない。しかし、米メディアの騒乱が呼び水になったのか、90年代に入ったころの英国メディアも同様に反応したことで、サタニック・パニックはより広範かつ深刻なものとなった。そのターゲットの一人には、Psychic TVとその首謀者ジェネシス・P・オリッジも含まれていた。
82年から始まったPTVとその参加者のネットワーク、Thee Temple Ov Psychic Youthは疑似カルト的フォーマットをとった60年代再考の一段階であった。80年代はさほど問題なく活動していたPTVだが、新聞誌『People』は88年7月発行の号でPTV初期のアーティスト写真を大々的に掲載し、「この下劣な男が子供たちを堕落させる」との見出しをつけた。そして決定打となるのが英民放局Channel 4が1992年に放映したドキュメンタリー『Dispatches』で、地下で活動していたPTVはいよいよ衆目へと引きずり出された。
番組の内容は悪魔崇拝の儀式の被害者とされる人物たちの証言や、物的な証拠がないまま「疑わしい」のレベルであらゆる要素を結び付けていくものだった。PTVが製作した映像作品『 First Transmission』は、悪魔崇拝者らによるイニシエーションとして紹介され、番組は参加者の女性が虐待を受けたという主張を紹介している。
『Dispatches』放映同時期に発行された英新聞紙『Observer』でもPTVが悪魔崇拝の儀式を行ない、参加者を性的に加害したという前提の記事が掲載された。マスコミは映像に出演していたデレク・ジャーマンのもとに(当時AIDSによって健康状態は深刻であった)押し寄せた。警察はベック・ロードにあったジェネシスらのアジトに家宅捜査を入れたが、ジェネシスら家族はタイへと出かけていたことで最悪の展開は免れた。
タイから帰国すれば家族が破綻する可能性を考慮した結果、ジェネシスは米国へと移住する。
まだポリティカル・コレクトネスという語がメディア上で踊らなかった頃の時代ではあるが、すでに厳しい審判、より過激な言い方をすれば検閲が諸文化内で見慣れた光景となってきた。ラヴェイやボイドたちにはこの光景が60年代後半の悪しき再来に映り、それゆえにあの時代のアウトサイドを回顧した。すなわち俗世に背を向けることの価値が見直されたのである。ヒッピー全盛の時代に「お金稼ぎもアートだ」と豪語したアンディ・ウォーホルが1987年に亡くなったことは、ボイドたちにとって一つの時代の終わりを指したかもしれないが、これもかの時代の再考のきっかけになったのではないか。
ウォーホルやリキテンシュタインらポップアートの延長線上に出てきたハイパーリアリズムは、米国の大量消費主義をターゲットにした運動であり、モダンすなわち進行中の現代を建設的に批判する精神があった。これに反発する形で逆転のハイパーリアリズムをアートの世界に放流したのが、次回更新分のショーン・パートリッジとThe Partridge Family Templeである。(続)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
