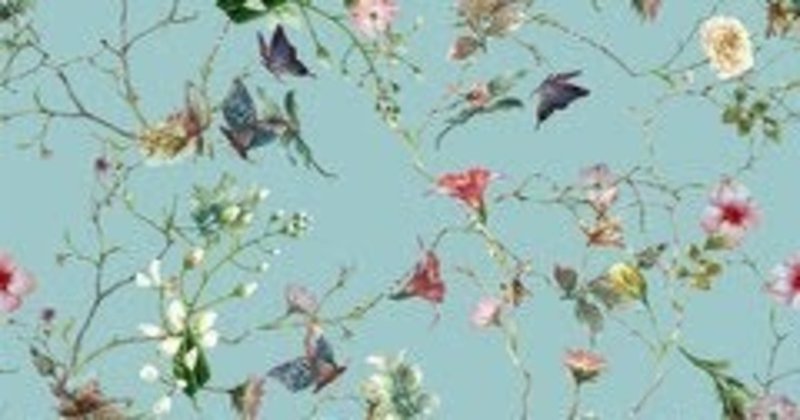
六枚道場感想 第七回
六枚道場も七回目。またしても投票はできなかったのですが、それはそれとして、感想を書きたいと思います。今回もバラエティに富んでいて面白かったです。繰り返しになりますが、私はこう読んだという以上のものではありませんので、お含みおきいただければ幸いです。
グループAはこちら
「ヨコバイの物語」
面白かったです! ヨコバイは知らなかったので検索しました。伯母さんが話してくれた、ヨコバイが斜めにしか進めない理由、本当にそうかも、と思わされます。伯母さんと主人公の関係性が読んでいてとても心地よく、同じシリーズの連作を読みたいと思いました。生き物への目線も優しくてホッとします。どんな生き物もそれぞれ理由があって、同じ世界に存在しているのだと感じました。
「新世代ほしペの本棚」
まぼは蝉で、きえあ(当初きへあだったものがきえあに変化)は猫で、話者は蝉から進化した生き物で、地球の蝉に擬態して猫と一緒に暮らしている。最初は猫の残虐さに憤慨したけれど、なかなかどうして猫も捨てたもんじゃないよ、みたいになっているのが良いですね。人間は獲物がとれなくて可哀想だからとってきているという人もいますが、その点に関する言及がなかったのは少し残念。もっとも、きえあに支配される人間を知的生命体と認識できなくても仕方ないのかもしれませんが。
「“Grillen” op. 12-4」
コラージュのような作品だと思いました。おそらく今の日本と、ボスニア紛争の頃の東欧が交差して、安全地帯から第三者として見ている自分が映し出されます。安全地帯側でも、志村けんさんが健在だったときと、感染が広がってからの日本が交差、同じ空間に一瞬だけ違う時間が流れているのがわかります。自分は観客である場合と、自分も時代を生きる一人である場合の、現場に居合わせることの意味について考えました。場所がアルコールを提供する飲食店なのは、苦境に喘ぐ業界へのオマージュなのかもしれません。
グループBはこちら
「雨は半分やんでいる」
序盤から不穏な空気が流れていて、緊張しながら読みました。とくに何も起こらない話なのかもしれませんが(車に乗ったまま海に落ちたりしないという意味で)、主人公のなかでは明らかな変化があります。緊張は解け、少しホッとして読み終えました。蛙のぬいぐるみはもしかしてピクルスかな、と思いましたがどうなんでしょう。もしそうなら何色かな~、などと思いました。
「拝啓、「普通」の私」
時空を超えた手紙、世界線をまたぐ手紙ということなんでしょうか。普通から逸脱し、普通であろうとする努力すらしたくない手紙の主にとっては、息苦しいことこの上ない世の中なのでしょう。もしや凶悪犯として処刑される直前、最後に手紙を書かせてやるとでも言われたのか。手紙を受け取った別の自分の反応はというと…。胸が苦しくなります。普通という言葉に苦しむ人に向けられた、優しく寄り添うような視線がせめてもの救い。
「タマコさんの話。」
とても良かったです。タマコさんのことを変わってると言うオギくんと、彼の分もお昼ごはんを作る主人公との関係は、もしかしたら少しずつ変わっていくのかもしれません。だって第2のタマコさんですよね? ある日オギくんから、変わったよな、と言われ「はあ~、どこが?」と叫んでしまうのではとさえ思えます。ということは、オギくんはやがて別の女性と付き合いはじめ、その女性もヨーグルを差し入れる主人公にシンパシーを感じ、そしてタマコさんはまた引き継がれていくのかな、と、その後の展開に期待してしまうのでした(笑)
グループCはこちら
「亜音速ガール」
思春期の焦燥感、それに疾走感。何ものかになりたい、ならなくては、という焦りだけが増幅していくあの感じ、とてもよく表れていると思います。このあと職員会議で議題にのぼったりしないのかな~、親が呼ばれたりしないのかな~、などと、激しく余計なお世話であろうことを考えました。がんばれ!!
「散弾」
現状を仕方ないと受け入れ、そうしなくては生き延びられなかったと自分を納得させながら、実際は激しく厭気がさしていて、現状をなんとかしたいと思っている。その気持ちが爆発するのが終盤子どもを救い出すところで、自分も爆発するけれども彼はずっとこうしたかったのだろうと思い、やっと救われたのだと、モヤモヤが晴れたように感じました。
「di-vision」
冒頭からとても素晴らしく、すいすい読めてするすると入ってきます。とくに良かったのが、停留所でバスを待っていたお婆さんが、財布を忘れたことに気づいてまた降りてから、風景がまったく変わらないところ。忘れたなら取りに戻るのが普通だろうと思いますが、そうならないところがむしろ作品の強さとなっています。途中まで一緒に帰宅する山田がいないことも、上述のお婆さんと同じ、見慣れた風景のなかの違和感。母親が高校の赤本を買ってきたことから、そろそろ受験なのだとわかります。di-visionは分割払いのことにも思えますが、見慣れた風景、これまでの日常と別れることも指しているのかもしれません。
グループDはこちら
「すでに失われてしまった物語」
二人称の物語で、半身という言葉が何を指すのか途中まではっきりしませんが、読み進める支障とはなりません。意味が判明したときにはなるほどと思い、交差する優しさに温かい気持ちになりました。積み重ねてきた年月、交わしてきた言葉、すべてがいとおしいということが、二人称によって上手く浮かび上がっています。下の名前を呼ばれた気がするところなど、認知症の妻の内面をわたし視点で書くよりも、終始二人称で夫から見た妻の様子を書くほうが効果的だったように思えて、唯一それが残念でした。
「金のなる木」
いったいどんなオチが待っているのか、途中からいくら頼んでも金が降ってこなくなるというのもよくあるよなあ、と思いながら読みました。結論をいうと全然違っていて、そっちか、というか、なるほどポンペイにアトランティスね、と思ったのでした。余談ですが、最初にお金を手にしたサラリーマンは仕事を辞めて大丈夫だったのでしょうか。あ、でも沈んじゃったから関係ないですね!(笑)
「夢の中の男女」
面白かったです。村上春樹の短編で、作家だというと、奇妙な話がお好きなんでしょうとばかりにいろいろ話してくれる、という始まり方をするのがあって、それを思い出しました。一つだけ気になったのが、二人のうち一人を知っているのなら、夢を見たとき誰かわからないのは不自然では?ということ。また、怪談の怖さは怪現象の恐ろしさもありますが、より根源的には人間の恐ろしさだと思います。そうであるなら、夢は引き続き見るけれど、馴れ初めから交際中の様子、そして最期に至るまでが夢の中で再現されるというのもありかも。もうすぐめった刺しになるの、それが楽しみだから何も言わない、と言われるほうが怖くないですか?(笑)
グループEはこちら
「浄化」
ああ、と思いました。話の流れから、たぶん例のおじさんが入院してくるんだろうなと思ったのですが…。この先、主人公はどう生きていくんでしょうか。逃げおおせたとして、歯止めが効かなくなっちゃうのかな…と心配です。アラームを止めた時点で思いとどまっていてくれたらいいのですけど。おじさんがもし口を利ける状態だったら、そしてあのときのことを覚えていたら、何かが変わったのだろうかと考えます。答えは出ません。
「試験問題(わたし)」
面白かったです。個人的には、夫が犬について話しはじめた個所の設問もほしかったと思います。私自身は妻の絶望に共感できず、妻の幸せについての設問は選択肢が少なすぎて選べませんでした。というか、妻の幸せなんて本文に書いてあったっけ?と。私はこの試験、落第点を取ることでしょう(笑)
「前の恋人」
主体性がない。この言葉が呪いになっているようです。呪いから逃げるためではなく、呪いを成就させにいってるのでは、と思うほどです。前の恋人の幻影を重ねて今の恋人とつき合うのは、誠実ではないかもしれません。でもそうしてしまう気持ちもわかる気がします。同じことを言われるかもしれないが言われるまでは一緒にいたい、そう思うのは本当に好きだからなのでは? 前の恋人と違うところもある今の恋人が、すべて受け入れてくれる人だったらいいなと思います。
グループFはこちら
「回転硝と得難い閃光」
すごく面白かったです! 止められない気持ち、何度ダメと言われても繰り返しやってしまう、どうしてもやらずにいられない、身体の奥底からふつふつとわき上がってくる衝動。みんなは横回転をして、社会の一員として生きる道を選ぶけれど、自分は縦回転せずにいられない。自分を止めようとして命を落とす人がいても、自分を含めみんなが不幸になるとしても、この動きは止められない。こういう人がきっと世の中を変えるのでしょう。世の中を変えたい強い気持ちを感じました。
「ピアノソナタ第8番「悲愴」第二楽章」
満月と、虫の声と、グレン•キンチー。自然の音に耳を傾けたくなるお話です。穏やかな休日。がん治療中、つかの間の休息を得た男性が考えるのは、自分が逝ったあとの妻のこと。さぞ無念でしょう。目が覚めて隣にあなたがいてほしい。妻のささやかな願いは、もう叶わないのでしょうか。満月を眺める男性の、奇跡的な回復を願わずにはいられません。
「卵焼きと思い出と音楽と猫」
卵焼きの味と猫に、別れた彼女の不在を思い知らされ打ちひしがれる主人公。環境の変化に対応できずにいる自分を、自虐的に眺めたものとして読みました。なんというか、悲しみにどっぷり浸るのも良いものですよね。再スタートの機運を高めてほしいです。余談ですが卵焼き、実家では甘い味つけでした。だし巻き卵は食べたことがなかったのですが、初めて食べたとき美味しくて驚きました。両方知ると、だし巻きの方がいいなあと思ってしまいます(甘い味つけ派の皆さんすみません)。
グループGはこちら
「赤頭巾」
なるほどそう来たか、というのが最初の感想でした。狼は、比喩的な意味での狼。祖母のパートはあるのだけど、何も書き込まれていません。やはり孫の顔もわからなくなっているからなんでしょうか。とても難しい挑戦で、挑んだ作者さんには尊敬しかありません。童話赤頭巾の現代版として途中まで読ませ、整合性を確保したまま、実はこういう翻案でした、と種明かしをするのです。大胆なお話で、おおっ、とトキメキすら覚えました。(確認なんですが、狼はお父さんで、援交の相手は娘だったんですよね?)
「断空」
どんな世界線においても彼女と出会おうとする主人公のお話。ヒントはあちこちにあるけれど、いつもそのヒントに気づけず、いつの間にか彼女を失ってしまいます。でも最後に見つけたヒントで、次は失わずにすむかも…。もしかしたら、それぞれの世界は断絶されているようでつながっているのかもしれません。まるでRPGのように。この先に行く世界では、どうか彼女と結ばれますように。
「抜けた足」
謎の生物が登場するお話。生物の描写からはルンバのような形態の、生き物とメカの中間のようなものを想像し、なんか面白いねこれ、と思いながら読みました。足をもいだところは「うへえ」と思ったし、だんだんグロテスクな展開になっていって、これってあれだよね、SNSで中傷が拡散されバッシングが広がって、最後にはやり過ぎだった、ってなる例のやつ、と思って居心地悪くなりました。すごくよかったです! もし私がここにいて、足を取ったらどうなるかなと友達が言い出したら、やめなよ、と言うでしょう。それでもやめなかったら、その場から逃げるかな。たとえ友達でいられなくなっても。
「わたしのいくところ」
ガンに冒され山にやってきた男の物語。何かあると山へ来ていたようで、憩いの場所だというのが見てとれます。帰らないつもりで来た男性。自然とともにあり、自然とともに朽ち果てたい。人間社会の都合ではなくあくまでも自然のタイミングで眠りにつきたい。人間は自然の一部だからーー。彼の願いが叶うよう、私も祈っています。
グループHはこちら
「焔」
ゆらりと立ちのぼる暑い空気が目の前に立ちはだかった気がするほど、夏の暑さを詠んだ句が輝きを放っています。私がとくに好きなのは、「心臓を夜へ還してゆく花火」と「長き夜のラップの箱の刃に触るる」の二句です。ラップの刃、今は紙刃もありますが、金属の刃を使っているものもまだあります。詠まれたのがどちらかはわかりませんが、刹那的な衝動が表現されているように感じました。
「黒鳥 白鳥」
とても良かったです。最初は同じようなものを持っていて、成長するにつれ持っているものが違ってくる。持ち札で勝負するしかない状況で、片方だけが持ち札を減らし、とくに疑問を持つこともないのだとしたら。そして持ち札を減らさないもう片方が、きちんと自覚しているのだとしたら。果たしてそれは不公平といえるのでしょうか。傍から見れば不公平で不公正かもしれません。でも二人のあいだのことで、二人にしか関わりのないことなら、外野がとやかく言う必要もなく、二人のあいだで話がついていたらよいのではないか。そんな風に感じました。
「お化粧しなくてもいいよ、ミス•パープル」
表面的には愉しげにも見えますが、とても切なくて、胸がぎゅっと締め付けられます。子供にとって、学校と家族は世界のすべてです。母が家を出て、赤ちゃん産んでくると言ったけど、もう帰ってこないかもしれないと知っている。学校も安らげる場所ではない。そんなとき子供が願うのは、どこかへ行きたいということ。ここではないどこか、誰も知っている人のいない、誰も自分を知らない世界へ。『ザリガニの鳴くところ』を思い出しました。あの話で主人公は生まれた場所にとどまりますが、このお話で、主人公はどうするでしょうか…。
今回も楽しませていただき、ありがとうございました! 第八回の公開前になんとか間に合ってよかったです。次はもう少し早めに読みたいですが、どうなることやら。毎日大変なことばかりですが、どうか皆様ご自愛くださいませ。
👻おしまい👻
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
