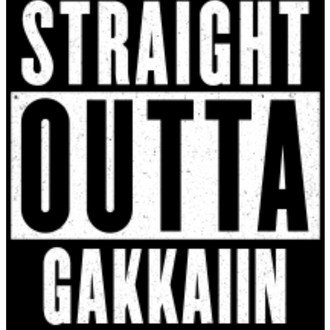2-15 本質から遠いところにこだわって、やり方を変えられない
博士 なるほど。上を変えようとするのは、「上の言うことを聞かなければならない」と思い込んでいるからであって、学会員が主体的に広宣流布を考えて進めるようになれば、話す相手は幹部ではなく、同じ視点に立つ同志になるんですね。これは学会を前向きに変容させていく上で重要なパラダイムシフトですね。
チェ 新しい考え方ではないんです。先生は、ずっとずっと、これを我々に語り続けてくださっていました。00年7月の第48回本部幹部会では「釈尊も、インドの大地を歩きに歩いて〈一対一の対話〉を続けていった。大聖人の〈立正安国論〉も、〈対話形式〉でしたためられている。〈対話〉こそ、仏法の永遠なる精神である。上からの命令では〈対話〉とはいえない。心を通わせ、ともに歩き、ともに行動する。そこに対話が生まれる」と言われています。そもそも上の言うことを疑問も持たず文句も言わずにやれなどとは言われていないのです。
博士 これらの指導は、学会員の皆さんが聞いているんですよね。
チェ 聞いています。しかし現場の風土は自由に意見を交わすより、決定事項を迅速に、大量にこなすことだけが重要視されていました。それに対して、「おかしいな、おかしいな」と思いながらも「先生に勝利の報告をしよう」と言われれば「そうだよな、頑張ろう」と奮起して活動していたんです。ところがその風潮というか、しきたりというか、伝統を引き継がない・理解しない世代が登場してきました。
また先生ではなく、本部執行部が学会の指揮を執るようになってから、強引な指導に何となく納得させられてきた学会員が、そんな自分たちの窮屈さを皮肉まじりに冷笑する場面が散見されるようになっています。
博士 学会が成長期を終えた三つ目の要因は〈タテマエの陳腐化〉でしたね。
チェ タテマエとは、幹部に批判的なことを思っていても話さない、深くツッコまない忖度(そんたく)のことです。
学会は伝統的に上意下達(トップダウン)の組織体質です。これは戸田先生が牧口先生の、池田先生が戸田先生の構想を愚直に実現してこられた歴史に根ざしています。また、日本の社会じたいが封建的で上意下達の風土だったため、誰もこれに疑問を持たず、むしろ一つの美徳と思ってすらいました。
博士 それはこれからの時代には・・・・・・というか、現代にも合いませんね。
チェ おっしゃるとおりです。学会員が「そういうものだ」と思い込んで忖度を繰り返しているうちに、世の中はすっかり変わってしまい、外部から見た学会の風土は、前時代的で全体主義的な特殊な風土になってしまったのです。
内部でも、二十代以下のメンバーには共感されにくいところが大きく、上意下達風土で育ってきた幹部は、このギャップに苦しんでいます。スムーズに行かないなら、方針転換すればいいのに「伝統だから」「訓練だから」「俺たちもやってきたから」と、本質から遠いところにこだわって、やり方を変えられないのです。
なにぶん、いい加減なことは書けないテーマゆえ、記事を書くための取材、調査、また構想から執筆、編集までかなりお金と時間と労力をかけております。 サポート、記事、マガジンの購入は本当に助かります。いただいたお志で、更に精度の高い文体を提供できます。本当にありがとうございます。