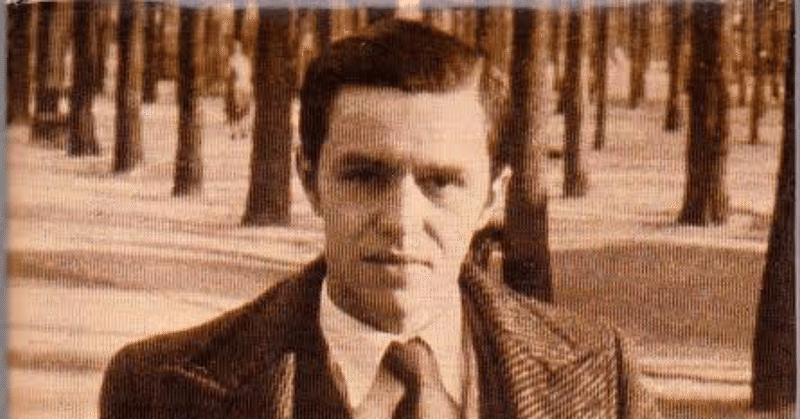
[書評]リュシアン・ルバテ『日曜日に銃殺はない』
「私にとっては死刑宣告こそ人間を弁別する。それは金で買えない唯一のものだ」
これは『赤と黒』に登場するマルチド・ド・ラ・モールの言葉であり、そして死刑を待つ恐怖から解放されたルバテが、死刑囚専用の独房五十六号室から出るときに壁に落書きしたものである。
戦勝国たるフランスは、自分たちが「勝者」の側にいるために、そして過去の忘れ去りたい「悪人」を抹殺するために無理矢理な裁判と、歴史修正に奔走する。フランスが果たして真に戦勝国なのか、よくよく考えれば、ヴィシー政権が正当なもので、ド・ゴールが単なる脱走兵に過ぎないという歴史的事実を踏まえるまでもなく、なかなか怪しいものだと感じるはずである。
平和だのヒューマニズムだのといった言葉を連呼し、小躍りする知識人が跋扈し、欺瞞に満ちた戦後フランス。ド・ゴールの手腕により戦勝国に名を連ねることができたフランスの戦後と、完全敗北した日本を重ね合わせるのは奇矯を通り越して、勘違いも甚だしいかもしれない。だが我が国もフランスのそれと根本を同じくし、フランス以上の欺瞞が終戦直後から満ちていたと私は考える。フランスで欺瞞に抗った、抗おうとした作家を私が追っているのは、我が国の戦後民主主義体制の欺瞞を暴くのに、多少は役に立つのではないかという希望的観測に起因する(本当は単に面白そうだから、という理由の方が大きいが)。
リュシアン・ルバテは戦後こそ、戦前の攻撃的なトーンを抑え、ファシストや反ユダヤ主義者であったことを反省している姿勢を見せるようになった。だがルバテは戦前から戦中にわたって、堕落したフランスに対して過激な筆を進めた作家だった。彼がファシストになった理由の一つは、時代の危機に対して真剣に取り組み、誠実であったからだろう。ルバテのそうした態度はナチ・ドイツ占領下で発表された『残骸』にて、人々をあっと言わせるかたちで現れる。
1946年、ルバテに死刑宣告が下る。欺瞞のもとで行われる裁判に公平さなどあるはずもなく、彼は欺瞞によって死刑が下されたも同然。獄中のルバテは、戦後の欺瞞が、自身の生死に関わっているのを自覚し、誰よりもその欺瞞に対して誠実に向き合うことができたのではないだろうか。時代や時の体制に批判の声をあげたり唾を吐くことは誰にだって出来ること。しかしそれが後世に残るものか、人々に影響を与えることができるかは当人の誠実さにかかっている。ルバテは自らの生死がかかっていたのだから、欺瞞に抗うのは否応でも誠実なものになった。
『日曜日に銃殺はない』はルバテが戦後、雑誌に発表したもので、日本語訳は国書刊行会から出ている池部雅英(訳)『残骸』に収録されている。1945年に連合軍に自首したルバテはその後、フレーヌ監獄に移送される。『日曜日に銃殺はない』は、ルバテと他二人の戦前の雑誌「ジュ・スイ・パルトゥ」の関係者が起訴された粛正裁判が開廷する前後から始まり、最後は恩赦となりフレーヌ監獄を感動的に発つ場面で幕を閉じる。いわば本書は回想録なのである。
1946年11月18日に開廷された裁判でルバテは主に戦前の言論活動について糾弾された。ほとんどが共産主義者に占められた裁判では、当然のごとくルバテらに不利に進んだ。もちろん戦前の対独協力と反ユダヤ主義的言論活動は事実である。しかしなかには、ド・ゴールに対する批判や事実無根に近いようなことさえ裁きの対象となった。弁護士の奮闘虚しく、11月23日、ルバテに死刑宣告が下された。
『日曜日に銃殺はない』の冒頭では、死刑宣告を受けるまでの獄中生活を振り返り「刑務所のお蔭で願ってもない自由を得たわけだ。一日に十四時間の文学三昧という理想的な日課にどっぷり浸かる自由だ」と明るく余裕そうに書かれている。死刑宣告の直後、「この宣告はただの見せかけの宣告に過ぎない」などと支援者や家族、弁護士らにルバテは励まされる。だが、看守の「死刑囚を護送!」という叫び声、それまで付けられていなかった死刑囚専用であろう鋼のロープでできた手錠、それらがフレーヌ刑務所へ戻る護送車のなかのルバテを不安にさせた。
「手錠は痛く、車内は真っ暗だった。車は三十分ほどがたごと揺れていた。宣告はすでに≪見せかけ≫どころではなかった。私は自分が死ぬかどうか深く考えたことはなかったけれど、きわめて不愉快な日々を生きなければならないだろうとは考えていたし、それが早くも始まったのだ。」
死刑囚となったルバテには、死刑囚専用の独房と手錠が待ち構えていた。刑務所での日々は一転して、いつ来るのか、本当に来るのかさえわからない死刑への恐怖と共に過ごすことになる。だがそうした日々のなかでもルバテは執筆活動を精力的に行い、筆が止まったときには「ラジオQ」と称して他の囚人達に向かって自前のジョークを披露して暇と不安を潰した。
ルバテにとって死刑は恐怖以外の何者でもなかった。本書では自分は絶対に恩赦となり死刑にはならない、と自信たっぷりの箇所もあれば、反対に死刑が近づいていると実感し妻を想い涙を流す場面、もう最期なのだと悟り、気が狂ったように手紙や遺書を書く場面もある。こうした死刑に対しての感情の不安定さこそ、彼がいかに死刑の恐怖と闘い日々を過ごしていたかがわかるのではないだろうか。
看守や他の囚人のほとんどがルバテに同情的だった。死刑宣告が下され、不安を胸にフレーヌ監獄に戻ったルバテを待っていたのは、温かいスープを用意していた看守たちだった。看守たちは口々に「死刑には絶対にならない」と励まし、裁判の不公平さを批判した。同じ刑務所にいた左翼系の囚人はルバテに向かって「人が著作のせいで死刑になるということはあってはならない」と話した。
恩赦が正式に決まり、死刑囚専用の独房から別の独房へ移る場面は何とも感動的である。移動する道すがら、大勢の看守と囚人たちに握手とサインを求められ、また熱狂的な祝福の声を受ける。この時のルバテの心中には何があったのか。恩赦となりこれからも生きていけることの喜びは当然、しかしそれとは別に彼の胸のなかには、自分の後ろで祝福の言葉を投げてくる「仲間」たちがいた。彼らもまた歴史的不正の犠牲者なのである。最後の行にルバテは記す。
「私はこの物語を彼ら(刑務所に残されている人々)に捧げる、彼らはこれを読むことを許されないだろうし、多分、私たちが共に耐え、味わったすべてのことからすれば如何ほどの価値もないだろうが。」
戦争が終わり、全体主義に対するヒューマニズの勝利に浮かれる文学者、知識人、そして大衆。しかしそうした「勝利」には欺瞞が隠され、その下ではルバテらを追い込んだような不正が蔓延り、時に全体主義と何ら変わりのない非人道的なことがまかり通る。ルバテに対する死刑宣告は「勝利」の欺瞞から放たれたものであり、死刑の恐怖に抗うことは「勝利」に抗うことと同じである。歴史の暗部に目を向けなくてはならない。リュシアン・ルバテ『日曜日に銃殺はない』は我々にそれをはっきりと訴える書ではないだろうか。
・参考文献
・(著)リュシアン・ルバテ、(訳)池部雅英、『残骸』、国書刊行会。
・(著)福田和也、『奇妙な廃墟』、国書刊行会。
本文でも書いた通り、日本語に翻訳された『日曜日に銃殺はない』は国書刊行会から出版された池部雅英先生翻訳の『残骸』に収録されている。『残骸』の続編をルバテは戦後に構想していたらしく、『日曜日に銃殺はない』はそのなかの一つのエピソードであることが推測できる。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
