
前方後円墳の考察⑬「神仙思想の反映」
卑弥呼の鬼道は神仙思想に基づく様々な方術(神仙方術)であり、卑弥呼はその方術を駆使して人々に福を招き入れる方士であったと考えます。弥生時代から古墳出現期にかけて倭国に神仙思想が広まっていたこと、その神仙思想にもとづく儀礼が行われていたことなどを想定しうる痕跡を見てみたいと思います。
①葬送儀礼における土器供献祭祀
弥生時代の方形周溝墓に見られる葬送儀礼における供献土器は壺が圧倒的に多いということを「祖霊と穀霊」で書きました。また、小南一郎氏の「壺型の宇宙」を通じて壺と神仙思想の強いつながりを見てきました。弥生の葬送儀礼で用いられた土器はまさに神仙思想の象徴である壺でした。そして、壺の供献はとくに弥生中期以降に顕著にみられるようになります。このことは弥生時代の中期以降、神仙思想が各地に広がっていたことの現れと言えます。
②鳥装したシャーマンの絵画土器
奈良県の唐古・鍵遺跡や隣接する清水風遺跡、坪井・大福遺跡、鳥取県の稲吉角田遺跡、長野県の長野遺跡群東町遺跡などから鳥装したシャーマンと思われる人物を描いた土器片が出土しています。いずれも弥生時代中期以降のものです。「なぜ壺なのか」でも書いた通り、祖霊が鳥の形を取るとする伝承は世界の各地に見られるもので、神仙が鳥に姿を変えたという伝説があり、神仙思想を奉じる方士は不老長寿や羽化を成し遂げようとしたとされます。中国の後漢時代以降の地下に石で造った墓の壁面にさまざまな絵を彫った画像石には身体に毛が生え、背中に翼をもった神仙が描かれます。鳥装したシャーマンは鳥になった神仙そのもの、あるいは神仙になった首長を表していると考えられ、ここでも弥生時代中期には神仙思想が各地に定着していたことが窺えます。さらに言えば、神仙になった首長に対する畏敬の念が土器に絵を描かせたのではないでしょうか。
③葬送儀礼に用いられた朱
丹後の大風呂南墳墓群や赤坂今井墳丘墓、出雲の西谷墳墓群、吉備の楯築遺跡など弥生時代後期の首長墓から、棺に朱が敷かれるなど葬送儀礼に朱が用いられた跡が見つかっています。朱は辰砂や丹などとも呼ばれますが、いわゆる硫化水銀のことです。墓に水銀朱が使われる風習は中国から伝わったとされますが、これも神仙思想によるもので、辰砂は不老不死の神仙になるための霊薬(仙丹)をつくる原料とされました。葬送儀礼に朱が使われたのは、魔除けや死者の再生を願ったとされていますが、死者の魂が神仙となって無事に神仙世界に辿り着いてもらいたいという意味があったのではないでしょうか。
④特殊器台・特殊壺
弥生時代後期に吉備で生まれた特殊器台、特殊壺は首長クラスの墳丘墓で葬送儀礼に使われました。いずれも弧帯文などの文様が描かれ、朱が塗られるなど、装飾性に富んだ土器です。特殊壺は底部が穿孔されているので、弥生時代中期以降に見られる土器供献と同様の意味合いがあると考えられます。円筒埴輪の原形となった特殊器台に注目が行きがちですが、葬送儀礼においては壺の役割の方が重要で、器台はあくまで壺をのせるためのものでした。弥生時代後期になって首長の葬送儀礼に朱を塗ったり文様で装飾するなど特別な壺を用いるようになったことは、壺の重要性が高まってきたことの現れではないでしょうか。
⑤神獣鏡(画文帯神獣鏡、三角縁神獣鏡)
大阪府にある古墳時代前期の前方後円墳である黄金塚古墳からは景初3年(239年)銘のある画文帯神獣鏡が出土しています。中国の後漢時代に作られた画文帯神獣鏡は神仙や霊獣の像を主文様とし、外側に飛仙などの群像を描いた画文帯をめぐらした鏡です。日本では畿内を中心に約60面が出土しています。画文帯神獣鏡と同様に出現期あるいは前期古墳から出土する鏡が三角縁神獣鏡で、その数は500面を上回ります。こちらも神仙や聖獣が刻まれ、特に伝説の神仙とされる崑崙山の西王母や蓬莱山の東王父が描かれたものがあります。景初3年(239年)、正始元年(240年)など魏の年号銘のあるもの、不老長寿・富貴栄達・子孫繁栄を願う銘文が記されたものも見つかっています。
弥生時代中期以降、徐福とともにやって来た方士たちは各地で暮らしながら、祈祷、卜占、呪術、占星術、煉丹術、医術などの神仙方術を人々に伝えたことでしょう。祈祷や呪術で禍を取り払い、福を招き入れ、医術によって病気を治し、辰砂から朱を取り出して不老不死の仙薬を作る。人々はそんな神仙方術を驚きをもって受け入れたと思います。とくに各地の首長たちは神仙の不老不死、不老長寿に大きな関心を持ったことでしょう。そして方士の説く神仙思想を受け入れた結果、神仙とみなされる鳥の姿を装い、神仙世界に通じる壺を用いた葬送儀礼を行い、棺には不老不死の仙薬の原料となる朱を敷きつめ、さらには特別な壺を生み出し、大陸からは神仙を刻んだ鏡を取り入れました。
倭国の社会、とくに首長層に神仙思想が定着する状況にあって、神仙方術の使い手であった卑弥呼は女性だったことから、神仙世界の女王的存在であった崑崙山の西王母に重ねられたことでしょう。その結果、大乱を収める女王に推挙されたのではないでしょうか。
(つづく)
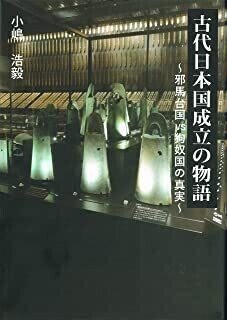
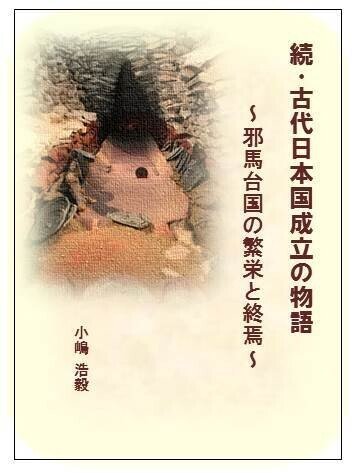
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
