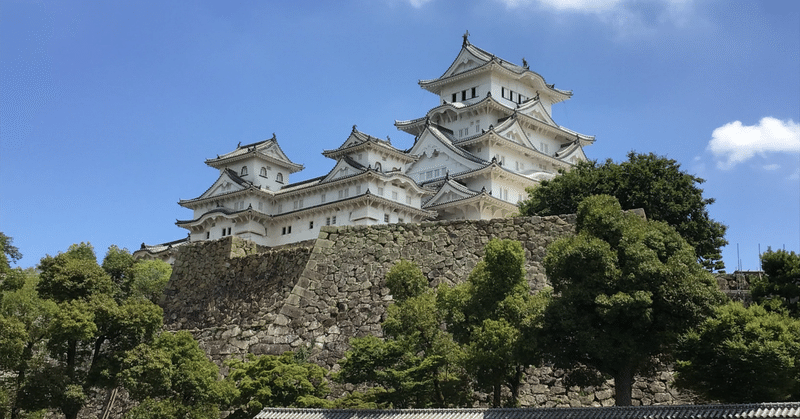
【風が吹けば】田んぼが不足すると戦国大名が出現する【桶屋が儲かる】
今回は日本史のお話を。
歴史は大きな流れであり、そこに至るまでの過程にはすべてに理由があります。
その流れを知っていると知らないとでは歴史の楽しみに大きな差が出ます。
大きな流れの一例として日本史の「口分田の不足」から「戦国大名の出現」までの過程を見てみましょう。
※主に小中学生向けの説明となっております。細かい部分に省略やデフォルメが含まれています。ご了承願います。
口分田が不足すると墾田永年私財法が施行される
時は奈良時代。
天皇を中心とした国づくりを行う律令国家の中で、租税(稲)の取り立てのために「口分田」を用いました。
口分田は6歳以上の人間に貸し与える田のことで、その収穫高の一部を税として取り立てるというシステムで運用していました。
このころは公地公民が原則で「お前の土地は国のもの、そしてお前も国のもの」というジャイアニズム国家だったんですね。
しかし、だんだん国が栄え人口が増えてくると貸し与えるための口分田が不足してしまいます。
政府は仕方なく「墾田永年私財法」を施行します。
これは「自ら開墾した土地を自分のものにしてよい」という制度で、公地公民の原則を揺るがすものでした。
墾田永年私財法が施行されると荘園が増える
墾田永年私財法は田の面積を増やし収穫高を上げるための苦肉の策でしたが、それを悪用して自分の土地を増やそうとするものが現れました。
東大寺などの大寺院は人海戦術を駆使して広大な土地を開墾し自分のものとしていったのです。
こうして得た私有地を荘園(初期荘園)と言います。
荘園が増えると武士が力をつける
荘園にはいくつかの種類と紆余曲折があるのですが、ざっくりいうと地方の荘園を任された役人たちがその土地や権利を守るために武装を強化し始めます。
源氏や平家などの武士団の登場です。
一部の名門の武士団は貴族たちにコネを作って国を動かすほどの大きな力を持つようになっていくのです。
やがて武士たちの力は朝廷を超えて、武士である将軍・源頼朝が国の実質的なトップとなるほどに力をつけました。
武士が力をつけると下剋上の世の中が訪れる
源頼朝の開いた鎌倉時代からは武士の統べる時代です。
守護・地頭として全国に派遣された武士たちが幅を利かすようになっていきます。
武士が力をつけていくと武家の相続問題も浮上してきます。
武家は鎌倉時代までは分割相続が基本で兄弟が複数人いれば親の土地や遺産を分割して分け与えていました。
しかし分割相続を続けると世代が下るにつれて一人一人の相続できる量はどんどん少なくなってしまいます。
これでは武士の力は先細りしてしまうので、室町時代あたりからは長男のみの単独相続へと変わっていきました。
相続できなかった弟たちはどうなるか。基本的には長男の家来として家を支えることになるのですが、それで納得いくお利口なものばかりでもないでしょう。
血気盛んな武士たちは力によって家督を得ようとするものが出てきます。
お家騒動だけではありません。
守護や守護代といった地方の役職も力づくで主従関係を逆転させてやろうという輩が現れました。
こういった風潮を「下剋上の世」といいます。
下剋上の世が始まると戦国大名が現れる
こうして各地で力による支配や権力の簒奪が横行するようになり、世はまさに戦国時代と相成るのでした。
将軍家の跡継ぎ争いに端を発する応仁の乱を皮切りに、各地で大名たちが血で血を洗う争いを繰り広げていくのです。
織田信長や豊臣秀吉、徳川家康などの英傑も争いの世の中で頭角を現していくのでした。
おわりに
繰り返しますが歴史は大きな流れであり、その流れには必ず因果が存在します。
かなり端折って不正確に説明しましたが、こうした流れを追うことこそ歴史の楽しさだと思います。
「なんで?」の連続が歴史を楽しむ一番の秘訣だと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
