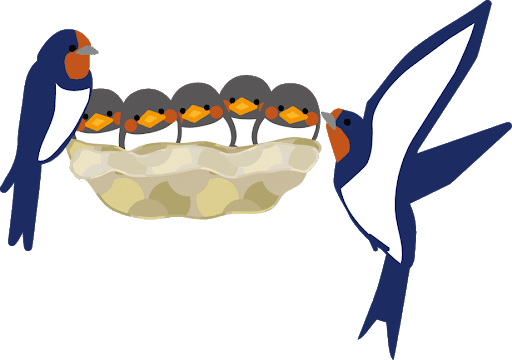第913回 都会に住む野鳥の減少と街中への進出
①http://www.tori-monogatari.com/illust_one.phpより引用の都会に住むハシブトガラス(体長約56㌢)の巣のイラスト
私たちが住んでいる街中には以前から住んでいる野鳥が、街中の発展とともに環境が変わって、去っていったカラスの仲間のハシボソガラス。その後釜に入るように、森から人が出すゴミ袋の中の残飯を求めて、やってきたハシブトガラス。そのハシブトガラスに縄張りを奪われ、田園地域に追いやられたハシボソガラス。街中にはハシブトガラスはいますが、ゴミステーションの拡充や黄色い辛子ゴミ袋の影響で、大都会では減少傾向に有るハシブトガラス。均衡は取れるのでしょうか。
②https://oyaziganko.exblog.jp/iv/view/?i=201801%2F24%2F33%2Fe0108233_18212247.jpgより引用の街中のドバトとスズメ
②の写真は公園や街中でよく見かける光景で、ドバトやスズメが餌を求めて群がっています。この二種の野鳥は私が物心ついた時から、私たちの身近にいる馴染みのある野鳥たちです。①のハシブトガラスは比較的に新しい身近なカラスで、私たちが幼少の頃のカラスはハシボソガラスで、街中のどぶネズミを捕獲するため、街中に現れ鳴き声を上げると、カラスが泣くから不吉なことが起きるとされました。スズメは木造住宅の減少とドバトは駅舎の寝床を追い出され、減少傾向です。
③http://www.wanpug.com/illust262.htmlより引用の田んぼがないビル街では営巣出来ないツバメ
また③のイラストのツバメもまた私たちの子供の頃の60年代は大阪市内でもどこにでも見られる夏の渡鳥の典型的な野鳥でした。当時の市内にはビルが少なく、木造住宅が建てならび、その間の道をツバメが、人や車と一緒に行き交うよな街並みでした。すこし離れた場所には、田んぼやら畑があり、餌の虫はいるし、営巣の材料となる枯れ草、ワラや泥などは十分過ぎるほどありました。現在で市内にはマンションが乱立し、田んぼや畑は壊されて、木造住宅は減少し住みにくいです。
④https://abikobird.at.webry.info/201402/article_7.htmlより引用の街中のヒヨドリとムクドリ
人が第一優先の街中は、野生の生物にとって住みにくい環境のはずです。ところが近年、都会にこれまで自然度の高い環境に住んでいた鳥たちが生息し増えています。今でこそ街中に堂々と現れているヒヨドリやムクドリにしろ、郊外に生息する野鳥でした。ところが、六十年代当時のヒヨドリは、十月くらいになると北方、または山のほうから飛んできてひと冬を過ごし、四月頃になるといなくなる典型的な冬鳥でした。それが家庭栽培の野菜や庭木が増え、留鳥として生息しています。
⑤-1.https://www.google.co.jp/amp/s/gamp.ameblo.jp/matheau/entry-12137920550.htmlより街中に進出して地上採餌するイソヒヨドリ
ムクドリだって同じです。今までからして、郊外の野鳥であったのが、いつの間にか街中にやってきて、ヒヨドリは食害、ムクドリは鳴き声による騒音と集団でねぐらを駅のロータリーで構えるので、その糞害といろんな社会現象を引き起こしました。最近ではムクドリへの対策も施され現在に至ります。そして新たなる街中への進出者は⑤の写真のイソヒヨドリと⑤の写真のハクセキレイです。イソヒヨドリは磯辺から、ハクセキレイは河川の中流から街中に進出してきています。
⑤-2.Twitterより引用の地上採餌するハクセキレイ
この二種のまた中への進出は十数年のことです。鳥は羽が生えていて、いつでもどこにでも羽を使い飛んでいけます。また視力がいいから空高くの位置から事細やかに見渡せるのです。もともとイソヒヨドリは高山の野鳥で、岩のような硬いものに営巣しますので、街中のビルでも平気にベランダに営巣します。またハクセキレイは水辺の野鳥でしたが、今では街中のコンビニ前駐車場をとことこ歩いています。この二種は共に地上採餌主義で虫を食します。それ故に二種はぶつかります。