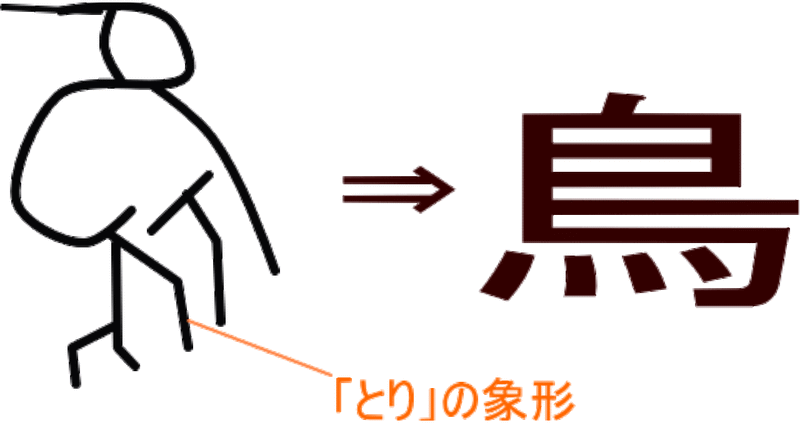
第703回 「鳥」が関わる用語
①https://okjiten.jp/sp/kanji58.htmlより引用の「鳥」の漢字のイラスト
鳥は人にとって、昔から本当に身近な存在でありましたから、いろんなところで「鳥」という漢字が使われ、それは直接に鳥に関するものから、直接関係のないものまで「鳥」という漢字を使っている「言葉」が存在します。鳥は自由に空を飛び、遠く離れた場所からやってきて、私たちに美しい姿を見せてさえずってくれます。そんな身近な存在であるが故にいろんな「鳥」という漢字を使った言葉が作り出されて、鳥の偉大さみたいなものを感じます。どんな用語があるのでしょう。
②http://www.tsurisoku.com/news/2017/05/28/946/より引用の「媒鳥(おとり)」

「 囮」とも漢字表記します。「媒鳥」は「おきとり(招き鳥)」の音変化とあります。メジロならメジロを籠に入れてさえずらせ、その周りにほかのメジロを引き寄せます。また、1.鳥や生き物を捕らえようとするとき、誘い寄せるために使う同類の鳥や生き物。(②のイラストは『囮アユ』) 2.相手を誘い寄せるために利用するもの。(例文として「格安品を―に客を集める」)。最近ではテレビの刑事もねなんかのおとり捜査の「囮」の方が一般的で「媒鳥」はあんまり使わなくなりました。
③https://kotanglish.jp/848より引用の「鳥渡(ちょっと)」のイラスト

「ちっと」の音変化。いまでは『一寸』1.物事の数量・程度や時間が僅かであるさま。すこし。「〜昼寝をする」「〜の金を惜しむ」「今度の試験はいつもより〜むずかしかった」2.その行動が軽い気持ちで行われるさま。「〜そこまで行ってくる」3.かなりのものであるさま。けっこう。「〜名の知れた作家」4.(多くあとに打消しの語を伴って用いる)簡単に判断することが不可能なさま、または、困難であるさま。「私には〜お答えできません」「詳しいことは〜わかりかねます」
④https://www.google.co.jp/amp/s/gamp.ameblo.jp/xiaof4tian/entry-12407020507.htmlより引用の「鳥兜(とりかぶと)」

1.舞楽の襲装束 (かさねしょうぞく) に用いるかぶり物。鳳凰 の頭をかたどり、厚紙に金襴・紅絹 (もみ) などをかぶせて作る。曲により形式・色彩などが異なる。2.キンポウゲ科の多年草。高さ約1m。葉は手のひら状に深く裂けている。秋、深紫色の冠状の花が集まって咲く。また、ハナトリカブトなどを含め、トリカブト属の総称。塊根は猛毒であるが、漢方では主根を烏頭 (うず) 、側根を附子 (ぶし) といい、神経痛・リウマチなどの鎮痛薬に用いる。かぶとぎく。かぶとばな。
⑤https://cherish-media.jp/posts/3421より引用の「鳥瞰(ちょうかん)」している合成写真

②の「媒鳥(おとり)」や③の「鳥渡(ちょっと)」は当て字でありましたが、この⑤の「鳥瞰(ちょうかん)」は[名](スル)鳥が空から見おろすように、高い所から広い範囲を見おろすこと。また転じて、全体を大きく見渡すこと。私たちが憧れた鳥の面目躍如な行動だと思います。また俯瞰 (ふかん)は自信がない時に俯いてしまうみたいな 。「山頂から市街を鳥瞰する」「日本経済を鳥瞰する」また将来の都市計画の時にはイラストであったり、コンピュータグラフィックスの鳥瞰図です。
⑥http://yamada-kuebiko.cocolog-nifty.com/blog/2009/01/post-597f.htmlより引用の「鳥総松(とぶさまつ)」

留守居松ともいわれ、松納めで門松を取り払った後に松の枝を一本折って挿しておく風習。本来、樵夫が大樹を切り倒した後に、山神を祭るため梢の枝を一本切り株に挿したことに由来する。とあり、若松の先端を短く切りとって、門松や松飾りがあった場所に挿しておくことを鳥総松(とぶさまつ)と呼ぶ。鳥総とは木の梢を意味し、本来、樵(きこり)が木を伐り出したあと、切り株の上に梢を据えて山の神様に感謝を捧げたことに由来する。松明にもなる油を含む松は重宝だった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
