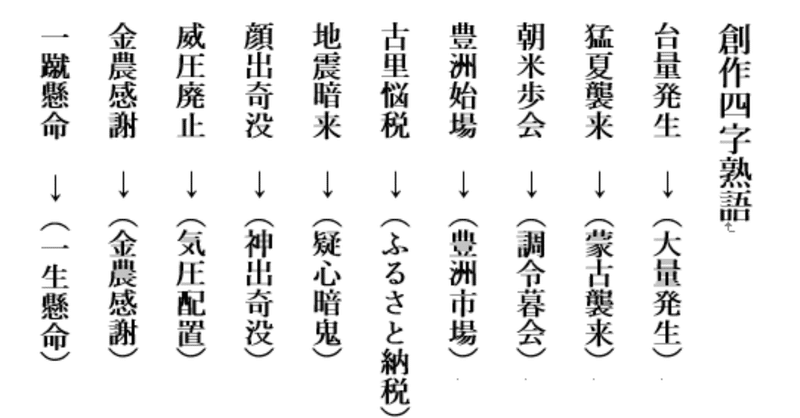
第783回 鳥の四字熟語 ⑵
①https://blog.goo.ne.jp/nkei9090/e/82389ff317d8595fe426af7f73daf92fより引用の「四字熟語」
②https://photohito.com/photo/3792464/より引用の「鳩首凝議(または鳩首謀議)」

(か行) 30.窮鳥入懐(きゅうちょうにゅうかい)→窮地に追い詰められて、人が助けを求めすがること。窮地に陥った人が助けを求めてきたら、どんな事情があっても見捨てずに助けてやるのが人の道である、ということのたとえ。31.牛刀割鶏(ぎゅうとうかっけい)→鶏をさばくのに牛を切る大きな包丁を用いる意から、小さなことを処理するのに、大げさな手段や方法を用いることのたとえ。また、それらを戒めたことば。32.金烏玉兎(きんうぎょくと)→太陽と月をいう。「金烏」は伝説上で太陽に住むという三本足の烏。転じて、太陽のたとえ。「玉兎」は伝説上で月に住むという兎。転じて月のたとえ。33.禽獣草木(きんじゅうそうもく)→鳥獣と植物。命あるものすべて。34.欣喜雀躍(きんきじゃくやく)→思わず小躍りするほど、大喜びすることのたとえ。
③https://japaneseclass.jp/img/鶏群一鶴?page=1より引用の「鶏群一鶴」

(か行) 35.禽息鳥視(きんそくちょうし)→獣のように息をして、鳥のように見る意から、無益に生きながらえるたとえ。禽獣が息をしたりものを見たりするのも、結局は食を求めることに過ぎず、ただいたずらに生きているに過ぎないことから。36.鶏群一鶴(けいぐんのいっかく)→多くの鶏の群れの中にいる一羽の鶴の意から、多くの凡人の中に、一人だけきわだってすぐれた人が混じっていることのたとえ。37.鶏口牛後(けいこうぎゅうご)→たとえ大きな組織や集団でも、末端にいるより、小さな組織、集団でもよいから第一人者となって重んじられるほうが良いということ。38.鶏尸牛従(けいしぎゅうしょう)→牛の大きな群れの後ろに従い行くよりは、小さくても鶏の群れの長になったほうがよいという意から、大きな集団や組織の末端にいるより、小さくても長となって重んじられるほうがよいということ。37.と似てる。
④http://kotowaza-kanyouku.com/keimeikutouより引用の「鶏鳴狗盗」

(か行) 39.鶏皮鶴髪(けいひかくはつ)→年老い衰えた老人のたとえ。「鶏皮」は鶏の肌のように、皮膚が張りや艶を失い衰えたさま。「鶴髪」は頭髪が鶴の羽のように白くなったさま。40.鶏鳴狗盗(けいめいくとう)→小さな策を弄する人や、つまらないことしかできない人のたとえ。また、つまらないことでも何かの役に立つことがあるたとえ。41.鴻雁哀鳴(こうがんあいめい)→雁が飛んで悲しげに鳴く意から、流浪の民がその窮状を訴えるたとえ。42.孤雲野鶴(こうんやかく)→世俗を遠ざかった隠者のたとえ。また、世俗の名利などから遠ざかった者のたとえ。ぽつんと一片だけ浮かぶ雲と野に住む鶴の意から。43.鵠面鳩形(こくめんきゅうけい)→飢えて痩せ果てている形容。「鵠面」は痩せ果て、顔の形が細くとがって鵠に似ていることから。「鳩形」は痩せ果てて胸が突き出て鳩に似ていること。
⑤https://blog.goo.ne.jp/nisikoku2kudamatu16ari5/e/22da8e11fefe6734d236d63433d953bdより引用の「雌伏雄飛」

(か行) 44.孤雌寡鶴(こしかかく)→夫を失った女性のたとえ。「孤雌」は雄を失った孤独な雌。「寡鶴」は配偶のいない鶴。 (さ行) 45.慙鳬企鶴(ざんきふかく)→自分が鴨であることを恥ずかしく思って、鶴になろうとする。自分の素質を考えないで、むやみに人の長所をまねようとする愚かさ。46.慈烏反哺(じうはんぽ)→情け深い烏が幼い時の恩を忘れずに、年老いた親に口移しで餌を与える意から、子が親の恩に報いて孝養を尽くすこと。親孝行のたとえ。47.雌伏雄飛(しふくゆうひ)→将来を期して人の下に従い、低い地位に甘んじ、やがては大きく羽ばたき活躍すること。「雌伏」は、雌鳥が雄鳥に従い伏す意味。転じて、人の下に付き従うこと。低い地位に辛抱していること。「雄飛」は、雄鳥が飛ぶように、盛んに活躍すること。
⑥https://idiom-encyclopedia.com/syaensyukou/より引用の「社燕秋鴻」

(さ行) 48.鴟目虎吻(しもくこふん)→フクロウの目付きと、虎の口元。残忍であくまでもむさぼりとろうとする態度、容貌を形容することば。「鴟」はフクロウ。49.社燕秋鴻(しゃえんしゅんこう)→出会って間もない間に分かれること。燕は春の社日に来て秋の社日に帰る。鴻(ヒシクイ)は秋に来て春帰る。50.雪泥鴻爪(せつでいこうそう)→人の行いなどは、儚いものであるたとえ。「雪泥」は、雪が解けた時のぬかるみ。「鴻」は、大きな鳥、雁。「鴻爪」は、雁の爪の跡。人生はちょうど渡り鳥の雁が雪解けのぬかるみを踏んだようなものである。ぬかるみにたまたま指や爪の跡は残るが、どの方向に飛び去ったのか分からないように、人生もはかなく分からないという意。51.巣林一枝(そうりんいっし)→鳥は木のたくさんある林に巣を作るが、それでもたった一本の枝にしか巣を掛けないという意から、分相応の小さい家に満足することをいう。ものには限度があるということ。
⑦https://www.google.co.jp/amp/s/twgreatdaily.com/q-KECWwBmyVoG_1Z8tT3.ampより引用の泰山鴻毛

(さ行) 52.鼠牙雀角(そがじゃっかく)→鼠や雀が屋根や壁を傷つけるために、本来持っていない牙や角があるのではないかと憶測すること。凶暴な者が非道なことをして争いの元を作り、訴訟を争うこと。一般に訴訟の事。 (た行) 53.泰山鴻毛(たいざんこうもう)→非常に重いものと軽いもの。重んずべきものと、軽んぜべきもの。隔たりが甚だしいことのたとえ。「泰山」は中国山東省にある名山で、極めて重いもののたとえ。「鴻毛」は鴻(おおとり)の羽毛の意で、極めて軽いもののたとえ。54.長頸烏喙(ちょうけいうかい)→長い頸ととがった口先。このような人相をした人物は、烏のように強欲、陰険で、苦労をしても安楽に暮らすことはできないという。中国春秋時代の越の国の范蠡が越王勾践について言った言葉。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
