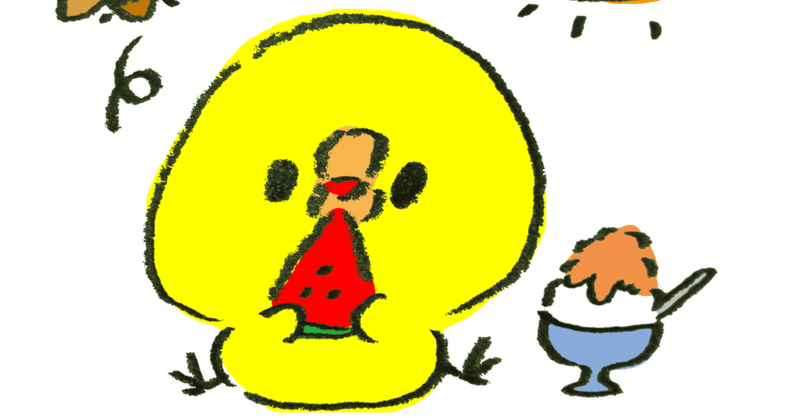
第615回 偏食する野鳥
①https://hiyokoyarou.com/megane-kumoru/より引用の偏食するヒヨコのイラスト
世界は広くて、ある一定のものしか食べない生き物がいます。アフリカには名前こそ優しそうなシルキーワシミミズク(別名:サルクイワシミミズク)、フィリピンにはカニクイザル、そのサルを食すフィリピンワシ(別名:サルクイワシ)、中南米にはアリやシロアリを食べるアリクイ、やはりアフリカにはヘビを食すヘビクイワシ、またナイル川にはイリエワニの口の中に寄生する虫を食べるナイルチドリ、同じくアフリカで蜜蜂の巣にいる虫をラーテルや人を使って食べるミツオシエなど…
②ハチが主食のハチクマ(体長約57〜61㌢)

この日本にも偏食?する野鳥がいます。②の写真のハチクマです。漢字表記は「蜂熊」「八角鷹」「蜂角鷹」でハチを主食とし、クマタカに似た姿だからこその名前の由来です。日本には初夏に夏鳥として渡来し、九州以北の各地で繁殖します。夏と冬にはスズメバチ類やアシナガバチ類といった蜂の巣に詰まった幼虫や蛹を主たる獲物とします。クロスズメバチやオオスズメバチなどの地中に営巣するハチであっても、巣の真上から足で掘り起こし、捕食してしまいます。
③https://www.google.co.jp/amp/s/kitamoto72.exblog.jp/amp/30482810/より引用のアリを食べるアリスイ(体長約17㌢)

③の写真も衝撃的だと思います。パッと見ましたら、ヘビが鎌首を伸ばして、舌を出しているとしか思えません。このヘビのウロコのような模様をしたこの野鳥は漢字表記で「蟻吸」でその漢字通り、アリを吸うようにして食べるアリスイです。私は初めてこんな擬態化した写真を見たとき、日本の野鳥ではなく、アフリカ砂漠辺りの野鳥と思いました。キツツキの仲間なのに、木を突くことはせず、約10㌢にも伸びる長い舌を木の穴などに差し込み、アリを吸い取り食します。
④http://digibirds.hatenablog.com/entry/20150318/1426604451より引用のヤドリギの実を食べるヒレンジャク(体長約17㌢)

歌舞伎役者のような衣装をまとっているようなキレンジャクとヒレンジャク。漢字表記は「黄連雀」「緋連雀」次列風切羽の先端に赤い蝋状の突起物が付いていることに由来し、この蝋状の物質が何の役に立つかは分かっていません。これだけでも不思議なのに、このレンジャクは皆んなが嫌う寄生植物のヤドリギの実は、丸くて大きく透明で美味しそうに見えますが、苦味があり粘着性があって美味しくありません。丸い実をくわえると、とても満足そうな顔をします。何故…
⑤毒とされるエゴの身を食べるヤマガラ(体長14約㌢)

⑤の写真はヤマガラです。秋が深まり、野鳥愛好家の方はこのヤマガラに会いたければ、エゴの木に行けば必ず会えるといいます。何故エゴの木かといいますと、このヤマガラは皆んなが嫌うエゴの木の実が大好物なのです。エゴの木の実は硬い殻と実の間に毒性のサポニンという物質があり、それをほかの野鳥は敬遠するのです。しかしヤマガラは両足で実を押さえて、コツコツ、コツコツとクチバシを突いて、この硬い殻を破って、中の美味しい実だけを食べるのです。
⑥http://www.hirahaku.jp/web_yomimono/tantei/dbtkodou.htmlより引用のスナック菓子を頬張るドバト(体長約33㌢)

⑥の写真はドバトです。何故このドバトが偏食なのかって言いますと、いつもは街の社寺仏閣や、公園、街の広場に集団でどこからともなく現れて、人間の近くに集まってきて、何やら地面をコツコツ、コツコツとクチバシで突いています。これは地面にある細かい砂つぶを食べて、内臓の砂嚢すなわち砂ずりというところにいれ、消化の助けをするためで、人間がくれるスナック菓子やパンなどを足元まで行って擦り寄り頬張ります。その姿を見ていたら何か偏食の子供のようです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
