
第700回 花札に登場する野鳥
①https://illust-imt.jp/archives/001913/より引用の花札のイラスト
花札は私たちが子供のに流行っていたトランプと並ぶカード遊びで、なぜかそのカードを販売しているのが街のタバコ屋さんでありました。一組48枚に、12か月折々の花が4枚ずつに書き込まれていました。48枚といえばトランプ(ババ二枚を入れると50枚)も同じ枚数です。このカレンダーのようになっている花札にも野鳥たちが登場しています。一月の「鶴」二月「鶯」四月「不如帰」八月「雁」十一月「燕」十二月「鳳凰」と架空の鳥を含め六種が四季の花と共に登場しています。
②http://monolith.mods.jp/2017/04/11/post-2031/より引用の花札の「松に鶴」
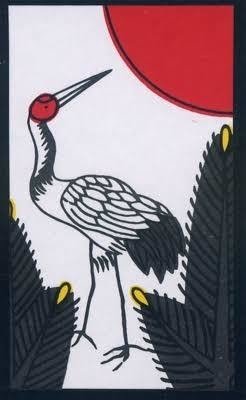
一月初っ端はめでたくお正月なので、めでたく「松に鶴」の組み合わせです。松は常緑樹(一年中葉が緑)なので「不老長寿」の象徴。鶴は「鶴は千年、亀は万年」というように「長寿」の象徴だったり、鶴の夫婦が仲良しな事から「夫婦鶴」と呼ばれたりと、おめでたい時やその席ではもてはやされる縁起物でもあります。それを現実的に見てみると「鶴」はタンチョウであります。そしてツルは後ろ趾(あしゆび)が短く、枝にとまれないのです。止まっているのは実はコウノトリなのです。
③http://monolith.mods.jp/2017/04/12/post-2045/より引用の「梅に鶯」

二月になると、もうそこには春がやってきています。 春告鳥の登場です。「梅に鶯」はもうこんな昔からいろんなところに描かれています。春を告げる梅の花と春告鳥を並べてあります。梅の花は五枚。福、禄、寿、喜、財の五福を意味します。鶯は青柳の糸で梅の花を縫って笠を作るという言い伝えがあるそうです。それを現実的に見てみると、ウグイスの姿勢が水平でなく、眼の上の眉斑もなく、過眼線もありません。体色も違うし、ウグイスより鮮やかなメジロじゃないか。
④https://sp.seiga.nicovideo.jp/seiga/#!/im4340503より引用の「藤に不如帰」
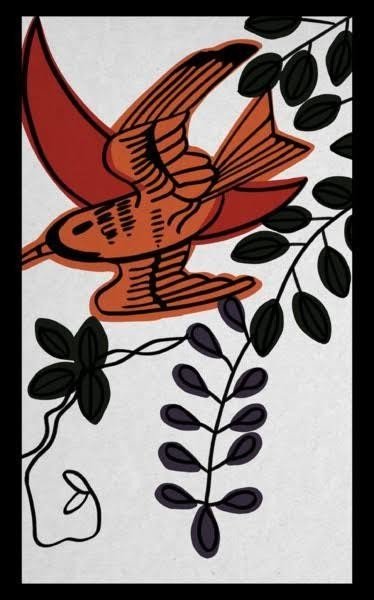
いよいよ四月ともなりますと、春本番です。『
藤波の 咲き行くれば ほととぎす 鳴くべき時に近づきにけり』(藤の花が咲くのを見ればもうすぐホトトギスの鳴く季節だな)万葉集。『ほととぎす 鳴きつるかたを ながむれば ただありあけの 月ぞ残れる』藤原実定。赤い月も描かれた夜の情景です。確かに習性としてホトトギスは夜も鳴きます。下面の横斑は似ているのでホトトギスに間違いありません。しかし四月…はいこの時代では夏の到来は四月だったのです。気候の変化です。
⑤https://www.google.co.jp/amp/www.epochtimes.jp/jp/2007/08/html/d22827_amp.htmlより引用の「薄に雁」

さあ八月の「薄に雁」は山から満月が現れて、雁が三羽山を越えて、そして山だけが残ります。山にはススキ。ってススキは秋の七草の一つで、ガンも秋。雁にしては翼が短く頭が赤いです。十一月は柳に燕。だんだん何かしらおかしくなってきました。ツバメの頭と尾が赤く描かれて、体は黄色だからツバメじゃない。そしてツバメがなんで十一月なの。そして師走の十二月は「桐に鳳凰」ここで架空の鳥が参上です。しかし、 桐の花期は五~六月です。『きり』は「限り」を意味する「切り」で、古代からある和語で、天正カルタで最終の十二枚目を『キリ』と呼んでいたので、同音の桐を十二月に持ってきたらしいです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
