
第886回 渡鳥って凄い
①https://www.photolibrary.jp/img231/87059_1720376.htmlより引用の朝の渡鳥
朝から昼に渡る野鳥は飛行高度が低く、帆翔する鳥に多いです。ハクチョウ、ツル、コウノトリ、ペリカンなど、鷲鷹類に襲われない大型の野鳥は、上昇気流を利用して体力の消耗を減らします。飛行が巧みで鷲鷹に襲われず、飛びながら餌をとれる、ツバメ類、アマツバメ類。密集した群れを作るムクドリ、コムクドリ、スズメ、メジロ、レンジャク類、ヒワ類。ツバメは昼ばらばらに渡り、夜集合して寝ます。ワシタカやヒヨドリ、メジロ、カラスなどは渡りは短距離なので、採餌と渡りの両方を昼に行えます。他にモズ、セキレイ類も。朝昼の渡りは太陽の位置から自分の位置を読み取り方向を決め、紫外線は雲を透過するので、渡鳥は曇天でも太陽の位置が判ります。体内時計の助けを借りて正確に位置を知ります。
②https://daily-keitaism.com/archives/6033より引用の夕方の渡鳥

昼と夜にガンカモ類、アオサギ、シギチなど干潮に合わせた採餌方の鳥は渡りも昼夜です。夜に渡る野鳥は長距離を渡る種が多いです。高度を高く
羽ばたいて飛ぶ鳥に多く、小鳥やフクロウ類、ヨタカ、クイナ類、ウ類、ホトトギス、一部のヒタキ(オオルリ、キビタキなど)、ムシクイ、アトリ、ツグミ類、ホオジロ類など多くの野鳥です。捕食者からの危険性が低く、昆虫食の鳥では夜飛行することで、日中は採餌に専念でき、暑さに弱い小鳥類では日中の暑さを避けられます。また乱気流が起こりにくいので、大気の状態が安定しているので直線距離を長距離移動するのに適していて、星座が方向を教えます。出発の時間は日没後30分~1時間で、多くのスズメ目、チドリ目の鳥は昼行性ですが、夜間に渡るものが多いです。
③https://jp.123rf.com/photo_35376216_v-編隊飛行移行の-greylag-ガチョウの群れ%E3%80%82.htmlより引用のV字型飛行の渡り
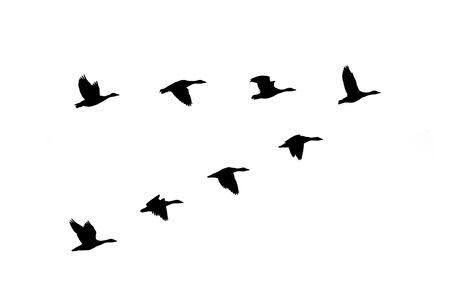
渡りはオスが早く渡ることが多く、メスが次で、若鳥が最後です。ハクチョウなどでは家族単位で渡ります。渡来が早い種ほど渡去は遅く、高緯度や高標高で繁殖するものほど渡来が遅く、渡去は早いです。また秋より春のほうが移動速度は速い
(オジロワシでは秋は細かく移動)。春は日本海側での多く、日没後1~3時間後から活発。緯度が高緯度になるほど夏は昼が長いので、昼が長いと採餌時間も長くとれ、効率良く短期間で育て上げることができます。この時期短期間に昆虫などが大発生。しかし、渡りを始めると短期間絶食する鳥が多いです。腸は退化して消化吸収能力を止めて、浮いたエネルギーを飛翔のエネルギーに回します。ベクトル航法仮説は本能的に渡っていくのか、遺伝的にプログラムされているという説。
④https://jp.123rf.com/photo_84957608_コウノトリは、森の上を飛んでします%E3%80%82コウノトリ秋移行%E3%80%82鳥飛行の平面イラスト%E3%80%82.htmlより引用の群れで飛行する渡鳥

春の渡りは生まれた場所への執着心で、秋の渡りは食物を求めます。その食物説は北半球では繁殖期に北部で虫が多く発生し、冬は虫が減るので南へ移動、少しずつ移動距離が長くなります。大陸移動説は渡りを大陸移動と結ぶ説。氷河説は氷河時代に温暖な地域に移動したが、氷河の後退に伴い北に移動し、この繰り返しが渡りに発展。
天体航法は鳥が太陽、星などの天体を手がかりに、飛行方向を定めることで、太陽コンパスは昼、太陽を利用し、星座コンパスは夜、星座を利用し、指標にしている特別な星があり、種により異なります。ホシムクドリでは北斗七星を指標とし、磁気コンパスは曇天時などを判断。ハトの幼鳥は磁気コンパスを利用しますが、成長の段階で太陽コンパス利用を達成していきます。
磁気センサーはハトの内耳にある壺嚢(このう)という感覚器官が磁気センサーの役割をしているとして、ハトの帰巣性は地磁気と関係があるとの説もあります。また方向を知る一つの方法として地球磁場を利用します。南北を指す磁石を持っているのではなく、地磁気の磁力線の方向と水平方向のなす角度で伏角の場所による違いを方角を知る手掛かりとしています。
光依存仮説は、磁気を目の感光色素で感知し、視覚情報を解して全能領域の一部(クラスターN)に伝えるという『磁場を見る』説です。野鳥は体内の磁気コンパスではなくて、体内の化学反応によって地磁気を感知して、進路を決定しているという説があります。地磁気で生じる化学反応を、野鳥が感知している可能性がある。野鳥は胎内にあるなんらかのセンサーにより渡りをします。
⑤https://jp.123rf.com/photo_89868608_鳥の群れのシルエット%E3%80%82黒の鳥の飛行の輪郭します%E3%80%82飛んでいるハト%E3%80%82タトゥー%E3%80%82.htmlより引用の帆翔する渡鳥

他には順位説があり、若い鳥は遠くの越冬地で過ごします。強い個体(成鳥オス)が近くの越冬地で、生活資源(餌など)を優先的に確保してしまうので、
劣位の個体はもっと遠くへ行って、食べ物を探す必要が有るります。オスは繁殖期に縄張を確保が必要で、繁殖地から近い方が有利。成鳥の雄は一番体力が有るので、多少の寒さに耐えます。
群れで渡る種は昼に渡る種に多く、シギチは昼でも夜でも群れ渡ります。ペリカン、ツル、ハヤブサなど帆翔する鳥は群れが多く、カモメ、アジサシ、ウミスズメ、ミズナギドリ、ウミツバメなどの海鳥は一般に群れで渡ります。またヒヨドリ、メジロ、カラスは他の鳥を見ながら渡るので、コースを間違える心配が少ないです。単独で渡る種は夜に渡る種に多く、ムシクイ、ヒタキ、ホオジロ、アトリです。ツバメはバラバラに昼渡りますが、夕暮れには集まって眠ります。サギ類、トキ類では昼渡る種は群れ、夜渡る種は単独。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
