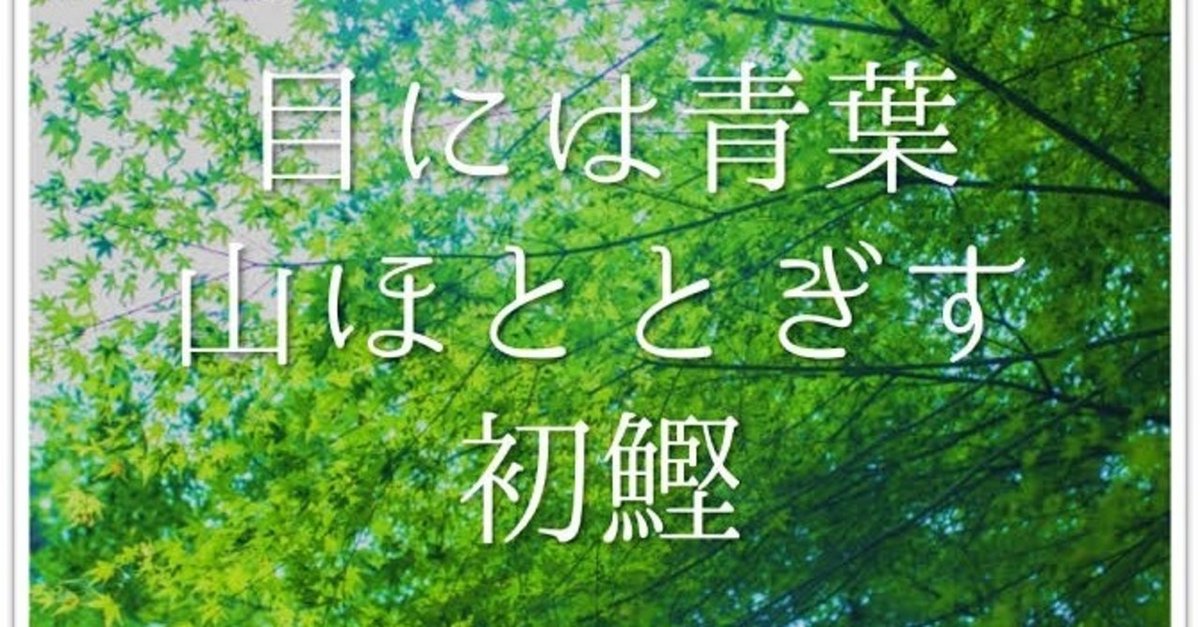
第972回 夏鳥のホトトギス(4回目)
①https://haiku-textbook.com/meniwaaoba/より引用のイラスト
毎年やってくるゴールデンウィーク過ぎの日本では初夏に当たり「目には青葉山ほととぎす初鰹」の俳句が思い浮かびます。「目には青葉」は私のマンションのベランダ側に山がありますので、その頃は若葉で眩しいくらいに青々と緑が眩いくらいに茂っています。また最後の括りの「初鰹」は本当に鰹に脂がのり、タタキで頂くと食欲が沸いてくるような気がします。山口素堂の句です。「青葉・ほととぎす・初鰹」は夏を表す季語です。この中のホトトギスは初夏に鳴く筈なのに、六月頃にしか私は鳴き声を聴きませんでした。
②ホトトギス(体長約28㌢)

夏鳥である日本でのホトトギスは古来、様々な文書に登場し、杜鵑、杜宇、蜀魂、不如帰、時鳥、子規、田鵑などと思い当たるだけでも数多くの漢字表記や異名が多い野鳥で有名です。「目には青葉山…」の俳句は松尾芭蕉と交際があった俳句の山口素堂の作品です。不如帰の名前の由来は中国文学から、『枕草子』ではホトトギスの初音を、正岡子規は不如帰で「鳴いて血を吐く」と言われたホトトギスと自分の結核を結び合わせ「子規」を自分の俳号としました。文学的要素が多いです。
③赤色のホトトギスのメス

夏鳥のホトトギスは日本では五月中旬頃にやってきて、他の渡鳥よりも渡来時期が遅いのは、托卵の習性のために対象とする鳥の繁殖が始まるのにあわせることと、食性が毛虫類を捕食するため、早春に渡来すると餌にありつけないためといいます。また食性が毛虫類を捕食するため、早春に渡来すると餌にありつけないためです。毛虫などの虫を主食とし、繁殖は自分の卵をウグイスなどの自分より小さな野鳥の営巣に産みつける「托卵」にて、自分の子供を育てさせる手段の野鳥です。
④毛虫が好きなホトトギス

ホトトギスを語る時はどうしても「托卵」や「文学」と切り離して語ることができません。それほどホトトギスはカッコウに比べて、日本に馴染み深い野鳥でありますのに、その名前の別名の漢字表記が「郭公」というのは、ハトより大きなカッコウとヒヨドリより少し大きなホトトギスを見間違えだ故の名付けの一つには何か解せないものがあります。これはホトトギスとカッコウがよく似ていることからくる誤りによるものと考えられています。松尾芭蕉もこの字を用いていました。
⑤https://www.google.co.jp/amp/s/weathernews.jp/s/topics/201805/100115/amp.htmlより引用のホトトギスのウグイスへの托卵

ホトトギスを語るときには、文学や托卵のことに埋もれて、冒頭の私の「山ほととぎす」で五月中旬にホトトギスのあの有名なききなしの「本尊掛けたか」や「特許許可局」や「テッペンカケタカ」が飛来しているのになぜかの疑問がありました。それは夜にも鳴くホトトギスはその年に初めての鳴き声を忍音(しのびね)として、けたたましいような声で「キョッキョッ キョキョキョキョ」と聞こえていました。この鳴き声がホトトギスの鳴き声であると思わず、今まで過ごしていました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
