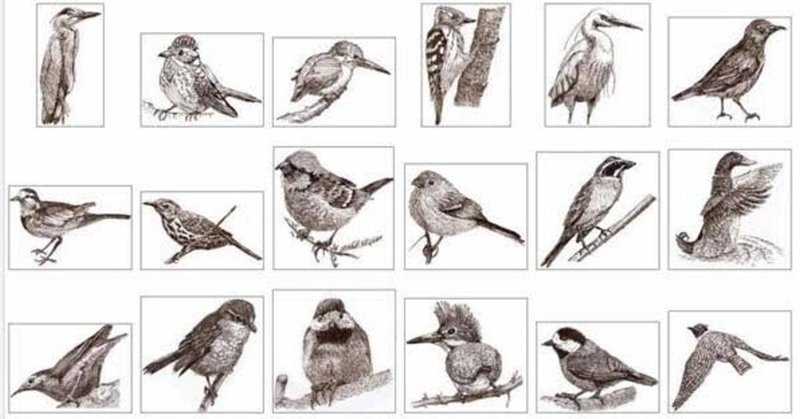
第1472回 野鳥の色んなこと ⑴
①https://doudesyo.blog.ss-blog.jp/2007-03-21より引用の色んな野鳥のイラスト
この世界には、色んな野鳥がいて、地味な体色の鳥もいれば、派手な体色の鳥も、またそのさえずりがとても綺麗な鳥もいれば、その鳴き声があまりにも大きすぎる鳥、又は自分のさえずりだけではもの足りず、ほかの野鳥や生き物、人工物の音を真似る鳥、はたまた、さえずりながら尾羽を鳴らしたり、翼を地面に打ちつけ母衣打ちで求愛ディスプレイする鳥、鳥とは思えない手の込んだ巣を作る鳥、人間でもないのに、男前や美人な鳥、家族を守るために擬傷や擬死を演じる鳥等等…
②-1.https://www.google.co.jp/amp/s/www.asahi.com/amp/articles/ASN9T6W0PN9PPTLC00H.htmlより引用のシロチドリ(体長約17㌢)の擬傷

②-2.https://hiroshi5351.cocolog-nifty.com/blog/2018/04/post-9833.htmlより引用の珍しいケリ(体長約36㌢)の擬傷

②-3.https://karapaia.com/archives/52210986.htmlより引用の車のボンネット上のシジュウカラ(体長約14㌢)の擬死?

偽傷という雛や卵を守るために親鳥が、外敵の眼を自分に向けさせて、そのばを凌ぐ行為で「チドリ類、シギ類、カモ類、ライチョウ、キジ類、ヨタカ、ホオジロ、ホオアカ、ヒバリ、ビンズイ、サンショウクイで知られます。どうしても見つかり易い地上に単独で巣作りする鳥で発達しています。雛を守りたいという気持ちと、逃げたいという葛藤が、このような行動を起こさせるという説もあります。ただ、②-3.のあたかも擬死に見えるシジュウカラは暖をとる為、車のボンネットに。
③https://hiyokoyarou.com/wedding-dress-hiyoko/より引用のひよこの花嫁衣装のイラスト
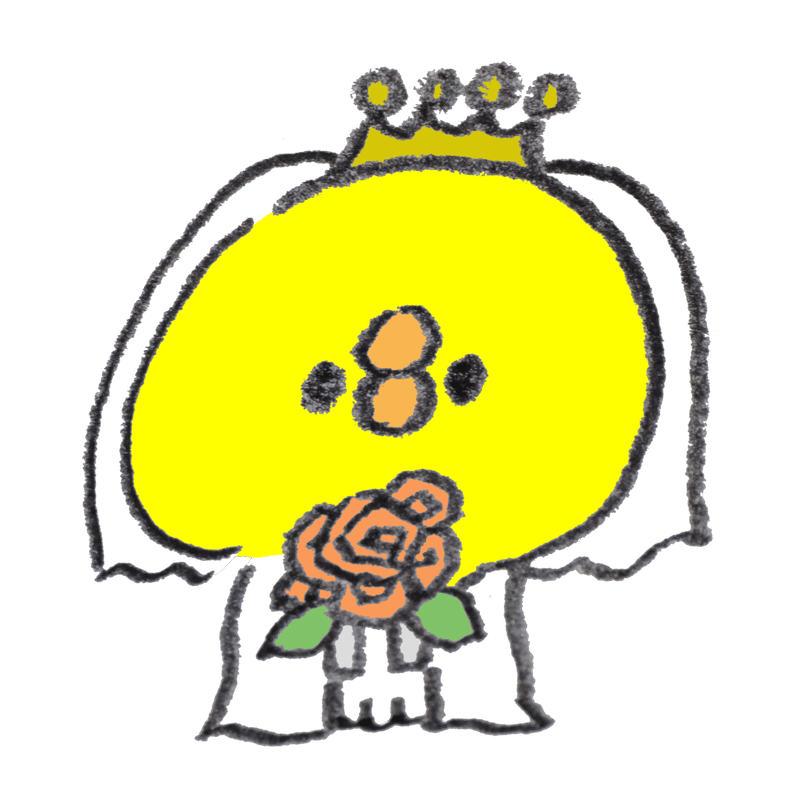
一番身近なスズメは、一般に留鳥とされていますが、日本で1920年〜40年代の移動性の調査によれば、移動距離が25km以内(特に5km以内)の真の留鳥集団と、100km以上を移動する移動性の高い集団が存在していること判明しました。この調査に於いて、新潟県で標識放鳥された約5700個体のうち7個体が岡山県で、3個体が高知県で標識回収された事が記録にあります。その殆どが私はオスだと思っていましたが、殆どがメスみたいです。鳥類の世界的では、冒険家は常にメスのようです。
④-1.http://blog.livedoor.jp/sumirerira/archives/14069315.htmlより引用のエナガ(左側、体長約14㌢)に先導されて後につくシジュウカラ(右側)

④-2.https://www.nature-engineer.com/entry/2020/10/03/090000より引用のゴジュウカラ(体長約13㌢)

④-3.https://www.google.co.jp/amp/s/gamp.ameblo.jp/sumire0521/entry-12634299662.htmlより引用のコゲラ(体長約15㌢)

以前にも何回か、冬になると餌探しの為に、カラの仲間が混群を結成することを紹介しました。またそのリーダーは簡単な単語を使い、文章化するシジュウカラがその混群の先導種であるとしましたが、細かい調査では、④-1.の一番小さな、生まれつき集団性の高いエナガも先導種に名前が載ります。小さい故に餌不足の危機感があるのかも。また混群の随伴種は何時もはキツツキのように木の幹にいるゴジュウカラがカラの仲間で追随し、その後に続き、随伴種としてコゲラが続きます。
⑤-1.http://opipo.blog.fc2.com/blog-entry-139.htmlより引用のイソヒヨドリ(左側がオス、右側がメス、共に体長約25㌢)のつがい

⑤-2.https://blog.goo.ne.jp/nekopunch-222/e/e9f97cbba0be4fdb2b68b51cd8348621より引用のシジュウカラ(左側がメス、右側がオス)のつがい

⑤-3.https://www.google.co.jp/amp/s/tontonoyaj.exblog.jp/amp/30811259/より引用のエナガの群れ

⑤-4.https://www.seikatsu110.jp/animal/am_pigeon/35213/より引用のハシブトガラス(体長約56㌢)の大群

全く群れずに冬を単独で過ごすのは、イソヒヨドリ、ルリビタキ、アカヒゲ、ミソサザイ、カワガラス、モズ、アカゲラ、カワセミ、ハイタカ、チョウゲンボウ。小群はホシガラス、カササギ、アオジ、ホオジロ、クロジ、ゴジュウカラ、コガラ、シジュウカラ、セグロセキレイ、アオバト、キジ。中群はカケス、イカル、メジロ、エナガ、シメ、ウソ、ツリスガラ。大群はハシブトガラス、ムクドリ、スズメ、マヒワ、カシラダカ、ヒガラ、ツグミ、キレンジャク、ツバメ、ハマシギ、カモメとやはり群れた方が過ごしやすそう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
