
第762回 野鳥ののど自慢 ⑵
①Twitterより引用のイラスト
鳥類の声でも高音の部分は遠くまで届きません。しかし、遮蔽物があっても届きやすいので森では有利です。また低音の声は遠くまで届きますが、遮蔽物があると遮断されますが、開けた場所で有利です。鳴き声の様式は五種あって、1.同音反復型=同じ短い要素を多数連続して鳴く。(ホーホー) 2.異音結合型=複数の異なる要素を組み合わせ繰り返し鳴く。(カッコー) 3.単一歌節型=構成要素や句の時間的配列が概ね決まっている。(ホーホケキョ) 4.異歌交唱型=複数の替え歌(レパートリー)を、例えばツーピーピーからツツピーツツピーへと変えて鳴く。5.異句交唱型=多様な要素、句、節を入れ替えつつ連続して鳴く。(ギョギョシギョギョシカイカイケケッケ)
②https://www.google.co.jp/amp/s/youpouch.com/2015/04/28/264490/amp/より引用のイラスト

コマドリのよく声の通る歌の要素は歌の最小単位で、時間的に途切れない一音です。句は複数の要素がごく短い間隔を開けて連なるもの。節は複数の句が小休止を置いて連なるもので、即ちフレーズのことです。ウグイスの仲間のサヨナキドリ(ナイチンゲール)のオスは一晩中さえずることがあります。雌雄はつがいになると、夜は歌わなくなり、独身のオスは、日中は鳴きながら移動し、夜は鳴くだけで移動しません。昼の歌は縄張りの境界を探るためのもので、夜の歌はメスを誘うためのもの。メスは夜も活発に行動し、夜につがい相手を探しまわります。
③https://www.pinterest.jp/pin/330170216413658239/より引用のイラスト

英語でも日本語でも「夜明けのコーラス」と呼ばれます野鳥のさえずりは、実際には夜明け前に最も盛んになります。メスの産卵は早朝で、メスが出てくるのは産卵直後。産卵直後に行う交尾が、翌日の産卵の受精に効果があります。早朝に交尾したいオスは早朝に盛んに囀る必要があり、夜明けの時間帯は、音の伝播条件が昼の二十倍も良いです。夜明けは、暗さと低温で、餌である虫などの活動が鈍く見つけにくい。そこで、餌探しは日中。さえずりは夜明けを中心に行ないます。日が昇る前は、空気が安定していて風がなく、風音に影響されにくいとか、セミが鳴かないので、邪魔されません。猛禽類はまだ活動前なので、襲われません。(ウグイスは、藪にいて猛禽類に襲われにくいので、鳴き始めが遅い)
④https://amanaimages.com/info/infoRM.aspx?SearchKey=22252002788より引用のイラスト
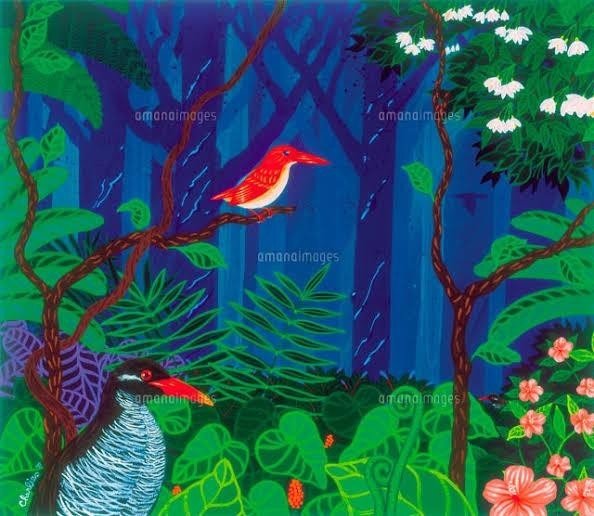
また生息場所によっても鳴き声は変わります。草原では音源定位に向いている高周波音が適している。森の周辺は中間。森の中からは森では音が木にぶつかりはね返されたり、吸収されることが多いので、長い波長を持つ低周波音のほうが適しています。開けた場所に生息する種は小さな声で、見通しの悪い場所に生息する種は声が大きい傾向が有ららます。シジュウカラ類の警戒声は8kHz以上で、シジュウカラ類には辛うじて聞こえるが、猛禽類には聞こえにくい音域です。
⑤http://nikosuzumemi.hatenablog.com/entry/2016/04/23/145515より引用のイラスト

小さな野鳥ほど、仲間に対して警戒音を発します。警戒の声はシジュカラは「ジュクジュク」ヤマガラは「ニーニー」メジロ「キュリキュリ」ムクドリ「ジャー、ツィッツィッ」スズメ「チーエ チーエ」さえずりでは、自分の居場所が分かりやすい音程で歌います。警戒の地鳴きでは居場所がつかみにくい高周波の声です。また人間と同じように、方言が確認されている鳥が、アカハラ、センダイムシクイ、ホオジロの三種で、どんな方言か是非とも聴いてみたいと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
