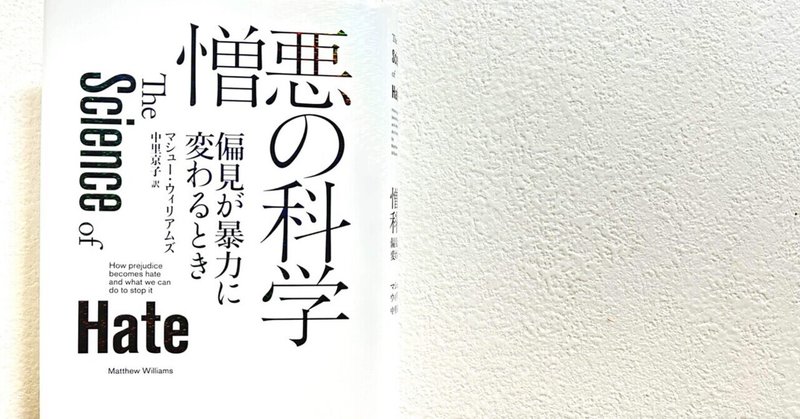
憎悪の科学/マシュー・ウィリアムズ
「私たちはみな偏見を抱えているが、すべての人が街に繰り出してヘイトクライムに走るわけではないからだ。相手が特定の集団に属しているという理由でその人を傷つけたり殺害したりするには、偏見を超える何かが関与している。この状態を表す言葉として通常使われるようになったのが“憎悪(ヘイト)”だ。」(p.28)
「憎悪についての科学的な研究では、“憎悪”という言葉はしばしば、相手の世界観が自分のものと対立しているため、または対立していると感じとれたために、その集団全体を除外したいと望む感情(対
集団的憎悪感情)を指すために留保されている。個人が憎しみの対象になることはあるとはいえ、それはその人の外集団との関わりのためだ。」(p.29)
「他人の感情に対する理解不足も、集団内で憎悪が蔓延する材料だ。共感の欠如ーーー相手の感情を共有するのを阻むことーーーは認知的共感性の行使を嫌うことから生じる。つまり”彼ら”の視点に立って物事を見ることを拒絶するのだ。心理学には、他者の視点に立つことに関する専門用語がある。「メンタライゼーション」とは”彼ら”の心の状態を想像することだ。また、「心の理論」を持つとは、他者の信念、意図、信条などが理解できることを指す。」(p.39)
「世界のいくつかの地域では、憎しみが路上やインターネット上で蔓延する状況が放置されている。かなりの数の人々にとって、人生の中でこれほど憎しみに包まれ、これほど憎しみに影響され、これほど憎しみに対抗する能力を失ったことはなかったろう。」(p.78)
「科学的なコンセンサスは明確で、偏見や憎しみがあらかじめ脳にインプットされた状態でこの世に生まれてくる人はいない、というものだ。私たちは、「我ら」と「彼ら」を識別する傾向のある脳を備えて生まれてくるように見受けられるが、「我ら」と「彼ら」が誰であるかは、固定されたものではなく、学習された結果である。このような神経学的メカニズムが組み込まれているということは、私たちはみな、偏見や憎しみを形成する最も基本的な土台を備えていることを意味する。この人間の特性に、ある種の出来事や環境が重なると、誰でも憎しみを抱える可能性があるのだ。」(p.86)
「人種に関するIATを受けた何百万人もの白人被験者のうち、約75%が、アフリカ系米国人よりも白人系米国人を自動的に選好することが示された。興味深いことに、黒人被験者の約50%も、アフリカ系米国人よりも白人系米国人をある程度好むことが示されている。」(p.94)
「人には自分と同じような人を好む傾向があるという強力な証拠がある。これこそ、憎悪の最も基本的な構成要素だ。だが、それが憎悪に移行するのは必然的なことではないし、他の人間との出会いの中で偏見に満ちた考え方をするようになるのも、脳の学習によるもので、生まれつきのものではない。」(p.141.142)
「人種差別に基づく憎悪は、過去のトラウマに由来する未解決のフラストレーションに都合の良い家庭、すなわち「コンティナー」を提供してくれた。理不尽ではあるものの、人種的な「他者」は、彼らがフラストレーションを簡単に投影できる標的になったのだ。」(p.203)
「国家レベルの選挙から管区レベルの警官殺害まで、ある種の出来事には偏見に満ちた態度を憎悪に満ちた暴力に駆り立てる力がある。」(p.238)
「「聖なる価値の保護」と呼ばれる心理学的現象は、トリガーイベントの後に、悪いことをする人と良いことをする人を分化する。イリノイ大学シカゴ校のリンダ・スキトカ教授らは、人々の聖なる価値観、つまり他のあらゆるものを超えて大切にしている価値観が、トリガーイベントによって脅かされたときに何が起こるかを検証する実験に着手した。研究者らは、同時多発テロのあと、差別やヘイトクライムなどを通して「義憤」を表現した人々のケースと、アメリカ国旗の掲揚、ボランティア活動、献血、家族に会う頻度を増やすことなどを通して「道徳的浄化」を表現した人々のケースがあったことを見出した。」(p.239)
「人間は、地球上で唯一、自らの死すべき運命を知っている種であり、この知識が自らの人間性や他者との関わり方を形作っている。」(p.245)
「たとえどのような形であっても、私たちの多くは死の恐怖から逃れるために、何らかの形の死後の世界(必ずしも宗教的な意味ではない)を信じようとする。それは、子孫のことかもしれないし、芸術作品や科学、あるいは単に充実した人生を送ったという事実であることもあるだろう。グリーンバーグ教授らは、この現象を「存在脅威管理」と呼んでいる。「存在脅威管理理論(TMT)」とは、人間は自らの死の不可避性を意識すると、文化的世界観を使って、その価値観を強化することにより「象徴的不死性」を手にしようとする、という仮説だ。」(p.247)
「この最初の実験以来、500あまりの研究が行なわれ、人は死の不可避性を思い起こすと(「死の顕現化」と呼ばれる)、自らの価値観(文化的世界観)を守ろうとする傾向が強くなり、その価値観に沿って生きようと努力するために気分が良くなる(自尊心が高まる)ことが実証されている。科学的な研究により、死の顕現化は、あらゆる背景の人々に、外集団をダシにして自らの世界観を強化させることが証明されている。」(p.248)
「誰にでも「今までいったい何のために努力してきたんだ」と思う瞬間がある。仕事を失ったり、学校を中退したり、恋人や連れ合いと別れたりすると、絶望感に襲われるだろう。だが、ほとんどの人は前に進む意欲を取り戻し、やがて自分の価値を再確認できるような事柄を探し出して、それと取り組むようになる。不確実性を強く感じるこの状態は「意義の探求」と呼ばれ、憎悪に満ちた過激派のカルチャーに加わる動機として、繰り返し登場する概念だ。」(p.261)
「天国には答えがないというなら、それは戦場で見つかるかもしれない。」(p.273)
「「戦士心理学」と呼ばれる科学分野では、集団への極端な結びつき、つまり個人と集団が一体となるアイデンティティ融合(アイデンティティ・フュージョン)の一形態が、自爆テロ犯に見られるような理解しがたい自己犠牲をもたらすという理論が検証されている。融合は、個人と集団が渾然一体となりはじめ、それらの境界線を引くことが困難になったときに生じる。」(p.274)
「科学者が研究対象とする人間は「焼き上がった状態」にある。そのため、人間の心に焦点を当てる科学は、質問をしたり行動を観察したりすることによって、その内部構造を明らかにしなければならない。人間の行動やその変化を生み出すために、どのような材料が、どのような順番で、どのような量で使われたのかを特定するのはとてつもない難題だ。」(p.351)
「憎悪を研究する科学者たちは、その懸命の努力にもかかわらず、様々な発見方法をもってしても「現実」を測定して真に表現することはできない。憎悪研究が生み出す結果は、現実の近似値である。つまり現実世界の不完全な描写にすぎず、その結果には常にある程度の誤差や不確実性がつきまとう。基本的な事実として、因果関係(「この現象は、これら一連の出来事の直接の結果である」ということ)を証明しようとする憎悪の科学は、たとえどのようなものであれ、決して完璧になることはない。」(p.353)
「世界中の人間は、多文化主義に適応し、それを美徳とすることができる。」(p.372)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
