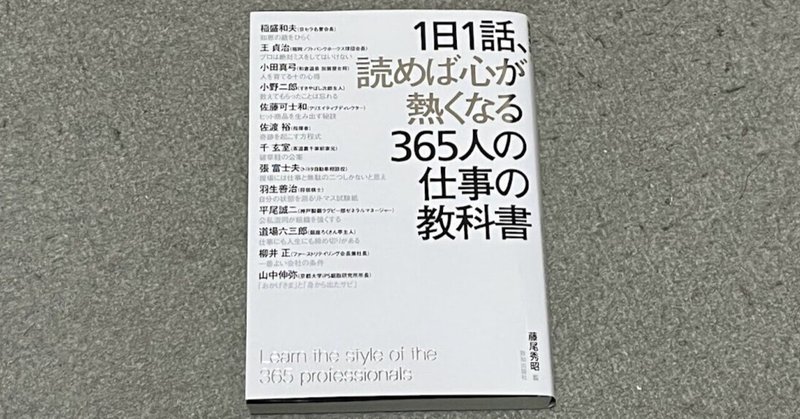
【書籍】挑戦を贈り物に変える人生哲学ー青山俊董氏の教え」
『1日1話、読めば心が熱くなる365人の仕事の教科書』(致知出版社、2020年)のp175「5月22日:病気も「ようこそ」と考える(青山俊董 愛知専門尼僧堂堂頭)」を取り上げたいと思います。
青山氏の体験は、生命と健康に対する深い洞察と仏教的な受容の精神を反映しています。30代後半で初めて重い病気に直面し、がんに移行する可能性がある状態に至った際、青山氏はこの挑戦を、ただの困難ではなく、仏様からの贈り物として受け入れることで心の転換を遂げました。この心境の変化は、日常生活における当たり前のことへの感謝の気持ちを深める契機となりました。食事ができること、眠ることができることなど、病気になるまで無意識のうちに享受していた多くのことが、実は当たり前ではない貴重な恵みであることを痛感させられたのです。
青山氏は、病気を受け入れることを「南無病気大菩薩」と表現し、病気という存在を歓迎する心境に至ったと述べています。この表現は、病気そのものに対する敬意と、それを通じて得られる教訓や成長の機会を尊重する仏教的な考え方を示しています。青山氏にとって、病気は人生を深く理解し、内省する機会を提供する教師のような存在であるといえます。
還暦を迎えた際の体験も、青山氏の人生観に深い影響を与えました。風邪が肺炎に悪化し、一時的に活動を停止することを余儀なくされたこの時期は、人生の「二度目の旅立ち」と捉えられました。生徒からの激励の手紙を受け取り、不快な症状に苦しむ中でも、これらの体験を人生の新たな章として受け止め、老いや病、死を含む人生の全ての側面を豊かな景色として受け入れる心構えを確固たるものにしました。
このようにして、青山氏は病気や困難をただの障害としてではなく、人生を豊かにするための機会として捉えることの価値を説いています。病気を経験することで失うものがあるかもしれないが、それを通じて得られる気づきや学びがあるという考え方です。この精神は、「三つ失ったら五つ気づく」という言葉に象徴されており、人生の困難を乗り越え、それを通じて得られる知識や成長を喜びとする心構えを示しています。
同じ病気をしましても、それをチャンスと受け止めれば、失うことを通し、病むことを通して学ばせていただくことがたくさんある。平素から、三つ失ったら、そのことを通して五つ気づくくらいの心構えでおれば、すべて喜びとなります。それが機を活かし、変に応ずる心構えと申しましょうか。
青山氏の教えは、病気や人生の困難に直面した時、それを乗り越えるための精神的な道具として、また、人生をより深く理解し、豊かにするための哲学として、多くの人々にとって大きな意味を持つものです。
人事の視点から考えること
青山氏の体験を通して病気という人生の試練に対する受容と向き合い方について学ぶことは、人事管理の観点からも大変示唆に富むものがあります。人事管理は、単に組織内の人的リソースを管理するだけでなく、社員一人ひとりの成長と組織全体の発展を促進する役割を担っています。この文脈で、青山氏の体験から得られる教訓を人事管理の各領域に応用することで、より人間中心の、レジリエントで柔軟性のある組織文化の構築に繋がります。
病気との向き合い方から学ぶ人事管理の原則
受容とポジティブなマインドセット
青山氏は病気を「仏様からの授かり物」として受け入れ、その中から学びと成長の機会を見出しました。人事管理では、組織が直面する課題や困難(例えば、業績不振、人材流出、内部コンフリクトなど)を否定的なものとしてではなく、改善と成長の機会として捉えることが重要です。このようなマインドセットを組織文化として根付かせることで、社員は困難に直面してもポジティブな態度で対応し、困難を乗り越える力を内部から養うことができます。
変化への適応と学び
青山氏の「活機応変」という考え方は、変化する環境や予期せぬ困難に対して柔軟に対応し、それを自己成長の機会として捉える姿勢を示しています。人事管理においては、組織の外部環境(市場の変動、技術革新、労働市場の変化など)に迅速かつ効果的に対応する能力が求められます。変化を恐れず、それを組織としての学びの機会と捉えることで、組織は持続的に成長し、競争優位性を維持することができます。
失敗からの学び
青山氏は病気を通じて、日常生活の当たり前のことへの感謝を再発見しました。同様に、人事管理では失敗やミスを単なる否定的な出来事としてではなく、学びと改善の機会として捉える文化を醸成することが大切です(もちろん対策は重要)。失敗を公平に評価し、その原因を分析することで、同じ過ちを繰り返さないための対策を講じ、組織全体の知識として蓄積することが重要です。これにより、組織はより強く、柔軟で、適応能力の高いものになります。
人事管理の具体的応用例
パフォーマンスマネジメント
社員のパフォーマンス評価を通じて、単に成果を評価するだけでなく、個人の成長と発展を支援する機会として捉える。目標設定、フィードバック、キャリア開発計画などを統合し、社員が自らの強みを活かし、挑戦を通じて成長できる環境を提供する。組織開発
組織内のコミュニケーションと協働を促進し、変化に対するレジリエンスを高めるためのプログラムを実施する。チームビルディング、リーダーシップ開発、ダイバーシティ&インクルージョンの推進などを通じて、組織の柔軟性と適応能力を強化する。福利厚生とワークライフバランス
社員が仕事と私生活のバランスを取りやすい環境を提供することで、ストレスを軽減し、全体の生産性と満足度を向上させる。フレキシブルな勤務時間、在宅勤務の選択肢、健康促進プログラムなどを通じて、社員の幸福感とエンゲージメントを高める。
まとめ
青山氏の病気との向き合い方から学ぶことは、人事管理においても非常に価値があります。病気という個人的な試練を通じて得た教訓を、組織や人事の課題に応用することで、より人間中心の、レジリエントで柔軟性のある組織文化を構築することが可能です。このような文化は、組織が直面する様々な挑戦や変化に対して柔軟に対応し、持続的な成長を遂げる基盤となります。人事はこの文化の醸成において中心的な役割を担い、組織と社員の両方にとって最良の成果を生み出すことができるのです。

青山俊董氏の教えを象徴する穏やかで啓発的なシーンを描いています。修道院の庭で、病気を贈り物として、成長の機会として受け入れることの反映として、老僧が静かに瞑想する姿が見られます。柔らかな日差しが木々を通して差し込み、やわらかい影を落としています。庭は内なる平和と感謝の象徴であり、人生の挑戦をポジティブな心持ちで受け入れる僧の旅路を象徴しています。この画像は、平和、回復力、そして人生の不完全さを受け入れる美しさの感覚を伝えます。
1日1話、読めば思わず目頭が熱くなる感動ストーリーが、365篇収録されています。仕事にはもちろんですが、人生にもいろいろな気づきを与えてくれます。素晴らしい書籍です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
