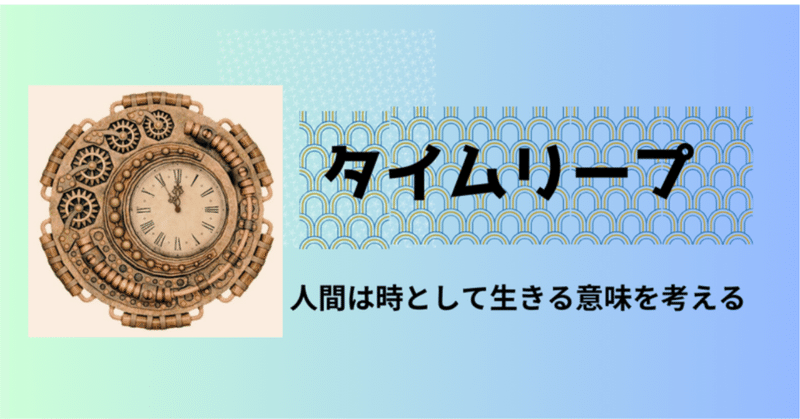
真の自由を手にいれるために➂
~ヘレン・ケラーとアン・サリヴァンの努力の物語~ シリーズ➊~➍
➌障がい者のポテンシャル

1889年10月、サリヴァン先生の母校であった遠くボストンのパーキンス盲学校を訪れたヘレンは、ここで生まれてはじめて自分と同年輩の多くの盲人のこどもたちと遊びました。そこで元気にはしゃぐ子どもたちが、みんな自分と同じ盲人であることを知った時の驚き、しかも子どもたちが実に幸福そうであること知ったヘレンの喜びは筆舌につくし難く、「私はどんなに生き甲斐を感じたことでしょう」と彼女の『自伝』に述べているのを見ても想像に難くありません。
この旅行では、当時の大統領クリーヴランドに招待され、ワシントンで大統領と会見し、雑誌に取り上げられました。古戦場を訪れたり、生れてはじめて汽船に乗るなど、次第に見聞を広めていきました。
1890年、ヘレン11歳の春、彼女が長い間、何とかして話したい、語りたいと念願していた悲願が達せられる日がやってきました。それまでは、一言でも「声」というものを発してみたいと思い、常に片手で自分ののどを抑え、片手を唇に触れて声を出そうと努めてきました。サリヴァン先生の口の中に指を突っ込んで、話す時の先生の舌の動きを知ろうとしたため、サリヴァン先生が嘔吐したことは一度や二度ではありませんでした。
周囲の人々は、そんな出来もしない発声を無理に実現しようとしてうまくいかず、それによって指文字や点字の習得が進まないことを恐れて、その方法には躊躇していました。
しかしヘレンは、当時ノルウェーで聴覚障がい者の発声研究が一部成功したことを伝え知って、矢も盾もたまらず、サリヴァンもその熱意に動かされて、遂にボストンのホレースマン聾学校にヘレンを連れて行き、校長のサラー・フラーに読話と発音法を学ぶこととなったのです。
ヘレンの『自伝』を読むと、「私は校長先生が一言を発するごとに彼女の顔の上に手をあて、その唇の運動や舌の位置を探って、その真似をして、一心に学んだ結果、 1時間後には六つの音の要素 (M.P.A.S.T.I)を覚えこんだのです。かくて私は最初に『It warm today. (今日は暖かです)』と自分には聞えないながらも、声を発することができた時の驚きと喜びは、終生忘れることはできません。
それは聞き取りにくい発音ではありながらも、間違いなく人間の言葉だったのです。「私はこれで永い間の苦悩から救い出された」という意味のことをヘレンが書いているのを見ても、その時の感激が如何に大きかったか想像にかたくありません。
ヘレンは更に1894年から2年間、ニューヨークのライトヒューメン聾啞学校で発声法の研究を積みましたが、この時はドイツ人について勉強したため、わずか数か月でドイツ語なら何でも判るようになったといいます。ヘレンの頭脳が優れていたことはもちろんですが、明けても暮れてもそばを離れずその手助けをしたサリヴァンの献身的努力は言葉では、到底語り尽くせないものでした。
その頃にはヘレンの学問も相当進みラテン語、歴史、文学、地理などには特に興味をもち、同じ年頃の優秀な男女生徒と同等の成績を得たと伝えられています。
ヘレンの向学心と知的好奇心はますます旺盛となり、是非とも大学教育を受けたいと熱心な希望をもらし始めました。幸いある方面から物質的な援助もあって、その準備教育をアイアン博士について家庭で始めました。
17歳になったヘレンは、ハーバード大学を特に希望し、その入学準備のためマサチューセッツ州ケンブリッジ市の女学校に入学します。
ハーバード大学の当時の入学試験科目は英語、歴史、フランス語、ドイツ語、ラテン語やギリシャ語による古典、そして代数と幾何でした。女学校での教育の受け方は、サリヴァンもヘレンと一緒に登校して同席し、教師の教えるところをサリヴァンがそのまま指文字でヘレンに伝え、また質問する時はヘレンが指文字でサリヴァンに伝え、更にサリヴァンから教師に口でその意味を説明するという極めて不便な方法でした。
ヘレンはラテン語が最も得意で、数学は一番苦手でしたが、3年間の大学入学準備期間は、睡眠時間も惜しんで、猛勉強をつづけ、指先から血がふき出るほど何度も点字本を読んだといいます。
しかしこうした労苦が遂に報いられる時が来ました。2回にわたる入学試験の結果、視聴覚障がいの身でありながら、優秀な成績のもと、ハーバード大学付属のラッドクリフ女子大学合格の栄誉を勝ちとったのです。へレン21歳の秋、「世界の歴史始まって以来の快挙」と、当時の新聞はほめたたえました。
大学の教室での勉強中も、休養の時間にも、夜間他の人々が寝た後も、ヘレンとサリヴァンは忙しく指先を動かし、あるいはタイプライターを打ちましした。ヘレンは古典文学と哲学に特に興味を持ち、そのために他から与えられた学資金も点字本を買ったり、参考書を点字にほん訳する費用のために遣い果したほどでした。その努力は報いられて、ヘレンは学友のなかでも極めて優秀な成績でラッドクリフ・カレッジを卒業、視聴覚障がい者としては前代未聞のバチェラー・オブ・アーツの学士号を獲得したのです。
卒業の年、1904年10月、当時開催中のセントルイス博覧会は特にヘレンの卒業を祝して “ヘレンケラー・デー”を設け、ヘレンを招いて大講演会を開催しました。“聴覚障がい者がものをいう”奇跡の人ヘレンの演説を聞こうと、大講堂の窓という窓が人で折り重なる大盛況となりました。
壇上におもむろに進んだヘレンは、生まれて初めて人前に立ち、力一杯の「声」を張り上げましたが、自分にはその「声」は聞こえません。実際喉から出た「声」は実に細く、側にいた人が辛うじて聞き取れる程度でしたが、博覧会会長がそのまま大声で復唱して聴衆に伝えたため、大講堂にあふれた聴衆は奇跡の実現に大いに驚きかつ感激し、演説が終って退場するヘレンの周りに殺到し、動けなくなる程の騒ぎに警察官が出動して整理しなければならないほどでした。
ヘレンの発声方法には、まだ不完全な点が多かったため、1909年から3年間、ボストン音楽学校の声楽教授ホワイト氏について勉強しなおしました。その努力と成果をもって、ヘレン・ケラーは、その後40数年間、海外の国々を訪れ、講演をはじめ、さまざまな活動を行いました。障がいを持つ者のポテンシャルを自ら体現したヘレンの訪問によって、世界各地に福祉事業が生まれ、障がい者への教育や施設の充実が図られることとなったのです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
