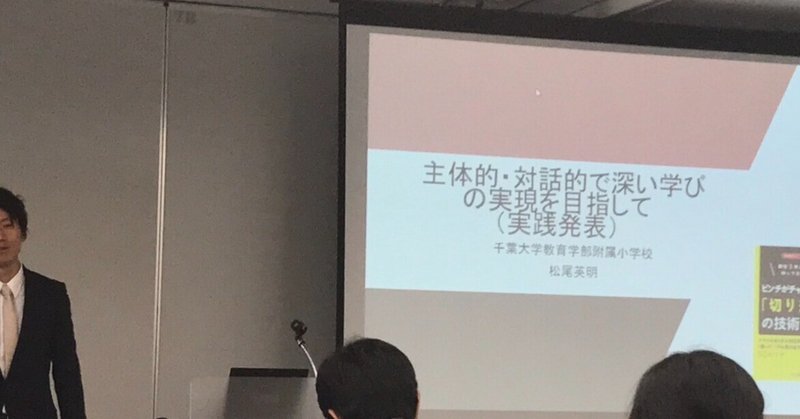
研修を実践にどう生かすか
各地で研修やセミナーが盛んである。
これらは、使い方次第で、大きな楽しみの一つになり得る。
社会科の大家、元筑波大附属小教諭の有田和正先生は、旅行も兼ねてネタ集めに奔走していたという。
数々の素晴らしい授業実践群は、これら休日を含めた日々の研鑽の賜物である。
やり方次第で、旅行すら立派に研修になりうる。
セミナー参加は傍目にもわかりやすい研修の機会である。
わざわざ休日に身銭を切って時間を使ってまで学ぼうというのはコストが高く、並々ならぬモチベーションである。
特に遠方まで行ってお金を払って学ぶような人は、少なくとも「普通」ではない。
コストをかける分、期待が高まる。
時に、相手が、自分の望む答えをもっているように感じてしまう。
悩んでいるほど「どうやるのが正解か」と他者にききたくなる。
ただこの姿勢だと、なかなかうまくいかない。
うまくいかなくても、変われなくても、「相手次第」と思えるからである。
実際は、どんな研修やセミナーであっても、「学び手次第」である。
この夏に出した新刊『学級経営がラクになる! 聞き上手なクラスのつくり方』にも書いたが、受け取る主体は常に「聞き手」にあるからである。
学ぶ時は、消化の仕方が肝である。
特に講師の側にうまくいった実績がある場合、それを真似すればうまくいく気がしてしまう。
実際、やってみるとわかるが、そううまくはいかない。
「変わるぞ!」と熱く燃えて決意したにも関わらず、続かない。
それは、そもそも相手と自分のもつストーリー、文脈が違うからである。
個々のもつ、そもそものベースも環境も全く違うからである。
様々な地へ行くとわかるが、学校の抱える課題も地域で全く違う。
先日の調査結果を受けて「学力向上」が主な課題になっている地域がある。
一方で、所変われば、「貧困」が問題になっている地域もあれば、「同和問題」が筆頭に来ている地域もある。
公立か私学かでも違う。
同じ手法が同じように通用する土台がない。
その研修やセミナーから学んだことを、自分なりにどう解釈して用いるか、実践が全てである。
正解かどうかわからずとも、自分で作るしかない。
いずれにしろ、経験は意図的に積み、そこに整理を加えないといけない。
これは、師の野口芳宏先生が事あるごとに口にされている教訓である。
講師に学んだ気になって満足してしまうのが一番恐ろしいことである。
せっかくの研修で学んだ内容は、自分なりに主体的に活用していきたい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
